更新日:2026/01/03
【2026年最新比較表あり】おすすめのFAQシステム比較17選!選び方のポイントとおすすめ製品を徹底解説
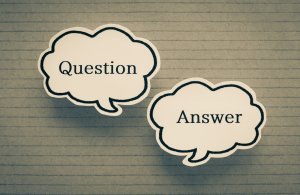

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
顧客や社員からの「よくある質問」対応に追われ、本来の業務が進まない、と感じていませんか?顧客満足度の向上と社内の業務効率化は、多くの企業にとって重要な経営課題です。FAQシステムは、これらの課題を解決する強力なツールとなります。しかし、多種多様なシステムが存在するため、「自社に最適な製品はどれか」「比較のポイントは何か」と悩む担当者も少なくありません。この記事では、2025年最新のFAQシステム17選を徹底比較し、導入成功のための選び方や活用法を詳しく解説します。
おすすめのFAQシステム一覧
scroll →
| 会社名 | サービス名 | 特長 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Zendesk | Zendesk |
|
Support Team $25 エージェント1人の月額(月払い) Suite Team $69 エージェント1人の月額(月払い) Suite Professional $149 エージェント1人の月額(月払い) Suite Enterprise $219 エージェント1人の月額(月払い) |
| 株式会社Helpfeel | Helpfeel |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社PKSHA Technology | PKSHA FAQ |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社PR TIMES | Tayori |
|
フリープラン ¥ 0/月 初期費用 : 無料 スタータープラン ¥ 3,800/月(税抜) 初期費用 : 無料 プロフェッショナルプラン ¥ 11,980/月(税抜) 初期費用 : 無料 エンタープライズプラン ¥ 25,400/月(税抜) 初期費用 : ¥50,000(税抜) |
| 株式会社CBIT | ナレッジリング |
|
ベーシックプラン 9,800円/月~+120円×ユーザー数 初期費用 98,000円 アドバンスプラン 20,000円/月~+150円×ユーザー数 初期費用 120,000円 エンタープライズプラン 50,000円/月~ 初期費用 150,000円 公開FAQプラン 50,000円/月~ 初期費用 150,000円 |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | アルファスコープ |
|
要お問い合わせ |
| noco株式会社 | ヘルプドッグ |
|
初期費用 100,000円(税別) Entry 39,800円 / 月 Professional 59,800円 / 月 |
| 株式会社サイシード | sAI Search |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社SyncThought | SyncAnswer |
|
エントリー 初期導入費 300,000円 月額費用 50,000円 スタンダード 初期導入費 300,000円 月額費用 100,000円 プロフェッショナル 初期導入費 300,000円 月額費用 200,000円 |
| テクマトリックス株式会社 | FastAnswer |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社セールスフォース・ジャパン | Service Cloud |
|
Starter Suite 3,000円JPY/ユーザー/月 Pro Suite 12,000円JPY/ユーザー/月 Enterprise 21,000円JPY/ユーザー/月 |
| 北日本コンピューターサービス 株式会社 | ふれあいコンシェルジュ |
|
月額利用料 18万円 ~ |
| 株式会社サンソウシステムズ | さっとFAQ |
|
エントリー 10,000円/月 ベーシック 30,000円/月 アドバンス 50,000円/月 |
| ゾーホージャパン株式会社 | Zoho Desk |
|
スタンダード ¥1,680/ユーザー/月額(年間払い) プロフェッショナル ¥2,760/ユーザー/月額(年間払い) エンタープライズ ¥4,800/ユーザー/月額(年間払い) |
| チャットプラス株式会社 | FAQPlus |
|
月額200,000円(税別) |
| 株式会社ギブリー | DECA カスタマーサポート |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社スカラコミュニケーションズ | i-ask |
|
要お問い合わせ |
この記事の目次はこちら
FAQシステムとは?
FAQシステムとは、顧客(社外向け)や社員(社内向け)から寄せられる「よくある質問(Frequently Asked Questions)」とその回答(Answer)をデータベース化し、ユーザーが自己解決できるようウェブサイトや社内ポータルに公開・管理するツールを指します。従来のエクセル管理や静的なWebページ作成とは異なり、質問の検索性や管理・更新の容易さが格段に向上します。多くのシステムでは、検索キーワードの分析やユーザーのフィードバック収集機能も搭載しており、回答の品質改善や顧客ニーズの把握に役立ちます。コールセンターやカスタマーサポート部門の問い合わせ対応業務を効率化し、オペレーターの負担を軽減するだけでなく、24時間365日いつでも回答を提供できるため、顧客満足度の向上にも直結します。また、社内向けに利用すれば、情報システム部門や人事総務部門への定型的な質問を減らし、ナレッジ共有を促進する効果も期待できます。導入目的(コスト削減、CX向上など)に応じて適切な製品を選ぶことが重要です。
FAQシステムの種類
FAQシステムは、主に利用対象と提供形態によって分類されます。利用対象による分類では、「社外向け(カスタマーサポート用)」と「社内向け(ヘルプデスク・ナレッジ共有用)」の2種類があります。社外向けは、顧客が自ら疑問を解決できるよう設計されており、高い検索性や分析機能、チャットボット連携などが重視されます。一方、社内向けは、社員からの問い合わせ対応(例:情シス、人事、総務)の効率化や、営業ノウハウなどのナレッジマネジメントを目的とします。こちらはアクセス制限や権限管理、既存の社内ツールとの連携機能が重要視される傾向があります。次に、提供形態による分類では、「クラウド型(SaaS)」と「オンプレミス型」があります。現在は、初期費用を抑えて迅速に導入でき、運用・保守の手間がかからないクラウド型が主流です。オンプレミス型は、自社サーバーに構築するため、セキュリティ要件が非常に厳しい場合や、基幹システムとの複雑な連携が必要な場合に選ばれますが、導入コストと運用負荷は高くなります。自社の利用目的とセキュリティポリシーに合った種類を選ぶことが比較検討の第一歩です。
FAQシステム導入のメリット・デメリット
FAQシステムの導入は、業務効率化や顧客満足度の向上に大きく貢献する一方、運用コストや工数といった側面も考慮する必要があります。メリットとしては、問い合わせ件数の削減によるオペレーターの負担軽減や人件費のコスト削減が挙げられます。また、顧客や社員が24時間いつでも必要な情報へアクセスできるため、利便性と満足度が向上します。さらに、FAQに蓄積されたデータは、サービス改善や製品開発の貴重なヒントにもなり得ます。しかし、導入には初期費用や月額料金が発生し、継続的な運用コストがかかります。デメリットを理解し、対策を講じることで、導入効果を最大化できます。
FAQ導入のメリット
FAQシステム導入の最大のメリットは、問い合わせ対応業務の大幅な効率化とコスト削減です。電話やメールでの定型的な質問が減ることで、オペレーターはより複雑で高度なサポートに集中できます。これにより、サポート品質が向上し、人件費の最適化にもつながります。また、顧客や社員は、時間や場所を問わずに疑問を自己解決できるため、顧客満足度(CS)や従業員満足度(ES)の向上に直結します。さらに、システムに搭載された分析機能を活用することで、ユーザーがどのようなキーワードで検索し、どのFAQがよく見られているかを可視化できます。このデータを分析することで、顧客ニーズの把握、製品・サービスの改善、分かりにくいマニュアルの改訂など、多角的な業務改善のインサイトを得られる点も大きな利点です。
FAQ導入のデメリット
FAQシステム導入のデメリット、すなわち注意点として、導入・運用コストの発生が挙げられます。高機能なシステムやAI搭載型、大規模なデータベースを扱う場合、初期費用や月額利用料が想定以上にかかる可能性があります。また、システムを導入するだけでは効果は出ません。質の高いFAQコンテンツを継続的に作成・更新・メンテナンスする運用工数が必要です。回答が古いまま放置されたり、検索してもヒットしない状態が続いたりすると、逆に顧客満足度を低下させる原因となります。この運用体制を社内で構築するか、ベンダーのサポートを活用するかを事前に決めておく必要があります。さらに、操作方法や分析機能の習得に時間がかかる場合もあり、導入後の社内トレーニングも考慮に入れるべきでしょう。
FAQシステムの選び方
FAQシステムの選び方で失敗しないためには、まず導入目的を明確にすることが最も重要です。「社外の顧客向け」なのか「社内の従業員向け」なのかで、必要とされる機能は大きく異なります。社外向けであれば、検索性の高さ、デザインの自由度、チャットボットとの連携、多言語対応などが比較のポイントになります。一方、社内向けであれば、アクセス権限の詳細な設定、WordやExcelファイルの添付機能、既存のグループウェア(例:Slack, Teams)との連携性、ナレッジ共有のしやすさが重視されます。次に、自社の運用体制を考慮し、FAQの作成・更新が容易に行えるかを確認します。直感的な操作が可能なエディタ、承認ワークフロー、AIによるサジェスト機能などがあると運用負荷を軽減できます。また、導入後のサポート体制が充実しているかも重要な比較ポイントです。導入支援だけでなく、運用開始後の分析サポートや活用コンサルティングを提供しているベンダーを選ぶと安心です。コストパフォーマンスの観点から、料金体系が自社の規模や利用量(ユーザー数、FAQ件数)に見合っているかもしっかりと確認しましょう。
FAQシステムの比較のポイント
数多くのFAQシステムを比較検討する際、どの点に着目すべきか迷うことも多いでしょう。多機能なシステムが必ずしも自社に最適とは限りません。重要なのは、自社の課題解決に必要な機能を見極め、コストと運用のバランスが取れた製品を選ぶことです。特に「機能性」「料金体系」「サポート体制」の3つは、導入後の満足度を左右する重要な比較のポイントです。これらのポイントを軸に各システムを評価することで、自社に最適なソリューションを選定しやすくなります。ここでは、具体的な比較のポイントを3つに分けて詳しく解説します。
ポイント1:機能性(検索性、作成・管理の容易さ)
FAQシステムの核となる機能は「検索性」と「管理の容易さ」です。ユーザーが求める回答に素早くたどり着ける高い検索性は、自己解決率の向上に直結します。AI技術を活用し、表記ゆれ(例:「ログイン」「ログオン」)や類義語、曖昧なキーワードでも適切な回答を提示できるか(検索サジェスト機能)、導入前にデモやトライアルで確認しましょう。一方で、管理側にとっての使いやすさも重要です。FAQの新規作成、編集、承認フローが直感的に行えるエディタ機能、カテゴリ分類の柔軟性、不要になった記事の管理機能などを比較します。特に運用担当者のITリテラシーに不安がある場合は、専門知識が不要なシンプルな操作性のシステムを選ぶことが、継続的な運用成功の鍵となります。
ポイント2:料金体系・コストパフォーマンス
料金体系は、FAQシステムを比較する上で非常に重要な要素です。多くのクラウド型システムでは月額制が採用されていますが、料金の算出基準は製品によって異なります。ID数(オペレーター数)、FAQ記事数、PV数(閲覧数)、機能のグレードなど、何によって費用が変動するのかを明確に確認する必要があります。初期費用が無料でも月額費用が高額であったり、逆に月額は安価でも必要な機能がオプション扱いであったりするケースもあります。自社の利用規模(想定ユーザー数やFAQ件数)を試算し、将来的な拡張性も考慮した上で、総コストで比較することが肝心です。無料トライアルやスモールスタートが可能なプランの有無も確認し、コストパフォーマンスを慎重に見極めましょう。
ポイント3:サポート体制・セキュリティ
導入後の安定運用を見据え、ベンダーのサポート体制とセキュリティレベルの確認は不可欠です。特にFAQシステムの運用に不安がある場合、導入時の初期設定支援だけでなく、運用開始後の活用支援(例:分析レポートの提供、改善コンサルティング)が充実しているかを確認しましょう。サポート窓口の対応時間や手段(電話、メール、チャット)も比較ポイントです。また、FAQシステムは顧客情報や社内ナレッジなど機密情報を含む可能性があるため、セキュリティ対策も重要です。SSL暗号化通信、IPアドレス制限、二要素認証、SAML認証(シングルサインオン)への対応、ISMS(ISO27001)などの第三者認証の取得状況を確認し、自社のセキュリティポリシーを満たしているか評価してください。
AI検索・高機能型 おすすめFAQシステム(サポート品質向上)
顧客満足度の向上や自己解決率の劇的な改善を目指す企業には、AIを搭載した高機能型FAQシステムがおすすめです。これらのシステムは、従来のキーワード検索では対応しきれなかった「話し言葉」や「表記ゆれ」「曖昧な表現」をAIが理解し、最適な回答を提示する能力に長けています。検索ヒット率が向上することで、ユーザーはストレスなく疑問を解消でき、サポート窓口への入電数を大幅に削減できます。また、AIが検索ログを分析し、FAQコンテンツの改善点を提案してくれる機能を持つ製品も多く、運用工数を削減しつつFAQの品質を継続的に高めることが可能です。ここでは、特に検索技術とサポート品質向上に強みを持つ6つのシステムを紹介します。
Helpfeel(ヘルプフィール): 圧倒的な検索ヒット率で「わからない」をなくす
Helpfeelは、「検索ヒット率98%」を謳う革新的なFAQシステムです。その最大の特徴は、独自のAI技術「意図予測検索」にあります。ユーザーが入力する曖昧な表現、感覚的な言葉、さらにはスペルミスや表記ゆれ(例:「キャンセル」「解約」「やめたい」)をAIが瞬時に解析し、最適な回答候補を提示します。これにより、ユーザーは検索キーワードを考える負担から解放され、自己解決率が劇的に向上します。また、導入後のサポートも手厚く、専任のカスタマーサクセス担当がFAQ記事の作成支援から検索データの分析、改善提案までを伴走型で支援してくれます。検索ログの分析結果はダッシュボードで可視化され、どのような言葉で検索されているかを把握できるため、顧客ニーズの的確な把握にも繋がります。サポート品質の向上と工数削減を両立させたい企業に最適です。
PKSHA FAQ(パークシャFAQ): 国内シェアNo.1、AIによる高度な自動最適化
PKSHA FAQは、国内シェアNo.1の実績を誇るFAQシステムであり、PKSHA Technologyグループが持つ高度な自然言語処理技術(AI)を強みとしています。このシステムは、社外向けカスタマーサポートから社内ヘルプデスクまで幅広く対応可能です。AIがユーザーの検索意図を深く理解し、表記ゆれや類義語を自動で吸収・補正するため、高い検索精度を実現します。さらに、AIが検索ログや閲覧データを分析し、FAQの回答候補を自動でサジェストしたり、不足しているFAQを可視化したりするなど、運用者のメンテナンス工数を大幅に削減する機能が充実しています。大手企業や金融機関での導入実績も豊富で、セキュリティ面でも信頼性が高いのが特徴です。既存のFAQ運用に課題を感じ、AIの力で自動化と品質向上を両立させたい企業に適しています。
アルファスコープ: AIがFAQを自動生成・メンテナンス、運用工数を大幅削減
アルファスコープは、AIによるFAQの「自動生成」と「自動メンテナンス」機能に特化したシステムです。多くのFAQシステムが導入後のコンテンツ作成・更新に多大な工数を要する中、アルファスコープは既存のマニュアル、規定集、仕様書などのドキュメントファイルをAIに読み込ませるだけで、FAQを自動生成します。これにより、導入時の初期工数を劇的に削減できます。さらに、AIがユーザーの検索ログやチャットボットの対話履歴を学習し、回答精度の自動チューニングや、不足しているFAQの追加提案を行います。運用担当者はAIの提案を承認するだけでFAQの品質を維持・向上できるため、属人化しがちなFAQ運用から脱却できます。社内に多くのドキュメントが点在しており、FAQの作成・管理工数を最小限に抑えたい企業に最適なソリューションです。
sAI Search(エスエーアイサーチ): サイト内検索強化型のAI-FAQ、高度な意図理解
sAI Searchは、自己解決率の向上を目的としたAI搭載型のサイト内検索・FAQソリューションです。最大の特徴は、ユーザーが入力したキーワードの「意図」をAIが深く理解し、質問と回答のペアだけでなく、関連するWebページやドキュメント(PDFなど)も含めて横断的に検索し、最適な答えを提示できる点にあります。これにより、情報がサイト内に点在していても、ユーザーは一度の検索で必要な情報にたどり着けます。また、AIが検索結果の0件ヒット(ゼロマッチ)を自動で分析し、類義語辞書に登録するなど、継続的に検索精度を自動で改善していきます。既存のWebサイトやヘルプページはそのままに、検索機能だけを高度化したい、あるいはFAQとサイト内検索をシームレスに連携させたいと考える企業にとって、強力な選択肢となるでしょう。
SyncAnswer(シンクアンサー): AIチャットボット連携に強み、会話形式で課題解決
SyncAnswerは、FAQシステムとAIチャットボットをシームレスに連携させることに強みを持つソリューションです。FAQとして蓄積したナレッジを、Webサイト上のFAQページでの検索だけでなく、チャットボットによる自動応答にも活用できる「ワンソース・マルチユース」を実現します。ユーザーは、検索窓にキーワードを入力するだけでなく、チャットボットとの自然な会話を通じて疑問を解決できるようになります。AIがユーザーの質問意図を解析し、FAQデータベースから最適な回答を引き出し、会話形式で提示します。もしAIチャットボットで解決できない場合は、有人チャットやコールセンターへスムーズに誘導する機能も備えており、顧客体験(CX)を損ないません。FAQとチャットボットを個別に導入・管理する手間を省き、顧客接点の自動化を推進したい企業に最適です。
DECA カスタマーサポート: 顧客接点データを活用するAIサポート、CX向上を実現
DECA カスタマーサポートは、単なるFAQシステムに留まらず、顧客接点(Webサイト、チャット、メールなど)から得られるデータを統合的に活用し、顧客体験(CX)の向上を目指すソリューションです。AIがFAQの検索ログやチャットの対話履歴を分析し、顧客の疑問や不満の根本原因を特定します。その分析結果に基づき、FAQコンテンツの改善はもちろん、Webサイトの導線改善や製品・サービスの改善提案まで行います。特徴的なのは、顧客の属性や行動履歴に応じて、表示するFAQやサポート手段(チャットボット、有人チャット、コールバック予約など)をパーソナライズできる点です。これにより、画一的なサポートではなく、個々の顧客に最適化された問題解決を提供できます。サポート部門をコストセンターからプロフィットセンターへと変革させたい企業に適しています。
多機能・CRM連携型 おすすめFAQシステム(業務全体を効率化)
カスタマーサポート業務の効率化を追求する上で、FAQシステムとCRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)システムとの連携は非常に重要です。多機能・CRM連携型のシステムは、単にFAQを公開するだけでなく、問い合わせ管理(チケット管理)、顧客情報の一元管理、オペレーターの応対履歴管理など、サポート業務全体をカバーする機能を備えています。CRMと連携することで、オペレーターは顧客の過去の問い合わせ履歴や購買履歴を参照しながら応対でき、より質の高いサポートを提供できます。また、問い合わせ内容を分析し、FAQコンテンツの充実や営業活動へのフィードバックにも活用可能です。ここでは、サポート業務全体のプラットフォームとして機能する6つのシステムを紹介します。
Zendesk(ゼンデスク): 世界的シェア、サポート業務全体を一元管理
Zendeskは、世界160カ国以上で10万社以上の導入実績を持つ、カスタマーサービスプラットフォームのグローバルリーダーです。その強みは、FAQ(セルフサービス)機能だけでなく、メール、電話、チャット、SNSなど、あらゆるチャネルからの問い合わせを「チケット」として一元管理できる点にあります。オペレーターは単一の管理画面で全ての顧客対応を完結でき、業務効率が飛躍的に向上します。FAQ機能(Zendesk Guide)は、強力な検索機能とシンプルなコンテンツ作成エディタを備えており、チケット管理システム(Zendesk Support)とシームレスに連携します。オペレーターは問い合わせ対応中にFAQ記事を簡単に参照・引用でき、顧客はまずFAQで自己解決を試み、解決しない場合のみ問い合わせを行うという理想的な導線を構築できます。拡張性が高く、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模のサポート体制に対応可能です。
Service Cloud(サービスクラウド): Salesforce連携で顧客情報とFAQをシームレスに統合
Service Cloudは、世界No.1のCRM/SFAプラットフォームであるSalesforceが提供するカスタマーサービスソリューションです。最大の強みは、Salesforceの顧客データベースと完全に統合されている点です。オペレーターは、問い合わせを受けている顧客の基本情報、過去の商談履歴、購買履歴、これまでのサポート履歴の全てを同じ画面で確認しながら対応できます。FAQ機能(Salesforce Knowledge)もこのプラットフォームに組み込まれており、顧客情報とナレッジ(FAQ)が連携します。AI(Einstein)が問い合わせ内容を分析し、関連するFAQ記事や類似の過去事例をオペレーターに自動で推薦(サジェスト)するため、応対時間の短縮と回答品質の均一化が図れます。すでにSalesforceを導入している企業、または営業部門とサポート部門の情報を一元化し、全社的な顧客対応力の強化を目指す企業に最適です。
Zoho Desk(ゾーホーデスク): 高コストパフォーマンス、Zohoエコシステムと強力連携
Zoho Deskは、非常に高いコストパフォーマンスで多機能なサポート体制を実現するクラウド型ヘルプデスクツールです。ZendeskやService Cloudと同様に、問い合わせのチケット管理、FAQ(ナレッジベース)の構築、チャット、電話(CTI連携)、SNS連携など、カスタマーサポートに必要な機能を網羅しています。特に、Zohoが提供する他の多様なビジネスアプリケーション(Zoho CRM, Zoho Projectsなど)との連携が強力で、サポート業務と営業・開発部門との情報連携をスムーズに行えます。AI「Zia」を搭載しており、問い合わせ内容の自動振り分けや、オペレーターへの回答サジェストも可能です。月額料金が比較的安価なプランから用意されており、機能とコストのバランスを重視する中小企業から、Zohoエコシステムで業務全体のDXを推進したい大企業まで、幅広く対応できる柔軟性が魅力です。
FAQPlus(エフエーキュープラス): 大規模・多言語対応、高機能カスタマイズに強み
FAQPlusは、大規模運用や複雑な要件に対応できる高機能FAQシステムです。長年の導入実績に裏打ちされた豊富な機能を備え、特に大企業やコールセンターでの利用に適しています。多言語対応(標準で日英中韓に対応)に強みを持ち、グローバル展開する企業のカスタマーサポート基盤として活用できます。また、柔軟なカテゴリ分類、詳細な承認ワークフロー、厳格な権限管理機能など、大規模組織での運用に必要な管理機能が充実しています。検索性においても、表記ゆれ吸収やサジェスト機能はもちろん、添付されたPDFファイル内のテキストまで検索対象にできるなど、高い精度を誇ります。CRMやチャットボットなど外部システムとの連携実績も豊富で、既存システムと組み合わせて自社独自のサポート環境を構築したい場合に頼りになるシステムです。
FastAnswer(ファストアンサー): コールセンター特化、オペレーター支援機能が充実
FastAnswerは、特にコールセンターやヘルプデスクのオペレーター支援(応対効率化)に特化したFAQ・ナレッジシステムです。顧客向けの公開FAQとしてだけでなく、オペレーター専用の「回答支援ツール」としての側面が強いのが特徴です。オペレーターが顧客と会話しながらでも素早く正確な回答を見つけられるよう、検索スピードと一覧性(アンサーの表示形式)が最適化されています。また、回答に利用したFAQのログが残り、どのFAQが応対品質の向上に貢献しているかを分析できます。CTI(電話システム)やCRMとの連携にも強く、入電と同時に関連するFAQをポップアップ表示させることも可能です。コールセンターの新人教育の効率化、オペレーターの応対品質の均一化、平均応対時間(ATT)の短縮といった具体的な課題を持つ企業にとって、即効性のあるソリューションとなります。
i-ask(アイアスク): 導入実績豊富、金融機関も採用するセキュリティと安定性
i-askは、300社以上の導入実績を持つ純国産のFAQシステムです。その最大の特徴は、金融機関や官公庁、インフラ企業など、極めて高いセキュリティ要件が求められる業界での採用実績が豊富な点にあります。堅牢なセキュリティ基盤と安定したシステム稼働は、企業の信頼性を支える上で重要な要素です。機能面では、直感的な操作が可能な管理画面、AI技術を活用した高精度な検索エンジン(表記ゆれ・同義語対応)、詳細な利用ログ分析機能など、FAQシステムとしての基本性能を高いレベルで満たしています。また、オンプレミス型での提供にも対応しており、クラウド利用が難しい企業のニーズにも応えられます。長年の運用ノウハウに基づいた手厚い導入・運用サポートも評価が高く、安心して長期的に利用できるFAQシステムを求める企業に適しています。
シンプル・低コスト導入型 おすすめFAQシステム
FAQシステムの導入を検討しているものの、「まずは低コストで始めたい」「多機能すぎても使いこなせない」と考える中小企業やスタートアップ、あるいは部門単位でのスモールスタートを希望する企業も多いでしょう。シンプル・低コスト導入型のシステムは、必要十分なFAQ機能に絞り込み、月額無料または数千円から数万円程度で利用できる手軽さが魅力です。操作も直感的で、専門知識がなくても短期間でFAQサイトを立ち上げることが可能です。まずはFAQ運用を始めてみて、その効果を測定しながらステップアップしたい場合に最適です。ここでは、迅速かつ低コストで導入できる5つのシステムを紹介します。
Tayori(タヨリ): FAQ・フォーム・チャットを低価格(月額0円~)で実現
Tayoriは、FAQ(ナレッジベース)の作成機能に加え、お問い合わせフォーム、チャットサポート、アンケート機能までをワンストップで、かつ非常に低価格(月額0円のフリープランから)で提供するツールです。特にスタートアップや中小企業にとって、顧客サポートの窓口をまとめて構築できるコストパフォーマンスの高さが最大の魅力です。FAQ作成画面は直感的で、専門知識がなくても簡単にデザイン性の高いFAQページを作成できます。フリープランでは機能や記事数に制限がありますが、FAQシステムの導入効果を試してみたい場合に最適です。有料プランも安価に設定されており、ビジネスの成長に合わせてチャット機能を追加するなど、段階的な機能拡張が可能です。まずはコストをかけずにFAQ運用と問い合わせ管理を始めたい企業にとって、最初の選択肢となるでしょう。
ナレッジリング: 社内ナレッジ共有に特化、シンプルな操作性と蓄積機能
ナレッジリングは、特に「社内向け」のナレッジ共有やヘルプデスク用途に特化したFAQシステムです。社外向けのようなデザイン性よりも、社内の情報(業務マニュアル、ノウハウ、日報など)をとにかく簡単に蓄積し、必要な時に素早く検索できる「シンプルさ」を追求しています。操作画面が非常に分かりやすく、ITツールに不慣れな社員でも迷わず情報やFAQを登録・閲覧できます。WordやExcel感覚で記事を作成でき、ファイル添付も容易です。社内FAQとしてだけでなく、プロジェクトの議事録管理や新人教育用のポータルとしても活用できます。高機能なシステムは不要で、とにかく社内に点在する情報を一元化し、社員の自己解決を促進したい、という明確な目的を持つ企業に適した、低コストで導入できるツールです。
ヘルプドッグ: シンプル機能と低コスト、FAQの分析機能も搭載
ヘルプドッグは、「シンプル・低コスト・高機能」のバランスが取れたFAQシステムです。月額数万円台から利用可能でありながら、FAQの作成・管理、高精度な検索(表記ゆれ対応)、利用状況の分析レポートといった、FAQ運用に必要な基本機能を過不足なく搭載しています。特に「分析機能」に強みがあり、検索キーワードのランキング、検索ヒットしなかったキーワード(ゼロマッチ)、よく見られているFAQなどをグラフで簡単に可視化できます。これにより、ユーザーが何を求めているのかを把握し、FAQコンテンツの継続的な改善活動(PDCA)を回しやすくなります。多機能すぎるシステムは不要だが、FAQの運用効果をしっかりと分析・改善していきたいと考える、コスト意識と運用意識の高い企業・部門に最適な選択肢です。
さっとFAQ: 月額1万円から導入可能、迅速な立ち上げを実現
「さっとFAQ」は、その名の通り、月額1万円(税抜)からという圧倒的な低コストで、迅速にFAQサイトを立ち上げられるクラウドサービスです。初期費用も不要で、申し込み後すぐに利用を開始できるスピード感が最大の特徴です。低価格ながら、カテゴリ分類、キーワード検索、画像挿入、スマートフォン表示対応など、FAQサイトとして必要な基本機能はしっかりと備えています。操作もシンプルで、マニュアルを見なくても直感的にFAQの登録・更新が可能です。とにかくコストを最小限に抑えたい、複雑な機能は不要なのですぐにでもFAQページを公開したい、という緊急性の高いニーズに応えます。まずは最低限のFAQ体制を構築し、顧客や社員の反応を見たいと考えるスモールスタートに最適なシステムと言えるでしょう。
ふれあいコンシェルジュ: FAQと高精度AIチャットボットをセットで安価に導入
ふれあいコンシェルジュは、FAQシステムと高精度なAIチャットボットをセットで、比較的安価な料金体系で導入できるソリューションです。FAQページでの検索による自己解決と、チャットボットによる会話形式での自己解決の両方を同時に実現します。AIチャットボットは、独自の自然言語処理技術により、高い回答精度を持ち、導入時の初期学習(AIへの教育)の負担が少ない点も特徴です。FAQシステムで作成したナレッジをチャットボットの回答にも活用できるため、運用の一元管理が可能です。低コストでFAQだけでなく、最近注目されているAIチャットボットによる自動応答も導入してみたい、と考える企業にとって、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。サポートチャネルの自動化を一歩進めたい場合に適しています。
FAQシステムの料金相場
FAQシステムの料金相場は、提供形態(クラウド型/オンプレミス型)や機能、サポート体制によって大きく変動します。現在主流のクラウド型(SaaS)の場合、初期費用と月額費用で構成されることが一般的です。初期費用は、無料のものから数十万円程度まで幅があります。月額費用は、システムの機能グレードや利用規模(ID数、FAQ記事数、PV数など)に応じて変動します。具体的な相場としては、「シンプル・低コスト型」であれば月額0円(フリープラン)から数万円程度で、基本的なFAQ作成・公開機能が利用できます。「多機能・CRM連携型」や「AI検索・高機能型」になると、月額数万円から数十万円、あるいはそれ以上になるケースも珍しくありません。特にAI機能の利用や大規模なCRM連携、手厚い運用サポートを求める場合はコストが上昇する傾向にあります。一方、オンプレミス型は、自社サーバーに構築するため、数百万円以上の高額な初期ライセンス費用と、別途保守費用が必要となり、導入のハードルは高くなります。自社の予算と必要な機能を見極め、複数のシステムで見積もりを取得し比較することが不可欠です。
FAQシステムを導入する際の注意点・導入ステップ
FAQシステムを導入する際、単に高機能なツールを選べば成功するわけではありません。注意点として最も重要なのは、「導入目的の明確化」と「運用体制の構築」です。まず、「誰の(顧客/社員)」「どの課題を(問い合わせ削減/ナレッジ共有)」解決したいのかを明確にし、必要な機能要件を定義します。次に、導入後の運用体制です。FAQは作成して終わりではなく、継続的なコンテンツの追加・更新・分析が不可欠です。誰が、どのくらいの頻度でメンテナンスを行うのか、承認フローはどうするのかを事前に決めておかなければ、せっかくのシステムが陳腐化してしまいます。導入ステップとしては、まず①現状の課題と目的の整理、②機能要件の定義、③複数システムの比較・選定(トライアル含む)、④運用体制の構築とコンテンツ準備、⑤導入・公開、⑥運用・分析・改善(PDCA)という流れが一般的です。特に④のコンテンツ準備は時間と労力がかかるため、既存のマニュアルや問い合わせ履歴を活用するなど、効率的な準備計画を立てることが導入成功の鍵となります。
FAQシステムに関するよくある質問(FAQ)
FAQシステムの導入を具体的に検討し始めると、機能や料金以外にも様々な疑問が浮かんでくることでしょう。例えば、無料プランでどこまでできるのか、導入決定から実際に利用開始できるまでの期間はどれくらいか、あるいは現在使用している他の業務システムと連携できるのか、といった点は、選定において重要な判断材料となります。これらの疑問を解消しておくことは、導入後のミスマッチを防ぎ、スムーズな運用体制の構築に繋がります。ここでは、FAQシステムの比較検討時によく寄せられる代表的な3つの質問について、分かりやすく回答していきます。
Q1. 無料プランやトライアルはありますか?
多くのFAQシステム、特にクラウド型(SaaS)では、無料プランや無料トライアル期間が提供されています。無料プランは、機能やFAQ記事数、ユーザー数などに制限があるものの、期間の定めなく基本的な機能を試せるため、Tayoriのように小規模な利用やスモールスタートに適しています。一方、無料トライアルは、通常14日間や30日間といった期間限定で、有料プランの全機能または一部機能を試用できる制度です。これは、本格導入の前に、自社の業務フローに合うか、操作性は直感的か、特に検索精度は十分かといった点を評価するために非常に有効です。高機能なシステムほど、実際の管理画面の使い勝手や分析機能の具体的内容をトライアルで確認することが推奨されます。導入の失敗リスクを避けるため、気になるシステムがあれば積極的にトライアルを申し込み、比較検討することをおすすめします。
Q2. 導入までにかかる期間はどれくらいですか?
導入までにかかる期間は、選択するシステムの種類、既存のFAQコンテンツの有無、必要なカスタマイズの度合いによって大きく異なります。クラウド型で、かつデザインテンプレートを使用し、必要なFAQコンテンツが既に揃っているシンプルなケースでは、契約後、最短で数日~1週間程度で公開が可能です。しかし、一般的には、要件定義、設定、デザインの調整、そして最も時間のかかるFAQコンテンツ(Q&A)の作成や移行作業を含め、1ヶ月から3ヶ月程度を見込むのが現実的です。特にAI搭載型システムの場合は、初期学習データの準備やチューニングに時間がかかることもあります。オンプレミス型や、基幹システムとの大規模な連携開発が必要な場合は、半年以上の期間を要することも珍しくありません。迅速な導入を目指す場合でも、コンテンツの品質を担保する期間を十分に確保することが重要です。
Q3. 既存のツール(CRM, SFAなど)と連携できますか?
FAQシステムと既存ツール、特にCRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)、チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)との連携は、業務効率化において非常に重要です。多くの多機能型FAQシステムは、Salesforce(Service Cloud)やZendeskのように、CRM機能が一体化しているか、あるいはAPI(Application Programming Interface)を介して外部システムと柔軟に連携できる機能を提供しています。例えば、CRMと連携することで、問い合わせ元の顧客情報を参照しながらFAQを検索・回答したり、問い合わせ内容をCRM側に自動で記録したりできます。社内向けでは、SlackやTeamsから直接FAQを検索できる連携も人気です。ただし、システムによって連携可能なツールや連携の深さが異なるため、比較検討時には、自社で利用中のツールと連携可能か、API連携に追加コストは発生しないかを必ず確認する必要があります。
まとめ
この記事では、FAQシステムの基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、そして2025年最新のおすすめFAQシステム17選を用途別に徹底比較しました。FAQシステムは、単に「よくある質問」を掲載するツールではなく、顧客満足度の向上、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクの業務効率化、そして蓄積されたデータの分析によるサービス改善を実現する強力な経営基盤です。
導入成功の鍵は、自社の目的(社外向けか社内向けか)、必要な機能(AI検索、CRM連携)、そして運用体制に見合ったコストパフォーマンスの製品を選ぶことです。「AI検索・高機能型」「多機能・CRM連携型」「シンプル・低コスト型」といった分類を参考に、気になるシステムがあれば無料トライアルや資料請求を活用し、実際の操作性やサポート体制を比較検討してください。本記事が、貴社の課題を解決する最適なFAQシステム選びの一助となれば幸いです。
おすすめのFAQシステム一覧
scroll →
| 会社名 | サービス名 | 特長 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Zendesk | Zendesk |
|
Support Team $25 エージェント1人の月額(月払い) Suite Team $69 エージェント1人の月額(月払い) Suite Professional $149 エージェント1人の月額(月払い) Suite Enterprise $219 エージェント1人の月額(月払い) |
| 株式会社Helpfeel | Helpfeel |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社PKSHA Technology | PKSHA FAQ |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社PR TIMES | Tayori |
|
フリープラン ¥ 0/月 初期費用 : 無料 スタータープラン ¥ 3,800/月(税抜) 初期費用 : 無料 プロフェッショナルプラン ¥ 11,980/月(税抜) 初期費用 : 無料 エンタープライズプラン ¥ 25,400/月(税抜) 初期費用 : ¥50,000(税抜) |
| 株式会社CBIT | ナレッジリング |
|
ベーシックプラン 9,800円/月~+120円×ユーザー数 初期費用 98,000円 アドバンスプラン 20,000円/月~+150円×ユーザー数 初期費用 120,000円 エンタープライズプラン 50,000円/月~ 初期費用 150,000円 公開FAQプラン 50,000円/月~ 初期費用 150,000円 |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | アルファスコープ |
|
要お問い合わせ |
| noco株式会社 | ヘルプドッグ |
|
初期費用 100,000円(税別) Entry 39,800円 / 月 Professional 59,800円 / 月 |
| 株式会社サイシード | sAI Search |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社SyncThought | SyncAnswer |
|
エントリー 初期導入費 300,000円 月額費用 50,000円 スタンダード 初期導入費 300,000円 月額費用 100,000円 プロフェッショナル 初期導入費 300,000円 月額費用 200,000円 |
| テクマトリックス株式会社 | FastAnswer |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社セールスフォース・ジャパン | Service Cloud |
|
Starter Suite 3,000円JPY/ユーザー/月 Pro Suite 12,000円JPY/ユーザー/月 Enterprise 21,000円JPY/ユーザー/月 |
| 北日本コンピューターサービス 株式会社 | ふれあいコンシェルジュ |
|
月額利用料 18万円 ~ |
| 株式会社サンソウシステムズ | さっとFAQ |
|
エントリー 10,000円/月 ベーシック 30,000円/月 アドバンス 50,000円/月 |
| ゾーホージャパン株式会社 | Zoho Desk |
|
スタンダード ¥1,680/ユーザー/月額(年間払い) プロフェッショナル ¥2,760/ユーザー/月額(年間払い) エンタープライズ ¥4,800/ユーザー/月額(年間払い) |
| チャットプラス株式会社 | FAQPlus |
|
月額200,000円(税別) |
| 株式会社ギブリー | DECA カスタマーサポート |
|
要お問い合わせ |
| 株式会社スカラコミュニケーションズ | i-ask |
|
要お問い合わせ |

