更新日:2025/07/02
【2025年版】経費精算とは?面倒な業務の効率化ガイド|書き方からシステム選びまで徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 経理財務課課長
藤田 貴英
経理一筋20年、中小企業から大企業までさまざまな規模の経理業務に従事。
株式会社ジオコードに入社後、経理財務課課長に就任し、IPO準備の中心メンバーとして上場に導く。
「毎月の経費精算、もっと楽にならないだろうか…」多くのビジネスパーソンが抱えるこの悩み。領収書の整理や申請書の作成、承認、そして経理部門での確認作業は、時間と手間がかかる業務の代表格です。本記事では、経費精算の基本的な知識から、従来のプロセスが抱える課題、そして業務を劇的に効率化するための具体的な方法までを網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたの会社の経費精算業務を改善するヒントがきっと見つかるはずです。
【比較表】請求書カード払いのおすすめサービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 手数料 | 対応しているクレジットカード |
|---|---|---|---|
DGFT請求書カード払い
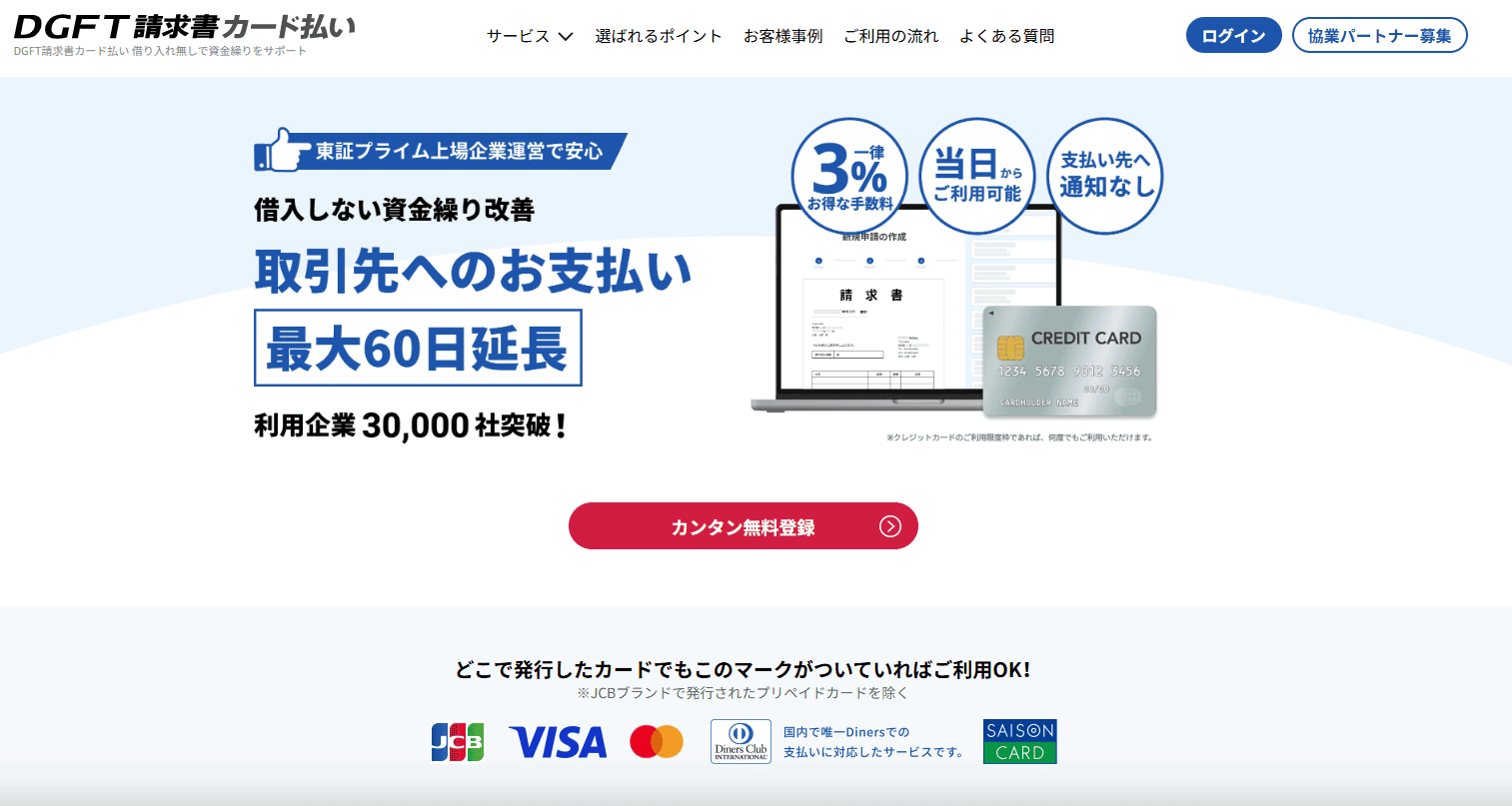
|
|
3% | JCB, VISA, Master, Diners Club,SAISON CARD |
Fintoカード払い

|
|
2.5% ※キャンペーン実施中※ 初回手数料2.0%、以降2.2% 期間:2025年11月1日〜2026年3月31日まで |
Visa、Mastercard、JCB、セゾンブランドのカード |
INVOYカード払い

|
|
3% | VISA、Mastercard、JCB |
LP請求書カード払い
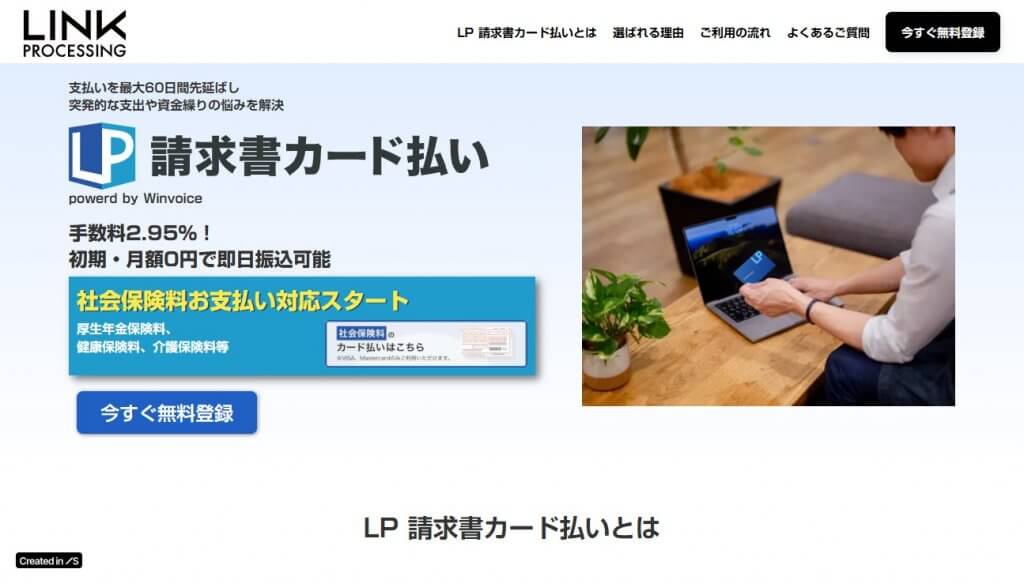
|
|
2.95% | Visa、Mastercard、JCB |
支払い.com

|
|
4% | SAISON CARD、VISA、Mastercard |
ラボル カード払い

|
|
3~3.5% | VISA、Mastercard、JCB |
フリーウェイ請求書カード払い

|
|
2.7% | VISA,Mastercard,JCB,デビットカード |
ゆとりペイ

|
|
2.9% | Visa、Mastercard、JCB |
| Money Foward請求書カード払い for Startups |
|
2.4%~ | VISA、Mastercard、JCB |
| 請求書カード払い JCB×Digital Garage |
|
2.98% | JCBグループのカード発行会社が提供するカードが対象 |
| Biz Forward請求書カード払い |
|
2.8% | 国内で発行されたVisa/Mastercard/JCBブランドのクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード |
| 請求書カード払い by GMO |
|
3% | Visa / MasterCard |
| NP掛け払い 請求書カード払い |
|
3% | VISA、Mastercard、JCB |
| 請求書支払い代行サービス |
|
3% | 国内で発行されたVisa/Mastercard |
この記事の目次はこちら
1. 経費精算とは?基本をわかりやすく解説
経費精算とは、従業員が事業活動のために一時的に立て替えた費用(経費)を、会社が精算し、従業員に払い戻す一連の手続きのことです。この業務は、会社の利益を正しく計算し、適切な税務申告を行う上で不可欠なものです。また、経費利用の妥当性をチェックすることで、不正利用を防ぎ、内部統制を強化する目的も担っています。このセクションでは、経費精算の対象となる費用の種類や、一般的な業務の流れといった、すべてのビジネスパーソンが知っておくべき基本的な知識を掘り下げていきます。
1-1. 経費精算の対象となる主な費用
経費精算の対象となる費用は、事業の遂行に直接関連するものに限られます。代表的な勘定科目には、顧客訪問や移動で発生した電車代やバス代を含む「交通費」、遠隔地での業務に必要な宿泊費や日当をまとめた「出張費」、顧客との会食にかかる「接待交際費」、そして事務用品や備品の購入に使われる「消耗品費」などがあります。これらの費用は、会社の経費規程に基づいて適切に申請される必要があります。個人的な食事代やプライベートな買い物は経費として認められないため、公私の区別を明確にすることが重要です。
1-2. 経費精算の基本的な業務フロー
一般的な経費精算の業務フローは、いくつかのステップで構成されています。まず、従業員が立て替えた費用の領収書を基に経費精算書を作成し、申請します。次に、申請書は直属の上長など、社内規程で定められた承認者の元へ送られます。承認者は内容を精査し、不備がなければ承認します。不備があった場合は申請者に差し戻されます。最終的に承認された申請書は経理部門にわたり、経理担当者が内容の最終確認と会計システムへの仕訳入力を行い、指定された日に従業員の口座へ振り込み処理を実行します。
1-3. 経費精算はいつまで?申請期限のルール
経費精算の申請期限は、会社の経費規程によって定められているのが一般的です。「費用が発生した月の末日まで」や「翌月の第3営業日まで」といったルールが多く見られます。この期限を設ける目的は、経理部門が月次決算をスムーズに進めるためです。期限を過ぎると、経費として認められなかったり、承認が遅れたりする可能性があるため注意が必要です。法律上、経費を請求する権利の時効は5年ですが、会社のルールが優先されるため、定められた期間内に必ず申請する習慣をつけましょう。
2. 経費精算書の書き方と注意点
経費精算を正確かつスムーズに進めるためには、経費精算書の正しい書き方を理解することが不可欠です。申請書類に不備があると、承認者や経理担当者からの差し戻しが発生し、精算が遅れる原因となります。誰が見ても内容が明確にわかるように、必要な情報を過不足なく記載することが求められます。このセクションでは、経費精算書に記載すべき必須項目から、証憑となる領収書の取り扱いにおける注意点まで、具体的な書き方のポイントを詳しく解説していきます。
2-1. 経費精算書に必要な項目
経費精算書には、いつ、誰が、何のために、いくら使ったのかを明確にするための項目を記載します。具体的には、「申請日」と「申請者名(所属部署)」をまず明記します。次に、費用ごとの「支払日」「支払先」「内容(摘要)」、そして「勘定科目」と「金額」を記入します。特に「摘要」は重要で、「〇〇社との打ち合わせのため」のように、具体的な目的を記載することで、承認者が経費の妥当性を判断しやすくなります。交通費の場合は、利用した交通機関や移動区間も忘れずに記入しましょう。
2-2. 領収書の正しい取り扱い方
経費精算における領収書は、支払いがあったことを証明する最も重要な証憑書類です。原則として原本の提出が求められ、経費精算書の裏面などに日付順で貼り付けます。領収書には「宛名」「日付」「金額」「但し書き」「発行者」が明記されているかを確認しましょう。もし領収書を紛失してしまった場合は、まず上長や経理部門に相談してください。レシートやクレジットカードの利用明細、または出金伝票を作成することで代替が認められるケースもあります。電子帳簿保存法に対応している場合は、スキャンデータでの提出も可能です。
3. なぜ面倒?従来の経費精算が抱える3つの課題
多くの企業で、経費精算は「面倒で非効率な業務」と認識されています。特に、紙の申請書とExcelを使ったアナログな運用を続けている場合、申請者、承認者、経理担当者という関わるすべての従業員が、それぞれ異なる種類の負担を強いられています。これらの課題は、個人の時間を奪うだけでなく、会社全体の生産性を低下させる要因にもなり得ます。ここでは、立場ごとに異なる経費精算の課題を具体的に浮き彫りにし、なぜ業務改善が必要なのかを明らかにします。
3-1. 【申請者】立替払いや書類作成の手間
申請者にとって、経費精算は大きな負担を伴います。まず、業務のために個人的な現金を一時的に立て替える必要があり、高額な出張費などが続くと金銭的な負担が大きくなります。さらに、業務の合間を縫って、保管していた大量の領収書を台紙に糊で貼り付け、Excelのテンプレートに一件ずつ手入力する作業は非常に手間がかかります。入力ミスや記載漏れがあれば差し戻され、やり直しになることも少なくなく、本来集中すべきコア業務の時間を圧迫してしまうのが現状です。
3-2. 【承認者】申請内容の確認・差し戻しの負担
承認者である管理職もまた、経費精算業務に多くの時間を費やしています。部下から提出される多数の申請書の内容を一件ずつ確認し、社の経費規程に違反していないか、勘定科目は適切かなどをチェックしなければなりません。特に月末は申請が集中しがちです。もし申請に不備を見つけた場合、具体的な修正内容を指示して差し戻す必要があり、このコミュニケーションにも手間がかかります。また、出張や外出が多い承認者の場合、オフィスに戻らないと承認作業ができず、精算全体の遅延を招く原因にもなります。
3-3. 【経理】手作業によるミスと月末の業務集中
経理担当者は経費精算プロセスの最終アンカーであり、最も多くの課題を抱えています。全従業員から集まってきた申請書の内容を再度チェックし、会計システムへ手作業で仕訳入力を行うため、入力ミスや勘定科目の間違いといったヒューマンエラーが発生しやすい環境にあります。また、月末や月初には申請が集中し、他業務を圧迫するほどの膨大な作業量になります。これに加えて、振込作業やファイリング、電子帳簿保存法などの法改正への対応も求められ、大きな業務負担となっています。
4. 今すぐできる!経費精算を効率化する具体的な方法
経費精算の非効率性を解消する方法は、大掛かりなシステム導入だけではありません。日々の業務プロセスを少し見直したり、便利なツールを活用したりするだけでも、大きな改善効果が期待できます。重要なのは、自社の状況に合わせて最適な手段を選択することです。このセクションでは、経費精算業務を効率化するための具体的なアプローチを3つのステップで紹介します。手軽に始められるキャッシュレス化から、社内ルールの整備、そして最終的な解決策としてのシステム導入まで、段階的に解説します。
4-1. キャッシュレス決済の活用
経費精算の効率化における第一歩は、現金での立替払いを減らすことです。法人カード(コーポレートカード)を従業員に配布すれば、利用履歴がデータとして一元管理されるため、従業員は支払いのために現金を準備する必要がなくなり、経理担当者は利用明細を基に正確な支出を把握できます。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードと連携できるシステムを使えば、移動履歴が自動で読み込まれ、交通費精算の手入力が不要になります。これにより、申請の手間と確認作業が大幅に削減されます。
4-2. 経費精算ルールの見直しと周知徹底
ツールの導入と並行して、社内の経費精算ルールそのものを見直すことも重要です。例えば、「申請期限を給与計算の締め日より前に設定する」「5,000円未満の交際費は事前申請を不要にする」など、現状に即してルールを明確化・簡素化するだけで、申請のばらつきや差し戻しを減らすことができます。改定したルールは、社内ポータルや研修などを通じて全従業員に周知徹底することが不可欠です。誰にとっても分かりやすく、公平なルールを整備することが、円滑な運用の鍵となります。
4-3. 経費精算システムの導入
アナログな業務の課題を根本的に解決し、最大の効率化を実現するのが経費精算システムの導入です。システムを使えば、スマートフォンアプリからの写真撮影で領収書をデータ化し、外出先からでも申請・承認作業が完結します。入力されたデータは自動で仕訳され、会計ソフトに連携できるため、経理担当者の手作業はほぼゼロになります。初期費用や月額費用は発生しますが、業務時間の大幅な短縮やペーパーレス化によるコスト削減を考慮すれば、費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。
5. 失敗しない経費精算システムの選び方と比較ポイント
経費精算システムを導入する決断は、業務効率化に向けた大きな一歩ですが、自社に合わないシステムを選んでしまっては、かえって現場の混乱を招きかねません。各社から多様なシステムが提供されており、機能や料金体系も様々です。選定にあたっては、単に多機能なものを選ぶのではなく、自社の規模や業種、そして現在抱えている課題を解決できるかどうかという視点が不可欠です。ここでは、システム選びで失敗しないために、比較検討すべき重要なポイントを3つの観点から解説します。
5-1. 機能:自社の経費精算ルールに対応できるか
「システムに合わせて運用を変える」のではなく、「自社のルールにフィットするシステムかどうか」を見極めることが、失敗しない選定のカギです。承認フローや法対応など、実際の業務で直面する課題に柔軟に対応できるかをしっかり確認しましょう。
承認フローの柔軟性
まず確認すべきは、自社の承認フローにシステムが対応できるかです。例えば、「申請額に応じて承認者が増える」「特定のプロジェクトでは別の承認者が必要」といった複雑なルールがある場合、それらを柔軟に設定できる機能が必須です。システムのデモやトライアルを活用し、自社の運用をシミュレーションしてみることが重要です。
法改正への対応力
2022年から本格化した電子帳簿保存法や、今後のインボイス制度への対応も重要な選定基準です。法律の要件を満たす形で領収書の電子データを保存できるか、タイムスタンプ機能が付与されるかなどを必ず確認しましょう。法改正に迅速に対応してくれるベンダーを選ぶことで、将来にわたって安心して利用できます。
5-2. 操作性:誰でも直感的に使えるか
経費精算システムは、多くの従業員が日常的に利用する業務ツールです。だからこそ、ITスキルの有無に関わらず、誰もが迷わず使える操作性が求められます。システムの導入効果を最大限に引き出すには、使いやすさの視点からも慎重に選定することが重要です。
申請者・承認者の使いやすさ
システムは経理担当者だけでなく、全従業員が利用するものです。そのため、ITに不慣れな人でもマニュアルを読まずに直感的に操作できる、分かりやすいインターフェースかどうかが極めて重要です。特に、スマートフォンのアプリからの申請や承認がスムーズに行えるかは、営業職など外出の多い従業員の利便性に直結します。
導入・運用サポート体制
導入時の初期設定や、運用開始後にトラブルが発生した際のサポート体制も確認しましょう。電話やメールでの問い合わせに迅速に対応してくれるか、専任の担当者がつくかなど、サポートの手厚さは安心感に繋がります。導入事例などを参考に、自社と近い業種や規模の企業での評判をチェックするのも良い方法です。
5-3. 連携:会計ソフトなど既存システムと繋がるか
「せっかくシステムを導入したのに、結局手入力が必要になっている」――そんな事態を防ぐには、会計ソフトなど他ツールとの連携機能を事前にチェックすることが欠かせません。日々の業務をさらに効率化できるかどうかは、連携機能にかかっています。
会計ソフトとのAPI連携
経費精算システムの大きなメリットの一つが、会計ソフトとの連携による仕訳の自動化です。現在利用している会計ソフトとAPI連携が可能かを確認しましょう。連携できれば、承認された経費データをボタン一つで会計ソフトに取り込めるため、経理担当者の入力作業が不要になり、転記ミスのリスクも撲滅できます。
その他のツールとの連携
チャットツール(SlackやMicrosoft Teamsなど)と連携し、申請や承認の通知をチャットで受け取れる機能も便利です。また、法人カードや交通系ICカードの利用明細を自動で取り込める機能も、業務効率を大きく向上させます。自社で利用しているツールとの連携性を事前に確認することで、よりスムーズな運用が実現します。
6. 経費精算に関するよくある質問(FAQ)
経費精算の実務においては、判断に迷う細かい疑問が生じることがよくあります。ここでは、多くの人が抱きやすい質問とその回答をまとめました。ルールを正しく理解し、スムーズな精算業務に役立ててください。
Q1. 領収書ではなくレシートでも経費精算できますか?
結論から言うと、多くの場合レシートでも経費精算は可能です。現在の税法上、領収書とレシートに法的な優劣はありません。重要なのは「取引年月日」「取引金額」「取引内容」「書類の作成者(店名など)」が記載されていることです。これらの情報が明記されていれば、レシートは有効な証憑として認められます。むしろ、品目まで詳細に記載されているレシートの方が、何に使ったのかが明確で望ましいと考える企業も増えています。ただし、会社の規程で「必ず宛名付きの領収書が必要」と定められている場合は、それに従う必要があります。
Q2. 経費精算の不正を防ぐにはどうすればいいですか?
経費精算の不正を防ぐには、ルールの明確化とチェック体制の強化が有効です。まず、何が経費として認められ、何が認められないのかを具体的に示した経費規程を作成し、全社に周知徹底します。次に、申請内容をチェックする承認者の役割が重要です。私的な飲食やカラ出張がないかなどを厳しくチェックする体制を整えましょう。経費精算システムを導入すれば、法人カードの利用履歴と申請内容を突合したり、過去の申請パターンから異常値を検知したりする機能もあり、不正の抑止力として非常に効果的です。
Q3. 無料のテンプレートやアプリではダメなのでしょうか?
個人事業主や数名規模の会社であれば、Excelの無料テンプレートや個人向けの家計簿アプリでも対応は可能です。しかし、従業員数が増え、承認フローが複雑になると限界が見えてきます。無料ツールは、申請・承認・仕訳といったプロセスが分断されているため、結局は手作業での確認や転記作業が発生します。また、電子帳簿保存法などの法改正への対応や、内部統制の観点からも十分とは言えません。会社の成長を見据えるならば、一連の業務を連携させ、自動化できる有料の経費精算システムを導入する方が、長期的にはコスト削減と生産性向上に繋がります。
7. まとめ
本記事では、経費精算の基本から、具体的な書き方、そして業務を効率化するための方法までを解説しました。紙やExcelによる従来の方法は、申請者から経理担当者まで多くの従業員の負担となっています。これを解決するには、キャッシュレス化やルールの見直しに加え、経費精算システムの導入が最も効果的です。システム選定の際は、機能、操作性、連携性を軸に自社に最適なものを選びましょう。日々の面倒な業務から解放され、会社全体の生産性を高めるために、まずは自社の経費精算プロセスを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。


