更新日:2025/01/08
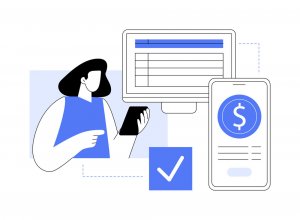
給与前払いサービスの基本的な仕組みやシステムの連携方法、導入や利用の流れを解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
給与の前払いを福利厚生の一環として導入する企業が増えています。しかし、給与前払いサービスにはさまざまなサービス会社があり、仕組みや導入方法などが分からない企業の担当者もいるでしょう。本記事では、給与前払いサービスの基本的な仕組みや導入の流れなど、給与前払いを導入する際に知っておきたいことを解説します。給与前払いの導入を検討中の担当者はぜひ参考にしてみてください。
【比較】おすすめの給与前払いサービス一覧
scroll →
| サービス名 | 企業名 | 特長 | 費用 |
|---|---|---|---|
| プリポケ | 株式会社マネーコミュニケーションズ |
|
立替払い型:導入費用0円、月額費用0円、前払い申請額×1.5% 直接払い型:月額固定料金1万円、前払利用毎 200円 |
| 前給 | きらぼしテック株式会社 |
|
初期導入費用:無料 月額費用:220円(前給を利用した1人当たり) |
| 即給 byGMO | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
|
要お問い合わせ |
| CRIA | 株式会社メタップスペイメント |
|
初期費用0円 月額費用0円 |
| Payme | 株式会社ペイミー |
|
要お問い合わせ |
| フレックスチャージ | 株式会社三菱UFJ銀行 |
|
要お問い合わせ |
| Advanced pay SAISON | 株式会社セゾンパーソナルプラス |
|
要お問い合わせ |
| 早トク給与 | 楽天カード株式会社 |
|
要お問い合わせ |
| 前払いできるくんLITE | 株式会社Payment Technology |
|
要お問い合わせ |
| Q給 | 株式会社デジタルプラス |
|
月額費用:11,000円 システム利用料:550円 |
この記事の目次はこちら
給与前払いサービスの基本的な仕組み
そもそも給与前払いとは、本来給料日に受け取るはずの給与の一部を給料日より前に受け取れる制度のことです。給与の前借りとは異なり、前払いはすでに働いた分の給与を受け取るため、例えば、病気や冠婚葬祭などで急な出費があった際や給料日までの生活費が足りない場合にも自分の給与で対応できます。
給与の前払いは以前からあった制度ですが、近年導入する企業が増えている背景には、働き方やライフスタイルの多様化により、給与の受け取り方も日払いや週払いなどニーズが多様化していることが影響しています。人材不足が叫ばれる中、福利厚生の一環として給与の前払いを導入することは、従業員の会社への満足度を高め、求人応募数の増加や離職率の低下を図るためにも効果的です。
しかし、給与の前払いを行うには、申請の受付や勤怠情報の把握、前払い金の計算、支払い、給料日に支払う残金の計算など手間と時間がかかります。そこで、注目されているのが給与前払いサービスです。給与前払いサービスを利用すれば前払いにかかる手続きを自動化し、自社の負担を増やさずに前払いが導入可能です。
給与前払いサービスの基本的な仕組みは立替払いと自社払いに分けられます。それぞれの違いを解説します。
立替払い
立替払いは、給与前払いサービスを提供する事業者が前払い金を立て替えて支払います。立て替えた分は後で企業側に請求されます。自社で前払い金を用意する必要がないため、支払いサイクルの変更やキャッシュフローに影響しないところがメリットです。また、立替払いは賃金規定や労使協定の改正が必要なく容易に導入できるため、多くの給与前払いサービス提供事業者で採用されています。
立替払いのデメリットは、前払いサービスを利用時3〜6%程度の手数料が発生することや導入前に企業に対して与信審査があり、結果によっては導入できない可能性があることです。
自社払い
自社払いは給与前払いサービスを提供する事業者が勤怠状況の確認や前払い金の計算を行い、自社で前払い金を用意します。支払い方法には、従業員の口座へ直接振り込む方法や、従業員がATMから預託金を引き出す方法があります。
自社払いは、前払いサービスを利用する企業が事務処理を委託する手数料を支払うため、従業員の金銭的な負担が軽減できるところがメリットです。デメリットは、企業が前払い分の資金を用意する必要があることや、導入する際に賃金規定や労使協定を改定する必要があること、初期費用や運用コストがかかることなどがあります。
給与前払いサービスと給与ファクタリングの仕組みの違い
給与前払いと似たサービスに給与ファクタリングがあります。給料日前に現金化できる点は同じですが、給与前払いサービスは企業向けのサービスであるのに対して、給与ファクタリングは個人向け金融サービスのため仕組みが異なります。
給与ファクタリングは、未払いの給与を債権としてファクタリング事業者から現金を借りる仕組みです。金融サービスのため手数料が発生し、利用者は給料日には手数料を含めた金額をファクタリング事業者に返済しなくてはいけません。ファクタリングを受ける金額は過去の給与額から利用額が決まるため、利用金額と手数料の合計が給与を超える可能性があります。そうなると次の給料日前にはまたお金が足りなくなり給与ファクタリングを利用するという悪循環につながり、生活破綻に陥るリスクがあるため注意が必要です。
また、給与ファクタリングの仕組み自体は違法ではありませんが、貸金業に該当するため、事業者は貸金業登録を受けなくてはいけません。しかし、貸金業登録を行わずに行っているケースがあるとされており、手数料として利用額の15〜40%程度を請求されるケースがあります。月利15〜40%は年利にすると180〜480%程度になる可能性を含み、一般的な消費者金融の上限金利年18%程度と比較して非常に高額です。そのため、従業員が違法なファクタリング事業者を利用すると悪質な取り立て被害に遭う危険性もあります。
一方、給与前払いサービスは企業向けのサービスで従業員は福利厚生の一部として利用できます。このサービスで利用できる金額は、すでに働いた分に基づいており、貸金業に該当しません。そのため、給与以上の金額を支払うことなく過剰な手数料も発生しないため、利用者にとって負担の少ない仕組みです。
給与前払いサービスの導入と利用の流れ
給与前払いサービスを導入する流れと、サービス利用の流れを解説します。
給与前払いサービスの導入流れ
給与前払いサービスの一般的な導入の流れは次のとおりです。
1.申し込み、財務審査
給与前払いサービスを提供する事業者に申し込みを行い、財務審査を受けます。サービス内容によっては財務審査が不要なケースもあります。
2.契約
3.システム連携
給与前払いサービスを利用するには勤怠情報を連携させる必要があります。
4.従業員に対する説明とID発行
従業員対して前払いサービスを利用するための初期設定や利用方法の説明、利用する際に必要なIDを発行します。
5.利用開始
給与前払いサービスの申し込みから利用開始までにかかる期間は、利用する事業者やシステム連携にかかる日数などにより異なり、早ければ1週間程度で導入できますが、2カ月程度かかることもあります。
給与前払いサービスの利用の流れ
給与前払いサービスの利用の流れは次のとおりです。
- 従業員が前払い申請する
- 前払いサービス提供事業者または、勤務先企業が前払い金を振り込む
- 給料日に前払い分を差し引いた金額を振り込む
- 立替払いを利用した場合は、前払いサービス提供事業者に前払いした金額を支払う
給与前払いには、勤怠データを確認して支払い可能額や給料日に振り込む金額の計算が必要です。サービスと勤怠システムを連携させると、前払いにかかる手間が省けます。
給与前払いサービスは自社の管理システムと連携できることが大切
給与前払いには、勤怠データの管理が必要です。勤怠管理を手書きやエクセルなどで行っている場合や、勤怠システムを利用していても前払いサービスのシステムと連携できない場合は、定期的なデータの移行が必要で、手間がかかるだけでなく入力ミスの恐れがあります。
前払いに関する負担の軽減や人的なミスを防ぐためには、給与前払いサービスを導入する際に管理システムを導入したり、スムーズに連携できる給与前払いサービスを選だりすることが大切です。給与前払いサービスと自社の管理システムを連携できれば、前払い可能額の計算や給料日に支払う金額の計算が容易になります。
給与前払いサービスを連携させる方法
自社の勤怠データを給与前払いサービスと連携させる方法には、API連携とCSV連携があります。事業者により連携方法が異なるため、利用しやすいところを選びましょう。
API連携
APIは、Application Programming Interfaceの頭文字を取った略称です。アプリとプログラムをつなぐものという意味があります。アプリケーションやシステムをAPIでつなげば、新たなシステムを開発する必要なく機能やサービスを拡張できます。また、API連携は自動でデータのやり取りができるため常に最新の情報の共有が可能です。
CSV連携
CSVは、Comma Separated Valuesの頭文字を取った略称です。コンマで区切られたデータという意味があり、テキストデータファイル形式のひとつです。CVSは互換性が高く、Excel・メモ帳・データベースソフト・メールなど多くのソフトにダウンロード可能で、閲覧や編集ができます。
CSVの編集は主にテキストエディタやExcelで行うため、使い慣れている方が多く導入が容易です。また、システム間に互換性がない場合でも連携でき、選択した範囲内のデータの更新が一括でできます。ただし、手入力が必要でリアルタイムでの情報共有はできないため、入力ミスや情報取得にタイムラグが生じる可能性があります。
給与前払いサービスにかかる費用相場
給与前払いサービスの利用には、初期費用・月額費用・振込手数料などがかかります。ここでは、給与前払いサービスにかかる費用を解説します。サービス提供事業者により発生する費用は異なるため、複数の事業者を比較して自社に合うところを選びましょう。
初期費用
初期費用は給与前払いサービス導入にかかる費用です。前払いサービスを導入する際、サービスを受ける企業が負担します。事業者により無料の場合や数十万円必要な場合もあり、金額に幅があります。
月額費用
月額費用は毎月発生する基本料金です。システム利用料と呼ばれることもあり、サービスを受ける企業が負担します。月額費用は毎月一定額発生するタイプ、利用申請額に応じて定率の金額が発生するタイプ、前払いを利用した人数に応じて定額が発生するタイプがあります。
費用相場は月額制の場合1万〜6万円程度、定率型の場合申請金額の3〜6%程度、利用人数の場合1人当たり100〜400円程度が相場です。月額制では費用が毎月一定ですが、定率型の場合、利用金額が増えると月額費用も増えます。定額型の場合は、利用人数が増えると月額費用が高くなります。自社の前払い利用状況に応じて選ぶことが大切です。
振込手数料
振込手数料は、前払い給与を振り込む際に発生する料金です。前払いを申請した従業員が支払います。振込手数料は1回に付き200〜600円程度が相場です。特定の口座を開設するなど一定の条件をクリアすると振込手数料が無料になるケースもあります。
給与前払いサービスは事業者による仕組みの違いを比較して選ぼう
給与前払いサービスの導入は企業にも従業員にもメリットがあります。企業側のメリットとしては、前払いにかかる手間が軽減、福利厚生の充実による求人数の増加見込みなどが挙げられます。従業員側のメリットは、急に必要なときなどに給与が受け取れるため、金銭的な安定が得られキャッシングなど金銭的なリスクを避けられることです。
しかし、前払いサービスは事業者により仕組みが異なります。手数料が高かったり、利便性が悪かったりすると利用されず、費用対効果が低くなる可能性があるため、複数のサービスを比較し、自社のシステムとの相性や従業員のニーズに適したものを選ぶことが大切です。
【2025年最新比較表あり】給与前払いサービス10社を比較!特徴やメリット、選ぶときのポイントを解説
【比較】おすすめの給与前払いサービス一覧
scroll →
| サービス名 | 企業名 | 特長 | 費用 |
|---|---|---|---|
| プリポケ | 株式会社マネーコミュニケーションズ |
|
立替払い型:導入費用0円、月額費用0円、前払い申請額×1.5% 直接払い型:月額固定料金1万円、前払利用毎 200円 |
| 前給 | きらぼしテック株式会社 |
|
初期導入費用:無料 月額費用:220円(前給を利用した1人当たり) |
| 即給 byGMO | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
|
要お問い合わせ |
| CRIA | 株式会社メタップスペイメント |
|
初期費用0円 月額費用0円 |
| Payme | 株式会社ペイミー |
|
要お問い合わせ |
| フレックスチャージ | 株式会社三菱UFJ銀行 |
|
要お問い合わせ |
| Advanced pay SAISON | 株式会社セゾンパーソナルプラス |
|
要お問い合わせ |
| 早トク給与 | 楽天カード株式会社 |
|
要お問い合わせ |
| 前払いできるくんLITE | 株式会社Payment Technology |
|
要お問い合わせ |
| Q給 | 株式会社デジタルプラス |
|
月額費用:11,000円 システム利用料:550円 |


