社員食堂のデメリットとは?代替案についてもご紹介

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「社員食堂=福利厚生の象徴」と考えられてきた一方で、最近ではその“維持コスト”や“運用負担”に課題を感じる企業も増えています。
本記事では、社員食堂の代表的なデメリット――初期投資や運営コストの高さ、利用率の低下、メニューのマンネリ化、衛生・人員管理の手間など――を具体的に解説します。さらに、そうした課題を解消しながらも“食の福利厚生”を実現できる代替手段として、宅配弁当・社食ケータリング・置き型社食サービスといった新しい選択肢もご紹介。
「コストを抑えつつ、社員満足度を下げない」オフィスランチ体制を検討中の担当者は、ぜひ参考にしてください。
【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
設置型 |
Office Stand By You
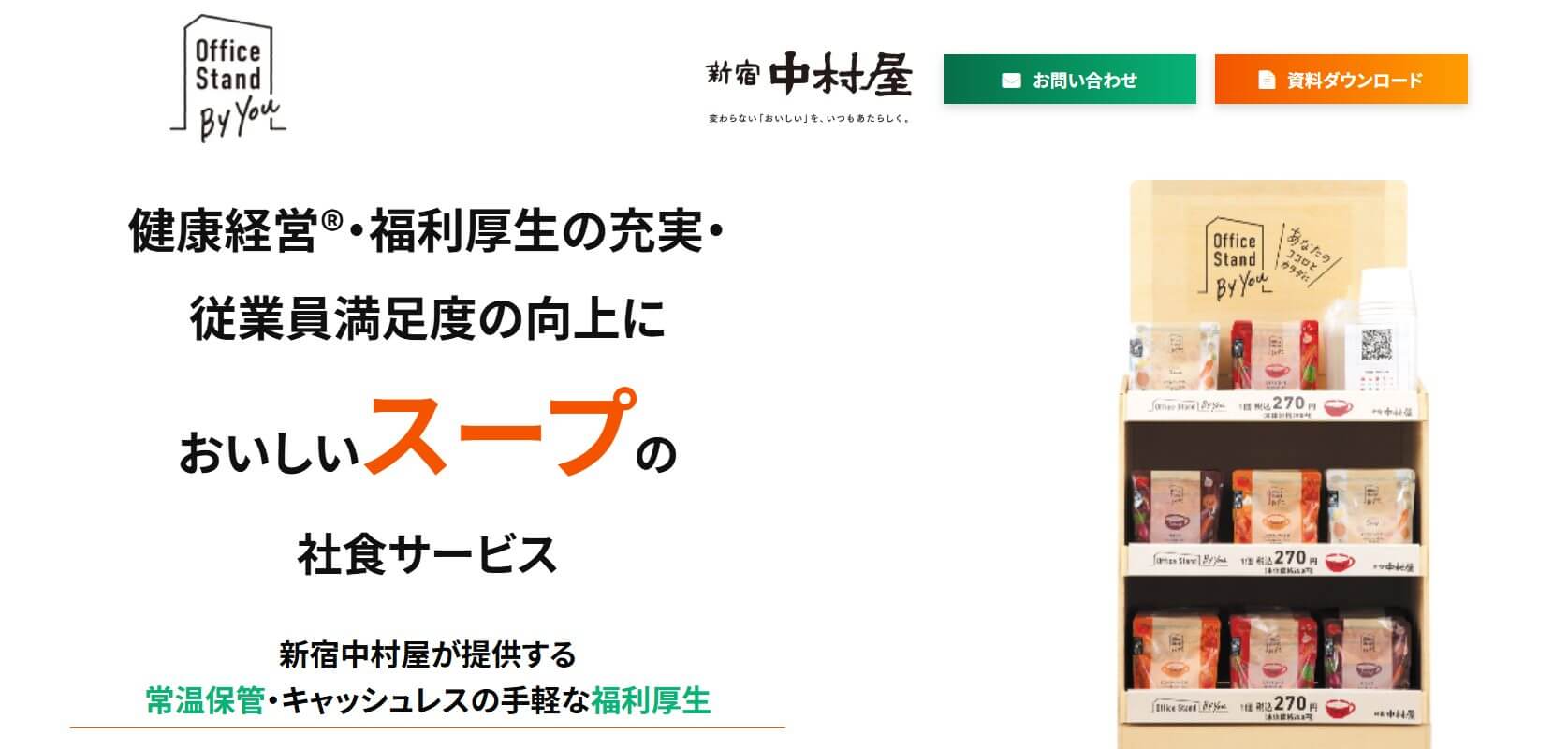
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
設置型 |
シャショクラブ

|
|
初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |
お弁当型 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |
設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| ESキッチン |
|
月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 設置型 |
| パンフォーユー オフィス |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| どこでも社食 |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| 社食ごちめし |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| まちなか社員食堂 |
|
初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |
外食補助型 |
| 筋肉食堂Office |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |
| 社食DELI |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| おべんとうの玉子屋 |
|
お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |
お弁当型 |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |
お弁当型 |
| お弁当.TV |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| はらぺこ |
|
要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |
| nonpi Chef’s LUNCH |
|
要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |
| 500円出張食堂 |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |
出張社内提供型 |
| DeliEats DR |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |
お弁当型 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
設置型 |
社員食堂導入の背景と期待される効果
企業の福利厚生として「社員食堂」は長年人気のある施策です。
社員が安心して食事を取れる環境を整えることで、健康経営の推進、従業員満足度の向上、コミュニケーションの活性化など、企業文化や働き方の質を高める効果が期待されます。
特に大企業や製造業では「社食=企業の魅力の象徴」として位置づけられており、採用や定着率の強化にも寄与してきました。
しかし、現代の働き方はリモートワークやフレックス制が普及し、出社人数が日々変動する状況です。
この変化によって、従来型の社員食堂が抱えるコスト構造や運用体制に歪みが生じています。
多くの企業が「福利厚生としての魅力」と「経営的な負担」の両立に悩むなか、社員食堂の導入可否は慎重に検討すべき経営判断のひとつになっています。
この記事では、社員食堂のデメリットを**企業視点(コスト・運用・スペース)と従業員視点(公平性・利便性・満足度)**の両面から整理し、さらに現代的な代替手段も紹介します。
導入を検討する際に見落としがちなリスクを可視化し、より効率的で公平な「食の福利厚生」を構築するための参考としてご活用ください。
この記事の目次はこちら
企業側が直面する社員食堂の4大デメリット
社員食堂は一見すると社員のモチベーション向上やブランド強化につながるように見えますが、導入・運用コストの高さや経営リスクを伴います。
ここでは、特に企業側が注意すべき4つの主要課題を解説します。
1. 莫大な初期投資と高額なランニングコスト
社員食堂を設置するには、厨房機器(コンロ・冷蔵庫・食器洗浄機など)、給排水・換気設備、内装工事などの大規模なインフラ整備が必要です。
初期投資は数千万円〜億単位に及ぶこともあり、中小企業には現実的な負担ではありません。
また、導入後も人件費・光熱費・食材費・メンテナンス費などの固定的なランニングコストが継続します。
特に2020年代以降、食材価格やエネルギー費の上昇が続いており、赤字運営に陥る企業が増加傾向にあります。
直営方式ではすべての費用を自社が負担し、委託方式でも運営委託費は年間で数百万円〜数千万円。
利用率が低下すれば損益分岐点を割り込み、固定費が利益を圧迫する構造になりやすい点が最大の課題です。
2. スペース確保とインフラ制約の問題
社員食堂には調理・提供・休憩スペースを合わせて100〜300㎡以上の面積が必要になるケースが一般的です。
都市部のオフィスでは空きスペースの確保が難しく、仮に確保できても高額な賃料が発生します。
さらに、厨房を設けるには給排水・ガス・排気設備が必須です。
ビル構造上これらが制限される場合、設置自体が不可能だったり、追加工事で多額の費用が発生したりします。
また、移転やフロア改修の際には撤去費・再設置費がかかり、長期的な柔軟性を損なう要因にもなります。
オフィススペースが貴重な都市型企業にとって、「社員食堂=固定化されたスペースコスト」として負担になりやすいのです。
3. 運営・衛生管理の難しさとリスク
社員食堂の運営は、単に食事を提供するだけではありません。
食材調達、在庫管理、調理、配膳、清掃、廃棄物処理など複数の工程を日々管理する必要があります。
加えて、HACCPなど衛生基準への対応、人員教育、異物混入リスクへの対策など、リスクマネジメント業務も不可欠です。
外部委託の場合も、発注管理や品質監督は企業の責任のもとで行わなければならず、「完全委託=手離れが良い」わけではないのが実情です。
もし衛生事故や異物混入が起これば、従業員の安全リスクだけでなく、企業ブランドに深刻なダメージを与えます。
食堂運営は日常業務と異なる専門性を必要とするため、管理部門の業務負荷増大は避けられません。
4. 費用対効果(ROI)の低下と利用率の伸び悩み
社員食堂のROIは「利用率」に大きく左右されます。
しかし、リモートワークやフレックス勤務の普及で出社率が低下し、食堂の利用者数が減少傾向にあります。
導入時に想定した稼働率を維持できず、固定費がそのまま赤字要因になるケースも珍しくありません。
また、メニューや味への不満が積み重なると、社員が外食やコンビニに流れ、食堂の稼働率がさらに下がる「負のスパイラル」に陥ります。
利用率が50%を下回ると、運営コストに対して利益を確保するのが難しくなり、費用対効果が著しく悪化します。
このように、社員食堂は「稼働率の維持」と「固定費の圧縮」が常にトレードオフの関係にあり、持続可能な運営を維持するには継続的な改善と投資が必要になります。
従業員側が感じる社員食堂の4つの不満・不公平感
社員食堂は一見“従業員のため”の制度に見えますが、運用次第では逆に不公平感や不満の温床となることもあります。
ここでは、社員視点で代表的な4つの課題を整理します。
1. 利用できる人が限られる(公平性の問題)
社員食堂の営業は多くの場合、平日昼のみです。
そのため、シフト勤務者・外勤営業・在宅勤務者は利用が難しく、福利厚生の恩恵を受けられません。
一方で、常時オフィス勤務の社員だけが食堂を利用できる構造は、**「社内格差」**を生みます。
福利厚生は本来、全従業員が公平に享受できるものであるべきですが、社員食堂はこの原則を満たしにくい制度です。
結果として「使えない制度への不満」や「優遇される部署への不信感」を招くリスクがあります。
2. 混雑・待ち時間・騒音によるストレス
利用時間が昼休みに集中するため、食堂内はピーク時に混雑します。
席を確保できない、配膳まで時間がかかる、落ち着いて食事ができないなど、快適性が損なわれる場面も多いです。
また、混雑を避けるために休憩時間を調整する必要が生じ、勤務スケジュールに影響する場合もあります。
この結果、「かえってストレスが増えた」と感じる社員も少なくありません。
3. メニューの固定化・食の多様性への対応不足
社員食堂ではコストと調理効率を優先するため、メニューが固定化しやすい傾向にあります。
和定食・カレー・麺類といった定番中心になり、利用者の嗜好や健康志向の変化に対応しづらくなります。
また、アレルギー、ベジタリアン、ハラール対応など、多様な食文化・宗教的背景を持つ社員への対応が難しいのも現実です。
結果として「飽きる」「選べない」「対応してもらえない」という声が上がり、利用離れを招く要因となります。
4. 味・価格・品質への不満
多くの企業で共通する課題が、「おいしくない」「値上がりした」「コスパが悪い」といった不満です。
運営を外部委託している場合、メニュー品質は業者依存となり、社員の声を反映しにくい構造です。
さらに、材料費高騰による価格改定やメニュー縮小が重なると、社員の満足度は急激に下がります。
こうした不満が長期化すると、「利用しない社員」が増加し、最終的に投資効果の低下につながります。
社員食堂を「魅力的な福利厚生」として維持するには、継続的な品質改善と社員の意見反映が不可欠です。
社員食堂のデメリットを補う3つの代替案
社員食堂は理想的な福利厚生の一つですが、前述の通り「初期費用」「運用コスト」「公平性」「利用率」などの課題を抱えています。
こうした問題を解決するため、現在はより柔軟で効率的な**“次世代型食の福利厚生”**へと移行する企業が増えています。
ここでは、社員食堂のデメリットを補う3つの代表的な代替案を紹介します。
1. 宅配弁当・置き型社食サービス
最も導入が進んでいるのが、宅配型社食・置き型社食サービスです。
企業は厨房を設ける必要がなく、業者が日替わり弁当や惣菜をオフィスに届ける、または冷蔵庫に補充するだけで運用できます。
特徴とメリット
- 初期費用がほぼゼロ:厨房・調理設備が不要。契約初月から稼働可能。
- 管理工数が小さい:在庫補充・回収・精算は業者が対応。
- 利用時間の自由度:従業員は自分のペースで購入・利用できる。
- 低コストで維持可能:1品100〜150円前後の惣菜から選べるサービスもある。
補えるデメリット
- 設備投資や運営負担といったコスト面の課題を解消。
- 営業時間や混雑に左右されず、シフト勤務や時差出勤にも対応。
- 小規模オフィスでも導入可能。
注意点
- 冷蔵・冷凍中心のため、「温かい食事を食べたい」というニーズには対応しづらい。
- メニューが限定的で、数か月単位でのマンネリ化が起こりやすい。
代表的なサービス例
オフィスおかん/OFFICE DE YASAI/弁当デリ など。
置き型社食は社員食堂の「スペース・コスト・運用負荷」という三重苦を解消する現実的な選択肢であり、
とくに中小企業や複数拠点企業で採用が広がっています。
2. 社食ケータリングサービス(キッチンレス社食)
次に注目されているのが、キッチンレス型の社食ケータリングサービスです。
専門業者が調理済みの温かい料理をオフィスまで運び、ブッフェ形式で提供・撤収まで行う方式です。
特徴とメリット
- 工事不要:厨房やガス設備なしで温かい料理を提供可能。
- 高品質なメニュー:有名レストラン監修や健康志向メニューなど多彩。
- 柔軟な運用:週1回・月数回など、開催頻度を自由に設定できる。
- コミュニケーション促進効果:ブッフェ形式のため、社内交流の場としても機能。
補えるデメリット
- 「温かい食事が取れない」という課題を解消。
- メニューの多様化・味の品質維持にも対応。
- 設備やスペース制約の問題を大幅に緩和。
注意点
- 一定の人数(10〜30食以上)が必要なケースが多く、小規模利用では割高になりやすい。
- 設営と撤収に時間がかかるため、オフィスの空間を一時的に占有する。
代表的なサービス例
nonpi Chef’s LUNCH/セカンドキッチン/イージーケータリング など。
社食ケータリングは、「温かい食事を提供したいが固定型の社食は難しい」という企業に最適な中間ソリューションです。
近年ではIT企業やスタートアップを中心に導入が拡大しており、**“工事不要で導入できる社食”**として注目されています。
3. デジタル食事補助制度(外部利用型)
社員食堂を持たず、従業員が外部の飲食店やデリバリーサービスで食事を取れるようにする制度です。
企業は社員の食事代の一部を補助する仕組みを導入し、チケットやアプリを通じて支援します。
特徴とメリット
- 導入が非常に簡単:契約・発行手続きのみで即時開始可能。
- 全国対応:在宅勤務者・地方拠点社員も平等に利用可能。
- 利用者の自由度が高い:好きな時間・場所で利用でき、メニューの多様性も確保。
- 税制優遇が受けられるケースもある:一定条件を満たせば福利厚生費として経費処理可能。
補えるデメリット
- 社員食堂が抱えていた「公平性の欠如」を完全に解消。
- 出社・在宅・外勤を問わず、全社員が等しく制度を活用可能。
- メニューや店舗選択の自由により、満足度が向上。
注意点
- 社内での“共食”文化は生まれにくく、コミュニケーション促進効果は限定的。
- 自由度が高いため、栄養バランスや健康志向のコントロールは難しい。
代表的なサービス例
エデンレッド/チケットレストラン/ごちクル for Business など。
在宅勤務が定着する現代では、こうした**「場所に縛られない福利厚生制度」**が注目されています。
代替案を比較する際の評価軸
代替施策を選ぶ際には、単に「コストが安い」「導入が早い」だけで判断するのは危険です。
自社の課題・目的・働き方に対して最も適した制度を選定するため、以下の評価軸で検討を行いましょう。
1. コスト構造の透明性
初期費用・月額利用料・補助率・最低注文数などの総コストを把握することが重要です。
特に固定費を抑え、従量課金型で運用できる仕組みを選ぶことで、出社率変動にも柔軟に対応できます。
2. 利用率と運用負荷
社員食堂のように「利用率の低下が赤字化につながる構造」を避けるため、利用率に応じて支払いが変動する仕組みが理想です。
また、業者が補充・精算を自動で行うタイプを選ぶと、管理部門の運用工数を80%以上削減できます。
3. 公平性・働き方への適合性
出社・在宅・外勤など、異なる勤務形態の社員が平等に利用できるかを確認しましょう。
特にハイブリッド勤務が進む企業では、「在宅社員も利用できる」制度が必須条件となります。
4. 健康経営との親和性
健康経営を推進している企業では、管理栄養士監修メニューやカロリー表示の有無も比較項目になります。
食の福利厚生を単なる食事提供にとどめず、健康支援制度として活用する視点が重要です。
5. 柔軟性・拡張性
企業規模や拠点数の増減に合わせて、導入規模を柔軟に変更できるサービスを選びましょう。
契約期間・最低利用人数・キャンセルポリシーも事前に確認しておくことが重要です。
社員食堂に代わる制度導入のステップ
代替施策を検討し、実際に導入するまでの基本ステップを以下にまとめます。
- 目的を明確化する
→ コスト削減、健康経営、従業員満足度の向上など、制度導入のゴールを定義します。 - 現状を分析する
→ 社員食堂の利用率、費用、スペース活用状況、社員アンケート結果を整理。 - 候補サービスを比較する
→ 各代替案の費用・対応エリア・提供方式を3〜5社で比較検討します。 - トライアル導入で検証
→ 実際の利用状況・満足度・業務負荷を短期的に検証し、問題点を可視化します。 - 本格導入・制度設計
→ 利用条件、補助額、支払い方法、キャンセルルールを明文化し、全社周知を行います。 - 定期評価と改善
→ 導入後も利用率やコストをモニタリングし、サービス変更やプラン見直しを定期的に実施。
このプロセスを踏むことで、社員食堂を廃止・縮小する場合でも混乱を最小限に抑えられます。
導入時に注意すべきリスク
代替案を選ぶ際は、以下のリスクを事前に把握しておくことが成功の鍵です。
- 業者依存リスク:特定のサプライヤーに依存しすぎると、価格改定や契約変更時に不利になる。
- 品質・衛生トラブル:ケータリングや宅配では温度管理・異物混入リスクを軽視しない。
- 利用格差リスク:拠点間や在宅社員との利用条件の差が不公平感を生む。
- 社内周知不足:制度変更時の説明不足で、利用率が上がらないケースもある。
これらを回避するには、制度設計と周知計画をセットで進めることが不可欠です。
まとめ
社員食堂は、従業員の健康促進や職場の一体感づくりに貢献してきた一方で、
高額な初期投資・固定費負担・スペース制約・利用率低下といった構造的デメリットを抱えています。
特にリモートワークが定着した現在、従来型の社員食堂は「全員に公平な制度」として維持することが難しくなっています。
その代わりとして、宅配弁当/置き型社食/社食ケータリング/デジタル食事補助制度など、
より柔軟で低コストな代替施策が注目を集めています。
これらを上手に組み合わせることで、コスト最適化・健康経営・従業員満足度のすべてを同時に実現することが可能です。
制度導入の目的を明確にし、トライアル検証と継続的な改善を行うことで、
「社員食堂に代わる最適な食の福利厚生」を自社の強みに変えることができるでしょう。
【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
設置型 |
Office Stand By You
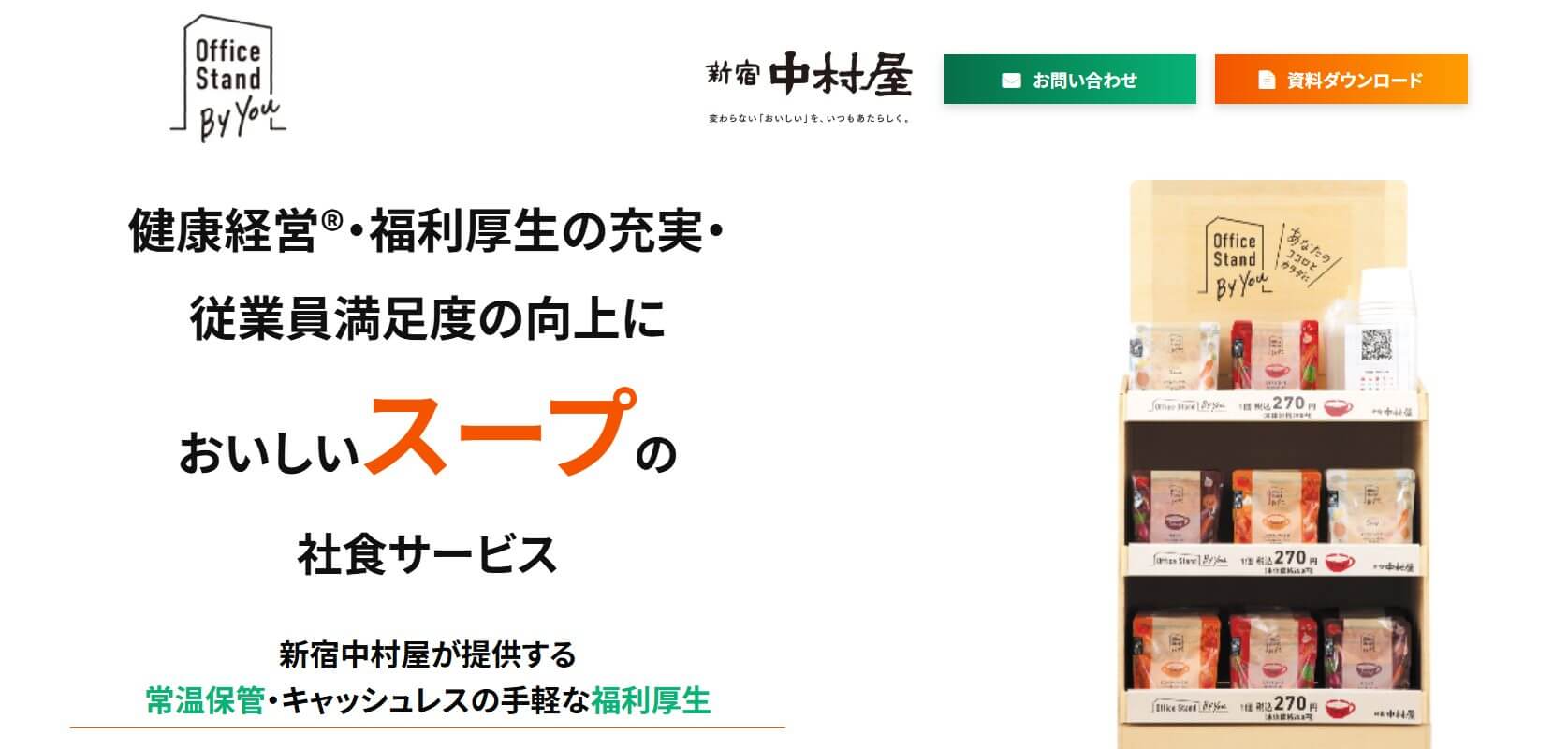
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
設置型 |
シャショクラブ

|
|
初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |
お弁当型 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |
設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| ESキッチン |
|
月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 設置型 |
| パンフォーユー オフィス |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| どこでも社食 |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| 社食ごちめし |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| まちなか社員食堂 |
|
初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |
外食補助型 |
| 筋肉食堂Office |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |
| 社食DELI |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| おべんとうの玉子屋 |
|
お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |
お弁当型 |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |
お弁当型 |
| お弁当.TV |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| はらぺこ |
|
要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |
| nonpi Chef’s LUNCH |
|
要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |
| 500円出張食堂 |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |
出張社内提供型 |
| DeliEats DR |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |
お弁当型 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
設置型 |


