福利厚生で人気の食事補助が非課税となる要件とは? 食事代の上限額や注意点などを解説


【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
企業の福利厚生の一つとして、食事補助を検討している総務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。福利厚生として食事補助を導入すると、従業員の健康維持や満足度の向上につながる他、食事補助の額が非課税になり節税効果を得られる可能性があります。
しかし食事補助の額を非課税にするには、一定の要件を満たさなければなりません。そこで本記事では、食事補助で非課税になる要件や注意点、食事補助を導入するまでの流れなどを詳しくご紹介します。
※本記事の情報は2025年10月時点の情報です
【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
設置型 |
Office Stand By You
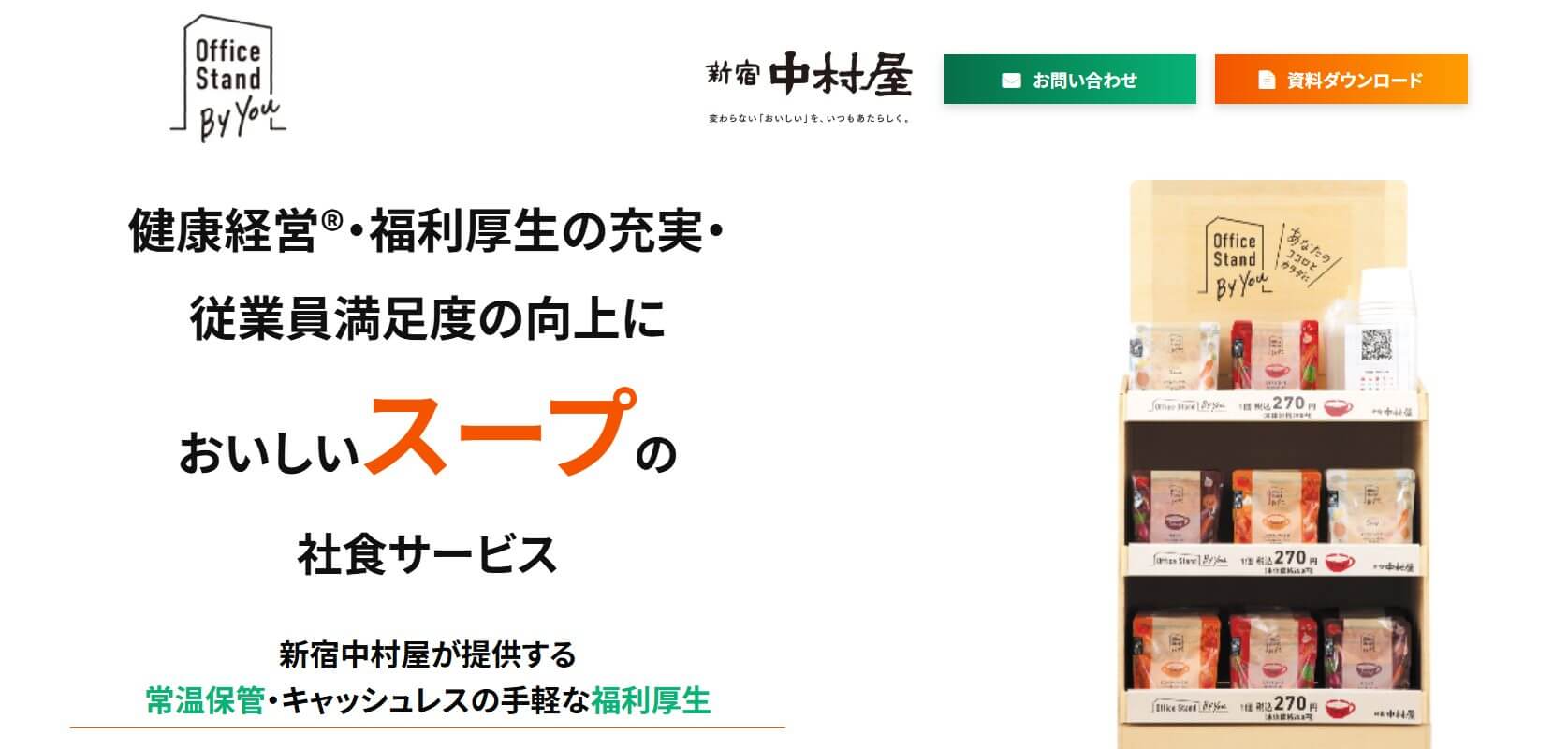
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
設置型 |
| シャショクラブ |
|
ライトプラン:5,000円/月 スタンダードプラン:9,820円/月 ゴールドプラン:13,500円/月 導入費:0円 |
お弁当型 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |
設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| ESキッチン |
|
月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 設置型 |
| パンフォーユー オフィス |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| どこでも社食 |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| びずめし |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| まちなか社員食堂 |
|
初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |
外食補助型 |
| 筋肉食堂Office |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |
| 社食DELI |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| おべんとうの玉子屋 |
|
お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |
お弁当型 |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |
お弁当型 |
| お弁当.TV |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| はらぺこ |
|
要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |
| nonpi Chef’s LUNCH |
|
要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |
| 500円出張食堂 |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |
出張社内提供型 |
| DeliEats DR |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |
お弁当型 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
設置型 |
この記事の目次はこちら
食事補助とは?
食事補助とは、企業が従業員の食事にかかる費用の一部または全額を負担する福利厚生制度です。福利厚生は法律で定められている「法定福利厚生」と、企業が独自に設ける「法定外福利厚生」の2つに分けられ、食事補助は法定外福利厚生に該当します。
法定外福利厚生は、企業文化や従業員のニーズに応じて自由に設計できる点が特長です。ただし、食事補助では企業負担額が非課税になる要件が明確に定められているため、導入する際は事前に確認しておきましょう。
食事補助は課税対象になるの?
食事補助を導入する場合、条件によって課税対象となるのか非課税となるのかが変わります。課税対象となるケースは、以下の通りです。
- 食事補助の対象が全従業員ではない場合
- 食事代を現金で支給する場合(深夜勤務時などは例外)
- 社会通念上の常識の範囲内の金額ではない場合
例えば、企業の役員や一部の従業員だけが食事補助を受けている場合、給与扱いとなり課税対象になります。現金で食事代を受け取っている場合も、課税対象です。
「社会通念上の常識の範囲内」の明確な定義はありません。しかし、後述する「非課税にするための会社負担の上限」が3,500円(/月)であるため、社会通念上の常識の範囲の金額も3,500円以下と考えておくのがよいでしょう。国税庁も「企業が従業員に支給した食事について、当該食事の価額から実際に従業員から徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、経済的利益はない( = 給与として含まない)」としています(※)。
※参考:国税庁.「〔給与等とされる経済的利益の評価〕」.https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm ,(参照2025-10-17).
食事補助が非課税となる要件
食事補助を非課税で運用するには「全従業員が対象であること」「社会通念上の常識の範囲内の金額であること」に加えて、以下の2つを満たす必要があります(※)。
- 従業員が食事の価額の半分以上を負担している
- 企業が負担する金額(食事の価額 – 従業員が負担している金額)が、1カ月当たり3,500円(税抜)以下である
これらの要件を全て満たしていない場合、企業が負担した金額は全額、従業員の給与として課税されます。例えば、以下のようなケースでは課税対象となります。
<例1>
- 1カ月当たりの食事価額:5,000円
- 従業員の負担額:2,000円
- 企業の食事補助額:3,000円
この場合、5,000円の半額である2,500円以上を従業員が負担していません。非課税の要件を満たしていないため、企業負担分の3,000円は全額従業員への給与として課税されます。
<例2>
- 1カ月当たりの食事価額:9,000円
- 従業員の負担額:4,500円
- 企業の食事補助額:4,500円
上記の場合、1カ月当たりの企業の負担額が3,500円(税抜)以下に当てはまりません。そのため企業負担分の4,500円が全額、従業員への給与として課税されます。なお、3,500円を超えた分(1,000円分)が課税されるのではなく、会社負担額の全額(4,500円分)が課税対象となる点に注意してください。
※参考:国税庁.「No.2594 食事を支給したとき」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm ,(参照2025-10-17).
残業中や深夜勤務の場合は例外
上記でご紹介した食事補助が非課税になる要件には、例外があります。
残業中や深夜勤務(22時〜翌5時)の従業員に提供される食事補助については、全額が非課税対象です(※)。具体的には、残業時の夜食や早出勤務の際の朝食などが該当します。
ただし、原則として現金支給は認められず、現物支給(食事そのものの提供)が基本です。
深夜勤務で周辺に営業中の飲食店がなく現物支給が難しい場合のみ、1食当たり300円(税抜)を上限として現金で支給できます。
※参考:国税庁.「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」.https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/840726/01.htm ,(1984-7-26).
食事補助における非課税の上限が引き上げられるかも?
現在の非課税要件は、1984年の制度導入以来一度も改正されていません。そのため物価上昇や外食費の高騰などにより、実情に合わないという声が多く上がっており、将来的にはこの要件が変更になる可能性があります。
2025年8月29日には、経済産業省が「令和8年度税制改正要望」を公表し、食事補助制度の非課税上限額の引き上げについて言及しました(※)。社会情勢の変化を踏まえ、企業負担の上限額の見直しを求めています。
2025年末までには税制調査会で審議が行われ、民間企業や経済団体の意見も取り入れながら、調整が進められる見込みです。今後の審議や調整次第では、より柔軟で実態に即した要件に改正される可能性もあるため、定期的に最新の情報をチェックしておくことが大切です。
※参考:経済産業省.「令和8年度税制改正に関する経済産業省要望」.https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/zeisei_r/25082902.pdf ,(2025-08).
食事補助の消費税率に注意
食事補助には、お弁当の宅配型のものや社員食堂で食事を提供するものなど、さまざまな提供形態があります。提供形態によって消費税率が異なり、結果的に非課税要件を満たすかどうかも変わる可能性があるのです。食事補助を検討している場合は、消費税率にも注意しましょう。
ここからは、お弁当を購入・宅配する場合と社員食堂・飲食店で食事をする場合の2つのケースで詳細をご紹介します。
お弁当を購入もしくは宅配する場合
お弁当を購入または宅配する食事補助の場合、消費税には軽減税率8%が適用されます。以下の例で具体的に計算してみましょう。
<例>
- お弁当の価額(税込):500円(消費税8%)
- 従業員負担額:310円
- 1カ月当たりの提供日数:20日
- 1カ月当たりのお弁当の価額(税込):500円 × 20日 = 10,000円
- 従業員の負担額:310 × 20日 = 6,200円
- 消費税8%を除いた企業負担額:(食事価額総額 – 従業員負担額)÷1.08 = (10,000円 – 6,200円)÷1.08 = 3,518.518……円
10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなるので、企業の負担額は3,518円です。従業員の負担額が半分以上であるものの、企業負担額が3,500円(税抜)以下をクリアしていません。そのため会社負担額は課税対象となります。
社員食堂や飲食店で食事をする場合
企業の社員食堂や飲食店で食事をする食事補助の場合、消費税には標準税率10%が適用されます。以下の例で具体的に計算してみましょう。
<例>
- 食事の価額(税込):500円(消費税10%)
- 従業員負担額:310円
- 1カ月当たりの提供日数:20日
- 1カ月当たりの食事の価額(税込):500円 × 20日 = 10,000円
- 従業員の負担額:310 × 20日 = 6,200円
- 消費税10%を除いた企業負担額:(食事価額総額 – 従業員負担額)÷1.1 = (10,000円 – 6,200円)÷1.1 = 3,454.545……円
こちらも10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなり、企業の負担額は3,450円です。従業員負担額が半分以上かつ、企業負担額が3,500円(税抜)以下という非課税の要件を満たしています。
このように軽減税率の適用によって非課税要件をわずかに超えてしまうケースもあるため、事前にシミュレーションをした上でどのような提供形態の食事補助にすべきか考えることが大切です。
福利厚生として食事補助を導入するメリット
企業で食事補助を導入すると、さまざまなメリットがあります。ここからはメリットについて詳しくご紹介します。
従業員の健康を促進できる
忙しい環境や職場周辺に飲食店が少ない環境では、食事を抜いたり簡単なもので済ませてしまう従業員もいるでしょう。その結果、栄養バランスが崩れて体調を崩したり、集中力が低下したりする恐れがあります。
食事補助制度を導入すれば、手軽に健康的で栄養バランスの取れた食事を摂取できる環境を整えられます。野菜中心のメニューやカロリー表示のある食事を提供することで、従業員の健康促進につながるでしょう。
社内コミュニケーションのきっかけになる
社員食堂や社食サービスがあると自然と従業員が集まり、仕事中とは違う和やかな会話が生まれます。リラックスした雰囲気の中で会話が広がり、新しいアイデアが生まれたり課題解決のヒントを得られたりすることもあるでしょう。
社内コミュニケーションのきっかけとなり、企業全体のチームワークや組織力の向上を図れます。
従業員満足度が向上する
食事補助を導入すれば、従業員は食事代を節約できる上に、バランスの良い食事を取りやすくなります。また混雑した飲食店に出向く必要がなくなり、休憩時間を有効に使えるようになるでしょう。
このような小さな積み重ねが従業員満足度を高め、離職率の低下や定着率の改善につながる可能性があります。
採用の際のアピールポイントになる
福利厚生の充実度は、求職者が企業を選ぶ際の判断材料の一つです。食事補助制度を設けている企業は、求職者に「従業員の生活を支援してくれる会社」というポジティブな印象を与えられます。
他社との差別化要素にもなり、採用活動におけるアピールポイントになるでしょう。
節税につながる
先述した通り、食事補助は一定の要件を満たせば非課税扱いにできます。従業員側は非課税となることで所得税の負担が増えず、企業側は福利厚生費として経費計上できるため法人税の負担を軽減可能です。
要件を満たすことで、従業員と企業双方にとってメリットがあります。
食事補助の主な種類
一口に食事補助といっても、その提供形態は多岐にわたります。企業の規模やオフィス環境、従業員数などによっても適した形態は異なるため、自社の状況に合わせて選びましょう。
ここからは、提供形態の主な種類についてご紹介します。
設置型
設置型の食事補助は、オフィス内に冷蔵庫や冷凍庫、常温ラックなどを設置して、食品をストックするタイプのものです。従業員は好きなタイミングで商品を購入・利用できるため、忙しい業務の合間でも手軽に食事を取れます。
冷凍のお弁当やスープ、サラダなど栄養バランスを考慮したメニューが豊富なサービスもあり、設備投資が比較的少ないです。いつでも利用できるので、夜勤やフレックスタイム制を設けている企業に適しています。
提供型
提供型の食事補助は、オフィス内の一角を活用し、決まった時間に温かい食事を提供するタイプのものです。
専用の社員食堂を持たない企業でも、会議室や休憩スペースさえあれば利用できます。従業員はできたての料理をその場で受け取ることができ、コミュニケーションの場にもなりやすいでしょう。
一方で提供時間が決まっているため、シフト勤務など柔軟な勤務体系のある職場では運用スケジュールの工夫が必要です。
お弁当型(宅配型)
お弁当型(宅配型)の食事補助は、指定の時間にお弁当がオフィスへ配達されるタイプのものです。中には、社内でお弁当が販売されているものもあります。
従業員は外出せずにお弁当を購入できるので、混雑する飲食店やコンビニエンスストアに並ぶ手間を省けます。
外食補助型(食費チケット型)
外食補助型の食事補助は、提携する飲食店やコンビニエンスストアなどで利用できる電子チケットやICカードを配布するタイプのものです。従業員は、提携先の店舗で自由に食事を選び、割引価格で利用できます。
リモートワークを導入している企業や全国に拠点を持つ企業でも、全従業員に平等に利用してもらえる点がポイントです。クラウド型で利用データを可視化できるサービスもあり、利用状況を分析して制度改善につなげることも可能です。
社員食堂
社員食堂は、社内で働く従業員のために企業が設置・運営する食事補助施設です。温かい食事を安価に提供できる点が魅力で、規模の大きい企業を中心に導入されています。
食堂の運営には設備投資やランニングコストがかかるものの、従業員の満足度や健康促進、社内交流の活性化など得られる効果も大きいのがポイントです。また周辺に飲食店が少ない地域や、出退勤時刻以外の従業員の入退室にリスクがある企業にも適しています。
福利厚生として食事補助を導入する際の流れ
食事補助を導入する際は提供形態やサービスを選ぶだけではなく、社内への周知や運用体制の構築が重要です。ここからは、福利厚生として食事補助を導入する際の大まかな流れをご紹介します。
1. 食事補助の形態・提供方法を検討する
まずは従業員の現状とニーズを調査し、制度導入の目的を明確化してください。社内でアンケートやヒアリングを行い「オフィス周辺に飲食店が少ない」「ランチ代が高い」「健康的な食事が取りにくい」など、どのような課題があるのかを把握しましょう。
現状の課題を基に、食事補助の提供形態を検討します。従業員が利用しやすい提供形態にすることで、導入後の定着率を高められるでしょう。
2. 食事補助の予算を決める
次に、先述した食事補助の非課税要件を踏まえて予算を設定します。「従業員負担額が半分以上」「企業負担額が月額3,500円以下」という基準を満たしつつ、従業員が満足できる補助レベルを決めてください。
費用対効果を見極めつつ、継続的に運用できる現実的な予算設定を行いましょう。
3. 導入前にトライアルを実施する
導入前には、一定期間のトライアルを実施するのがおすすめです。トライアル期間中に従業員の利用率や満足度、実際のコストなどを確認しましょう。その上で運用体制や提供メニューなどを調整することで、導入後の定着率の向上につながります。
4. 導入・運用する
トライアルを実施して本導入が決まったら、社内説明会を実施して従業員に目的や利用方法などを周知しましょう。また管理体制を確立させ、規定の整備も行ってください。就業規則や福利厚生規程に食事補助制度を明記することで、全従業員との合意形成を図れます。
さらに食事補助の導入後も定期的に効果測定を行い、利用状況や従業員の意見を反映しながら改善を続けることが大切です。継続的な運用改善により、福利厚生としての価値を高められます。
まとめ
食事補助は、従業員の健康維持や満足度向上につながる福利厚生の一つです。一定の要件を満たすことで非課税になり、節税効果も得られます。導入する際には、非課税要件や提供形態などをしっかり把握した上で、自社に適した食事補助のサービスを選びましょう。
また食事補助のサービスにはさまざまなものがあります。自社に合ったサービスを見つけたい場合は、費用や提供形態、特長などを比較できる以下の記事を参考にしてみてください。無料トライアルを実施しているサービスもあるので、少なくとも3つのサービスを選んで、資料請求・問い合わせをして詳細を確認するのがおすすめです。
【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
設置型 |
Office Stand By You
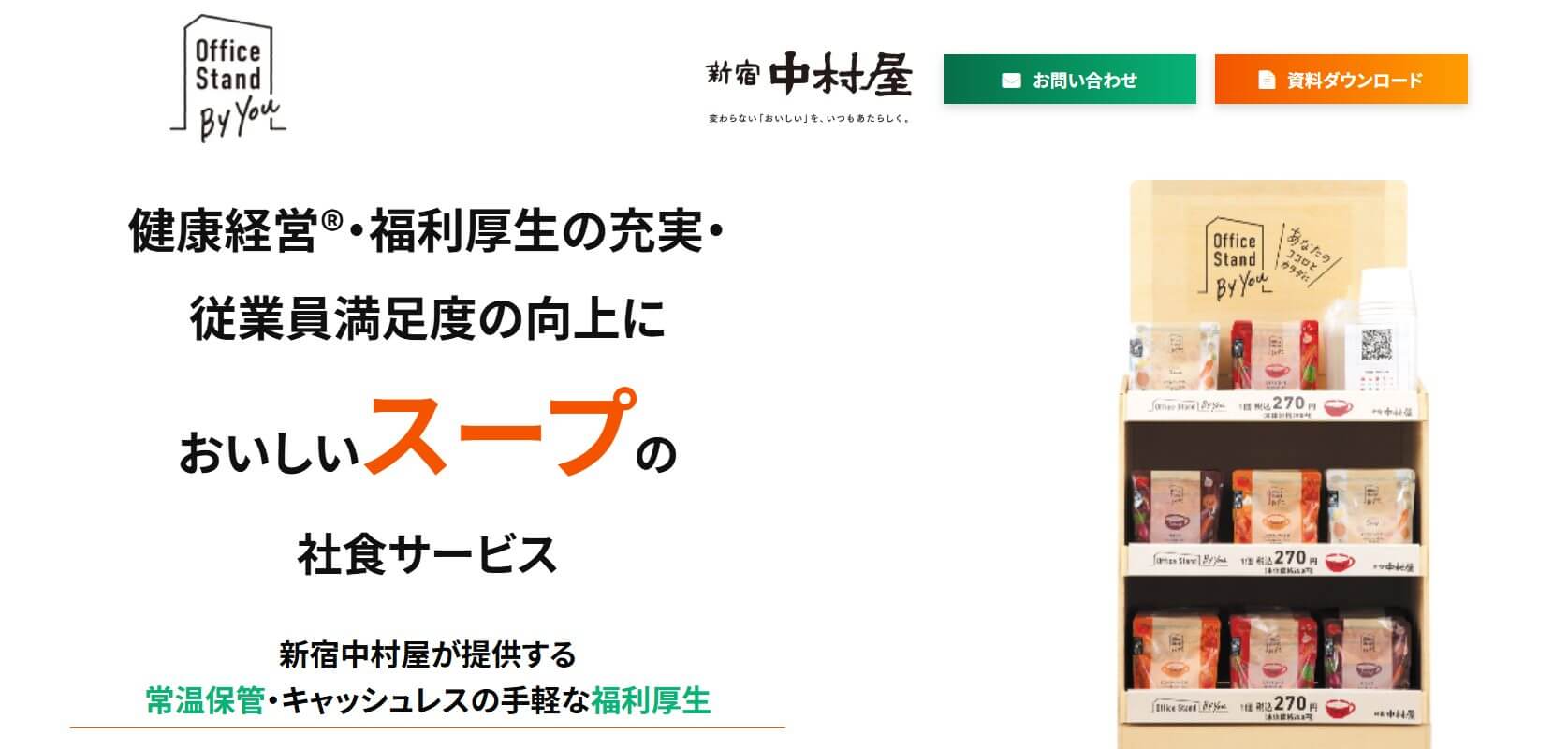
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
設置型 |
| シャショクラブ |
|
ライトプラン:5,000円/月 スタンダードプラン:9,820円/月 ゴールドプラン:13,500円/月 導入費:0円 |
お弁当型 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |
設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| ESキッチン |
|
月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 設置型 |
| パンフォーユー オフィス |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| どこでも社食 |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| びずめし |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| まちなか社員食堂 |
|
初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |
外食補助型 |
| 筋肉食堂Office |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |
| 社食DELI |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| おべんとうの玉子屋 |
|
お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |
お弁当型 |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |
お弁当型 |
| お弁当.TV |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| はらぺこ |
|
要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |
| nonpi Chef’s LUNCH |
|
要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |
| 500円出張食堂 |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |
出張社内提供型 |
| DeliEats DR |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |
お弁当型 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
設置型 |

