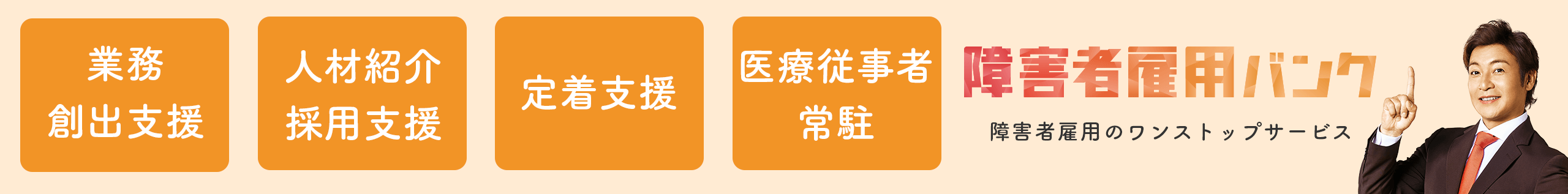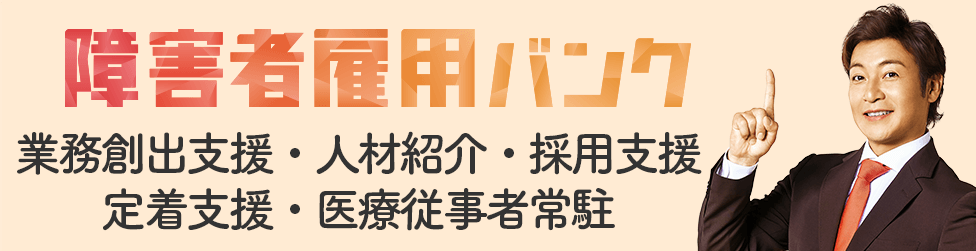『チャレンジ雇用』とは?メリット・デメリットから活用の全手順まで徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに:障害者雇用、「最初の一歩」の不安を解消する戦略的制度
企業の持続的成長において、ダイバーシティ&インクルージョン、とりわけ障害者雇用の推進は、今や避けて通れない重要な経営課題です。法定雇用率の達成という側面はもちろん、多様な人材が活躍できる組織文化を構築することは、企業の競争力そのものに直結します。
しかし、障害者雇用、特に知的障害や精神障害のある方の採用となると、「どのような仕事を任せられるのか分からない」「受け入れ後のフォロー体制をどう構築すればよいのか」「採用のミスマッチが起きた場合のリスクが怖い」といった不安から、最初の一歩をなかなか踏み出せない、という人事責任者の方も多いのではないでしょうか。
もし貴社が同様の課題を抱えているのであれば、その有効な解決策の一つとなるのが、国や地方自治体が主導する「チャレンジ雇用」制度です。この制度は、障害者雇用に初めて取り組む企業や、採用ノウハウに不安がある企業にとって、極めて低いリスクで受け入れ経験を積み、自社にマッチした人材を見極めることができる、画期的な仕組みです。
本記事では、この「チャレンジ雇用」とは一体どのような制度なのか、その基本的な仕組みから、企業側が享受できる具体的なメリット、そして実際に活用するための流れまでを、専門用語を避けつつ体系的に解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、障害者雇用に対する漠然とした不安が解消され、貴社の組織力を強化する、確かな一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えるはずです。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
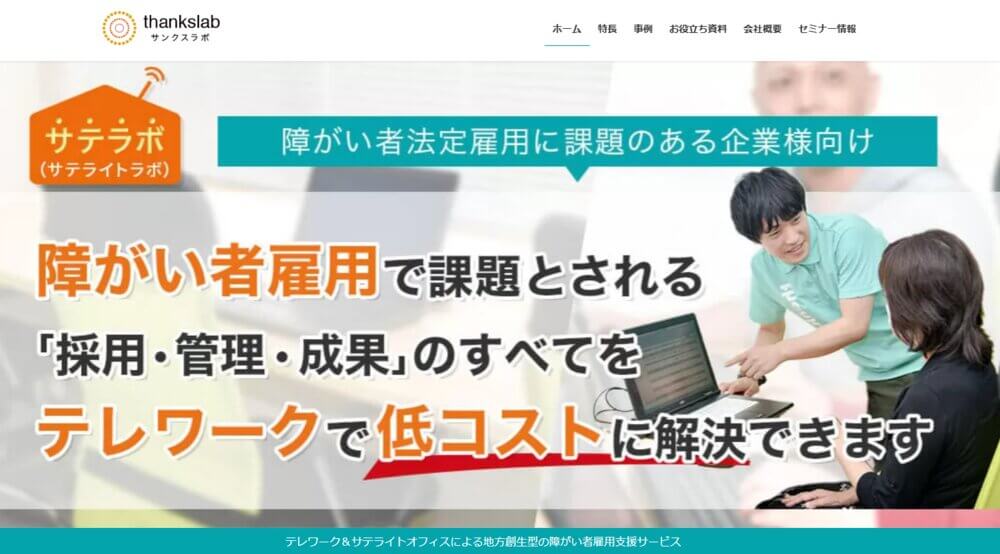
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
チャレンジ雇用の全体像|目的・仕組みと企業の役割を理解する
「チャレンジ雇用」とは、簡単にお伝えすると、国や地方自治体などが雇用主となり、民間企業が職場を提供する形で行われる「職場実習・試行雇用」制度のことです。就労経験が乏しい知的障害者や精神障害者などを対象に、実際の職場で働く経験を通じて、本人の職業能力や適性を高め、一般雇用(企業による直接雇用)への移行を支援することを目的としています。
この制度を理解する上で、企業担当者がまず押さえるべき最も重要なポイントがあります。それは、チャレンジ雇用期間中、対象となる障害のある方の雇用主は、あくまで国や地方自治体であるという点です。
- 雇用主は国・地方自治体: 企業は、業務を遂行するための「場所」と「実務経験の機会」を提供する協力事業所という位置づけになります。雇用契約は国・自治体と本人の間で結ばれるため、企業が直接雇用契約を結ぶわけではありません。
- 賃金・社会保険料の負担は発生しない: 雇用主が国・自治体であるため、チャレンジ雇用期間中の賃金や、労働保険・社会保険といった各種保険料は、すべて国・自治体によって支払われます。企業側の金銭的な負担は原則として発生しません。
- 対象者: 主に、ハローワークに登録している障害者のうち、就労経験が乏しい、あるいは長期のブランクがある知的障害者や精神障害者、発達障害者などが対象となります。これまで働く機会が限られていた方々が、社会へ出るためのステップアップとして活用されています。
- 実施期間: 期間は自治体等によって異なりますが、原則として3ヶ月以内で設定されることが一般的です。この短期間に集中して、本人は仕事のスキルや職場でのコミュニケーションを学び、企業側は本人の適性や必要な配慮を見極めます。
このようにチャレンジ雇用は、企業が金銭的リスクを負うことなく、障害のある方の受け入れを「お試し」できる制度です。採用という大きな決断を下す前に、社内の受け入れ体制をテストしたり、どのような業務を任せられるかを具体的に確認したりするための、非常に有効な準備期間として機能するのです。
【重要】トライアル雇用との違いは?自社に合う制度の選び方
障害者雇用の支援制度を調べる中で、多くの人事担当者が「チャレンジ雇用」と混同しやすいのが「障害者トライアル雇用助成金」を活用した、いわゆる「トライアル雇用」です。両者は共に、本採用を視野に入れた試行的な雇用制度という点では似ていますが、その仕組みと目的は大きく異なります。この違いを正確に理解し、自社の状況に合わせて使い分けることが、効果的な障害者雇用戦略の鍵となります。
以下に、両制度の決定的な違いをまとめます。
- チャレンジ雇用
- 雇用主: 国・地方自治体
- 賃金の支払い元: 国・地方自治体
- 社会保険の加入: 国・地方自治体が手続きを行う
- 制度の目的・位置づけ: 本格的な雇用契約を結ぶ前の「職場実習」や「適性評価」としての性格が非常に強いです。企業はあくまで職場を提供する「協力者」という立場になります。
- 企業の金銭的負担: 原則としてなし。
- 障害者トライアル雇用
- 雇用主: 受け入れ先の企業
- 賃金の支払い元: 受け入れ先の企業
- 社会保険の加入: 企業が手続きを行う
- 制度の目的・位置づけ: あくまで企業が雇用主となり、本採用を前提とした「試用期間」を設ける制度です。企業はこの試用期間に対して、国から「障害者トライアル雇用助成金」という形で金銭的な支援を受けます。
- 企業の金銭的負担: 賃金の支払い義務があり(ただし、助成金によって一部が補填される)。
この二つの制度を、企業の状況に応じてどのように使い分ければよいのでしょうか。
- チャレンジ雇用が適しているケース:
- 知的障害者や精神障害者の雇用経験が全くなく、何から手をつければよいか分からない。
- どのような業務を任せられるか、社内で切り出すところから始めたい。
- 採用に伴う人件費や社会保険料などの金銭的リスクを限りなくゼロに近い状態で、受け入れを試してみたい。
- まず社内の受け入れ体制や、指導担当者の育成をテストしたい。
- トライアル雇用が適しているケース:
- ある程度の受け入れ経験やノウハウは既に持っている。
- 採用したい人物像が比較的明確で、良い人材がいれば早期に直接雇用へと繋げたい。
- 助成金を活用しつつも、最初から自社の従業員として迎え入れ、責任を持って育成したい。
このように、チャレンジ雇用は「採用前の準備・お試し期間」、トライアル雇用は「採用後の試用期間」と捉えると、その違いがより明確になるでしょう。
企業がチャレンジ雇用を活用する5つの戦略的メリット
チャレンジ雇用制度は、障害のある方にとってはもちろん、受け入れる企業側にとっても計り知れないメリットをもたらします。特に、障害者雇用に対して漠然とした不安を抱える企業にとって、その価値は絶大です。ここでは、企業が享受できる5つの主要なメリットを具体的に解説します。
メリット1:採用ミスマッチのリスクを大幅に軽減できる
障害者雇用において企業が最も懸念する点の一つが、採用後のミスマッチです。履歴書や数回の面接だけでは、本人の真の能力や、実際の職場環境への適応力を見極めることは容易ではありません。チャレンジ雇用を活用すれば、最長3ヶ月間の実務を通じて、本人の得意なこと・苦手なこと、仕事への取り組み姿勢、集中力の持続性、チームメンバーとの相性などを、じっくりと時間をかけて確認することができます。これにより、「採用してみたが、任せられる仕事がなかった」「職場の雰囲気に馴染めなかった」といったミスマッチのリスクを限りなくゼロに近づけ、納得感のある直接雇用へと繋げることが可能です。
メリット2:人件費・社会保険料の負担なく受け入れ経験を積める
前述の通り、チャレンジ雇用期間中の雇用主は国や地方自治体であるため、企業側に賃金や社会保険料などの直接的な人件費負担は一切発生しません。これは、障害者雇用のための予算確保に課題を抱える企業や、新たな人件費の発生に慎重な経営層を説得する上で、極めて強力なメリットとなります。コストを気にすることなく、純粋に「障害のある方と共に働く」という経験を積むことで、社内に実践的なノウハウを蓄積できます。
メリット3:手厚い公的サポートを受けながら、受け入れノウハウを蓄積できる
チャレンジ雇用は、企業と障害のある方をマッチングさせて終わり、という制度ではありません。期間中、ハローワークの担当者や、地域の障害者就業・生活支援センターなどに所属する専門のジョブコーチ(職場適応援助者)が、定期的に職場を訪問します。彼らは、本人への業務遂行上のアドバイスを行うだけでなく、企業の指導担当者に対して「このような指示の出し方が効果的です」「本人は今、こんなことで悩んでいるようです」といった専門的な助言を提供してくれます。企業は、こうした専門家と二人三脚で進めることで、障害特性への理解を深め、効果的な指導方法や環境整備のコツを学ぶことができます。
メリット4:法定雇用率の達成に向けた、スムーズな足がかりになる
チャレンジ雇用は、それ自体が直接的に法定雇用率に算定されるわけではありませんが、期間終了後に本人を直接雇用へと切り替えることで、法定雇用率の達成に大きく貢献します。リスクを抑えた形で候補者を見極め、万全の準備を整えた上で本採用に至るため、採用後の定着率が高くなる傾向があります。これは、単に頭数を揃えるための雇用ではなく、企業の戦力として長期的に活躍してくれる人材を確保するという、障害者雇用の本来あるべき姿を実現するための、極めて有効で戦略的なステップと言えるでしょう。
メリット5:CSR・ESG経営の推進と組織力の強化に繋がる
チャレンジ雇用の活用は、企業の社会的責任(CSR)を果たす具体的なアクションとして、社内外にポジティブなメッセージを発信します。ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資家や取引先からの企業評価を高める効果も期待できます。さらに、障害のある方を受け入れる過程で、業務の棚卸しや指示系統の明確化が進むことは、組織全体の生産性向上に寄与します。多様な人材と共に働く経験は、管理職や現場社員のマネジメント能力やコミュニケーションスキルを向上させ、組織全体の力を底上げする貴重な機会となります。
導入から本採用までの具体的ステップと企業が準備すべきこと
チャレンジ雇用制度を効果的に活用するためには、その手続きの流れを理解し、協力事業所として主体的に準備を進めることが不可欠です。ここでは、制度利用の基本的なステップと、企業側が事前に整えておくべき事項について解説します。
活用の基本ステップ
チャレンジ雇用の利用は、一般的に以下の流れで進みます。
- 管轄のハローワークに相談: まずは企業の所在地を管轄するハローワークの障害者雇用担当窓口に、「チャレンジ雇用制度を利用したい」と相談することから始まります。制度の詳細な説明や、協力事業所となるための要件などを確認します。
- 協力事業所としての登録・申し込み: ハローワークからの案内に従い、協力事業所としての登録手続きを行います。この際、どのような業務を任せる予定か、どのような環境を提供できるかなどをまとめた計画書を提出することがあります。
- ハローワークによる候補者とのマッチング: 企業の希望(任せたい業務内容など)と、チャレンジ雇用を希望する障害のある方の特性やスキルを基に、ハローワークが最適な候補者を探し、企業に紹介します。
- 職場見学・面談の実施: 本格的な実習開始前に、候補者が職場を見学したり、企業の担当者と簡単な面談を行ったりする機会が設けられます。ここでお互いの雰囲気や条件を確認します。
- 職場実習(チャレンジ雇用)の開始: 双方の合意が得られれば、チャレンジ雇用がスタートします。期間中は、事前に作成した計画に沿って業務に従事してもらいます。
- 期間中の振り返りと支援機関との連携: 期間中は、企業の指導担当者が日々の業務指導を行います。同時に、ハローワークの担当者やジョブコーチが定期的に訪問し、本人・企業・支援者の三者で面談を行い、進捗の確認や課題の共有、解決策の検討を行います。
- 期間終了後、直接雇用の検討・判断: チャレンジ雇用期間の終了が近づいたら、企業は実習中の本人の働きぶりや適性を総合的に評価し、直接雇用(本採用)に移行するかどうかを最終的に判断します。
企業側が準備すべきこと
チャレンジ雇用は、企業が「受け身」で待っているだけでは成功しません。実りある実習期間にするために、以下の準備を主体的に進めることが求められます。
- 指導担当者(メンター)の選任: 日常的な業務の指示出しや、困った時の相談役となる担当者を、あらかじめ部署内に決めておきます。その担当者には、制度の趣旨や対象となる方の障害特性について、事前に学習してもらうことが望ましいです。
- 具体的な業務内容の切り出し: 「何か簡単な仕事を」と漠然と考えるのではなく、「書類のPDF化作業」「データ入力」「郵便物の仕分け」など、具体的で手順が明確な業務を事前にいくつかリストアップしておきます。
- 受け入れ部署への事前説明: チャレンジ雇用が始まる前に、配属先の部署メンバーに対して、制度の趣旨や、共に働く上で心がけてほしいこと(例:丁寧なコミュニケーション、分かりやすい指示)などを説明し、協力的な雰囲気を作っておくことが重要です。
- 支援機関との連携体制の構築: ジョブコーチなどが訪問した際に、誰が対応するのか、どのような情報を共有するのかをあらかじめ決めておき、円滑な連携体制を築きます。
まとめ:チャレンジ雇用を、企業の持続的な成長力へ
本記事では、障害者雇用、特に知的障害や精神障害のある方の採用における有効な一手として、「チャレンジ雇用」制度を多角的に解説しました。
チャレンジ雇用の最大の価値は、企業が金銭的なリスクを負うことなく、実際の業務を通じて候補者の適性を見極め、同時に社内の受け入れノウハウを蓄積できる点にあります。採用後のミスマッチを恐れるあまり、障害者雇用への一歩を踏み出せずにいる企業にとって、これほど効果的で安心な「お試し期間」は他にありません。
この制度は、単に法定雇用率を達成するための短期的な解決策ではありません。ジョブコーチなど専門家のサポートを受けながら、障害のある方と共に働く経験を積むことで、企業は「どのような業務を切り出せばよいか」「どのような指示の出し方が伝わりやすいか」「どのような環境整備が必要か」といった、実践的で価値のある知見を社内に蓄積することができます。
それは、障害者雇用の成功に不可欠な「土壌」を育むことに他なりません。チャレンジ雇用をきっかけとして直接雇用に至った人材が、生き生きと活躍する姿は、周囲の社員にポジティブな影響を与え、組織全体のダイバーシティへの理解を深めるでしょう。
障害者雇用に対する漠然とした不安を、具体的な行動に変えるための第一歩として、まずは貴社の所在地を管轄するハローワークの専門窓口に、ぜひ一度相談してみてください。チャレンジ雇用は、企業の社会的責任と持続的な成長を両立させる、極めて戦略的な一手となるはずです。