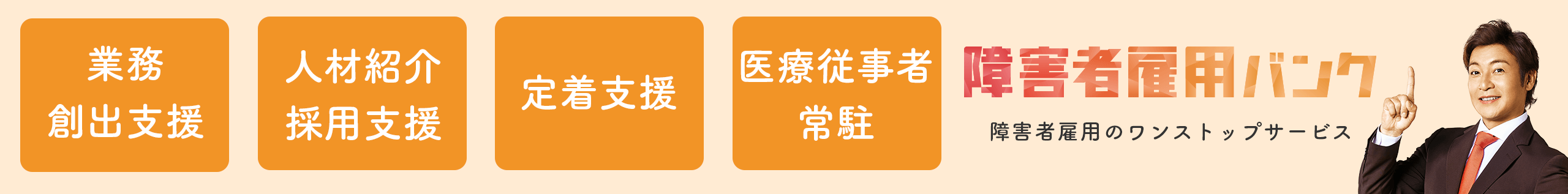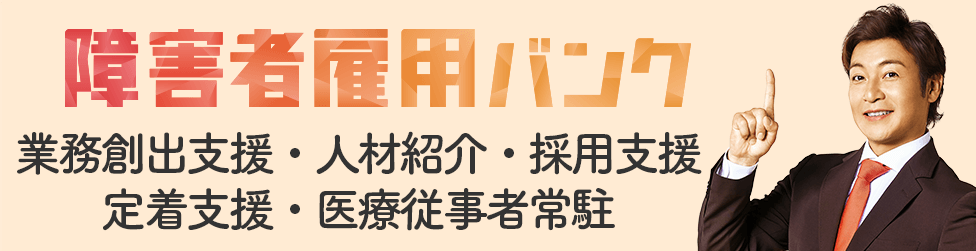【徹底比較】障害者雇用と一般雇用の違いとは?採用・給与・法律の観点から人事担当者向けに解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「障害者雇用を始めたいが、一般の採用と同じように考えて良いのだろうか」「給与や待遇に、違いを設けるべきなのか」 障害者雇用の推進が企業の社会的責任として、また重要な人材戦略として注目される中、多くの人事責任者や経営者がこのような根本的な疑問に直面しています。
結論から言えば、障害者雇用と一般雇用には、「同じように扱うべき部分」と「特別に配慮・対応すべき部分」が明確に存在します。この境界線を正しく理解しないまま、一般雇用の延長線上で採用やマネジメントを行ってしまうと、知らず知らずのうちに法律に抵触していたり、採用のミスマッチによる早期離職を招いたりするリスクがあります。
本記事では、企業の決裁者・人事責任者の方々が安心して障害者雇用に取り組めるよう、その「違い」を法律、採用プロセス、労働条件、入社後のマネジメントといったあらゆる側面から徹底的に比較・解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
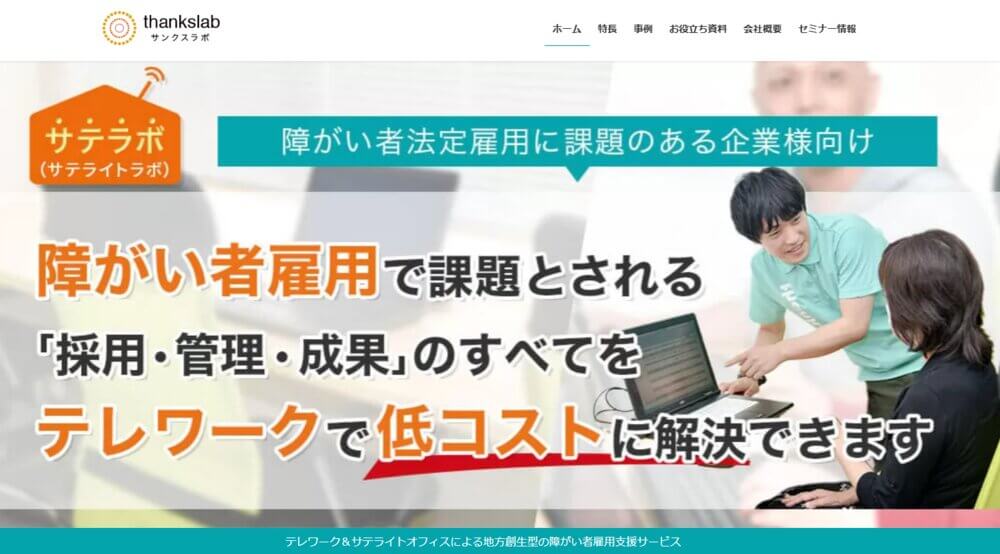
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
まずは基本から。「障害者雇用」と「一般雇用」の定義の違い
障害者雇用と一般雇用の違いを理解する上で、まず「障害者採用枠」と「一般採用枠」という言葉の定義を整理しておく必要があります。これは、応募者が自身の障害を企業に開示するかどうかによって区別されます。
障害者雇用(障害者採用枠)
これは、応募者が自身の障害(障害者手帳を所持していること)を企業に開示(オープン)した上で応募し、採用される働き方を指します。「オープン就労」とも呼ばれます。この枠で採用した場合、企業は応募者の障害特性を認識した上で選考を行い、入社後はその特性に応じた「合理的配慮」を提供する法的な義務を負います。求人自体が、障害のある方を対象として募集されます。
一般雇用(一般採用枠)
これは、障害の有無にかかわらず、全ての求職者が同じ条件で応募・採用される、従来からの働き方です。障害のある方が、自身の障害を企業に開示せず(クローズ)に応募することも可能です。この場合、企業は応募者に障害があることを知らないため、障害を理由とした選考上の配慮や、入社後の体系的な合理的配慮は提供されにくいのが実情です。
本記事では、企業が法定雇用率の達成などを目的に、意図して「障害者採用枠」で募集・採用する場合と、通常の「一般採用枠」での雇用との違いに焦点を当てて解説を進めます。この違いを理解することが、適切な制度運用の第一歩となります。
【法律・制度編】企業が負う「義務」と享受できる「権利」の決定的な違い
障害者雇用と一般雇用を分ける最も根本的な違いは、その背景にある法律や制度にあります。企業が負う「義務」と、活用できる「権利(メリット)」が明確に異なります。
違い①:障害者雇用率制度の有無
最も大きな違いは、障害者雇用率制度の存在です。障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の企業は、全従業員数に対して法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この義務は、一般雇用には存在しません。法定雇用率を達成できない企業は、不足人数に応じて障害者雇用納付金を支払う必要があり、行政指導の対象にもなります。つまり、障害者雇用は、企業の社会的責任であると同時に、遵守すべき法的な義務なのです。
違い②:合理的配慮の提供義務の明確さ
次に重要なのが「合理的配慮」の提供義務です。一般雇用においても、企業は従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。しかし、障害者雇用においては、障害者雇用促進法によって、一人ひとりの障害特性や困りごとに応じた、より個別具体的な配慮(例:車椅子用のスロープ設置、業務指示方法の変更など)を提供することが明確に義務付けられています。これは単なる努力目標ではなく、本人との対話を通じて、企業に過重な負担にならない範囲で提供すべき法的な義務です。
違い③:助成金制度の活用の可否
義務の違いだけでなく、企業が活用できる「権利」にも大きな違いがあります。障害者雇用を推進する企業に対しては、国から手厚い支援策が用意されています。採用活動、職場環境の整備、定着支援、能力開発など、様々なフェーズで活用できる豊富な助成金制度が存在します。これらを活用することで、企業は経済的な負担を大幅に軽減しながら、障害者雇用を進めることができます。このような雇用に特化した助成金は、一般雇用には原則としてありません。
【採用プロセス編】出会い方から内定を出すまでの違い
障害者雇用と一般雇用では、採用に至るまでのプロセスや、重視するべきポイントが大きく異なります。一般雇用と同じやり方では、適切な人材と出会うことすら難しいかもしれません。
募集・求人チャネルの違い
一般雇用では、民間の大手求人サイトや自社の採用ページ、人材紹介会社、リファラル採用などが主な募集チャネルとなります。 一方、障害者雇用では、これらのチャネルに加えて、あるいはそれ以上に、ハローワークの専門援助部門や、各地域の就労移行支援事業所、特別支援学校の進路指導部、障害者専門の人材紹介会社といった、独自のチャネルを活用することが不可欠です。これらの機関は、障害のある方の特性や希望を深く理解しており、企業と求職者の最適なマッチングを支援してくれます。
選考・面接で重視するポイントの違い
一般雇用の面接では、主に職務経歴やスキル、専門性、コミュニケーション能力といった点が評価の中心となります。 これに対し、障害者雇用の面接では、もちろん職務遂行能力も重要ですが、それに加えて「本人が自身の障害特性をどの程度理解しているか(自己理解度)」「必要な配慮を自分の言葉で説明できるか」「主治医や支援機関と連携し、安定して働ける状態にあるか」といった点が極めて重要な評価ポイントになります。単に能力を測るだけでなく、「どうすればこの人が能力を発揮できるか」を、対話を通じてすり合わせる場なのです。
職場実習の重要性の違い
一般雇用において、インターンシップはありますが、選考プロセスの一環として数日間の実習を行うケースは限定的です。 しかし、障害者雇用においては、「職場実習」が採用のミスマッチを防ぐための非常に有効なプロセスとして、多くの企業で導入されています。実際に数日間一緒に働くことで、書類や面接だけでは分からない本人の業務適性、職場への順応性、体力面などを確認できます。これは企業側だけでなく、本人にとっても「この仕事なら続けられそうか」を判断する貴重な機会となり、双方の納得感を高める上で欠かせないステップです。
【労働条件・待遇編】給与・契約形態・働き方の違い
人事担当者が特に気になるのが、給与や契約形態といった労働条件の取り扱いです。ここでは、誤解の多い待遇面の違いについて、法的な原則を基に解説します。
給与:原則「違いはない」。同一労働同一賃金が基本
最も重要な原則は「障害があることのみを理由に、給与を低く設定することは許されない」ということです。これは、障害者差別解消法で禁じられている「不利益な取り扱い」に該当し、明確な法律違反となります。給与は、障害の有無ではなく、あくまで他の社員と同様に、その人が担う職務内容、役割、責任の重さ、本人のスキルや経験に基づいて、公正に決定されなければなりません。パートタイム・有期雇用労働法で定められている「同一労働同一賃金」の考え方は、障害者雇用においても当然適用されるのです。
雇用契約:原則「違いはない」。ただし配慮事項を明記
正社員、契約社員、パート・アルバイスなど、雇用契約の形態自体に、一般雇用との違いを設ける必要はありません。企業の就業規則や雇用方針に基づき、他の社員と同様に適用されます。ただし、障害者雇用特有の違いとして、採用選考の段階で本人と合意した「合理的配慮」の内容を、雇用契約書や労働条件通知書に明記しておくことが推奨されます。例えば、「週に一度の通院に配慮し、中抜けを認める」「業務指示は口頭ではなく、チャット等のテキストで行う」といった項目を文書化することで、入社後の「言った、言わない」というトラブルを防ぎ、本人も安心して働くことができます。
働き方(労働時間・休日):柔軟な対応が求められる「違い」
働き方については、一般雇用以上に個別最適な「柔軟性」が求められる点が大きな違いです。障害特性によっては、長時間の勤務が体調に影響を与えたり、定期的な通院が必要だったりする場合があります。そのため、本人の状況に応じて、短時間勤務制度を適用したり、ラッシュアワーを避けるための時差出勤やフレックスタイム制度を認めたりといった配慮が必要になることがあります。障害者雇用率制度自体が、週20時間以上30時間未満の短時間労働者もカウント対象としているように、制度的にも多様な働き方が想定されているのです。
【入社後のマネジメント編】定着・活躍を支える環境づくりの違い
採用後のマネジメントや職場環境の作り方にも、一般雇用とは異なる配慮や工夫が求められます。この「入社後の違い」への対応が、定着率を左右する鍵となります。
業務の指示・指導方法の違い
一般雇用では、OJTを中心に、ある程度の「背中を見て学ぶ」「空気を読んで行動する」といったことが期待される場面も少なくありません。 一方、障害者雇用では、そのような曖昧な指導では、本人が混乱し、能力を発揮できない可能性があります。求められるのは、「具体的・視覚的・段階的」な指示です。業務手順を写真や図で分かりやすくマニュアル化したり、作業項目をチェックリストにしたり、一度に一つの指示を出すなど、誰が見ても誤解の生まれない「仕組み」で指導することが、本人の安心とパフォーマンス向上に直結します。
コミュニケーション・面談の頻度と質の違い
一般雇用では、半期や四半期ごとの目標設定・評価面談がコミュニケーションの中心となることが多いでしょう。 しかし、障害者雇用では、それとは別に、業務上の困りごとだけでなく、体調の変化や職場の人間関係といった、よりデリケートな側面をフォローするための、高頻度かつ定期的な面談が極めて重要になります。週に一度、あるいは月に一度でも、1on1で話す時間を確保することで、問題が深刻化する前に早期発見・早期対応が可能となり、信頼関係の構築と長期的な定着に繋がります。
外部機関との連携の有無
これは、両者の決定的な違いの一つです。一般雇用では、マネジメントは基本的に企業と本人の二者間で完結します。 それに対し、障害者雇用では、採用まで本人を支援してきた就労移行支援事業所や、入社後の職場適応をサポートしてくれるジョブコーチ、生活面も含めて相談に乗ってくれる障害者就業・生活支援センターといった、外部の支援機関と連携(チーム支援)することが一般的であり、また非常に有効です。社内だけでは解決が難しい課題に対して、専門的な第三者の視点から助言を得ることで、より効果的で持続可能なサポート体制を構築できます。
まとめ:「違い」の理解が、障害者雇用の成功と企業成長の第一歩
本記事では、「障害者雇用」と「一般雇用」の違いを、法律・制度から採用、待遇、入社後のマネジメントに至るまで、様々な角度から比較・解説しました。
給与や契約形態といった基本的な労働条件においては「違いはない」ことが大原則ですが、その背景にある法的義務と、個々の特性に合わせた個別最適な対応が求められる点で、両者は大きく異なります。
結論として、障害者雇用と一般雇用の最大の違いは、「画一的な管理」ではなく「対話を通じた合理的配慮」が、法律と実務の両面で強く求められる点にあると言えるでしょう。
この「違い」を正しく理解し、恐れるのではなく、適切に対応していくこと。それこそが、コンプライアンス違反という法的リスクを回避し、障害のある社員を企業の貴重な「戦力」として活かし、ひいては全ての従業員にとって働きやすい職場環境を創造する、企業成長の第一歩となるのです。
とはいえ、これらの専門的な対応や制度構築を自社だけで行うのが難しい場合もあるでしょう。その際は、障害者雇用の「違い」を熟知した専門の支援サービスをパートナーとして活用することが、成功への最も確実な近道となるはずです。