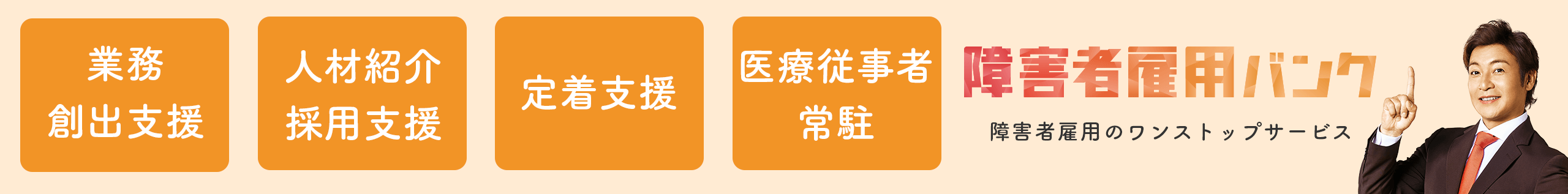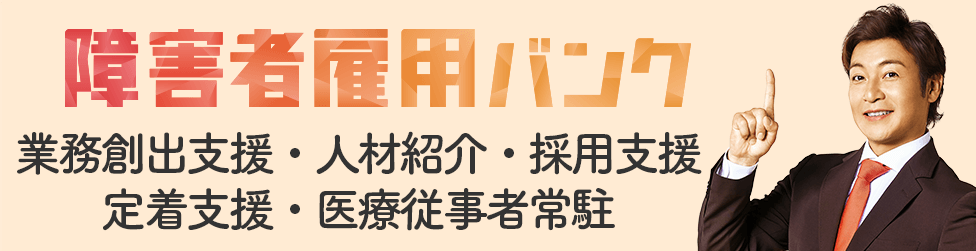障害者雇用における解雇の正しい手続きについて解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
障害者雇用の推進が進む中で、企業として避けて通れないテーマの一つが「解雇」に関する対応です。通常の労働者と同様に、障害のある方に対しても雇用契約上のルールは適用されますが、特に障害者雇用においては、法的・社会的な配慮がより一層求められます。不適切な対応は、労務トラブルや企業イメージの毀損につながるリスクもあるため、慎重かつ適正な手続きが不可欠です。本記事では、障害者の解雇に関する基本的な考え方から、実務上の注意点、適法なプロセスまでをわかりやすく解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
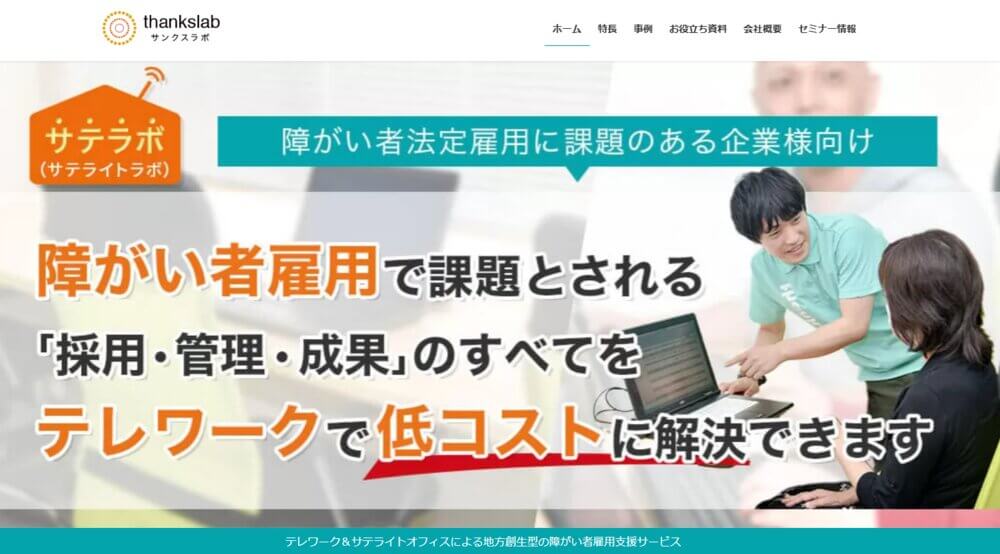
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障害者雇用と解雇問題の重要性およびその背景
障害者雇用は、企業が社会的責任を果たし、ダイバーシティやインクルージョンを実現するための重要な施策です。
昨今、政府の法定雇用率の引き上げや国際社会での障害者権利の重視が背景となり、多くの企業が障害のある人材の採用に力を入れ始めています。しかし、その一方で、採用後の労務管理―特に解雇に関しては、通常の従業員の解雇とは一線を画す高度な法的配慮が求められます。
採用背景と企業の課題
企業は、障害者雇用を通じて組織の多様性を促進し、社会的評価の向上や市場競争力の強化を図ります。さらに、障害者雇用は、企業ブランドの向上やCSR活動の一環としても注目されており、積極的な取り組みが評価されています。しかし、採用後の従業員管理において、業務の遂行状況、労働環境の整備、合理的配慮の提供など、各方面からの検証が必要となります。特に、解雇に至る場合は、労働契約法が定める「解雇権濫用法理」や、障害者差別禁止法、障害者雇用促進法による合理的配慮義務を厳守しなければなりません。
法令遵守と合理的配慮
障害者雇用においては、以下の点が特に重要です。
客観的な評価
従業員の業務遂行状況や出勤記録、評価面談の内容など、数値的かつ客観的なデータに基づく評価を行う必要があります。
合理的配慮の実施
障害に応じた就業環境の改善措置(例:物理的環境の整備、作業内容の調整、支援機器の導入など)を講じ、従業員が能力を発揮できる環境を確保します。
透明性の高い手続き
解雇を決定する際には、内部手続きを文書化し、後日のトラブル回避に努めるとともに、解雇理由や配慮措置の記録を残しておくことが求められます。
採用段階では企業と応募者の相互理解を深め、職場見学や試用期間を活用するなどしてミスマッチを防ぐとともに、採用後も定期的な評価や面談を通じて、従業員の状況を正確に把握し、必要な支援策を講じることが重要です。
企業が直面するリスク
もし、十分な合理的配慮や客観的評価のプロセスが欠如した状態で解雇措置が行われれば、企業は下記のような重大なリスクを負うことになります。
法的制裁
不当解雇として裁判所で無効と判断され、バックペイや慰謝料の支払い、さらには助成金の返還を求められる可能性がある。
経済的損失
労働争議に発展した場合、企業の財務状態に大きな負担がかかる。
社会的信用の低下
解雇措置における不透明さが公になれば、企業のブランド価値や従業員のモチベーションが大きく損なわれ、採用活動にも悪影響を及ぼす。
以上のように、障害者雇用における解雇は、その背景にある社会的意義と同時に、極めて慎重な対応が求められるテーマであることが分かります。本ガイドは、これらの背景とリスクを踏まえ、企業が安心して意思決定できるための基盤整備および内部管理体制の構築に向けた知識提供を目指します。
障害者雇用に関する法的背景
障害者雇用を適切に進めるうえで、法的な知識は欠かせません。とくに雇用継続や解雇といったセンシティブな場面では、法令に基づいた判断と手続きが求められます。日本では、労働契約法をはじめ、障害者差別禁止法や障害者雇用促進法など、障害者の就労機会を保障し、職場での不当な取り扱いを防ぐ複数の法律が整備されています。本項では、これらの法的基盤の概要と企業が守るべき基本的なルールについて整理し、解雇判断時における法令順守の重要性を解説します。
法的基盤の概要
日本における障害者雇用は、複数の法令によって厳格に規定され、企業はこれらの法令を遵守することが求められます。まず、労働契約法では、いかなる解雇措置も「客観的かつ合理的な理由」が不可欠であり、主観的な評価のみでの解雇は許されません。特に「解雇権濫用法理」に基づき、解雇の正当性が厳しく審査されるため、企業は定量的な評価データを蓄積する必要があります。
障害者差別禁止法の趣旨
次に、障害者差別禁止法は、障害を理由とする不当な差別的取扱いの一切を禁止しています。企業は、採用のみならず解雇においても、障害そのものを理由とすることが明確に禁じられているため、評価基準には障害に関連する不利益な扱いが含まれてはならず、平等な基準に則った判断が要求されます。
障害者雇用促進法による合理的配慮
さらに、障害者雇用促進法は、障害者が職場においてその能力を十分に発揮できるよう、企業に対して合理的配慮の提供を義務づけています。具体的な合理的配慮とは、以下のような対応が含まれます。
- 物理的な環境整備:バリアフリー化、車椅子用のスロープやエレベーターの設置。
- 就業条件の調整:勤務時間の柔軟化、業務内容の見直し、作業環境の改善。
- 支援システムの導入:必要な支援機器の導入、専門家による相談窓口の設置、定期的な健康管理や面談の実施。
企業がこれらの法令に基づいて社内規程や評価システムを整備することで、障害者雇用における解雇が、法令違反とならず、透明性の高い手続きで実施されることが保証されます。
正しい解雇手続きのステップと重要ポイント
障害者雇用において、解雇を最終手段とする場合、企業は法令遵守と透明性を維持しながら慎重に手続きを進めなければなりません。本節では、具体的な解雇手続きのステップと、その各段階における重要ポイントを、以下の4つの主要ステップとして解説します。
【ステップ1:事前調査と内部状況の整理】
解雇手続きの第一歩は、解雇理由の正当性を裏付けるための徹底した事前調査です。企業は、障害者従業員の業務遂行状況、出勤状況、成果、及び人事評価や面談記録を定量的に把握し、記録として保存する必要があります。
- 徹底した評価体制の構築
- 定期的な人事評価を実施し、数値データや具体的事実をもとに客観的な評価基準を確立する。
- 面談記録や指導履歴をもとに、改善指導や警告の履歴を文書化する。
- 定期的な人事評価を実施し、数値データや具体的事実をもとに客観的な評価基準を確立する。
- 内部記録の透明性
- すべての評価資料や業務記録は、将来の監査や訴訟対応のために整理・保存する。
- 内部で合意形成がなされたプロセスを、透明性のある文書としてまとめる。
- すべての評価資料や業務記録は、将来の監査や訴訟対応のために整理・保存する。
【ステップ2:解雇理由の明確化と文書化】
事前調査で得られたデータをもとに、解雇理由の正当性を明確にするための文書を作成します。これにより、解雇措置が恣意的でなく、客観的かつ合理的な判断に基づいていることを示せます。
- 具体的な根拠の提示
- 数値データ、面談記録、業務上の実績や警告履歴など、具体的な事実を盛り込む。
- 障害者特有の配慮措置の実施状況と、その効果の有無について明記し、合理的配慮を尽くした上での判断であることを文書で示す。
- 数値データ、面談記録、業務上の実績や警告履歴など、具体的な事実を盛り込む。
- 文書化の徹底
- 解雇通知書や解雇理由証明書を、労働基準法に則り作成する。
- 書面での通知により、後日のトラブル回避や第三者への説明責任を果たす。
- 解雇通知書や解雇理由証明書を、労働基準法に則り作成する。
【ステップ3:社内承認と通知プロセスの実施】
解雇判断は、企業内の複数部門との連携および承認を経て確定させる必要があります。
- 内部承認のプロセス
- 上位管理職、労務管理部門、及び関係部署との十分な連携を取り、社内の承認ルートに従って判断を進める。
- 各部署の意見を集約し、最終決定に反映させる。
- 上位管理職、労務管理部門、及び関係部署との十分な連携を取り、社内の承認ルートに従って判断を進める。
- 通知方法の厳守
- 解雇予告(30日前の通知または予告手当の支払い)の法定要件を遵守する。
- 書面による解雇通知を実施し、解雇理由と今後の手続き、異議申し立て方法などを明瞭に伝える。
- 通知の記録を残すことで、外部調査時に正当性を証明できるようにする。
- 解雇予告(30日前の通知または予告手当の支払い)の法定要件を遵守する。
【ステップ4:フォローアップとリスクマネジメント】
解雇決定後も、企業は継続的なフォローアップと内部統制を徹底し、不測のトラブルに迅速に対処する体制を整える必要があります。
- 専任窓口の設置
- 解雇後の問い合わせや異議申し立てに対応するための窓口を設置し、迅速な対応を実施する。
- 担当部署や上位管理職が連携して、問題の早期解決に努める。
- 解雇後の問い合わせや異議申し立てに対応するための窓口を設置し、迅速な対応を実施する。
- 内部監査・研修体制の強化
- 定期的に労務監査を行い、手続きの適正性をチェックする。
- 管理職向けに最新の法令、合理的配慮、および解雇手続きに関する研修を実施し、社内全体の知識と意識を高める。
- 定期的に労務監査を行い、手続きの適正性をチェックする。
- 外部専門家との連携
- 必要な場合は、社会保険労務士や弁護士等の外部専門家と連携し、法的アドバイスを迅速に得る体制を整える。
- 必要な場合は、社会保険労務士や弁護士等の外部専門家と連携し、法的アドバイスを迅速に得る体制を整える。
各ステップに共通するのは、透明性および客観性の徹底です。企業は、すべての手続きが客観的記録に基づいて実施され、外部からも正当性が立証できる体制を構築することが、障害者雇用 解雇における法的リスクを最小限に抑える鍵となります。
解雇手続きにおける注意点とリスクマネジメント
障害者雇用での解雇措置は、極めて慎重な手続きが要求され、客観的な評価や合理的配慮の徹底、文書による透明な記録管理が不可欠です。企業は、解雇の正当性を証明するため、以下のポイントを厳守すべきです。
- 客観性の確保
定量的な評価、出勤記録、面談・指導履歴などをもとに、解雇理由の根拠を文書で明示します。これにより、不当解雇の疑いを払拭し、万一の訴訟時にも正当性を証明可能とします。 - 合理的配慮の実施
障害者特有の困難に対し、適切な環境整備、業務内容の再調整、支援措置の記録を徹底します。これにより、十分な配慮の上での解雇判断であることを示し、法的リスクを低減します。 - 通知と内部承認の厳格な手続き
解雇は必ず書面(解雇通知書や解雇理由証明書)で行い、労働基準法の規定に基づく解雇予告(または解雇予告手当)の実施を徹底します。また、上位管理職や労務管理部門との連携を通じ、内部承認プロセスを明確化し、透明性を保持することが重要です。 - フォローアップ体制の構築
解雇後の問い合わせや異議申し立てに備え、専任の窓口や社内監査、定期的な内部研修を実施し、全体的な労務管理の改善に努めます。必要に応じて外部専門家と連携することで、より厳格な内部統制を図ります。
これらの取り組みを包括的に実施することで、企業は法的リスクの最小化とともに、組織全体の信頼性と透明性を向上させ、安心して多様な人材の活用が可能な職場環境を築くことが可能となります。
まとめと今後の企業内取組みへのアドバイス
本ガイドは、障害者雇用 解雇に関する正しい手続きと法令遵守、合理的配慮の重要性を詳述しました。まず、企業は障害者雇用において、客観的な評価と記録の整備、ならびに合理的配慮の実施を徹底し、解雇措置を極力最終手段とする必要があります。内部承認の厳格なプロセスと書面による通知、加えて解雇後の迅速なフォローアップ体制は、法的リスクの低減と企業の信頼性維持に直結します。今後は、内部規程や研修の定期見直し、外部専門家との連携強化を通じ、企業全体の労務管理体制の継続的改善を図り、安心して障害者雇用が実現できる職場環境の構築に努めることが不可欠です。