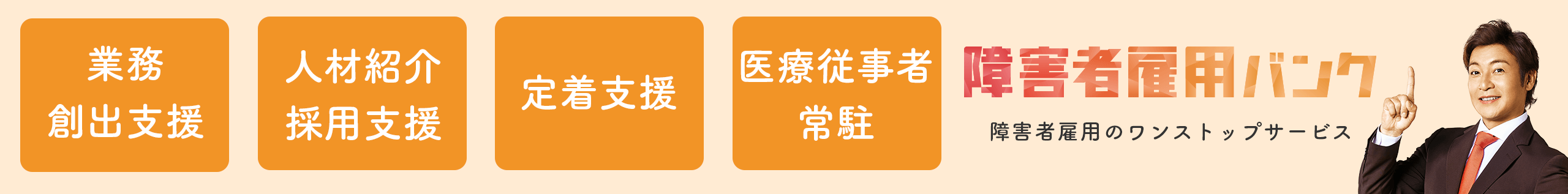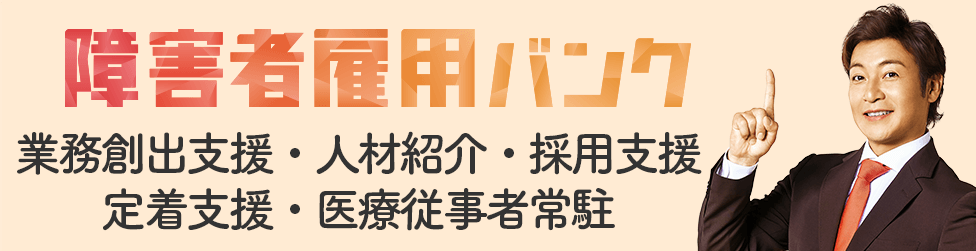『障害者雇用納付金』とは?計算方法から企業価値向上に繋げる戦略まで解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「障害者雇用納付金」この言葉に、単なるコストやペナルティという印象をお持ちではないでしょうか。法定雇用率が未達成の場合に発生するこの納付金は、企業の財務に直接的な影響を与えるため、人事責任者や経営層にとって看過できない課題です。しかし、この制度の本質は罰金ではなく、障害のある方の雇用機会を社会全体で支えるための「社会的連帯責任」という理念に基づいています。法定雇用率の段階的な引き上げが決定している現在、納付金制度への理解はこれまで以上に重要性を増しています。対応が後手に回れば、納付金の負担増だけでなく、企業の社会的評価やブランドイメージにも影響を及ぼしかねません。本記事では、障害者雇用納付金制度の基本的な仕組みや計算方法、申告手続きといった実務的な知識を網羅的に解説します。それに留まらず、コンプライアンスという守りの視点を超え、障害者雇用をいかにして企業価値の向上、すなわちESG経営やダイバーシティ&インクルージョンの推進、そして持続的な成長戦略へと繋げていくかという「攻めの視点」を提供します。本質を理解し、戦略的に取り組むことで、納付金という課題を企業の未来への投資へと転換する道筋を示します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
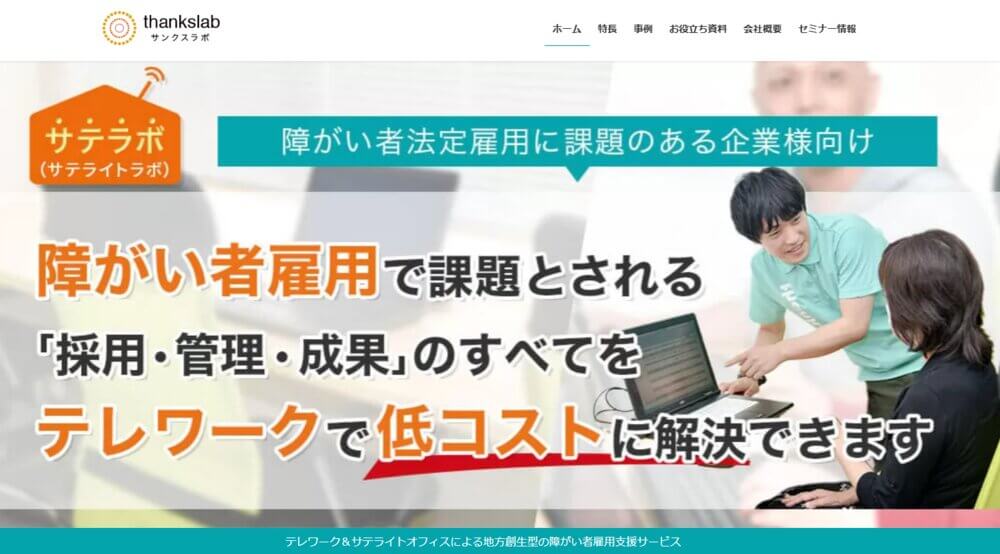
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障害者雇用納付金制度の理念と全体像
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用促進法に定められた、企業間における障害者雇用の経済的負担を公平に調整するための仕組みです。常用労働者が100人を超える企業を対象とし、法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、それを原資として法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に調整金や報奨金を支給します。この制度の根底にあるのは、障害者の雇用は個々の企業の努力だけに委ねるのではなく、社会全体で連帯してその責任を果たすべきだという「社会的連帯責任」の理念です。決して罰金やペナルティではありません。この循環的な仕組みを通じて、社会全体で障害者の雇用を支え、共生社会の実現を目指しています。制度の全体像は、以下の3つの主要な給付金で構成されています。
- 障害者雇用納付金 常用労働者100人超の企業が法定雇用率を下回る場合、不足する障害者1人につき月額50,000円を申告・納付する義務があります。
- 障害者雇用調整金 逆に、常用労働者100人超の企業が法定雇用率を上回った場合は、超過1人につき月額29,000円が支給されます。企業の積極的な取り組みを経済的に支援するインセンティブです。
- 報奨金 常用労働者100人以下の企業が一定数以上の障害者を雇用した場合に支給されます。中小企業における障害者雇用を奨励するための制度です。
この相互扶助の仕組みを正しく理解することが、適切な対応への第一歩となります。
【担当者必見】納付金の計算方法と3つの重要ポイント
障害者雇用納付金の金額は、複数の要素を組み合わせて算出されるため、担当者はそのプロセスと重要ポイントを正確に理解しておく必要があります。計算は大きく分けて4つのステップで構成されます。
ステップ1:常用労働者総数の把握
まず、自社の「常用労働者」の総数を正確に把握します。ここでのカウント方法は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が30時間以上の労働者:1人としてカウント
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者:0.5人としてカウント
ステップ2:法定雇用障害者数の算出
次に、ステップ1で算出した常用労働者数に、国が定める「法定雇用率」を乗じて、企業が雇用すべき障害者の数(法定雇用障害者数)を算出します。
- 計算式:常用労働者総数 × 法定雇用率
- 法定雇用率の注意点:この率は段階的に引き上げられます。2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%となるため、常に最新の率を確認することが不可欠です。
ステップ3:常用雇用障害者数のカウント
実際に雇用している障害者(常用雇用障害者)の数をカウントします。ここでのカウントは障害の種別や程度、労働時間によって異なり、特に注意が必要です。
- ダブルカウント:週30時間以上勤務する重度身体障害者や重度知的障害者は、1人で2人分としてカウントされます。
- 短時間労働者の特例:2024年4月から、週10時間以上20時間未満で働く特定の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者も0.5人として算定可能になりました。
ステップ4:納付金額の確定
最後に、ステップ2の「法定雇用障害者数」からステップ3の「常用雇用障害者数」を差し引き、不足人数を確定させます。
- 計算式:(法定雇用障害者数 – 常用雇用障害者数) × 50,000円 × 12ヶ月
この計算過程では、労働者の定義やカウントの特例など、誤解しやすいポイントが多数存在するため、厚生労働省やJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)が提供する手引きを精読し、慎重に実務を進めることが求められます。
申告手続きのフローと会計・税務上の取り扱い
障害者雇用納付金の申告・納付は、法律で定められた手続きに則って毎年定期的に行う必要があります。このプロセスを怠ると、追徴金や延滞金といったペナルティが課されるだけでなく、行政指導の対象となり、最終的には企業名が公表されるリスクもあるため、人事・経理部門は連携して遺漏なく対応しなければなりません。
申告・納付の年間フロー
主な流れは、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の雇用実績に基づいて行います。
- 申告期間:原則として毎年4月1日から5月15日までです。
- 必要書類:「障害者雇用状況等報告書」や「障害者雇用納付金申告書」などが必要です。
- 提出方法:利便性の高い電子申請システム(e-Gov)の利用が原則とされています。
- 納付:申告内容に基づき確定した納付金額を、定められた期限までに日本銀行または指定の金融機関を通じて納付します。納付額が100万円以上の場合、企業の申請により年3回の延納(分納)も可能です。
会計・税務上の取り扱い
納付した障害者雇用納付金は、会計および税務上、適切に処理する必要があります。
- 税務上の扱い:法人税法上、「損金」として算入することが認められています。これにより、企業の課税所得から控除され、税負担が軽減されます。
- 会計上の勘定科目:一般的に「租税公課」として処理されます。「法定福利費」とは性質が異なるため注意が必要です。
この一連の手続きは毎年の定型業務ですが、制度改正が頻繁に行われるため、常に最新情報を確認することが肝要です。経理部門や会計士と事前に連携し、申告内容の正確性を確保するダブルチェック体制を構築することが、不要なリスクを回避する上で不可欠です。
法定雇用率達成のインセンティブ(調整金・報奨金)
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率未達成企業から納付金を徴収するだけでなく、積極的に障害者雇用に取り組む企業を経済的に支援するインセンティブの側面も持ち合わせています。これにより、企業の積極的な取り組みを後押しし、制度全体の好循環を生み出しています。代表的なものが「障害者雇用調整金」と「報奨金」です。
障害者雇用調整金
障害者の雇用に伴って必要となる作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な配慮などに要する追加コストを補填し、法定雇用率を超えた雇用を促進することを目的としています。
- 対象企業:常用労働者100人超の企業
- 支給要件:法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している場合に支給されます。
- 支給額:超過人数1人につき月額29,000円です。
報奨金
特に中小企業における障害者雇用を推進するための経済的基盤を支える重要な役割を担っています。
- 対象企業:常用労働者100人以下の企業
- 支給要件:これらの企業には納付金の納付義務はありませんが、障害者雇用への取り組みを奨励するために、各月の常用労働者数の4%または72人のいずれか多い数など、一定の基準を超えて障害者を雇用している場合に支給されます。
- 支給額:超過人数1人につき月額21,000円です。
これらの給付金制度は、障害者雇用を単なる「コスト」ではなく、企業の生産活動や組織力向上に貢献する「投資」と捉え直すきっかけとなり得ます。法定雇用率の達成をゴールとするだけでなく、それを超えた雇用を推進することが、結果的に企業の財務面にもプラスに働く可能性があることを示唆しています。
納付金削減から企業価値向上へ繋げる戦略的アプローチ
障害者雇用を、納付金の回避というコンプライアンスの観点のみで捉えるのは、企業の成長機会を逸していると言っても過言ではありません。むしろ、これを戦略的に推進することで、企業は大きな経営メリットを享受できます。
アプローチ1:ESG経営の推進と企業価値の向上
近年、投資家は企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを重視するESG投資を加速させています。障害者雇用は、まさに「S(社会)」の中核をなすテーマであり、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」や目標10「人や国の不平等をなくそう」にも直結します。積極的な取り組みは、企業の社会的責任に対する姿勢を内外に示し、投資家や顧客、そして未来の優秀な人材からの信頼を獲得することに繋がり、結果として企業価値そのものを高めます。
アプローチ2:ダイバーシティ&インクルージョンによるイノベーションの創出
多様な背景を持つ人材が集まることで、組織には新たな視点や価値観がもたらされ、硬直化した思考パターンを打ち破るきっかけとなります。障害のある当事者の視点を取り入れた製品開発が、新たな市場を開拓するユニバーサルデザイン商品を生み出すなど、イノベーションの源泉となり得ます。オムロンの「ニューロダイバーシティ雇用」のように、個々の特性を強みとして活かす先進的な取り組みも、企業の競争力強化に貢献しています。
アプローチ3:組織力の強化と持続的な人材確保
障害のある社員が活躍できる職域を創出し、働きやすい環境を整備する過程は、業務プロセスの見直しやコミュニケーションの活性化、柔軟な働き方の導入など、全従業員にとっての働きやすさ向上に直結します。ユニクロの「1店舗1人以上の障害者雇用」という目標は、業務の標準化と教育体制の強化をもたらしました。労働力人口が減少する日本において、障害者雇用は重要な人材確保戦略であり、組織全体の生産性向上と持続的成長の基盤を築くのです。納付金を払って終わりにするのではなく、その原資を自社の雇用環境整備に投資することが、真の企業成長に繋がります。
まとめ:障害者雇用を企業の成長戦略へ
障害者雇用納付金制度は、単なる罰金ではなく、障害者の雇用を社会全体で推進するための循環的な仕組みです。その計算や申告は複雑ですが、本質を理解し、適切に対応することが不可欠です。しかし、本質的な課題は、この制度をいかにして企業の成長に結びつけるかという点にあります。法定雇用率の達成は、もはやCSRの基本要件です。その一歩先、つまり障害者雇用を企業の成長戦略の一環として積極的に位置づけることが、これからの企業経営には求められます。多様な人材がその能力を最大限に発揮できるインクルーシブな職場環境は、新たなイノベーションの土壌となり、組織全体の生産性を向上させます。また、ESG投資が主流となる現代において、企業の社会的姿勢は企業価値を左右する重要な経営指標です。障害者雇用への真摯な取り組みは、企業価値を高め、優秀な人材を惹きつけ、持続的な成長を実現するための強力なエンジンとなり得ます。納付金という課題を、企業の未来を創造するための戦略的投資へと転換する。その視点を持つことが、変化の時代を勝ち抜くための第一歩となるでしょう。