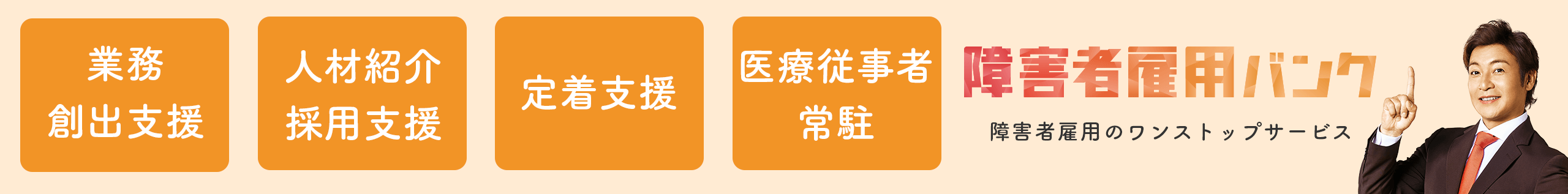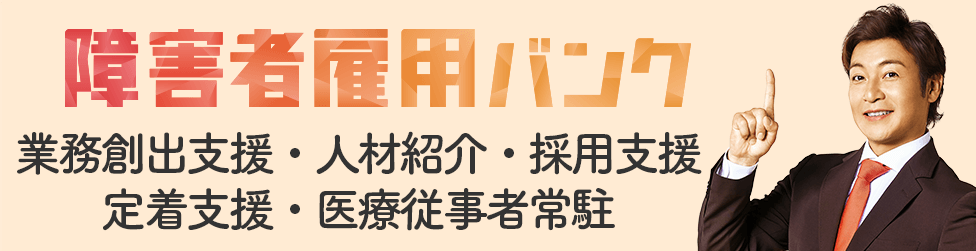障害者雇用における解雇は可能か?法的リスクを回避し、安定雇用を実現する企業の対応策

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
障害者雇用促進法の改正により法定雇用率が段階的に引き上げられ、障害者雇用はすべての企業にとって避けて通れない経営課題となりました。採用活動が活発化する一方で、雇用後のミスマッチやトラブルを背景に、障害のある社員の「解雇」が深刻な問題として顕在化しています。
しかし、障害者雇用における解雇は、一般の従業員の場合と比較して、法的に極めて厳格な判断がなされます。安易な判断は「不当解雇」として訴訟に発展するだけでなく、助成金の返還命令や企業イメージの失墜といった、計り知れない経営リスクを招きかねません。
本記事では、障害者雇用の解雇に関する法的な論点を整理し、企業が直面する具体的なリスクを解説します。その上で、解雇という最悪の事態を回避し、障害のある社員が定着・活躍できる「安定雇用」を築くための具体的なポイントを、企業の決裁者・人事責任者の視点から網羅的に解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
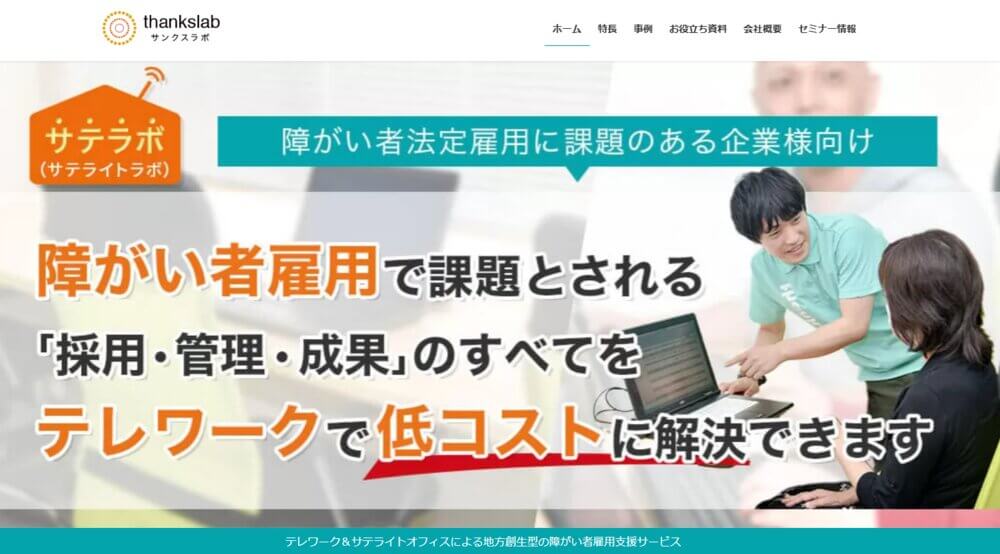
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障害者雇用の解雇が困難な理由と、企業が負う3つの経営リスク
障害者雇用における解雇が法的に困難とされる背景には、労働契約法と障害者雇用促進法という二つの大きな法的枠組みが存在します。まず、すべての労働者に適用される労働契約法第16条は解雇権濫用法理を定めており、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必須です。誰が見ても納得できる正当な理由と、解雇という手段が妥当であることの証明が求められます。
障害者雇用の場合、この判断基準がさらに厳格になります。障害者雇用促進法や障害者差別解消法は、障害を理由とする不利益な取り扱いを明確に禁止しているからです。解雇理由が障害特性に起因する場合、それは差別と見なされ、不当解雇と判断される可能性が極めて高くなります。
不適切な解雇に踏み切った場合、企業は主に3つの重大な経営リスクを負うことになります。
法的・金銭的リスク
不当解雇が認定されると、従業員から地位確認やバックペイ(解雇期間中の未払い賃金)の支払いを求める訴訟や労働審判を起こされる可能性があります。敗訴すれば多額の金銭的負担が生じます。さらに、障害者の安定雇用を条件とする各種助成金(例:特定求職者雇用開発助成金など)は、その趣旨から継続雇用が前提です。不適切な解雇は支給停止や、場合によっては過去に遡っての返還命令を受けるリスクもあり、企業の財務に直接的な打撃を与えます。
行政上のリスク
法定雇用率が未達となれば、行政指導の対象となり、不足人数に応じた障害者雇用納付金の支払い義務が生じます。これは単なる金銭負担にとどまりません。度重なる指導にもかかわらず改善が見られない場合は、厚生労働省のウェブサイトなどで社名が公表されることもあり、企業のコンプライアンス体制そのものが社会的に問われる事態に発展します。
レピュテーションリスク(評判リスク)
現代において最も恐ろしいリスクの一つです。「障害者を不当に解雇した企業」という評判は、SNSなどを通じて瞬時に、そして意図しない形で拡散する可能性があります。一度損なわれた社会的信用を回復するのは容易ではありません。結果として、BtoCビジネスであれば顧客離れに、BtoBビジネスであれば取引上の不利益に繋がります。また、採用市場においても致命的で、優秀な人材からの応募が激減するだけでなく、既存の従業員の士気低下や離職を招くなど、事業の根幹を揺るがす深刻なダメージに繋がりかねません。
これらのリスクを正しく認識し、解雇は単なる労務問題ではなく、企業の存続にも関わる重大な経営リスクであると理解することが不可欠です。
【法的条件】障害者の解雇が認められる場合・認められない場合の境界線
では、どのような場合に解雇が認められ、どのような場合に認められないのでしょうか。その境界線を分けるのが、企業側が「合理的配慮」と「解雇回避努力」を尽くしたかどうかです。
原則として解雇が認められにくいケース
企業の担当者が特に判断に迷う以下の理由は、それ単体で解雇の正当性を主張することは困難です。
能力不足・成績不良
期待した業務遂行能力に達しない場合、企業側はまず、業務指示や指導方法が適切であったか、本人の障害特性に合った業務設計であったか、必要な教育・研修の機会を提供したか、といった点を問われます。業務の指示が大雑把でなかったか、本人が質問しやすい環境だったかなど、マネジメント側の在り方が厳しく評価されます。
協調性の欠如
障害特性が原因で他の従業員とのコミュニケーションに課題が生じている場合、企業には本人への指導だけでなく、周囲の従業員への理解促進(例:障害特性に関する研修の実施)や相談体制の整備といった環境調整の義務があります。放置したまま「協調性がない」と判断するのは許されません。
体調不良による勤怠不良
体調不良による欠勤が続く場合でも、まずは休職制度の適用や、時短勤務、在宅勤務への切り替え、通院への配慮、業務負荷の軽減といった対応が求められます。これらの配慮を行わずに解雇に踏み切れば、安全配慮義務違反や差別的取り扱いを問われる可能性が極めて高いでしょう。
解雇の正当性が検討されるための3つの要件
障害のある社員の解雇がやむを得ないと判断されるには、少なくとも以下の3つの要件を客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
- 業務遂行が著しく困難であること:合理的配慮を尽くしてもなお、担当業務の遂行が明らかに不可能、あるいは企業の業務運営に重大な支障を及ぼす状態であること。「支障」の程度も客観的に評価され、単なる生産性の低下だけでは不十分とされる場合が多いです。
- 改善の見込みがないこと:十分な指導や教育、配置転換などを試みたにもかかわらず、改善の見込みが全く立たないこと。ここでの「配置転換」は、形式的なものではなく、本人の能力や特性を考慮した上で、現実的に配置可能な部署を真摯に検討したかどうかが問われます。
- 解雇以外の他の手段がないこと:休職、業務内容の変更、他部署への異動など、雇用を継続するためのあらゆる手段を検討し、実行してもなお、問題が解決しないこと。解雇は「最終手段」でなければならない、という原則です。
これらを満たすには、障害者本人の状況だけでなく、企業側の「支援の努力」が最も重要な判断材料となります。そのため、面談記録、指導履歴、検討した配慮の内容などを具体的に記録として残すことが、企業防衛の観点からも不可欠です。
解雇トラブルを未然に防ぐ!安定雇用を実現する5つの実務ポイント
解雇という深刻な事態を回避するためには、場当たり的な対応ではなく、採用から定着までの一貫した仕組みづくりが不可欠です。どの企業でも実行可能で、かつ効果的な5つの実務ポイントを解説します。
採用選考段階での「戦略的ミスマッチ防止」
すべての問題は、入口のミスマッチから始まります。募集段階で、担当業務、必要なスキル、職場の環境などを具体的に明記したジョブディスクリプション(職務記述書)を整備しましょう。面接では、応募者本人から障害特性や必要な配慮事項について具体的にヒアリングし、企業が提供できる配慮とすり合わせる「建設的対話」の場を設けることが、後のトラブルを防ぐ上で最も重要です。「どのような状況で困ることがありますか」「その際、どのようなサポートがあれば働きやすいですか」といった具体的な質問を通じて、相互理解を深めます。
合理的配慮の「継続的かつ柔軟な」提供
合理的配慮は、採用時に一度行えば終わりではありません。本人の体調や業務の習熟度に応じて、継続的に見直し、柔軟に調整することが求められます。例えば、定期的な面談を通じて業務負荷を再評価し、必要に応じて勤務時間を調整したり、通院に配慮したり、業務で使うツール(例:ノイズキャンセリングヘッドホン、読み上げソフト)を変更したりといった日々の細やかな調整が、安定した就労の鍵となります。
強みを活かす「業務の切り出しと最適設計」
既存の業務プロセスにそのまま当てはめるのではなく、本人の強みや特性を活かせる業務を組織内から戦略的に切り出す視点が重要です。例えば、高い集中力を活かせるデータ入力やチェック業務、丁寧な作業が得意な特性を活かせるファイリングや備品管理など、適材適所の配置は本人の活躍を促し、組織全体の生産性向上にも繋がります。これは「やさしい仕事」を与えるのではなく「特性が活きる仕事」を任せるという発想の転換です。
成長を支える「指導・教育体制とモニタリング」
指示は具体的に、フィードバックは客観的な事実に基づいて行うなど、現場のマネジメント層の指導スキル向上が不可欠です。月1回以上の定期面談(モニタリング)を設定し、業務上の課題や悩みを早期に発見・解決する体制を整えましょう。現場の上司が一人で抱え込まないよう、人事部が面談に同席したり、相談窓口となったりするサポート体制も重要です。指導や面談の内容を記録に残しておくことは、本人の成長支援に役立つだけでなく、万が一の際に企業の対応の正当性を証明する重要な証拠となります。
組織全体で支える「社内理解の促進と外部連携」
障害者雇用は人事部だけの仕事ではありません。経営層から現場の社員まで、全社で障害の多様性について学ぶ機会(例:アンコンシャスバイアス研修、当事者を招いた講演会など)を設け、共に働く仲間として自然に協力し合える風土を醸成することが、定着支援の最も強力な基盤です。また、自社だけで抱え込まず、就労移行支援事業所やジョブコーチ、地域の就労支援センターといった外部の専門機関と連携し、専門的な知見を活用することも安定雇用への近道です。
【攻めの視点】安定雇用を企業の成長に繋げるマネジメントのコツ
解雇リスクを回避するという「守り」の視点から一歩進み、障害者雇用を企業の成長に繋げる「攻め」のマネジメントを実践することも可能です。重要なのは、障害のある社員を単なる「コスト」や「リスク」としてではなく、組織に新たな価値をもたらす「タレント(人材)」として認識することです。
1.「できること」「得意なこと」の源泉
まず、障害特性を「できないこと」のリストとして見るのではなく、「できること」「得意なこと」の源泉として捉え直す視点が求められます。例えば、特定の物事に対する強いこだわりは、品質管理や校正といった正確性が求められる業務において、他の誰にも真似できない高いパフォーマンスを発揮する可能性があります。このように、本人の強みと業務内容を戦略的にマッチングさせることで、個人の活躍が事業への直接的な貢献に繋がります。
2.小さな成功体験の積み重ね
次に、エンゲージメントを高める工夫として「小さな成功体験の積み重ね」が有効です。本人のスキルや習熟度に合わせて達成可能な目標を設定し、クリアするごとに具体的に評価・賞賛することで、本人の自信と仕事へのモチベーションを育みます。このプロセスは、自己肯定感を高め、より挑戦的な業務に取り組む意欲を引き出す好循環を生み出します。
さらに、定期的な面談を通じて、本人のキャリアに対する意向や目標を共有し、企業としてどのような成長を期待しているのか、どのようなキャリアパスを用意できるのかを具体的に示すことも重要です。障害の有無にかかわらず、社員が成長できる機会を提供することは、優秀な人材のリテンションに繋がります。実際に、障害のある社員の中からリーダーや管理職が生まれることは、組織全体のダイバーシティを体現し、他の社員にとっても大きな刺激となります。
障害者雇用への真摯な取り組みは、多様な人材が活躍できる組織風土を醸成し、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。それは結果的に、イノベーションの創出や企業価値の向上に大きく貢献する、未来への投資となるのです。
まとめ:解雇回避から、企業価値向上のための戦略的人材活用へ
本記事では、障害者雇用における解雇のリスクと、それを回避するための具体的な方策について解説しました。障害者雇用における安易な解雇は、法的に極めて認められにくく、企業にとって訴訟や賠償、社会的信用の失墜といった計り知れないリスクを伴います。
解雇という最終手段を検討する前に、企業には「合理的配慮」の提供を軸とした、あらゆる手立てを尽くす義務があります。
- 採用段階での戦略的なマッチング
- 本人との対話を通じた継続的な業務調整
- 成長を支援する指導・教育体制の整備
- 組織全体での理解促進と外部機関との連携
これら一連の取り組みは、解雇リスクを回避するための「守りの一手」であると同時に、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる強い組織を築くための「攻めの一手」でもあります。
障害のある社員が安心して長く働ける環境を整えることは、コンプライアンス遵守という側面だけでなく、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、ひいては企業価値の向上に直結する重要な経営戦略です。もし、現在対応に苦慮している、あるいは今後の雇用推進に不安がある場合は、自社だけで抱え込まず、障害者雇用に詳しい社会保険労務士や弁護士、専門の支援サービスへ速やかに相談することをお勧めします。専門家の知見は、問題解決への最も確実な近道となるはずです。