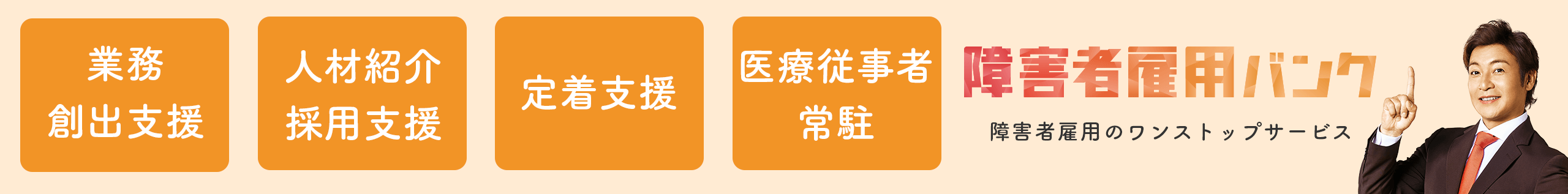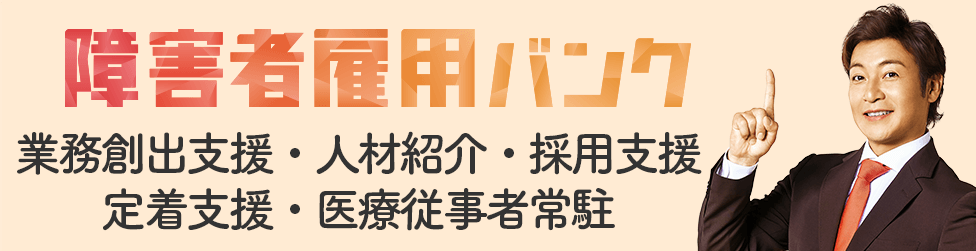障害者雇用の除外率とは?制度廃止に向けた計算方法と企業の対策

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに:貴社の障害者雇用義務、変わります。なぜ今「除外率」の理解が不可欠なのか?
障害者雇用に取り組む企業の経営層、人事責任者の皆様にとって、法定雇用率の達成は常に重要な経営課題の一つです。その複雑な計算に関わる専門的な制度の一つに「除外率制度」が存在することをご存じでしょうか。この制度は、特定の業種において、障害者の就業が困難であると認められる職務があることを考慮し、法定雇用率の算定時に一定の労働者数を分母から除外することを認める特例措置です。
一見すると、企業側の負担を軽減する制度に思えるかもしれません。しかし、社会情勢の変化とノーマライゼーションの理念の浸透を背景に、この除外率制度は今、大きな歴史的転換点を迎えています。具体的には、2025年4月から除外率が一律で引き下げられ、将来的には完全に廃止されることが決定しています。
これは、これまで除外率制度の恩恵を受けてきた企業にとって、実質的な法定雇用率の引き上げと同義であり、雇用すべき障害者の人数が大幅に増加することを意味します。この制度改正のインパクトを正しく理解し、今から計画的に対策を講じなければ、近い将来、法定雇用率の未達成やそれに伴う納付金の発生、さらには行政指導や企業名公表といった重大なリスクに直面しかねません。
本記事では、この重要な局面にある「除外率制度」に焦点を当て、その基礎知識から具体的な計算方法、そして制度改正の核心と企業が取るべき具体的な対応策までを網羅的に解説します。制度廃止という変化を乗り越え、企業の持続的成長に繋げるための知識と戦略を、ぜひ本稿から得てください。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
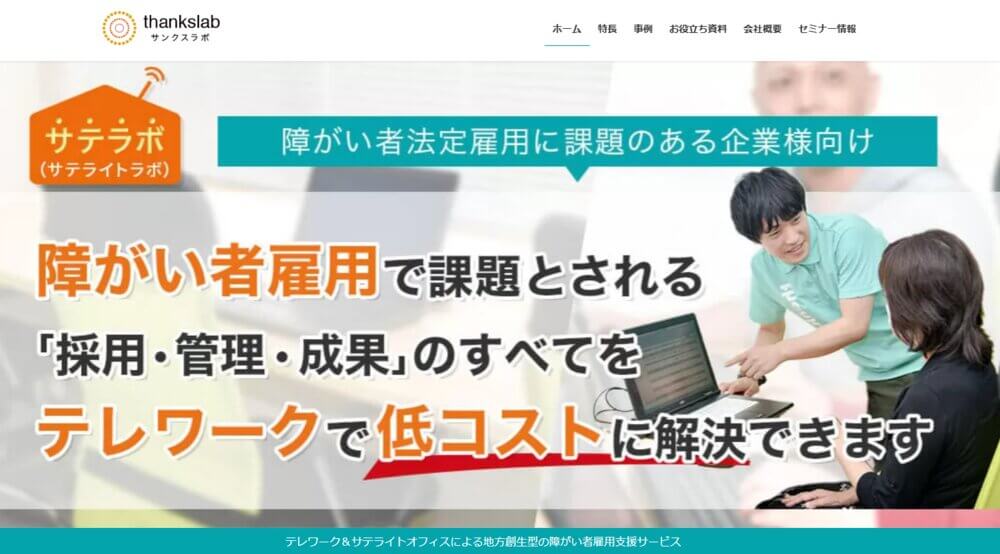
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
そもそも障害者雇用の「除外率制度」とは?制度の目的と基礎知識
障害者雇用率制度における「除外率制度」とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる特定の職種が多い業種について、雇用率の算定対象となる労働者の総数から、一定の割合で労働者数を控除(除外)することを認める特例的な制度です。
この制度は、障害者雇用促進法の前身である身体障害者雇用促進法が制定された1960年当初から存在し、当時の社会状況や労働環境を反映したものでした。具体的には、建設現場の高所作業員や、海上を航行する船舶の船員、あるいは危険を伴う業務に従事する警察官や自衛官など、障害の種類や程度によっては、安全の確保や業務の遂行が極めて難しいと考えられる職務への配慮がその根底にあります。
制度の目的は、こうした特殊な業種に対して、画一的な雇用率を適用するのではなく、業種の実情に合わせて雇用義務を調整することで、制度全体の公平性と実効性を担保することにありました。
しかし、この制度はあくまで「特例」です。すべての企業に適用されるわけではなく、障害者雇用促進法施行規則で定められた特定の業種のみが対象となります。また、企業全体に適用されるのではなく、除外率が設定された業種の事業所に所属する労働者に対してのみ適用される点も重要です。例えば、建設会社であっても、本社で働く事務職の従業員は除外の対象とはならず、現場作業員などの特定の職務に従事する従業員のみが計算の対象となるのです。
この制度の存在により、対象となる企業は、見かけ上の従業員数が同じであっても、非対象の企業に比べて雇用すべき障害者の人数が少なく計算されていました。しかし、この半世紀以上続いた前提が、今まさに崩れようとしています。技術革新や労働安全衛生の向上、そして何よりも障害者が活躍できる職域が広がった現代において、除外率制度はその歴史的役割を終え、新たなステージへと移行する段階に来ているのです。
【具体例で解説】除外率を用いた障害者雇用率の計算方法
除外率制度が自社の障害者雇用義務にどう影響するのかを理解するには、具体的な計算方法を知ることが不可欠です。ここでは、順を追って計算プロセスを解説します。
STEP1:基本となる法定雇用障害者数の計算式
まず、除外率を考慮しない場合の基本的な計算式を理解しましょう。法定雇用障害者数は、企業の常用労働者数に法定雇用率を乗じて算出します。
- 算定基礎となる労働者数 = 常用労働者数 + (短時間労働者数 × 0.5)
- 法定雇用障害者数 = 算定基礎となる労働者数 × 法定雇用率 ※法定雇用率は2025年7月時点で2.5%です。 ※計算結果の端数は切り捨てます。
STEP2:除外率を適用する場合の計算式
次に、除外率を適用する場合の計算です。ポイントは、算定基礎となる労働者数から「除外すべき労働者数」を差し引く点にあります。
- 除外すべき労働者数 = 除外率設定業種の労働者数 × 除外率
- 除外率適用後の算定基礎 = 本来の算定基礎 − 除外すべき労働者数
- 法定雇用障害者数 = 除外率適用後の算定基礎 × 法定雇用率
STEP3:モデルケースでの計算シミュレーション
具体的な数値で見てみましょう。 【モデルケース】
- 企業全体の常用労働者数:1,000人(うち建設事業部門の現場労働者:400人)
- 短時間労働者数:0人
- 業種:建設業(除外率20%)
- 法定雇用率:2.5%
【現在の除外率(20%)を適用する場合】
- 除外すべき労働者数:400人 × 20% = 80人
- 除外率適用後の算定基礎:1,000人 − 80人 = 920人
- 法定雇用障害者数:920人 × 2.5% = 23人
【2025年4月からの改正後除外率(10%)を適用する場合】
- 改正後の除外率:20% − 10% = 10%
- 除外すべき労働者数:400人 × 10% = 40人
- 除外率適用後の算定基礎:1,000人 − 40人 = 960人
- 法定雇用障害者数:960人 × 2.5% = 24人
このケースでは、法改正により、雇用義務が1人増加します。除外率の引き下げは、法定雇用率そのものが変わらなくても、企業の雇用義務人数に直接的な影響を与えます。自社の数値を当てはめて正確にシミュレーションすることが極めて重要です。
除外率の対象となる業種とそれぞれの除外率一覧
除外率制度は、全ての業種に適用されるわけではありません。障害者雇用促進法施行規則の別表に定められた特定の業種のみが対象となります。以下に、主な対象業種と、2025年3月31日までの現行の除外率、そして2025年4月1日からの改正後の除外率を記載します。自社の事業がこれらに該当するかどうか、また、改正による影響がどの程度あるかをご確認ください。
- 除外率80%の業種(改正後70%) 船員による運送事業など(船員法第1条に規定する船員を雇用する事業)
- 除外率60%の業種(改正後50%) 旅客定期航路事業など(船員以外の乗組員を雇用する事業)
- 除外率55%の業種(改正後45%) 非鉄金属第一次製錬・精製業など
- 除外率45%の業種(改正後35%) 石炭・亜炭鉱業
- 除外率35%の業種(改正後25%) 林業、非鉄金属・同合金第二次製錬・精製業
- 除外率30%の業種(改正後20%) 金属鉱業、砕石・砂利採取業、鉄鋼業、鋳物製造業、道路旅客運送業、水運業、倉庫業、こん包業
- 除外率25%の業種(改正後15%) 木材・木製品製造業、パルプ・紙製造業、窯業・土石製品製造業、港湾運送業
- 除外率20%の業種(改正後10%) 建設業、重構桁・金属プレス製品・その他の金属製品製造業、道路貨物運送業
- 除外率15%の業種(改正後5%) 各種商品卸売業、衣服・身の回り品卸売業など
- 除外率5%の業種(改正後0%=廃止) 食料品・たばこ卸売業、医薬品・化粧品卸売業など
また、国および地方公共団体の非現業機関においても、警察官、自衛官、皇宮護衛官、刑務官、入国警備官など、特定の官職には別途、除外率が設定されています。これらの業種に該当する企業は、2025年4月からの除外率引き下げによる雇用義務人数の増加に備える必要があります。
【最重要】2025年制度改正の核心と企業へのインパクト
これまで見てきた除外率制度は、2025年4月1日をもって大きな転換点を迎えます。これは障害者雇用に取り組むすべての企業、特に除外率対象業種の企業にとって極めて重要な変更です。
なぜ制度が改正されるのか?
制度が設けられた1960年代から半世紀以上が経過し、日本社会は大きく変化しました。
ノーマライゼーション理念の浸透
障害の有無にかかわらず、誰もが社会の一員として共に生き、支え合うという考え方が社会の基本理念として定着しました。特定の職種をあらかじめ障害者には困難と決めつけるのではなく、個々の能力や意欲に応じて活躍できる社会を目指す動きが加速しています。
技術革新と労働安全の向上
ICT技術の発展、ロボットやパワーアシストスーツの導入など、テクノロジーの力で身体的な負担を軽減できるようになりました。また、労働安全衛生に関する法整備や企業の意識向上により、かつて危険とされた職場の安全性も格段に向上しています。
障害者の就業意欲と職域の拡大
障害のある方々の教育水準の向上や、社会全体の支援体制の充実に伴い、就業への意欲は非常に高まっています。実際に、これまで障害者の就業が難しいとされてきた分野で活躍する事例も数多く生まれています。
これらの背景から、障害者雇用政策審議会での議論を経て、除外率制度はその歴史的役割を終え、段階的に縮小・廃止する方針が決定されました。
具体的な改正内容とそのインパクト
- 2025年4月1日から一律10ポイント引き下げ: 全ての対象業種で除外率が一律10ポイント引き下げられます。
- 将来的には完全廃止へ: 今回の引き下げは第一段階であり、今後も段階的に除外率を引き下げ、最終的には制度自体を完全に廃止することが予定されています。
この改正が企業に与えるインパクトは、「実質的な法定雇用率の引き上げ」です。法定雇用率のパーセンテージ自体は変わらなくても、算定の分母となる労働者数が増えるため、結果として雇用しなければならない障害者の人数が増加します。特に、建設業や運輸業、製造業など、これまで比較的高い除外率が適用されてきた企業ほど、その影響は甚大です。自社の正確な影響人数を試算し、早期に対策を講じることが、コンプライアンス遵守と安定的な事業運営の鍵となります。
除外率廃止に向けて企業が今から取るべき3つの対策
除外率の段階的な引き下げと将来的な廃止は、対象企業にとって待ったなしの経営課題です。この大きな変化を乗り越え、むしろ組織変革の好機とするために、企業が今から取り組むべき具体的な対策を3つのステップで解説します。
対策1:正確な雇用義務人数の再計算と現状把握
まず着手すべきは、自社の現状を正確に把握することです。
- 影響人数のシミュレーション: 人事部門が中心となり、2025年4月からの新しい除外率を適用した場合、自社の法定雇用義務人数が何人になるのかを再計算します。これにより、新たに雇用する必要がある人数(不足人数)が具体的に可視化されます。
- 経営層・事業部門との共有: 算出した結果は、速やかに経営層に報告し、全社的な課題としての認識を共有します。また、除外率が適用されていた事業部門の責任者とも情報を共有し、今後の採用・配属に向けた協力を要請することが不可欠です。不足人数の達成は、人事部だけの問題ではなく、全社で取り組むべきミッションであることを明確にします。
対策2:新たな職域開拓と戦略的な業務の切り出し
雇用義務人数が増加するということは、これまで以上に障害のある社員が活躍できる場を社内に創出する必要があるということです。
- 固定観念の打破: 「この部署では障害者の雇用は難しい」といった固定観念を捨て、全社的な視点で業務の棚卸しを行います。
- 業務の切り出しと再構築: 各部署の業務フローを分析し、「障害の特性を強みとして活かせる業務」や「ICTツール等を活用すれば遂行可能な業務」を意図的に切り出します。例えば、几帳面さや集中力が求められるデータチェック、図面修正、品質管理、研究開発の補助業務などが考えられます。このプロセスは、結果的に既存業務の効率化や標準化にも繋がります。
対策3:採用戦略の抜本的な見直しと外部リソースの活用
これまで通りの採用活動だけでは、増加する採用目標を達成することは困難です。採用戦略を抜本的に見直す必要があります。
- 採用チャネルの多様化: ハローワークだけに頼るのではなく、地域の就労移行支援事業所、特別支援学校、障害者雇用に特化した人材紹介会社など、多様なチャネルとの連携を強化します。
- 採用基準・選考プロセスの見直し: 障害特性への理解に基づいた採用基準を設け、面接では本人の能力や意欲、必要な配慮などを丁寧に確認するプロセスを構築します。職場実習の受け入れも、ミスマッチを防ぐ有効な手段です。
- 外部専門サービスの活用: 自社だけで採用から定着までを担うのが難しい場合は、障害者雇用のコンサルティングサービスや、採用・定着を一体で支援するサテライトオフィス型サービスなどの活用も有効な選択肢となります。
まとめ:除外率廃止は、多様な人材活用を加速させる好機
本記事では、障害者雇用における除外率制度の基礎知識から、2025年に迫る制度改正の重要性、そして企業が取るべき具体的な対策までを網羅的に解説しました。除外率の段階的な引き下げと将来的な廃止は、対象となる企業にとって、雇用すべき障害者人数の増加という直接的なインパクトをもたらす、避けては通れない大きな変化です。
しかし、この変化を単なる「負担増」や「リスク」として捉えるのは早計です。むしろ、これはこれまで障害者の活躍の場が少ないとされてきた業種や職種において、本格的にダイバーシティ&インクルージョンを推進する絶好の「機会」と捉えるべきです。
新たな職域を開拓し、多様な人材がその能力を最大限に発揮できるような業務プロセスや職場環境を構築する取り組みは、障害の有無にかかわらず、すべての従業員の働きやすさと生産性の向上に繋がります。それは、組織全体の創造性を高め、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となるでしょう。
まずは、改正後の自社の数値を正確に把握することから始めてください。そして、全社一丸となって、この変革を前向きな組織進化のきっかけとして活用していくことが、今まさに求められています。