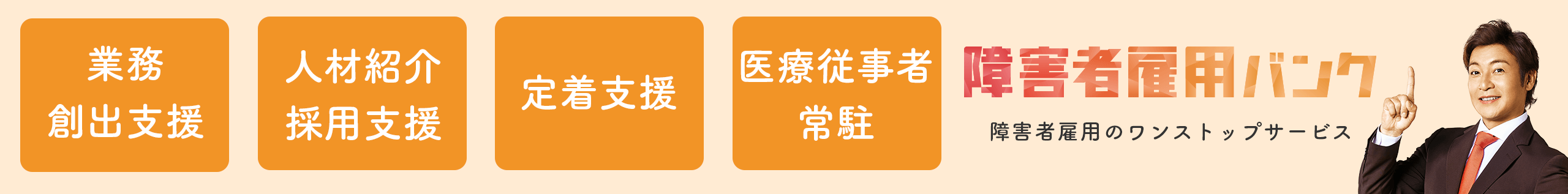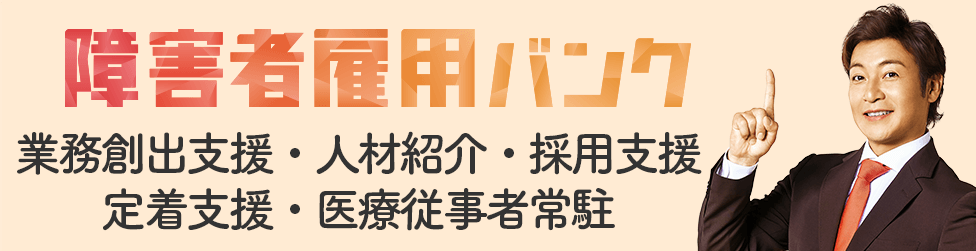障害者雇用の罰金(納付金)とは?計算方法から企業名公表リスクまで徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
企業活動において、法令遵守は経営の根幹です。中でも「障害者雇用促進法」に基づく障害者の雇用義務は、もはや任意ではなく、すべての企業が向き合うべき法的義務であり社会的責務です。法定雇用率が未達成の企業には、一般に「罰金」と認識されている金銭的な負担が発生します。
しかし、この制度は単なるペナルティなのでしょうか。実際には「障害者雇用納付金」と呼ばれる制度であり、その目的は罰することだけではありません。未達成のリスクは納付金の支払いに留まらず、行政指導や企業名の公表といった、より深刻な経営リスクにまで及びます。
本記事では、企業の意思決定に関わる決裁者や人事責任者の方々が知っておくべき障害者雇用納付金制度の仕組み、具体的な計算方法、そして企業が見過ごしてはならない経営リスクについて、専門的かつ分かりやすく解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
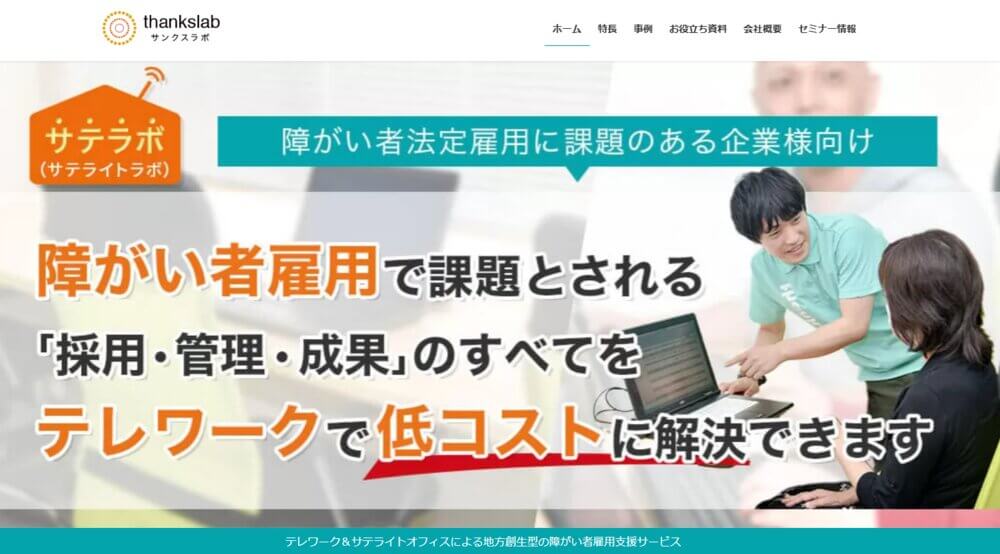
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
「罰金」ではない?障害者雇用納付金の本当の目的と仕組み
多くの企業担当者が法定雇用率未達成の際に懸念する「罰金」ですが、法律上の呼称は正確ではありません。正しくは「障害者雇用納付金制度」に基づく**「納付金」**です。この二つは性質が根本的に異なり、その違いを理解することが第一歩となります。
障害者雇用納付金は「企業間の経済的負担の調整」が目的
納付金制度は、障害者を雇用する企業とそうでない企業との間に生じる経済的負担の差を調整し、社会全体として障害者雇用を推進することを目的としています。つまり、ペナルティではなく相互扶助の精神に基づいた制度です。
- 仕組み: 雇用義務を果たしている企業は、障害者のために特別な施設改善や職場環境の整備、専門の指導員配置などで追加の経済的負担を負っています。法定雇用率未達成の企業が納める納付金は、これらの費用を助成するための原資となります。
- 納付金の使い道: 集められた納付金は、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対して支給される「障害者雇用調整金」や、100人以下の企業向けの「報奨金」の財源となります。
このように、納付金は罰則というよりも、企業間の公平性を保ちながら社会全体の雇用機会を創出するためのシステムと言えます。ただし、「納付金を支払えば義務を果たしたことになる」という安易な考えは、後述するさらなるリスクを招くため極めて危険です。
注意すべき本当の「罰則(罰金)」
納付金制度とは別に、障害者雇用促進法には明確な**「罰則(罰金)」規定**が存在します。これは義務違反に対する明確な刑事罰であり、納付金とは全く性質が異なります。
- 対象となる行為:
- 雇用状況の未報告・虚偽報告: 企業は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務(通称:ロクイチ報告)がありますが、これを怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合。
- 調査の拒否: 厚生労働省からの関連調査を正当な理由なく拒否した場合。
- 罰則の内容: 上記の違反があった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
決裁者や人事責任者としては、雇用率未達成による「納付金」のリスクと、報告義務違反などによる刑事罰としての「罰金」のリスクを明確に区別して理解し、両方の義務を確実に果たしていく必要があります。
【2025年最新】法定雇用率の動向と自社の義務範囲の確認
障害者雇用を検討する上で、全ての基礎となるのが「法定雇用率」です。この率は定期的に見直されており、最新の動向を正確に把握しておくことが企業のリスク管理において不可欠です。
法定雇用率の段階的な引き上げ
障害者雇用の対象者を拡大するため、法定雇用率は段階的に引き上げられています。
- 2024年4月1日〜: 従来の2.3%から**2.5%**へ引き上げ。
- 2026年7月1日〜: さらに**2.7%**へ引き上げ予定。
この変更により、これまで義務のなかった企業が新たに対象となったり、既存の対象企業で必要な雇用人数が増加したりするため、中長期的な視点での人員計画の見直しが急務です。
雇用義務の対象となる事業主と「常用労働者」の定義
法定雇用の義務対象となるのは、常用労働者を40.0人以上雇用する事業主です。自社が対象となるかを判断するには、「常用労働者」の正しいカウント方法を理解する必要があります。
- 常用労働者の定義: 雇用契約の形態(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)にかかわらず、1年を超えて雇用される見込みのある労働者を指します。
- カウント方法:
- 週の所定労働時間が30時間以上の労働者: 1人としてカウント。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者: 0.5人としてカウント。
- 週の所定労働時間が20時間未満の労働者は、現状では算定基礎に含まれません。
この計算に基づき、自社の正確な常用労働者数を把握し、それに対して法定雇用率を乗じて必要な雇用障害者数を算出することが、すべての始まりとなります。この計算が、納付金の発生有無やその後の行政指導の対象となるかを判断する基準となるため、人事部門は極めて正確な管理を求められます。
なお、かつて一部業種で適用されていた「除外率制度」は段階的に縮小・廃止される方向であり、いかなる業種であっても障害者雇用を推進すべきという社会的な要請が強まっています。
納付金の計算方法とシミュレーション【不足1人月5万円】
法定雇用率の未達成が確定した場合、企業が最も関心を寄せるのが、具体的にいくらの金銭的負担が発生するのかという点です。
納付金の対象企業と金額
まず、障害者雇用納付金の対象となるのは、常用労働者数が100人を超える企業です。100人以下の企業は、現時点では未達成であっても納付金の徴収対象とはなりませんが、雇用義務そのものが免除されるわけではない点に注意が必要です。
- 納付金額: 法定雇用率に対して不足している障害者の人数1人につき月額50,000円。
- 年間負担額: 不足1人あたり60万円。
この金額は企業の規模や業績に関わらず一律であり、不足人数が多ければ多いほど、その負担は雪だるま式に増加していきます。
【シミュレーション】自社の納付金額を計算する方法
具体的な納付金額は、次のステップで計算します。
ステップ1:法定雇用障害者数を算出する 自社が雇用すべき障害者の人数を計算します。 (常用労働者数 + 短時間労働者数 × 0.5)× 法定雇用率(2.5%) ※計算結果の小数点以下は切り捨てます。
ステップ2:不足人数を算出する 法定雇用障害者数 − 実際の実雇用障害者数 ※実雇用障害者数のカウントにも、重度障害者はダブルカウントするなど独自のルールがあります。
ステップ3:年間納付額を算出する 不足人数 × 50,000円 × 12ヶ月
<計算例> 常用労働者450人、短時間労働者100人、実雇用障害者数8人の企業の場合
- 算定基礎となる労働者数: 450人 + (100人 × 0.5) = 500人
- 法定雇用障害者数: 500人 × 2.5% = 12.5人 → 12人 (小数点以下切り捨て)
- 不足人数: 12人 − 8人 = 4人
- 年間納付額: 4人 × 600,000円 = 240万円
この申告と納付は、毎年、対象年度の翌年度の4月1日から5月15日までに行う必要があり、経理・人事部門は年間のスケジュールに組み込んで対応しなければなりません。
納付金より深刻?企業が見過ごせない3つの経営リスク
障害者雇用の未達成がもたらす影響は、納付金の支払という直接的な金銭コストだけに留まりません。むしろ、企業の信頼性や持続可能性を揺るがしかねない、より深刻な経営リスクが存在します。
リスク1:ハローワークからの行政指導
法定雇用率が著しく低い企業に対しては、まず管轄のハローワークから障害者の雇入れに関する計画書の作成が指導されます。
- 雇入れ計画作成命令: 2年間の採用計画を策定し、その進捗を定期的に報告するよう求める法的な命令です。これは企業の採用活動に直接的な行政の介入が始まることを意味します。
- 指導の強化: 計画通りに進捗が見られない場合、指導は「適正実施勧告」や「特別指導」といった、より厳しい段階へと進みます。このプロセスは人事部門にとって大きな負担となるだけでなく、企業の自主的な経営判断が制約される状況に陥ることを意味します。
リスク2:改善が見られない場合の「企業名公表」
度重なる指導にもかかわらず、改善が全く見られないと判断された場合、最終手段として厚生労働省はその企業名をウェブサイトなどで公に発表します。これは、障害者雇用に対する取り組みが著しく不十分であると社会的に告知される「無形の罰」であり、企業のレピュテーションに深刻かつ永続的なダメージを与えます。
- もたらされる影響:
- 取引先や金融機関からの信用失墜
- 優秀な人材の獲得競争における圧倒的な不利
- ブランドイメージの悪化による顧客離れや不買運動
- 一度公表されれば、その事実はデジタルタトゥーとして残り続ける
これはもはや人事部門だけの問題ではなく、全社的な危機管理マターとなります。
リスク3:CSR・ESG評価の低下による信頼失墜
現代の経営環境では、**ESG(環境・社会・ガバナンス)**への取り組みが投資家や顧客からの評価を大きく左右します。障害者雇用は、まさに「S(社会)」の中核をなすテーマです。
- 投資家からの評価低下: 法定雇用率の未達成や企業名公表といった事実は、企業の社会的責任に対する意識の低さを露呈するものと見なされます。これにより、ESG評価が低下し、機関投資家からの投資が引き揚げられる可能性があります。
- ブランドイメージの悪化: 公式サイトでダイバーシティを謳いながら、実態が伴っていないことが明らかになれば、ダブルスタンダードと見なされ、顧客や求職者からの信頼を大きく損ないます。社内に目を向けても、自社が社会的な責任を果たしていないという事実は、従業員のエンゲージメントやロイヤリティを低下させる要因となり得ます。
リスクを回避し、企業価値を高めるための社内体制構築
法定雇用率の達成は、単にリスクを回避するための受け身の活動ではありません。多様な人材が活躍できる組織を構築し、企業価値を高めるための攻めの経営戦略と捉えるべきです。リスクを最小化し、雇用を推進するための継続的な仕組みづくりが重要です。
1. 担当者任せにしない、部門横断型の管理体制
障害者雇用は人事部門の専属課題ではなく、法務・労務・現場部門など多岐にわたる課題です。経営トップがその重要性を理解し、明確なコミットメントを社内外に発信することが全ての出発点となります。その上で、各部門が連携した横断的な推進体制を構築することが不可欠です。特に、現場の管理職が障害特性への理解や適切なマネジメントができるよう、研修などの機会を提供することが成功の鍵を握ります。
2. 採用計画の見直しと採用手法の多様化
従来のハローワーク経由の公募だけで人材を確保しようとしても、採用競争が激化する中で限界があります。
- 連携先の多様化:
- 障害者雇用に特化した人材紹介サービス
- 実践的な職業訓練を行う就労移行支援事業所
- 地域の特別支援学校
- 情報発信の強化: 自社のウェブサイトや採用イベントで、障害者採用を積極的に行っている姿勢を明確に打ち出し、意欲の高い求職者へアピールすることも有効です。
これらの機関は企業のニーズと求職者の特性を理解した上でマッチングを行うため、採用の精度と定着率の向上が期待できます。
3. 業務の切り出しと職場環境の整備
採用した人材が定着し、活躍するためには、適切な業務と環境の提供が不可欠です。
- ジョブ・カービング: 既存の業務プロセスを見直し、障害特性や本人の希望に応じて任せられる業務を戦略的に切り出す考え方が有効です。
- 合理的配慮の提供: 物理的なバリアフリー化はもちろん、ICTツールを活用した情報保障や、相談しやすいメンター制度の導入といった「合理的配慮」の提供は、法律で定められた企業の義務であり、働きやすい環境を作る上で必須の取り組みです。
- 多様な働き方の検討: グループ全体で雇用を推進する「特例子会社制度」や、通勤の負担を軽減する「在宅雇用」など、柔軟な選択肢も視野に入れるべきです。
まとめ:制度遵守は“コスト”ではなく“経営戦略”
障害者雇用制度における罰金(納付金)とそれに伴うリスクは、単なるペナルティにとどまらず、企業の社会的信頼性や持続可能性に大きく関わる経営課題です。本記事のポイントを以下にまとめます。
- 法定雇用率未達の代償: 不足1人あたり月額5万円(年60万円)の納付金が発生する。
- 本当の罰金: ロクイチ報告の未提出や虚偽報告は、30万円以下の罰金という刑事罰の対象となる。
- 深刻な経営リスク: 納付金に加え、行政指導、企業名公表、ESG評価の低下という信頼を失うリスクが存在する。
- 今後の動向: 2026年には法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、対象企業の拡大と負担増加が予想される。
- 求められる対応: 担当者任せにせず、部門横断の体制を構築し、採用手法や職場環境を計画的に整備することが不可欠。
障害者雇用は“守るべき法令”であると同時に、企業価値を高める経営戦略の一環です。コストとして後ろ向きに捉えるのではなく、多様な人材の活躍が組織にもたらす新たな可能性への「投資」と捉えることが、今後の企業経営における重要な視点となるでしょう。