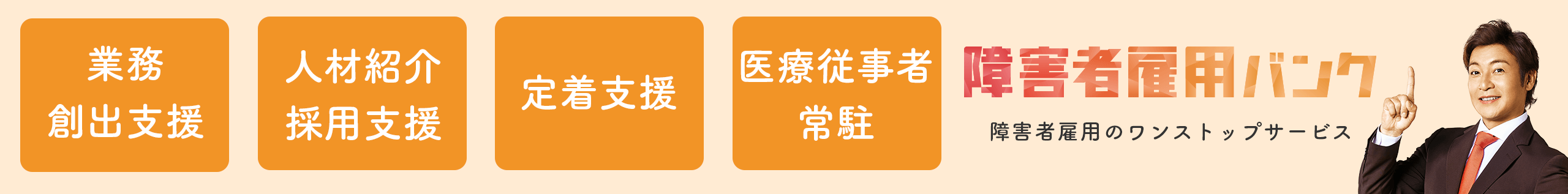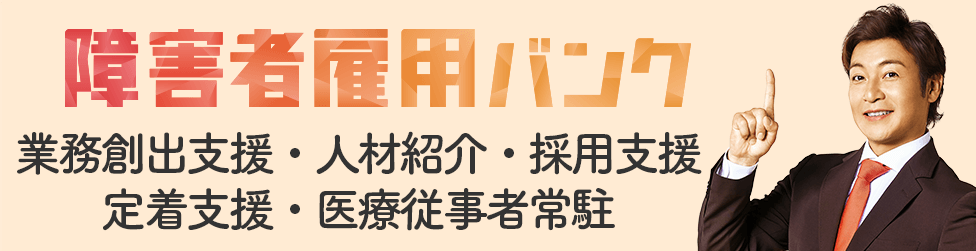障がい者向けのインターンシップとは?導入メリットと成功のポイントを徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
企業の多様性やインクルージョンへの取り組みが注目される中、「障がい者インターンシップ」の導入が新たな選択肢として広がりつつあります。障がいのある方に職場体験の機会を提供するこの取り組みは、雇用前の相互理解を深めるだけでなく、企業にとっても実務を通じた適性の確認や職場環境の見直しといったメリットがあります。しかし、ただ受け入れるだけでは真の成果にはつながりません。制度の意義を理解し、効果的な設計と運用を行うことが、インターンシップ成功のカギを握ります。
この記事では、障がい者インターンシップの基本から、導入のメリット、成功させるためのポイントまでをわかりやすく解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
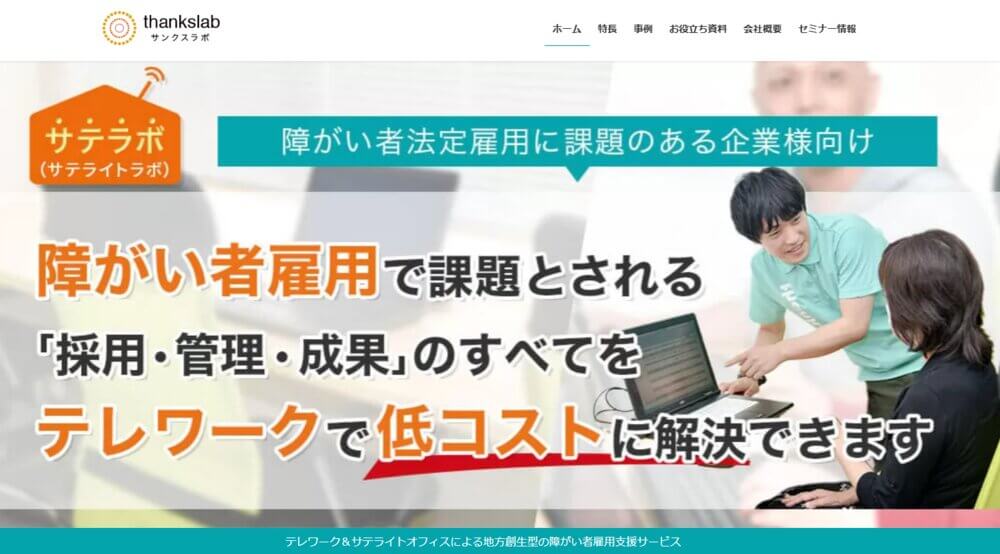
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障がい者向けインターンシップとは?その定義と目的
障がい者インターンシップとは、障害のある学生や一般の求職者が、企業において一定期間、実際の業務に携わる就労体験プログラムを指します。この制度の最も重要な目的は、参加者(インターン生)と受け入れ企業双方の相互理解を深めることにあります。
参加者にとっては、以下のような目的があります。
- 自己理解の深化: 自身の適性や興味関心、強みや課題を探る機会となります。
- 職業理解の促進: 具体的な仕事内容や職場の雰囲気、企業文化を実体験として知ることができます。
- キャリアプランの具体化: 働くことへのイメージを明確にし、将来のキャリア設計に役立てます。
- 就職活動への準備: 必要なスキルや配慮事項を企業に伝え、円滑な就職活動に繋げるための準備期間となります。
一方、企業側にとっては、以下のような目的が挙げられます。
- 人材の理解と発掘: 採用選考だけでは把握しきれない参加者の潜在的な能力、意欲、人柄、仕事への取り組み姿勢などを実務を通じて見極めることができます。
- 受け入れ体制の検証と整備: 自社の業務内容や職場環境が、障害のある方にとってどの程度適しているか、受け入れに必要な配慮(合理的配慮)は何かといった点を具体的に検証し、社内体制を整備・改善する契機となります。
- 採用ミスマッチの防止: 事前に相互理解を深めることで、入社後のギャップを減らし、定着率の向上に繋げます。
一般的なインターンシップとの最も大きな違いは、「合理的配慮」の提供が前提となる点です。参加者一人ひとりの障害特性や状況に合わせて、業務内容の調整、作業環境の整備(物理的なバリアフリー化、情報保障ツールの導入など)、コミュニケーション方法の工夫などが求められます。これには、プログラム開始前の丁寧なヒアリングと、実施中の状況に応じた柔軟な対応が不可欠です。
また、障がい者インターンシップは、障がい者雇用促進法などの関連法規の趣旨を踏まえ、障害のある方の職業的自立を支援するという社会的側面も持ち合わせています。単なる労働力としての体験に留まらず、参加者のキャリア形成支援と、企業のダイバーシティ&インクルージョン推進の双方に資する戦略的な取り組みとして位置づけられます。企業はこのインターンシップを通じて、多様な人材がその能力を最大限に発揮し、活躍できる組織基盤を築き、新たな価値創造へと繋げていくことが期待されるのです。障がい者雇用をより深く理解し、実践するための重要なステップと言えるでしょう。
障がい者向けのインターンシップの重要性
現代の企業経営においてダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進は、単なる社会貢献活動ではなく、持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営戦略として位置づけられています。特に、障がい者雇用促進法の改正に伴う法定雇用率の段階的な引き上げもあり、障がい者雇用への関心と具体的な取り組みの必要性は急速に高まっています。多くの企業が優秀な人材の確保と多様性に富んだ組織づくりを目指す中で、「障がい者雇用」は避けて通れないテーマとなりました。
このような背景の中、障害のある方の活躍を推進する具体的な施策として「障がい者インターンシップ」が注目されています。これは、障害のある学生や求職者が本格的な就職活動の前に、企業で一定期間の就労体験を積む制度です。企業にとっては、採用候補者の能力や適性、人柄などを従来の選考プロセスだけでは見極めきれない側面から深く理解し、同時に自社の受け入れ体制や合理的配慮のあり方を実践的に検証・整備する絶好の機会となります。一方、参加者にとっては、実際の業務内容や企業文化を肌で感じ、自身のキャリアプランを具体化させるための貴重なステップとなります。
しかし、障がい者インターンシップの導入と成功には、一般的なインターンシップとは異なる視点での計画的な準備と配慮が求められます。この記事では、障がい者雇用の推進を検討されている企業の人事部や経営層、決裁者の皆様に向けて、障がい者インターンシップの基礎知識から、導入によって企業が得られる具体的なメリット、導入と実施のためのステップ、そしてプログラムを成功に導くための重要なポイントまでを網羅的に解説します。本稿が、貴社における障がい者インターンシップ導入検討の一助となり、障がい者雇用を新たなステージに進めるための一歩となることを目指します。これは、企業の持続的成長に貢献する人材戦略の一環となり得る重要な取り組みなのです。
企業が障がい者インターンシップを導入するメリット
障がい者インターンシップの導入は、企業にとって単なる社会貢献活動に留まらず、多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。人事部や決裁者が理解しておくべき主な利点を以下に示します。
新たな人材の発掘と確保
従来の採用チャネルでは出会えなかった、意欲と能力の高い潜在的な人材に早期に接触できます。実務を通じてそのポテンシャルや職場への適応力を見極めることが可能となり、将来の優秀な社員候補を発掘する機会となります。
採用ミスマッチの低減と定着率の向上
インターンシップ期間を通じて、企業は候補者の適性や職場へのフィット感を慎重に評価でき、候補者は企業文化や業務内容を深く理解できます。これにより、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを大幅に低減し、早期離職の防止に繋がります。結果的に、採用コストの削減と人材の定着率向上に貢献します。
実践的な受け入れ体制の整備・改善
実際にインターン生を受け入れるプロセスを通じて、自社に必要な物理的な環境整備(バリアフリー化など)、情報保障のあり方、コミュニケーション方法、業務の切り出し方や指示の出し方などを具体的に検討し、課題を洗い出すことができます。これにより、将来的な障がい者雇用を円滑に進めるための実践的なノウハウが社内に蓄積されます。
従業員の障害に対する理解促進と意識改革
インターン生と日常的に接し、共に働く経験を通じて、社員は多様な価値観や働き方に触れることになります。障害のある同僚と共に働くことへの心理的な壁が自然と低減され、障害への理解が深まります。これは、インクルーシブな組織風土の醸成に繋がり、組織全体の活性化を促します。
企業の社会的責任(CSR)とブランドイメージの向上
障がい者雇用への積極的な姿勢は、企業の社会的責任を果たしている証として、外部からの評価を高めます。ステークホルダー(投資家、顧客、地域社会、従業員など)からの信頼を得て、企業イメージの向上に寄与します。これは、採用活動や従業員エンゲージメントにも好影響を与える可能性があります。
イノベーションの促進と業務改善
多様な視点や経験を持つ人材が加わることで、従来の業務プロセスに対する新たな気づきや改善提案が生まれることがあります。固定観念にとらわれない発想が、業務効率の向上や新しいサービス・商品の開発に繋がる可能性も秘めています。
法定雇用率達成への間接的な貢献
インターンシップ自体が直接的に法定雇用率に算定されるわけではありませんが、インターンシップを通じて優秀な人材を発掘し、正規雇用に繋げることで、結果的に法定雇用率の達成・維持に貢献します。
障がい者向けのインターンシップの具体的な内容
障がい者向けインターンシップは、単に職場を体験するだけでなく、将来の就労に向けた第一歩としての役割も担っています。企業側は、業務内容や勤務日数、サポート体制などを柔軟に設計し、参加者が無理なく力を発揮できる環境づくりを行います。また、実務だけでなく、社会人としての基本マナーやキャリア支援といった要素も含まれており、総合的な成長の場として注目されています。ここでは、障がい者向けインターンシップの具体的な内容について、詳しくご紹介します。
業務内容は多様に対応可能:事務・軽作業・IT補助など
障がい者向けのインターンシップでは、一人ひとりのスキルや希望、障害特性に応じた業務を柔軟に設定することが一般的です。たとえば、事務補助ではデータ入力や書類整理、備品の管理など比較的定型的な業務が中心です。軽作業では、商品の仕分けやラベル貼り、在庫チェックなど身体的負荷を考慮した作業が選ばれる傾向にあります。近年では、ITに強みを持つ方に対してWebサイトの更新作業や表計算ツールを使った入力補助などの実務を任せる企業も増えています。
スケジュールは柔軟に設計:時短・短期など無理のない日程
障がい者インターンシップの特徴の一つに、参加しやすいスケジュール設計が挙げられます。体調や生活リズムを考慮し、1日あたりの勤務時間を短くした「時短型」や、週2~3日勤務といった「通所型」、または1~2週間程度の「短期集中型」など、多様なスタイルが採用されています。無理なく参加できる設計によって、インターン生のパフォーマンス向上や継続意欲にもつながります。
実務だけでなく、マナー研修やキャリア支援も実施
実務体験だけではなく、ビジネスマナーの基本や職場でのコミュニケーションの取り方を学ぶ研修を取り入れる企業も多くあります。加えて、期間中や終了後にキャリア面談を実施し、就職活動へのアドバイスや今後の課題整理を行うケースも。こうした取り組みは、インターン生の自己理解と自信の醸成につながり、将来の一般就労への橋渡しとなります。
障がい者向けのインターンシップ導入のステップ
障がい者インターンシップを成功させるためには、場当たり的な対応ではなく、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。以下に、導入から実施、フォローアップまでの基本的なステップを示します。
企画・計画段階
障がい者インターンシップを円滑かつ効果的に実施するためには、事前の企画・計画段階での準備が成功の鍵を握ります。なぜインターンシップを行うのかという目的の明確化から始まり、受け入れ部署や担当業務の選定、さらに現場の支援体制や予算の確保まで、一つひとつを丁寧に検討することが求められます。
目的・目標の明確化
まず、何のためにインターンシップを実施するのか、具体的な目的を定めます。「採用候補者の発掘」「社内理解の促進」「受け入れノウハウの蓄積」「特定の業務での活躍可能性の検証」など、目的によってプログラムの内容、期間、対象者像、評価指標などが変わってきます。経営層や関連部署と目的を共有することが重要です。
受け入れ部署・担当業務の検討
インターン生がやりがいを感じられ、かつ能力を発揮できる可能性のある部署や業務を選定します。本人の能力や意欲、障害特性への配慮はもちろん必要ですが、過度に簡単な作業に限定せず、成長に繋がる機会を提供することも考慮します。
体制構築と予算確保
指導担当者(メンター)や関係部署の役割分担を明確にし、必要な協力体制を構築します。謝礼、交通費、合理的配慮にかかる費用(物品購入、支援員配置など)、研修費用などの予算を確保し、経営層や受け入れ現場の理解と承認を得ます。
準備段階
障がい者インターンシップの実施にあたっては、インターン生が安心して力を発揮できるよう、受け入れ前の準備も重要なステップとなります。まずは、参加意欲を高める魅力的な募集要項の作成と、適切な選考プロセスの設計が求められます。さらに、実際に働く環境のバリアフリー化や情報保障の整備、業務上の支援体制も不可欠です。そして何より、インターン生を支える指導担当者(メンター)の役割は大きく、事前研修による準備が成果を左右するといっても過言ではありません。ここでは、受け入れに向けた実務的な準備のポイントをご紹介します。
募集・選考
魅力的な募集要項を作成し、大学のキャリアセンター、地域の就労支援機関、ハローワークなどを通じて広く告知します。選考プロセスは、公平性を保ちつつ、アクセシビリティに配慮する必要があります(例:オンライン面接の可否、筆記試験の代替手段など)。
受け入れ環境整備
物理的なバリアフリー化(スロープ設置、机の高さ調整など)や、情報保障(PCの読み上げソフト導入、コミュニケーションツールの準備など)を進めます。必要に応じて、業務マニュアルの整備やツールの準備も行います。
指導担当者(メンター)の選任と研修
インターン生のサポート役となる指導担当者を選任し、事前に研修を実施します。障害に関する基礎知識、コミュニケーション方法、合理的配慮の考え方、適切な業務指示の出し方などを学んでもらいます。
実施段階
インターン生が安心して業務に取り組み、能力を発揮できる環境を整えるためには、受け入れ後のサポート体制が極めて重要です。初日のオリエンテーションでは、企業や部署の概要、職場のルール、相談体制などを明確に伝え、不安を取り除くことが第一歩となります。業務面では、一人ひとりの理解度に合わせた丁寧な指示とサポートを行い、必要に応じた合理的配慮を柔軟に提供する姿勢が求められます。また、インターン期間中には定期的な面談やフィードバックの機会を設け、信頼関係を築くことで、より充実したインターンシップの実現につながります。
オリエンテーション
初日に丁寧なオリエンテーションを行い、企業の概要、部署の役割、業務内容、職場のルール、緊急時の連絡体制、相談窓口、提供できる配慮事項などを明確に伝えます。
業務指示と遂行支援
業務指示は具体的かつ段階的に行います。一度に多くの情報を与えず、理解度を確認しながら進めることが重要です。必要に応じて、マニュアルやチェックリスト、ツールなどを活用します。
合理的配慮の提供と調整
事前にヒアリングした内容に基づき合理的配慮を提供しますが、状況は変化する可能性があるため、固定的なものと考えず、本人の状況や意向を定期的に確認しながら、柔軟に調整・提供します。
コミュニケーションとフィードバック
指導担当者や人事担当者は、定期的にインターン生と面談の機会を持ちます。業務の進捗状況、困りごとや不安がないかなどを確認し、具体的で建設的なフィードバックを行います。気軽に相談できる雰囲気づくりが大切です。
評価・フォローアップ段階
障がい者インターンシップを一過性の取り組みに終わらせず、継続的な価値ある制度とするためには、実施後の振り返りと改善が欠かせません。まずは、インターン期間中の成果や成長を客観的に評価し、本人に対して今後に活かせる具体的なフィードバックを行うことが大切です。さらに、受け入れ部署からの声を収集することで、現場でのリアルな課題や気づきを把握できます。プログラム全体としても、目的達成度や満足度、体制面の負担などを多角的に評価し、次回以降の改善や、将来的な障がい者雇用の仕組みづくりにつなげていきましょう。
評価とフィードバック
インターンシップ期間中のパフォーマンスや成果、成長などを事前に設定した基準に基づいて評価します。評価結果は本人に丁寧にフィードバックし、今後の学業や就職活動に活かせるように伝えます。受け入れ部署からも、インターン生の様子やプログラムに関するフィードバックを得ます。
効果測定と改善
プログラム全体の効果測定を行い(目的達成度、参加者満足度、部署の負担感など)、課題や改善点を洗い出します。この結果を次回以降の実施計画や、本格的な障がい者雇用の採用活動、受け入れ体制の整備に活かします。
障がい者インターンシップを成功させるための重要なポイント
障がい者インターンシップを単なる体験で終わらせず、企業と参加者双方にとって実りあるものにするためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。人事部や決裁者、そして現場の指導担当者が特に意識すべき点を以下に挙げます。
明確な目的意識の共有
インターンシップの目的(採用選考の一環なのか、社内理解促進が主目的なのか等)を明確にし、それを経営層から現場の指導担当者、関連部署の社員まで、関わる全員が正しく理解し、共有することが最も重要です。目的が曖昧では、効果的なプログラム運営や適切なサポートは望めません。
合理的配慮への深い理解と実践的な対応
「合理的配慮」は、法律で求められる義務であると同時に、インターン生が能力を発揮するための基盤です。障害特性や必要な配慮は一人ひとり異なります。事前のヒアリングで本人の希望や必要な配慮を丁寧に確認することはもちろん、実施中も状況の変化に応じて柔軟に対応する姿勢が求められます。「過剰な配慮」も「配慮の不足」も避け、本人と対話しながら最適な形を探ることが重要です。特別扱いではなく、あくまで能力発揮を支援するという視点を持ちましょう。
丁寧な双方向コミュニケーション
業務指示やフィードバックを具体的かつ分かりやすく行うことは基本ですが、それ以上に、インターン生が困っていることや不安に感じていることを気軽に相談できる関係性を築くことが成功の鍵です。指導担当者やメンターは、定期的な面談だけでなく、日常的な声かけや、質問しやすい雰囲気づくりを心がける必要があります。
指導担当者(メンター)の役割の重要性
指導担当者は単なる業務指導者ではありません。インターン生の成長をサポートする伴走者であり、精神的な支えとなる存在です。また、インターン生と他の社員との橋渡し役や、必要な配慮に関する調整役も担います。適切な人材を選任し、必要な知識やスキルを習得するための研修機会を提供することが不可欠です。
「戦力」としての期待と適切な業務設定
障害のある方を「保護すべき存在」として特別扱いするのではなく、一人の潜在的な戦力として期待し、その能力を発揮できるような適切な業務内容や仕事の進め方を提供することが、本人の意欲と成長に繋がります。簡単すぎる業務ばかりではやりがいを感じられず、逆に過度な負荷は負担になります。本人のスキルや経験、意欲、そして必要な配慮を踏まえた上で、挑戦と達成感を感じられる業務を設計することが望ましいです。
外部の専門機関との連携
大学のキャリアセンター、地域の就労支援機関、ハローワーク、障がい者職業センターなどの外部専門機関と連携することも有効です。募集や選考に関する協力、合理的配慮に関する専門的なアドバイス、トラブル発生時の相談など、様々なサポートを得られます。自社だけで抱え込まず、積極的に外部の知見やリソースを活用しましょう。
スモールスタートと継続的な改善
最初から大規模に始める必要はありません。まずは短期間・少人数でのスモールスタートを検討し、経験を積みながら課題を洗い出し、改善を重ねていく方法も有効です。重要なのは、失敗を恐れずに挑戦し、その経験から学び、次に活かすという継続的な改善の姿勢です。初めての取り組みでは予期せぬ課題も発生しますが、それを乗り越えるプロセス自体が、組織にとって貴重な学びとなり、ノウハウの蓄積に繋がります。
導入を検討する上での注意点とリスク管理
障がい者インターンシップは多くのメリットをもたらしますが、導入を成功させ、継続的な取り組みとするためには、事前に検討すべき注意点や潜在的なリスクも理解しておく必要があります。安易な導入は、かえって混乱を招いたり、参加者・企業双方にとってマイナスな結果になったりする可能性もあります。
法令・ガイドラインの遵守と理解
障がい者雇用促進法はもちろん、関連するガイドライン(合理的配慮指針など)、個人情報保護法などを正しく理解し、遵守することが大前提です。特に、募集・選考段階での差別禁止や、合理的配慮の提供義務に関する理解は不可欠です。必要に応じて、専門家(弁護士、社労士など)に相談し、社内ルールや運用マニュアルを整備することが重要です。コンプライアンス違反は、企業のレピュテーションリスクに直結します。
社内コンセンサスの形成と情報共有
経営層や人事部だけで進めるのではなく、実際にインターン生を受け入れる現場部署の理解と協力が不可欠です。導入の目的、メリット、具体的な進め方、必要な配慮などについて、事前に十分な説明を行い、社内コンセンサスを形成する必要があります。また、実施中も関係者間での情報共有を密に行い、課題や懸念点を早期に発見し、対応できる体制を築くことが重要です。認識のずれや協力体制の不備は、現場の混乱やインターン生の不安に繋がります。
適切な業務設計と指導体制の確保
インターン生に任せる業務内容が、本人の能力や特性、そしてインターンシップの目的に合っているか、慎重に検討する必要があります。安全への配慮も重要です。また、指導担当者(メンター)が十分な時間とリソースを確保できるか、負担が過重にならないかも考慮すべき点です。指導担当者任せにせず、部署全体や人事部がサポートする体制が必要です。
ミスマッチや早期終了のリスク
事前の準備やマッチングが十分でない場合、インターン生が業務内容や職場環境に適応できず、早期に終了してしまう可能性もあります。また、企業側が期待していた能力と実際のパフォーマンスにギャップが生じることも考えられます。こうしたリスクを低減するためには、事前の丁寧なヒアリングと情報提供、そして実施中の柔軟な対応とサポート体制が重要になります。
個人情報・プライバシーへの配慮
インターン生の障害に関する情報は、非常にセンシティブな個人情報です。本人の同意なく、必要範囲を超えて情報を共有することは厳禁です。情報管理体制を整備し、関わる社員への教育を徹底する必要があります。
成果の可視化と継続性の担保
インターンシップの効果を測定し、経営層や関係部署に報告することで、取り組みの意義を社内に示し、継続的な実施への理解と協力を得ることが重要です。単発のイベントで終わらせず、長期的な人材戦略の一環として位置づけ、PDCAサイクルを回しながら改善していく視点が求められます。
まとめ
障がい者インターンシップは、障害のある方に実践的な就労体験を提供するだけでなく、企業側にとっても多様な人材の発掘や受け入れ体制の整備、採用ミスマッチの防止といった多くのメリットをもたらします。導入を成功させるには、明確な目的設定、関係者との情報共有、計画的な準備、合理的配慮、そして丁寧なコミュニケーションが欠かせません。決して特別な制度ではなく、スモールスタートからでも取り組める実践的な手段です。
本記事で紹介した内容を参考に、自社に合った形で障がい者インターンシップを導入し、多様な人材が活躍できるインクルーシブな職場づくりに向けて一歩を踏み出してみてください。