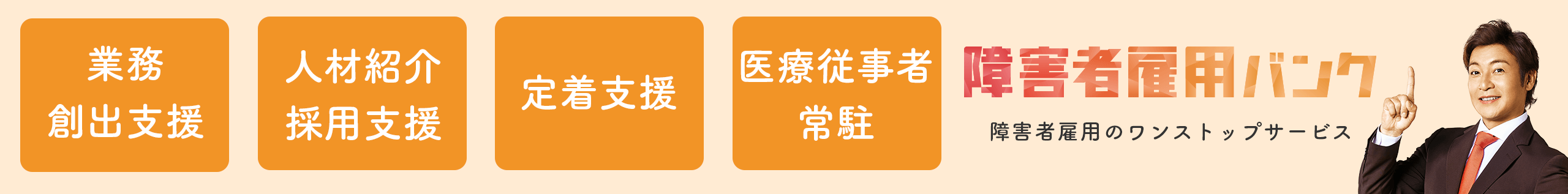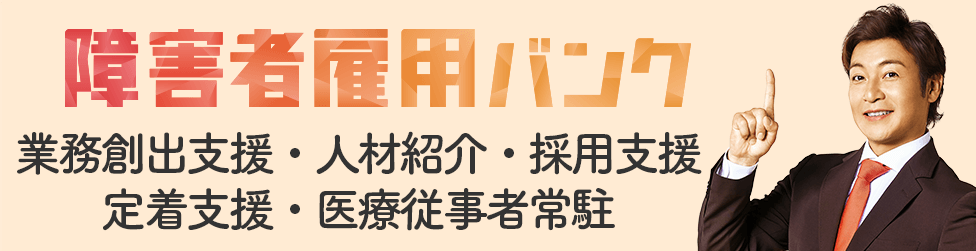障害者雇用は在宅ワークが新常識に!採用を成功に導く業務設計とマネジメント手法を解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
序論:採用難を乗り越える一手、「在宅」という選択肢
法定雇用率の段階的な引き上げが続く中、多くの企業で障害者雇用は喫緊の経営課題となっています。人事責任者や決裁者の皆様は、「採用計画はあるが、求める人材からの応募がない」「採用しても、職場環境への適応が難しく定着に繋がらない」といった深刻な課題に直面しているのではないでしょうか。従来の採用手法の延長線上では、この採用難を乗り越えることはますます困難になっています。しかし、その解決策は、これまで当たり前とされてきた「オフィス出社」という前提そのものを見直すことにあります。通勤という物理的・心理的負担が障壁となり、高い能力や働く意欲を持ちながらも就労を諦めている人材は、全国に数多く存在します。もし、その障壁を取り払うことができれば、企業の採用ターゲットは劇的に拡大するはずです。そこで本記事では、障害者雇用における「在宅ワーク」という選択肢が、なぜ企業の採用課題を根本から解決し、持続的な成長戦略となり得るのかを、具体的な業務設計やマネジメント手法といった実務的な観点から徹底的に解説します。在宅雇用はもはや特別な選択肢ではなく、企業の競争力を高めるための「標準装備」となりつつあります。この記事が、貴社の障害者雇用を次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
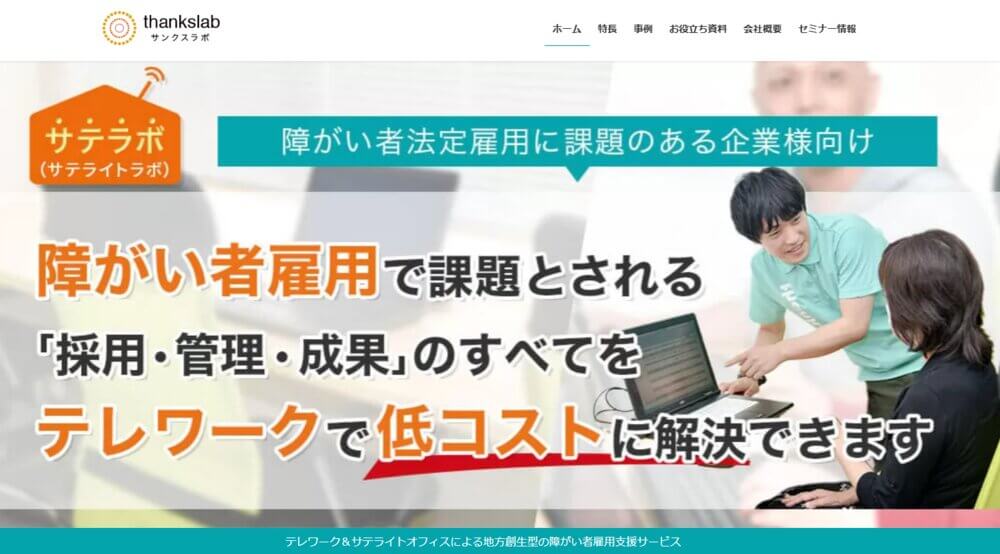
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
なぜ今「在宅雇用」が障害者雇用の切り札なのか?企業が享受する4つのメリット
障害者雇用において在宅ワークを導入することは、単に社会的な要請に応えるだけでなく、企業経営に多大なメリットをもたらす戦略的な一手です。これまで採用に苦戦してきた企業にとって、在宅雇用はまさに「切り札」となり得ます。その具体的なメリットを4つの経営視点から解説します。
メリット1:【採用力の飛躍的向上】勤務地の制約をなくし、全国から優秀な人材を獲得
最大のメリットは、採用可能な母集団が圧倒的に拡大することです。オフィス出社を前提とした場合、採用ターゲットは通勤可能な圏内に限定されます。しかし、障害のある方の中には、能力は高いものの、公共交通機関の利用が困難であったり、長時間の通勤が体調に影響したりするため、就労を断念しているケースが少なくありません。在宅ワークは、この「通勤」という最大の物理的障壁を取り除きます。これにより、これまでアプローチできなかった全国の優秀な人材が採用ターゲットとなり、採用競争において大きな優位性を確保できます。地方在住の専門スキルを持つ人材や、特定の環境下でこそ高い集中力を発揮できる人材など、新たな才能との出会いが期待できます。
メリット2:【定着率の改善】働きやすい環境が、エンゲージメントを高める
採用後の定着は、障害者雇用における永遠の課題です。在宅ワークは、この定着率の改善にも大きく貢献します。従業員は、最もリラックスでき、自身の体調管理がしやすい自宅という環境で業務に集中できます。通勤による肉体的・精神的ストレスから解放されることは、パフォーマンスの安定に直結します。また、個々の障害特性に合わせて、照明の明るさや室温、使用する椅子やデスクなどを自由に調整できるため、働く上で障壁となる物理的・感覚的なストレスを最小限に抑えることが可能です。このような個別最適化された働きやすい環境は、従業員のエンゲージゲージメントと企業への帰属意識を高め、長期的な活躍を促します。
メリット3:【コスト構造の最適化】オフィス関連コスト・採用コストの削減
在宅雇用の推進は、企業のコスト構造にも良い影響を与えます。在宅ワーカーが増えることで、オフィスの物理的なスペースを縮小でき、それに伴う賃料や光熱費、備品購入費といった固定費を削減できます。また、採用エリアが全国に広がることで、人材獲得競争が激しい都市部の高い採用単価に依存する必要がなくなり、採用コスト全体の最適化も図れます。
メリット4.:【事業継続性の強化】BCP対策としての有効性
パンデミックや自然災害など、不測の事態が発生した際に事業を継続させるBCP(事業継続計画)の観点からも、在宅雇用は極めて有効です。従業員が地理的に分散しているため、特定地域の機能が停止しても、他の地域の従業員が業務を継続できます。出社が困難な状況下でも事業を止めない、柔軟で強固な組織体制の構築は、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高め、リスク管理能力を向上させます。
在宅で任せられる業務とは?戦略的な「業務設計(ジョブクリエイション)」の進め方
「在宅で一体どんな仕事を任せられるのか」これは、在宅雇用を検討する際に多くの企業が抱く疑問です。しかし、適切な業務設計、すなわち「ジョブクリエイション」を行うことで、在宅ワーカーが活躍できるフィールドは無限に広がります。重要なのは、既存の職務に当てはめるのではなく、業務を分解し、再構築するという視点です。
在宅勤務に適した業務の具体例
まず、在宅ワークと親和性の高い業務領域を理解することが第一歩です。これらは多くの場合、PCスキルを活かせる業務です。
- PC完結型業務: データ入力、Webサイトからの情報収集・リサーチ、音声データの文字起こし、PowerPointなどでの資料作成、Webサイトの記事更新・簡単な修正作業など、場所を選ばずに遂行できる定型的な業務。
- 事務・バックオフィス系業務: 経費精算システムの入力・チェック、勤怠データの集計・管理、受発注データのシステム入力、顧客からの問い合わせメール・チャットへの一次対応など、企業の基幹業務を支える重要な役割。
- 専門・クリエイティブ系業務: Webデザイン(バナー作成、LPデザイン)、ライティング(ブログ記事、メルマガ作成)、翻訳、CADを用いた図面作成、プログラミングやソフトウェアのテストなど、専門スキルが求められる高度な業務。
戦略的な業務を切り出すための3ステップ
これらの業務を自社で創出するためには、以下の3つのステップで進めることが有効です。
- STEP1:既存業務の棚卸しと可視化 まず、社内の各部署で行われている業務をすべて洗い出します。担当者へのヒアリングや業務フロー図の作成を通じて、「誰が」「何を」「どのように」行っているかを徹底的に可視化します。この段階では、先入観を持たずにあらゆる業務をリストアップすることが重要です。
- STEP2:「切り出し可能」な業務の特定 次に、可視化した業務の中から、在宅でも遂行可能な業務を特定します。判断基準は、「場所を選ばないか」「PCとインターネット環境で完結するか」「定型的でマニュアル化しやすいか」「個人で完結できる、またはチームでの連携がオンラインで可能か」といった点です。複数の部署にまたがる細切れの業務でも構いません。
- STEP3:業務の再構築とマニュアル作成 最後に、STEP2で特定した複数の細切れの業務を組み合わせ、一人の担当者が担う新しいポジションとして再構築します。そして、その業務内容について、誰が読んでも理解でき、同じ品質で作業ができるように、手順や判断基準、注意点などを詳細に記した業務マニュアルを作成します。このマニュアルが、在宅雇用の成否を分ける重要な鍵となります。
導入の壁を乗り越える!在宅雇用のマネジメント手法と解決策
在宅雇用の導入を検討する際、多くの人事責任者や決裁者が「勤怠管理はどうするのか」「孤独を感じて生産性が落ちないか」「オフィスにいない社員をどう評価すればいいのか」「情報セキュリティは大丈夫か」といったマネジメント上の課題に直面します。これらの懸念はもっともですが、その大半は、精神論ではなく、適切なツールと仕組みを導入することで解決可能です。ここでは、代表的な4つの課題とその具体的な解決策を解説します。
課題1:労務・勤怠管理 →【解決策】ツールの活用とルールの明確化
「見えない場所」での労働時間をどう管理するかは最初の壁です。これを解決するには、PCのログオン・ログオフ時間と連動する勤怠管理システムを導入するのが最も客観的で確実です。これにより、始業・終業時刻や休憩時間を正確に記録し、労働時間を客観的に把握できます。また、時間外労働については、必ず事前申請を必須とするルールを設け、承認された範囲でのみ残業を認める運用を徹底します。これにより、長時間労働の防止と適切な労務管理を両立できます。
課題2:コミュニケーション →【解決策】意図的な接点とオープンな環境作り
在宅勤務で最も懸念されるのが、孤独感によるエンゲージメントの低下や、業務上の連携不足です。これを防ぐには、意図的にコミュニケーションの機会を創出する仕組みが不可欠です。
- ビジネスチャットツールの導入: 業務連絡はもちろん、「雑談チャンネル」など気軽に発言できる場を設け、偶発的なコミュニケーションを促します。
- Web会議システムの定例利用: 毎日決まった時間にチームで朝会・夕会を実施し、顔を合わせて進捗や課題を共有する場を作ります。
- 定期的な1on1面談: 上長と部下が週に1回、あるいは隔週で1対1の面談を実施し、業務の悩みだけでなく、心身のコンディションについても話せる時間を確保します。
課題3:業務進捗と成果評価 →【解決策】プロセスの可視化と成果物での評価
勤務態度が見えにくい在宅ワーカーを公平に評価するためには、評価基準そのものを変える必要があります。「頑張っている姿」ではなく、「創出された成果」で評価するのです。
- タスク管理ツールの導入: TrelloやAsanaといったツールを活用し、「誰が」「何のタスクを」「いつまでに」行うのかをチーム全員が見える状態にします。これにより、業務プロセスが可視化され、進捗管理が容易になります。
- 成果物(アウトプット)基準の評価制度: 評価期間の初めに具体的な目標(KPI)と達成基準を明確に設定し、その達成度合いに基づいて評価を行います。これにより、働く場所にかかわらず、公平で納得感のある評価が実現します。
課題4:情報セキュリティ →【解決策】物理的・技術的対策の徹底
機密情報や個人情報の漏洩は、企業にとって致命的なリスクです。在宅勤務環境のセキュリティを確保するためには、技術的な対策が必須です。
- VPN接続の義務化: 社内システムへのアクセスは必ずVPN(仮想プライベートネットワーク)を経由させ、通信を暗号化します。
- 貸与PCのセキュリティ強化: 会社が管理するセキュリティソフトを導入し、USBメモリの使用制限やデータの持ち出し制限といった設定を施したPCを貸与します。
- 定期的な研修: 情報セキュリティに関するルールや、最新のサイバー攻撃の手口などについて、定期的に研修を実施し、従業員のセキュリティ意識を高めます。
成功に導く体制づくり|活用できる助成金と外部サービス
在宅での障害者雇用を成功させるためには、自社の努力だけでなく、国が提供する支援制度や、専門知識を持つ外部サービスを戦略的に活用することが極めて有効です。これらを組み合わせることで、導入・運用にかかるコストやノウハウ不足といった課題を効率的に解決できます。
国の支援制度を有効活用する
障害者雇用に取り組む企業を支援するため、国は様々な助成金制度を用意しています。在宅雇用の導入においては、特に以下の制度が活用できる可能性があります。
- 障害者作業施設設置等助成金: この助成金は、障害のある方が業務を遂行しやすくするための設備投資を支援するものです。在宅勤務においては、在宅勤務用PCやその周辺機器、Webカメラ、ソフトウェア、通信機器の導入などにかかる費用の一部が助成対象となり得ます。初期投資の負担を大幅に軽減できるため、必ず確認したい制度です。
- 障害者介助等助成金: 業務の遂行に介助や支援が必要な場合に、その費用を助成する制度です。例えば、聴覚に障害のある従業員とのWeb会議において、オンラインで手話通訳者を配置するための費用などが対象となる場合があります。コミュニケーションの質を確保し、円滑な業務遂行を支えるために活用できます。
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース): 障害のある従業員に対して、職業能力の開発・向上のための研修(OJTを除く)を実施した場合に、その経費や期間中の賃金の一部を助成します。在宅勤務に必要なITスキルの習得などを目的とした研修に活用できます。
これらの助成金は、申請要件や対象経費が詳細に定められています。活用を検討する際は、必ず事前に管轄の労働局やハローワーク、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に相談し、最新の情報を確認することが重要です。
外部専門サービスの戦略的活用
自社に障害者雇用のノウハウが不足している場合や、管理リソースを割けない場合には、外部の専門サービスを利用することが成功への近道です。
- 在宅雇用支援サービス: 採用活動から、前述した業務の切り出し(ジョブクリエイション)、マニュアル作成、勤怠・業務管理システムの提供、日々のコミュニケーションサポート、定着支援までをワンストップで提供してくれるサービスです。企業の負担を最小限に抑えながら、質の高い在宅雇用を実現できます。
- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング): 経理や人事、データ入力といった特定の業務プロセスごと外部に委託し、その業務を委託先の専門スタッフの管理下で、障害のある在宅ワーカーが担うモデルです。企業は業務の品質を担保しつつ、間接的に障害者雇用を進めることができます。
これらのサービスは、法定雇用率の達成という目的だけでなく、ノンコア業務のアウトソーシングによる生産性向上という側面も持ち合わせており、一石二鳥の効果が期待できます。
まとめ:在宅雇用は、障害者雇用の「標準装備」へ
本記事では、障害者雇用における在宅ワークの有効性と、それを成功に導くための具体的な手法について解説してきました。法定雇用率の引き上げが続く現代において、「採用難」と「定着難」は多くの企業が直面する共通の課題です。在宅雇用は、この根深い課題を解決するための極めて強力な一手となり得ます。勤務地の制約を取り払うことによる採用母集団の劇的な拡大、そして個々の特性に合わせた働きやすい環境の提供による定着率の向上は、企業に計り知れないメリットをもたらします。かつて導入の障壁とされた労務管理、コミュニケーション、評価、セキュリティといった課題も、今や適切なITツールと仕組みの導入によって十分に克服可能です。むしろ、これらの仕組みを整備する過程は、社内業務の可視化や標準化、そして成果に基づく公正な評価制度の構築を促し、組織全体の生産性向上にも繋がります。障害者雇用における在宅ワークは、もはや特別なケースや一部の先進企業だけの取り組みではありません。法定雇用率の達成はもとより、多様な人材が活躍できるインクルーシブな組織を構築し、企業の競争力を高めるために、すべての企業が検討すべき「標準装備」です。「在宅雇用」という戦略的な一手への決断が、今、求められています。