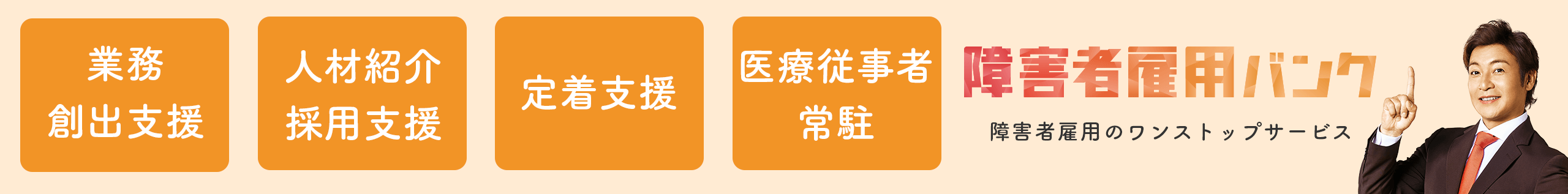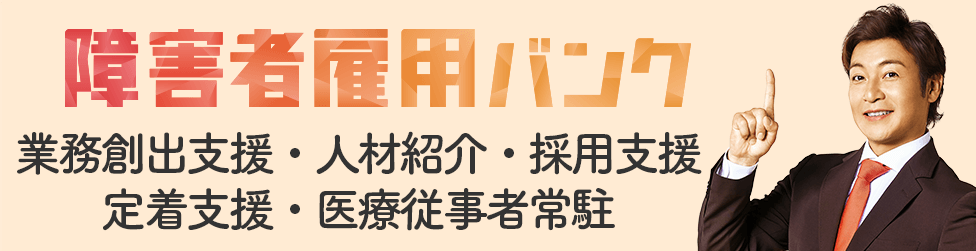【企業向け】知的障害者の雇用を成功させる方法|戦力化のための業務切り出しから定着支援まで完全ガイド

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「知的障害のある方に、どんな仕事を任せればいいのか分からない」「コミュニケーションが難しそうで、採用に踏み切れない」 障害者雇用の推進が企業の重要な経営課題となる中で、特に知的障害のある方の雇用に対して、このような漠然とした不安を抱える企業の決裁者・人事責任者様は少なくありません。
しかし、その不安は、知的障害のある方の「特性」を正しく理解し、適切なステップを踏むことで、「大きな可能性」へと変わります。知的障害者雇用は、単なる社会貢献活動ではありません。彼らの持つ真面目さや集中力といった「強み」を活かすことで、企業の戦力として、そして組織を活性化させる存在として、大きな価値をもたらす「戦略的投資」となり得るのです。
本記事では、その漠然とした不安を「成功への具体的な自信」に変えるための完全ガイドとして、知的障害のある方の特性理解から、戦力化を実現する業務の切り出し方、採用で失敗しないための鍵、そして長期的な定着に繋がる支援体制の構築まで、網羅的に解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
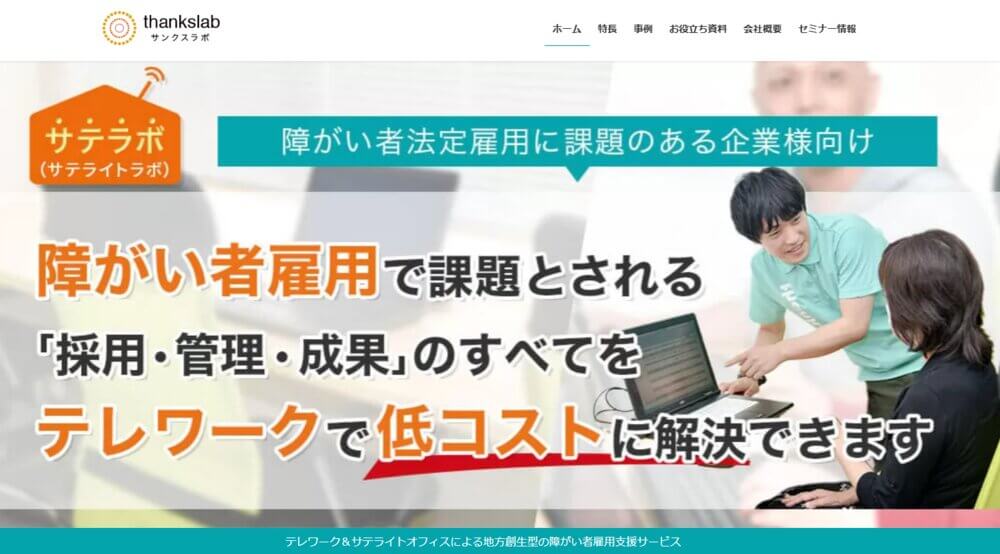
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
知的障害者雇用の第一歩。「特性」と「強み」を正しく理解する
知的障害者雇用を成功させるための全ての土台は、彼らの特性を正しく理解することから始まります。知的障害とは、全般的な知的機能が平均よりも低く、それによって日常生活や社会生活における「適応機能」(例:コミュニケーション、自己管理、社会参加など)に制約がある状態を指します。発達障害や精神障害と混同されることもありますが、知的障害は発達期(おおむね18歳まで)に生じる知的機能の遅れを中核とする点で区別されます。
企業の人事担当者が押さえるべきは、こうした定義そのものよりも、彼らが持つ仕事上の「強み」と、企業側がサポートすべき「苦手」な側面です。
◆知的障害のある方の「得意なこと(強み)」
彼らの特性は、見方を変えれば、企業にとって大きな戦力となりうる強みです。
- 素直さと真面目さ:指示されたことを、自分なりの解釈を加えずにストレートに受け止め、真面目にコツコツと取り組む傾向があります。
- 高い集中力と持続力:一度手順を覚え、自分の役割だと認識した業務に対しては、驚くほどの集中力を持続させることができます。
- 反復作業への耐性:健常者であれば飽きてしまうような、変化の少ないルーティンワークを、高い品質を保ったまま正確に、そして継続的に行うことができます。
- 丁寧さと正確性:決められたルールや手順を忠実に守り、一つひとつの作業を丁寧に、着実にこなすことを得意とします。
◆企業が配慮すべき「苦手なこと」
一方で、以下のような点は、業務を遂行する上で企業側のサポートが必要となります。
- 抽象的な表現の理解:「あれ、やっといて」「適当に」といった曖昧な指示では、何をすれば良いのか分からず混乱してしまいます。
- 応用・自己判断:マニュアルに記載のないイレギュラーな事態や、急な変更に対して、自分で判断して柔軟に対応することが苦手です。
- マルチタスク:複数の作業を同時に、あるいは並行して進めることは、情報処理の面で大きな負担となります。
- 対人関係の構築:相手の表情や言葉の裏にある意図を汲み取ったり、自分の気持ちや状況を的確に言葉で伝えたりすることが難しい場合があります。
これらの「得意」と「苦手」を正しく理解することが、次のステップである「業務切り出し」や、採用後の「効果的なマネジメント」に直結するのです。
【業務切り出し編】知的障害のある方が「戦力」になる仕事とは?
「知的障害のある方に任せられる仕事が、うちの会社にあるだろうか」これは、人事担当者が抱える最大の懸念の一つです。しかし、結論から言えば、ほとんどの企業に彼らが活躍できる業務は存在します。重要なのは「特別な仕事を用意する」のではなく「既存の業務を分解・整理し、彼らの強みが活きる部分を切り出す」という発想です。
この業務の棚卸しを行う過程は、属人化していた業務がマニュアル化されたり、非効率なプロセスが見直されたりと、組織全体の生産性向上に繋がるという副次的効果も期待できます。知的障害のある方の強みである「集中力」「正確性」「反復作業への耐性」を活かせる業務の具体例を以下に示します。
- 事務補助業務 オフィス内には、知的障害のある方が担える定型業務が数多く眠っています。
- PC作業:データ入力、アンケート集計、書類のPDF化・スキャン、議事録の文字起こし
- 書類整理:ファイリング、ラベリング、コピー、製本作業
- 庶務業務:備品管理・補充・発注、郵便物の仕分け・発送、会議室の清掃・セッティング、シュレッダー作業
- 軽作業・製造補助業務 工場や倉庫、店舗のバックヤードなどでも、彼らの特性は大きな戦力となります。
- 物流・倉庫業務:商品の検品、梱包、ラベル貼り、ピッキング、棚卸しの補助
- 製造ライン業務:簡単な組み立て作業、部品の仕分け、完成品のチェック
- 清掃・メンテナンス業務:施設内の清掃、ベッドメイキング、リネン類の管理
これらの業務に共通するのは「手順が明確で、変化が少なく、自己判断をあまり必要としない」という点です。まずは、社内の様々な部署の社員にヒアリングを行い、「単純だけど時間がかかる作業」「誰がやっても同じ結果になる作業」をリストアップすることから始めてみましょう。そこに、知的障害のある方が活躍できる大きな可能性があります。
採用を成功させる3つの鍵。出会い方から見極めまで
知的障害のある方の採用を成功させるためには、一般的な採用活動とは異なるアプローチが求められます。ここでは、ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材と出会うための3つの重要な鍵を解説します。
鍵①:支援機関との強力なパートナーシップを築く
自社だけで求人媒体に募集をかけても、適切な人材と出会うことは困難です。成功の絶対条件は、ハローワーク、就労移行支援事業所、特別支援学校といった支援機関と緊密に連携することです。これらの機関には、障害者雇用の専門知識を持つ職員がおり、求職者一人ひとりの障害特性、得意なこと、苦手なこと、職歴などを詳細に把握しています。企業側が求める人物像や業務内容を具体的に伝えることで、自社にマッチする可能性の高い人材を紹介してくれます。日頃から担当者と良好な関係を築き、信頼できるパートナーとして付き合うことが何よりも重要です。
鍵②:「職場実習」の徹底活用でミスマッチを防ぐ
書類選考や数十分の面接だけで、その人の適性や能力を正確に見極めることはほぼ不可能です。ここで最も有効なのが「職場実習」です。実際に数日間から数週間、職場で働いてもらうことで、企業側は本人の実務能力や職場への適応力を、本人側は仕事内容や職場の雰囲気を、お互いに深く理解することができます。この「お試し期間」は、採用後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを劇的に減らします。 【職場実習で見るべきポイント】
- 勤怠:時間通りに出勤できるか、無断欠勤・遅刻はないか
- 指示理解:具体的な指示を正しく理解し、行動に移せるか
- 作業遂行力:業務の正確性、スピード、持続力
- 報告・連絡・相談:分からないことを質問できるか、終わったことを報告できるか
- 疲労度:業務後に疲れすぎていないか、体力的に無理はないか
鍵③:具体的で「誤解のない」求人と面接を行う
知的障害のある方に対しては、抽象的な表現を徹底的に排除し、具体性・明確性を追求することが求められます。求人票には、「コミュニケーション能力の高い方」といった曖昧な言葉ではなく、「決められた手順に沿って、パソコンで文字入力ができる方」のように、具体的な業務内容や必要なスキルを記載します。面接においても、「あなたの長所は何ですか」といった質問は、彼らを混乱させるだけです。代わりに「この書類を番号順に並べ替えることはできますか」と問いかけたり、簡単な作業を実際にやってもらったりすることで、より正確な能力評価が可能になります。
【定着支援編】効果的なコミュニケーションとマネジメントのコツ
無事に採用が決まっても、それがゴールではありません。知的障害のある社員が安心して能力を発揮し、長く働き続けてもらうためには、日々のコミュニケーションと適切なマネジメントが不可欠です。ここでは、現場ですぐに実践できる具体的なコツを紹介します。
指示・指導の基本ルール:「あ・な・た」で伝える
彼らに指示を出す際は、3つのポイントを意識すると格段に伝わりやすくなります。
- あ(焦らず、ゆっくり):本人の理解のペースを尊重し、早口で話すのは避けましょう。
- な(具体的に、分かりやすく):「あれ」「それ」といった指示語は使わず、「青いファイルを、3番の棚に入れてください」のように、具体的かつ明確に伝えます。
- た(短く、一つずつ):一度に複数のことを伝えると混乱の原因になります。「まず〇〇をしてください。終わったら報告してください」と、指示は一つずつ区切って出しましょう。 また、口頭での説明に加えて、写真や図、イラストを使った作業マニュアルや、手順をリスト化したチェックリストを用意する「視覚的支援」は、記憶を定着させ、作業の抜け漏れを防ぐ上で非常に効果的です。
モチベーションを高める「褒め方」と、パニックを防ぐ「叱り方」
部下や同僚の能力を引き出し、モチベーションを高めるためには、適切なタイミングで具体的に褒めること、そして感情的にならず、冷静に改善点を伝える叱り方を身につけることが不可欠です。
- 褒め方:できたことは、その場ですぐに、具体的に褒めることが重要です。「ありがとう、助かるよ」といった感謝の言葉も効果的です。「〇〇さんのおかげで、時間通りに作業が終わったよ」のように、具体的に伝えることで、本人の自信と「役に立っている」という実感に繋がります。
- 叱り方:失敗した際に、感情的に叱責することは絶対に避けるべきです。パニックを引き起こし、萎縮させてしまいます。重要なのは、人前ではなく個別に、冷静に、事実に基づいて伝えることです。「なぜダメだったのか」を簡潔に説明し、「次はこうしてみようか」と具体的な改善策を一緒に考える姿勢が、本人の成長を促します。
安心して働ける環境づくりと評価制度
安心して能力を発揮してもらうためには、環境の整備も欠かせません。例えば、聴覚が過敏な方には、電話の音が少ない静かな席を用意するといった物理的な配慮が考えられます。また、「困ったことがあったら、いつでも相談してね」と伝え、気軽に話せる担当者を決めておくといった心理的なサポート体制も重要です。評価制度においては、「等級」ではなく「職務・役割・達成度」を基準とします。本人と一緒に具体的な業務目標を設定し、その成果とプロセスを公正に評価し、定期的な面談でフィードバックを行うことで、成長意欲を育むことができます。
組織で支える体制づくり。外部の専門家と助成金をフル活用する
知的障害者雇用を成功させる上で、最も避けなければならないのは、特定の担当者や現場の上司一人に、すべての負担を集中させてしまう「属人化」です。組織全体で支える体制を構築し、活用できる外部のリソースを最大限に利用することが、持続可能な雇用への鍵となります。
担当者一人にしない。全社で取り組むための役割分担
知的障害者雇用は、会社全体のプロジェクトとして捉えるべきです。
- 経営層:障害者雇用の方針を明確にし、その重要性を全社に発信するリーダーシップを発揮する。
- 人事部:採用活動の主導、支援機関との連携、社内研修の企画、助成金の申請など、全体をコーディネートする。
- 現場の上司・同僚:日々の業務指導やコミュニケーション、相談対応といった最も身近なサポートを担う。 このように役割を明確にし、定期的に情報共有の場を設けることで、現場の負担を軽減し、組織的な課題解決が可能になります。
困った時の駆け込み寺。外部の専門家(支援機関)と連携する
社内だけで解決できない問題が発生した場合、専門家の力を借りることをためらってはいけません。
- ジョブコーチ(職場適応援助者)支援:専門の支援員が一定期間、職場を訪問し、本人への指導方法や、職場内でのコミュニケーションの円滑化など、企業と本人の双方に対して具体的かつ専門的な助言を行ってくれる制度です。
- 障害者就業・生活支援センター:仕事上の課題だけでなく、本人の生活面も含めた相談に乗ってくれる非常に心強いパートナーです。「最近、遅刻が増えた」といった変化が見られた際に相談すれば、その背景にある生活上の課題解決をサポートしてくれることもあります。
経済的負担を軽減する助成金制度
知的障害のある方を雇用する企業は、様々な助成金を受給できる可能性があります。これらを活用することで、経済的な負担を大きく軽減できます。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):ハローワーク等の紹介で知的障害のある方を雇用した場合に、賃金の一部が助成されます。
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース):常用雇用を前提に、まずは短期間(原則3ヶ月)試行雇用する場合に、奨励金が支給されます。
- 障害者雇用安定助成金:職場への定着を図るための措置(指導員の配置、研修など)に対して、費用の一部が助成されます。
まとめ:知的障害者雇用は、企業の未来を創る「人材戦略」である
本記事では、知的障害者雇用を成功に導くための具体的なステップとノウハウを、特性の理解から業務切り出し、採用、定着支援まで一貫して解説しました。
知的障害のある方の雇用は、多くの企業が考えるほど「難しい」ものではありません。彼らの持つ「強み」を正しく理解し、適切な業務を設計し、分かりやすいコミュニケーションを心がける。この基本的なステップを踏めば、彼らは企業の貴重な「戦力」として、大きな貢献をしてくれます。
そして、その効果は単なる労働力の確保にとどまりません。業務プロセスが見直され、社内のコミュニケーションが丁寧になり、多様性を受け入れる文化が醸成される。知的障害者雇用への真摯な取り組みは、組織全体にこのようなポジティブな変化をもたらす「戦略的投資」なのです。
成功の鍵は、自社だけで全てを抱え込まず、支援機関やジョブコーチといった外部の専門家、そして国が用意する助成金制度を最大限に活用することです。これらのサポートをテコにすれば、リソースが限られる企業でも、十分に知的障害者雇用を成功させることができます。
この記事が、貴社にとって、不安を自信に変え、新たな人材戦略への大きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。