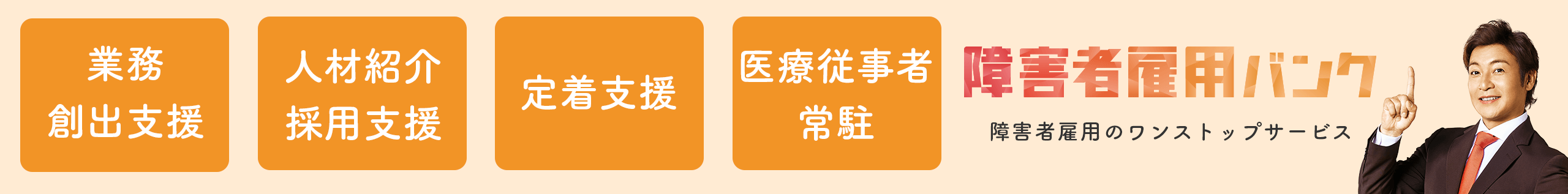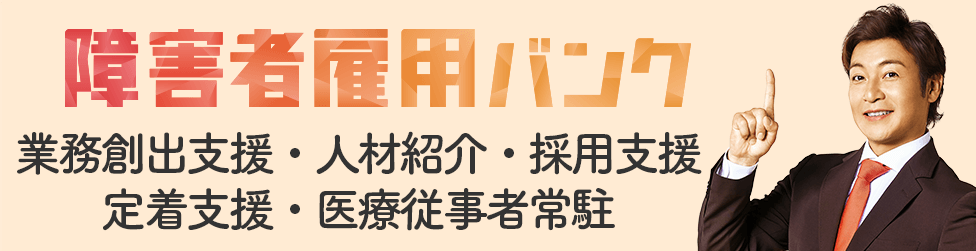視覚障害者の雇用を成功させる全手順|法的義務から職場定着まで

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに:法的義務から「企業の戦力」獲得へ
障害者雇用促進法が定める法定雇用率の遵守は、現代の企業が果たすべき重要な責務です。2024年現在の法定雇用率は2.5%、さらに2026年度中には2.7%へと引き上げが予定されており、未達成の場合には納付金が課されるなど、経営上のリスクともなり得ます。しかし、この障害者雇用を単なる「義務」や「コスト」として捉えるか、それとも「新たな人材獲得の機会」として捉えるかで、企業の未来は大きく変わります。
特に「視覚障害者」の雇用については、「オフィスでの業務は難しいのではないか」「どのような仕事を任せられるのか」といった先入観から、採用活動が思うように進まないケースが少なくありません。しかし、その固定観念は、企業の成長機会を逃している可能性があります。視覚障害のある方は、視覚情報に頼らない代わりに、聴覚や記憶力、論理的思考力、そして高い集中力など、特筆すべき能力を持っていることが多く、適切なITツールと職場環境さえあれば、専門性の高い分野で企業の重要な戦力となり得るのです。
視覚障害者の雇用を成功させる鍵は、漠然とした同情や一方的な「特別扱い」ではありません。それは、障害特性を正しく理解し、テクノロジーを活用して情報格差をなくし、誰もが働きやすいユニバーサルな環境を構築するという、極めて戦略的なアプローチにあります。本記事では、採用担当者が知っておくべき法的義務や障害特性の基礎知識から、採用選考、職場環境の整備、そして社内文化の醸成に至るまで、雇用を成功に導くための全手順を体系的に解説します。この記事を通じて、貴社にとっての新たな人材獲得の可能性を見出し、確信を持って採用活動へ踏み出すための一助となれば幸いです。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
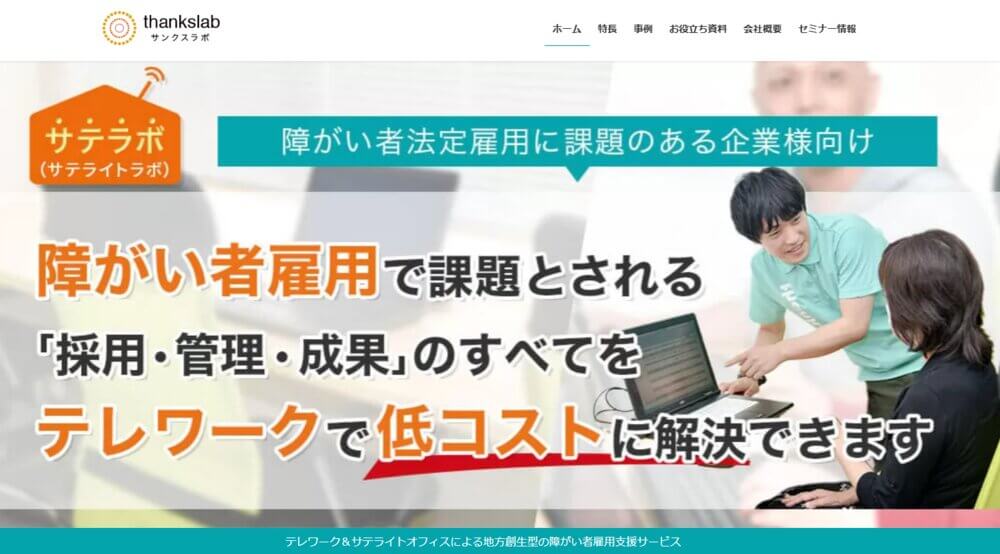
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
視覚障害の正しい理解|多様な「見え方」と業務遂行を支えるテクノロジー
視覚障害者の雇用を検討する上で、最初のステップは「視覚障害」という言葉が持つ多様性を正しく理解することです。画一的なイメージで捉えるのではなく、一人ひとりの「見え方」や「情報の得方」が異なることを認識することが、適切な配慮の出発点となります。
まず、視覚障害は大きく二つに分類されます。
- 全盲(ぜんもう): 光も感じない、あるいは明暗がかすかにわかる程度の状態を指します。視覚からの情報入力が全くないため、聴覚や触覚を最大限に活用して情報を得ます。PC操作は、後述するスクリーンリーダーによる音声読み上げや、点字ディスプレイを主に使用します。
- 弱視(じゃくし/ロービジョン): 視力は低いものの、メガネやコンタクトレンズで矯正しても、日常生活や就労で不自由を感じる状態です。しかし、何らかの形で視覚情報を活用しており、その「見え方」は千差万別です。代表的な見え方には以下のようなものがあります。
- 視野狭窄(しやきょうさく):見える範囲が極端に狭く、筒の中から覗いているような状態です。
- 中心暗点(ちゅうしんあんてん):視野の中心部分が見えず、周辺部のみ見える状態です。
- 羞明(しゅうめい):光に対して非常に敏感で、強いまぶしさを感じるため、通常の照明下でも作業が困難な場合があります。
これらの障害特性を補い、業務を遂行するために、様々な支援技術(アシスティブテクノロジー)が活用されます。特にオフィスワークにおいては、以下のツールの理解が不可欠です。
- スクリーンリーダー: PCの画面に表示されているテキスト情報や操作メニューを、合成音声で読み上げるソフトウェアです。視覚障害者がPCを操作するための最も基本的なツールと言えます(例:NVDA、JAWSなど)。
- 点字ディスプレイ: スクリーンリーダーが読み上げた情報を、リアルタイムで点字に変換して表示する機器です。指で触れて読むことで、文章の校正やプログラミングなど、より緻密な作業が可能になります。
- 拡大読書器: 紙の資料や書籍などをカメラで写し、モニターに大きく拡大して表示する装置です。
企業が理解すべきことは「見えないからできない」ではなく、「見えなくてもできる方法を用意すればできる」という発想の転換です。障害の等級や診断名だけで判断するのではなく、「その人が、どのツールを使い、どのように情報をインプット・アウトプットしているのか」を具体的に把握することで、企業として提供すべきサポートが明確になります。
活躍できる職種と業務設計のポイント
「視覚障害者にはどのような仕事を任せられるのか」という疑問は、多くの採用担当者が抱くものです。しかし、前述の支援技術を活用することで、活躍の場は企業が想像する以上に多岐にわたります。視覚情報への依存度が低く、PCスキル、論理的思考力、コミュニケーション能力が活かせる職種が中心となります。
IT専門職(プログラマー、システムエンジニア、QAテスターなど)
論理的思考力が求められるIT分野は、視覚障害者が強みを発揮しやすい代表的な職域です。スクリーンリーダーや点字ディスプレイを駆使し、コードの記述やデバッグ、システムテストを行います。画面の色やデザインに依存しないバックエンド開発や、品質保証(QA)の分野で活躍する方が多くいます。
事務職・バックオフィス業務
多くの定型的なオフィスワークは、PC操作が中心であるため、視覚障害者にとって取り組みやすい業務です。
- データ入力・処理: テキストベースのデータ入力や集計作業は、スクリーンリーダーを使えば効率的に行うことが可能です。
- 書類作成: WordやExcelなど、アクセシビリティが確保されたソフトウェアを使えば、報告書や資料の作成も問題なく行えます。
- 電話応対・カスタマーサポート: 優れた聴覚や落ち着いた対応力を活かし、顧客からの問い合わせ対応などで高いパフォーマンスを発揮する方もいます。PCでの顧客情報検索や応対記録の入力も並行して行います。
専門職・クリエイティブ職
特定の専門知識やスキルを活かす職務でも活躍の場は広がっています。
- ライター・編集者・翻訳者: 高い言語能力や集中力を活かし、文章の執筆や校正、翻訳業務に従事します。
- 研究職・分析職: 膨大なテキストデータの中から必要な情報を読み解き、分析・考察を行う業務で力を発揮します。
ヘルスキーパー(企業内理療師)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持ち、企業内で従業員の心身の健康維持・増進を担う専門職です。伝統的に視覚障害者が多く活躍してきた職種であり、福利厚生の充実と障害者雇用の両面で導入する企業が増えています。
ここで重要なのは、企業側が「この仕事は視覚的に確認する必要があるから無理だろう」と安易に決めつけないことです。業務プロセスを分解し、「本当に視覚が不可欠な作業は何か」「その作業は他の手段で代替できないか」を本人と共に検討する姿勢、そして視覚障害のある方にとっての「苦手」ではなく「強み」を見つけ、適材適所の配置を行う視点が、戦力化への近道です。
採用プロセスの設計|公正な選考とミスマッチ防止の具体策
視覚障害のある優秀な人材と出会い、その能力を正しく評価するためには、採用活動のプロセス自体に配慮が求められます。これは、応募者にとっても、また評価を行う企業にとっても、公正な選考を実現するために不可欠です。
募集・求人時の工夫
応募の段階から、企業の受け入れ姿勢を明確にすることが、安心してエントリーできる環境づくりに繋がります。
- 業務環境の情報を開示する: 求人票に、業務で使用するPCのOS(Windows/Mac)や、主要な業務ソフトウェア(例:Microsoft 365, Google Workspace)などを明記しておくと、応募者が自身のスキルや使用している支援技術との適合性を判断しやすくなります。
- 受け入れ姿勢を具体的に示す: 「スクリーンリーダー使用者歓迎」「ITアクセシビリティに配慮した職場環境です」といった一文を加えるだけで、応募者の心理的ハードルは大きく下がります。
- 応募書類の形式: 書類提出の手段として、PDFだけでなくWordファイルなどテキスト形式での応募も可能であることを明記します。
面接での配慮と確認事項
面接は、応募者のスキルと人柄を理解するための対話の場です。円滑なコミュニケーションのために、以下の点を心がけましょう。
- 事前の情報提供: 面接で用いる資料や会社案内などがあれば、可能な限り事前にテキストデータ(Wordファイルなど)で送付しておくと、応募者は内容を把握した上で面接に臨むことができます。
- 当日の環境設定と案内: 面接室に入室する際、「私、人事の〇〇です」とまず名乗り、応募者を席まで案内します。その際、「ドアは右側に引いて開きます」「お席は2歩ほど進んだ左側です」のように、物理的な環境を口頭で具体的に説明します。
- 面接の進行:
- 面接官が複数いる場合は、質問の前に各自が「営業部長の△△です」と名乗るようにします。
- 「あちら」「そちら」といった指示語は避け、「あなたの右手にあります資料の、3ページ目についてですが」のように、具体的で明確な言葉を選びます。
- 相槌を打つだけでなく、「はい、おっしゃる通りです」「なるほど」など、うなずきや表情といった非言語情報を言葉にして伝えると、応募者は安心して話すことができます。
- 質問内容: 障害そのものではなく、他の応募者と同様に、これまでの職務経歴やスキル、成功体験などを中心に質問します。その上で、面接の最後に「私たちの会社で業務を行う上で、どのような配慮や支援ツール、あるいは業務上の工夫があれば、〇〇さんの能力を最大限発揮できるとお考えですか?」と、必要なサポートについて本人に直接確認することが最も重要です。これは、入社後の具体的な環境整備を検討するための、非常に価値のある情報となります。
【最重要】職場環境整備|ハード・ソフト両面からのアプローチ
採用決定後、視覚障害のある社員がスムーズに業務を開始し、長期的に活躍するためには、職場環境の整備が不可欠です。これは障害者雇用における「合理的配慮」の核心部分であり、物理的な環境とデジタルな環境の両面からのアプローチが求められます。
物理的環境への配慮(ハード面の整備)
オフィスの安全性と移動のしやすさを確保することが基本です。
- 安全な動線の確保: 廊下や執務室の床に、段ボールやカバンといった障害物を置かないことを徹底します。通路の幅を十分に確保し、誰もが通りやすい環境を維持します。
- オフィスレイアウトの固定: デスクやキャビネット、コピー機などの配置を頻繁に変更しないようにします。もしレイアウトを変更した場合は、必ず本人に伝え、再度一緒に歩いて位置を確認します。
- 触覚による目印(ランドマーク)の活用: 本人のデスクやロッカー、頻繁に使う会議室のドア、給湯室の電子レンジのボタンなど、特定の場所に触ってわかるシール(点字シールや凹凸のあるシール)を貼ることで、本人が位置を特定しやすくなります。
- 入社初期のオリエンテーション: 入社初日や部署移動時には、担当者が付き添い、執務室からトイレ、休憩室、食堂、そして最も重要な避難経路までを、実際に一緒に歩いて案内します。
デジタル環境への配慮(ITアクセシビリティの確保)
現代のオフィスワークにおいて、物理環境以上に重要となるのがデジタル環境の整備です。
- PCおよび支援ソフトウェアの準備: 本人が使い慣れた、あるいは希望するスクリーンリーダー等のソフトウェアをPCに導入し、正常に動作するかを事前に確認します。業務に必要なソフトウェアとの相性問題が発生する場合もあるため、トライアル期間を設けることも有効です。
- 社内システム・ツールのアクセシビリティ: 勤怠管理システムや経費精算システム、社内イントラネットなどが、スクリーンリーダーで正しく操作できるかを確認します。もし操作できない箇所があれば、代替手段(例:代理入力、Excelでの申請)を明確に定めます。
- 情報共有のルール作り: 全社的に「アクセシブルな情報作成」を心がけることが、情報格差を防ぎます。
- 文書ファイル: PDFで共有する際は、画像ではなくテキスト情報が含まれた「テキストPDF」で作成します。スキャンしただけの画像PDFは、スクリーンリーダーでは読み上げられません。
- 画像・図表: メールや資料に画像やグラフを挿入する際は、その内容を説明する代替テキスト(altテキスト)を必ず設定するか、本文中に「〇〇を示すグラフ」といった説明を記述します。
- 会議の投影資料: 会議でスクリーンに映し出す資料は、可能な限り事前にデータで本人に共有します。
これらの取り組みは、結果的に社内の情報共有のあり方を標準化・明確化し、全社員にとって分かりやすい職場環境の実現に繋がります。
法的義務「合理的配慮」と活用できる公的支援制度
視覚障害者の雇用においては、障害者雇用促進法および障害者差別解消法に基づき、「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。合理的配慮とは、障害のある方が他の社員と平等に能力を発揮できるよう、個々の状況に応じて職場環境や業務方法を調整する措置を指します。提供を怠った場合、差別に該当する可能性があり、企業は是正指導の対象となり得ます。
- 合理的配慮の具体例(視覚障害)
- 採用面接において、事前に資料をテキストデータで提供する。
- 業務マニュアルや研修資料を、点字や音声データで提供する。
- スクリーンリーダーで読み上げ可能なPCやソフトウェアを準備する。
- 会議において、投影資料の内容を口頭で説明したり、発言者の名前を明確にしたりする。
- 移動に配慮し、オフィスの動線上の障害物を取り除く。
ただし、これらの配慮は、企業にとって「過重な負担」にならない範囲で提供されるものとされています。事業活動への影響度や費用負担の程度などを総合的に考慮し、本人と十分に話し合いながら、実行可能な配慮内容を決定していくプロセスが重要です。
- 負担軽減のために活用できる公的支援制度 合理的配慮の実施に伴う企業の経済的負担を軽減するため、国は様々な助成金制度を用意しています。これらを積極的に活用することで、より質の高い職場環境整備が可能になります。
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金: 視覚障害者用の拡大読書器、点字ディスプレイなどの機器購入費や、施設のバリアフリー化工事費、介助者の配置費用などが助成の対象となります。
- 障害者介助等助成金: 業務遂行に必要な支援機器の導入費用や、通勤を容易にするための介助者の配置費用などを助成します。
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業: 専門的な知識を持つジョブコーチが職場を訪問し、本人への支援や、事業主・同僚への助言を行います。
これらの制度の詳細は、管轄のハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で確認できます。制度を形式的に整えるだけでなく、こうした外部の専門機関や公的支援を有効活用することが、本質的な雇用支援の実現に繋がります。
雇用定着の鍵|チーム全体の理解と協力体制の構築
制度や環境を整えても、共に働く周囲の社員の理解と協力がなければ、本当の意味でのインクルージョンは実現しません。日々の円滑なコミュニケーションが、本人の心理的安全性を確保し、チームの一員としてのエンゲージメントを高めます。
社内への事前周知と理解促進
まず最も重要なのは、本人の同意を得ることです。障害の状況や必要な配慮について、本人がどこまでの範囲(部署内、全社など)で、どのような内容を周知してほしいかを確認し、その意向を絶対に尊重します。その上で、受け入れ部署のメンバーなどを対象に、説明の場を設けましょう。その際は、以下のような具体的な内容を共有すると、現場の戸惑いを減らすことができます。
- 本人が使用する支援ツール(スクリーンリーダーなど)の簡単な説明。
- 物理的な配慮(床に物を置かないなど)の必要性。
- 以下に挙げるような、具体的なコミュニケーション方法。
具体的なコミュニケーションの工夫
少しの心がけが、コミュニケーションの質を大きく向上させます。
- 声のかけ方: 後ろから突然話しかけるのではなく、まず相手の近くに行き、「〇〇さん、人事の△△です」と自分の名前を名乗ってから用件を話し始めます。これにより、誰が話しているのかを相手が確実に認識できます。
- 方向の伝え方: 「あそこ」「そっち」といった曖昧な指示語は避け、「〇〇さんの右斜め前、机の上にあります」「時計で言うと3時の方向です」のように、本人の位置を基準に、具体的・客観的に伝えます。
- 非言語情報の言語化: 会話中に自分が同意してうなずいているだけでは、相手に意図が伝わりません。「はい、そうですね」「なるほど、理解しました」のように、相槌や表情を言葉にして返します。会議の場での挙手なども同様に「〇〇が挙手しています」と誰かが発言すると親切です。
- 言葉遣いへの過度な遠慮は不要: 「こちらの資料をご覧ください」「またお目にかかりたいです」といった、視覚に関する言葉は、多くの場合、日本語の慣用句として定着しています。本人は聞き慣れていることがほとんどなので、過度に言葉を選びすぎず、自然体で接することが、かえって良好な関係を築きます。わからないこと、不安なことがあれば、本人に直接「このように接して大丈夫ですか?」と尋ねることが、相互理解への一番の近道です。
まとめ
視覚障害者の雇用を成功に導くための要諦は、「特別な誰かのために、特別な何かをする」という発想からの転換にあります。それは、「情報のアクセシビリティを確保し、誰もが能力を発揮できる職場環境を標準仕様にする」という、より普遍的で戦略的な視点を持つことです。
本記事で解説した、障害特性の正しい理解、支援技術の活用、採用プロセスにおける配慮、そして物理的・デジタル両面での環境整備は、すべてこの視点に基づいています。特に、スクリーンリーダーで読み上げ可能なデジタル文書の作成や、視覚情報に頼らない明確なコミュニケーションルールの設定といった取り組みは、結果として社内の情報伝達を効率化し、全社員の生産性を向上させる可能性を秘めています。
企業が主導してこれらの準備と環境構築を行うことは、視覚障害のある社員が持つ専門性やスキルを最大限に引き出し、企業にとって欠かせない「戦力」として活躍してもらうための、最も確実な投資です。一方的な「支援」ではなく、共に成長するための「協働」へ。その第一歩を踏み出すことで、貴社は真のダイバーシティ&インクルージョンを実現し、組織としての新たな力を手に入れることができるでしょう。