聴覚障害者の雇用を成功させる全手順|採用・環境整備・定着の秘訣

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに:法的義務から企業の新たな「戦力」獲得へ
障害者雇用促進法が定める法定雇用率の達成は、現代企業が果たすべき重要な社会的責務です。2024年現在の民間企業における法定雇用率は2.5%であり、この数値は2026年度中に2.7%へと引き上げられることが決まっています。この法的義務への対応は、多くの人事責任者にとって喫緊の課題と言えるでしょう。
その中でも、特に聴覚障害のある方の雇用については、コミュニケーション面での漠然とした不安から、採用に二の足を踏むケースが少なくありません。しかし、その判断は、企業にとって大きな機会損失となっている可能性があります。聴覚障害のある方は、静かな環境で発揮される高い集中力、正確性が求められる業務における緻密さ、そして音声情報に頼らない独自の視覚的・論理的思考力といった、多くの強みを持つ潜在的な戦力です。
採用や定着のハードルとなっている課題は、実は企業の少しの工夫と正しい理解、そして体系的な準備によって十分に乗り越えることが可能です。重要なのは、一方的に「配慮する」という姿勢ではなく、共に働く仲間として「情報格差をなくす仕組み」を整えるという視点です。本記事では、聴覚障害のある方の雇用を成功に導くため、担当者が知るべき障害特性の基礎知識から、採用選考時の具体的な注意点、受け入れ後の職場環境整備、そして法的義務である「合理的配慮」の考え方までを網羅的に解説します。漠然とした不安を解消し、聴覚障害者の雇用を企業の確かな成長力へと変えるための一歩を、ここから踏み出してください。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
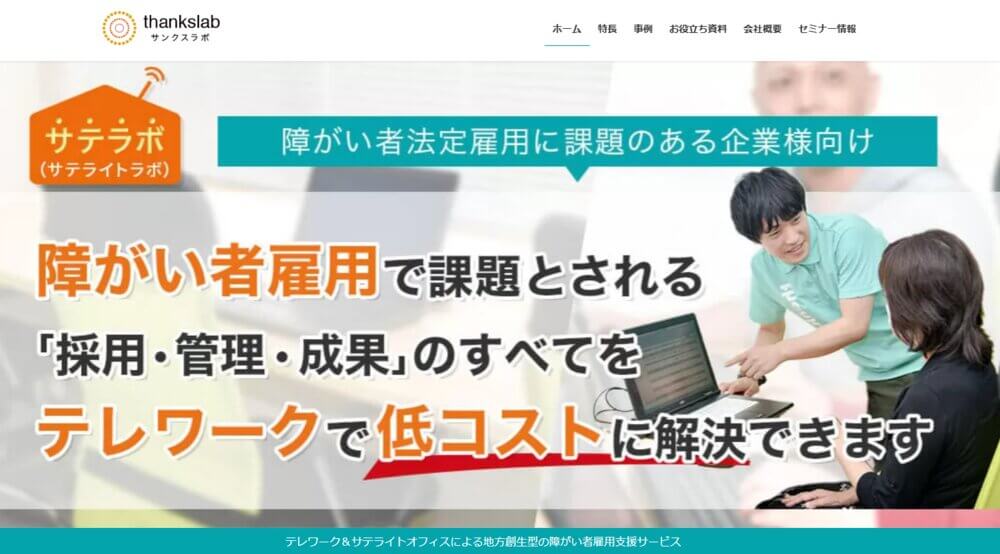
|
|
要お問い合わせ ※初期費用:0円 ※人材紹介料は一切かからない |
要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
聴覚障害の多様な特性とコミュニケーション
聴覚障害者の雇用を検討する上で、最初のステップは「聴覚障害」という特性を画一的なイメージで捉えず、正しく理解することです。大前提として、聞こえ方は一人ひとり全く異なります。「聴覚障害=全く音が聞こえない(全ろう)」という認識は誤りです。
聞こえ方の多様性
障害の程度は軽度・中等度・重度と様々で、音が小さく聞こえる難聴の方もいれば、特定の周波数(高い音・低い音)が聞き取りにくい方、音は感知できても言葉として正確に聞き分けることが難しい方など、その状態は実に多様です。補聴器や人工内耳を装用することで、一定の会話が可能になる方もいます。障害者手帳の等級はあくまで目安の一つであり、その人の聞こえ方やコミュニケーション能力を断定するものではありません。先入観を持たずに、目の前にいる本人と直接対話し、特性を理解しようと努める姿勢が何よりも重要です。
主なコミュニケーション手段
本人がどの方法を希望し、得意とするかを把握することが、円滑な雇用の第一歩です。
- 筆談: 紙やホワイトボード、PCのチャットツールなどを用いる、最も確実性の高い手段です。認識の齟齬が起きにくく、記録として残るメリットもあります。
- 口話(読話): 相手の口の動きを読み取る方法です。非常に高い集中力を要するため、早口や専門用語、複数人での会話、マスク着用時などでは読み取りが困難になります。あくまで補助的な手段と捉えるのが適切です。
- 手話: 独自の文法体系を持つ一つの「言語」です。もし候補者が手話を主なコミュニケーション手段とする場合、必要に応じて面接や会議に手話通訳者の配置を検討する必要があります。
- 音声認識アプリ/ツール: 近年、スマートフォンの音声認識アプリやPCの文字起こしツールの精度が向上しており、会議やミーティングでの強力な補助ツールとなり得ます。
職場において聴覚障害のある方が直面する最大の課題は、電話対応、口頭での指示、会議、雑談など、音声情報に依存したやり取りの中で生まれる「情報格差」です。この情報格差が、業務理解の遅れや孤立感に繋がりかねないことを認識し、代替手段によって情報をいかに正確に届けるかを考えることが、雇用成功の基礎となります。
採用活動の準備と選考プロセスにおける重要ポイント
優秀な人材を確保するためには、採用活動の各フェーズで適切な準備と配慮が求められます。これは「特別扱い」ではなく、応募者が持つ本来のスキルや経験を公正に評価するための「環境調整」です。
募集・求人時の工夫
企業の受け入れ姿勢を明確に示すことが、応募の心理的ハードルを下げ、母集団形成に繋がります。
- 業務内容の明記: 「電話応対業務なし」「電話対応は他社員と連携」など、音声コミュニケーションへの依存度を具体的に記載します。
- 配慮内容の提示: 「業務上の指示や連絡はチャットツールを使用」「会議での文字起こし支援あり」など、提供可能な配慮を具体的に示すことで、応募者は安心してエントリーできます。
面接の準備と実施
事前の準備が成否を分けます。応募者の能力を正しく見極めるために、以下の点を徹底しましょう。
- コミュニケーション方法の事前確認: 面接日程の調整と併せて、メール等のテキストで、応募者が希望するコミュニケーション方法(筆談、PCでの文字入力、手話通訳者の同席など)を必ず確認します。
- 環境の整備: 周囲の雑音が少ない静かな個室を用意し、互いの表情や口元がはっきり見えるよう、照明が明るい環境を確保します。オンライン面接の場合は、背景をシンプルにし、通信環境を安定させます。
- 面接の進行:
- 一度に多くの質問をせず、一つひとつ区切って、明確かつ簡潔な言葉で問いかけます。
- 抽象的な表現や業界用語は避け、具体的な業務をイメージできるよう、PC画面で資料やマニュアルを見せながら説明すると効果的です。
- 聴覚に障害があるからといって、障害に関する質問ばかりをするのは不適切です。他の応募者と同様に、これまでの経験、スキル、仕事への意欲を評価するという基本姿勢を貫きます。
重要なのは、「聞こえないこと」を課題として見るのではなく、「業務に必要な情報を、音声以外の代替手段で伝達し、理解してもらえるか」という視点で評価することです。この丁寧なプロセスが、企業の誠実さを伝え、入社後の信頼関係の礎となります。
【最重要】社員の活躍を支える職場環境整備の具体策
採用決定後、聴覚障害のある社員が能力を最大限に発揮し、長期的に活躍するためには、受け入れ体制と職場環境の整備が不可欠です。これは「合理的配慮」の核心部分であり、企業の真価が問われるポイントです。ハード面とソフト面の両方からアプローチします。
- ハード面:情報保障と安全確保の仕組み化 視覚的に情報を得られる設備やツールの導入が重要です。
- 会議・ミーティング: リアルタイム字幕ツールや文字起こしソフトの活用が極めて効果的です。また、事前にアジェンダや資料を共有し、会議後には決定事項をまとめた議事録を速やかに共有する運用を徹底します。
- 社内連絡: 朝礼や全社放送など、口頭での一斉連絡は、必ずチャットやメールで同じ内容を配信します。「音声情報とテキスト情報は常にセットで発信する」ことをルール化しましょう。
- 安全確保: 火災報知器や緊急地震速報など、安全に関わる音声通知には、光の点滅で危険を知らせる回転灯(パトライト)や、振動で知らせるデバイスを連動させるなど、視覚・触覚での代替手段が必須です。
- 設備・備品: 業務で電話対応が必須な場合は、音声とテキストを自動で変換する電話リレーサービスやツールの導入を検討します。
- ソフト面:業務フローとルールの見直し ツールだけでなく、日々の仕事の進め方を見直すことが、本質的な支援に繋がります。
- 業務指示のテキスト化: 上司からの指示や同僚への依頼は、必ずチャットやメールなど形に残る方法で行います。これにより「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、指示内容の正確な理解を促します。
- 座席配置: 本人の希望を聞きながら、周囲の人の動きや表情が視覚的に把握しやすい席、あるいは逆に集中しやすい席など、最適な配置を一緒に考えます。
- OJT担当者の選任: テキストコミュニケーションを丁寧に行える社員をOJT担当者に任命し、業務の進め方や社内ルールを指導する体制を整えます。
これらの整備は、聴覚障害のある社員のためだけのものではありません。業務プロセスの可視化と標準化は、組織全体のコミュニケーションロスを減らし、結果として全社員の生産性向上にも寄与する投資なのです。
法的義務「合理的配慮」の理解と活用できる公的支援制度
聴覚障害者の雇用においては、障害者雇用促進法で定められた「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。合理的配慮とは、障害のある方が他の社員と平等に能力を発揮できるよう、個々の状況に応じて職場環境や業務方法を調整する措置を指します。提供を怠った場合、差別に該当する可能性があり、企業は是正指導の対象となり得ます。
- 合理的配慮の具体例(聴覚障害)
- 会議や研修の際に、手話通訳者を配置したり、PCで要約筆記者(ノートテイカー)を手配したりする。
- 採用面接において、筆談やチャットツールでの応答を可能にする。
- 口頭での指示を、必ずメールや指示書など書面で補足する。
- 電話対応が必須の業務を、本人の同意の上で、メールやチャットでの対応業務に変更する。
- 緊急時に備え、音声警報と連動する光警報装置(パトライト)を設置する。
ただし、これらの配慮は、企業にとって「過重な負担」にならない範囲で提供されるものとされています。事業活動への影響度や費用負担の程度などを総合的に考慮し、本人と十分に話し合いながら、実行可能な配慮内容を決定していくプロセスが重要です。
- 負担軽減のために活用できる公的支援制度 合理的配慮の実施に伴う企業の経済的負担を軽減するため、国は様々な助成金制度を用意しています。これらを積極的に活用することで、より質の高い職場環境整備が可能になります。
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金: 手話通訳者の派遣費用、筆談のための機器購入費、社内研修の実施費用などが助成の対象となります。
- 障害者介助等助成金: 職場介助者の配置や、業務遂行に必要な支援機器の導入費用を助成します。
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業: 専門的な知識を持つジョブコーチが職場を訪問し、本人への支援や、事業主・同僚への助言を行います。
これらの制度の詳細は、管轄のハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で確認できます。制度を形式的に整えるだけでなく、こうした外部の専門機関や公的支援を有効活用することが、本質的な雇用支援の実現に繋がります。
雇用定着の鍵|全社で取り組むべき社内理解と人間関係の構築
どんなに優れた制度やツールを導入しても、共に働く社員の理解と協力、すなわち「心理的安全性」が確保された職場でなければ、長期的な雇用定着は望めません。ソフト面の環境構築こそが、定着率向上の最も重要な鍵となります。
プライバシーへの配慮と同意の徹底
まず大前提として、障害の状況や必要な配慮について、本人以外の社員にどこまで、どのような内容を伝えるかは、必ず事前に本人の同意を得なければなりません。本人の意向を無視して情報を共有することは、信頼関係を著しく損なう行為です。本人が開示を希望する範囲と内容を確認し、その合意に基づいて情報共有を進めます。
受け入れ部署への事前研修
本人の同意を得た上で、配属先の部署メンバーを中心に、事前研修や説明会を実施しましょう。その場では、単に「聞こえないので配慮してください」と一方的に伝えるのではありません。
- 聴覚障害の多様な特性(聞こえ方は人それぞれであること)を共有する。
- 筆談やチャットでのコミュニケーションの具体的なコツを伝える(例:「大きな声より、正面を向いて口をはっきり動かす方が伝わりやすい場合がある」「結論から話すと分かりやすい」など)。
- 本人がどのような場面で情報から疎外されやすいかを具体的に説明する。
- 「後ろから声をかけても気づかないので、肩を優しくたたく」「視界に入ってから合図する」など、日常的な呼びかけのルールを決めておく。
インフォーマルなコミュニケーションへの配慮
業務上の会話だけでなく、ランチや休憩中の雑談といったインフォーマルなコミュニケーションの輪から本人が取り残されないよう、周囲が意識的に筆談やスマートフォンのメモ機能を使って会話に巻き込んでいく姿勢が、孤立を防ぎます。
定期的に上司が1on1の面談(もちろん本人が希望する方法で)を実施し、業務上の課題や人間関係の悩みを丁寧にヒアリングする機会を設けることも極めて重要です。こうした地道な働きかけが、障害の有無に関わらず誰もが尊重され、安心して働ける企業文化を醸成します。
まとめ|持続可能な障害者雇用を「企業の力」に変える視点
聴覚障害者の雇用は、単なる法的義務の遵守や社会貢献活動にとどまるものではありません。それは、企業の人材活用力とダイバーシティ推進の本気度を測る、重要な試金石です。
本記事で解説した、採用段階からの配慮、情報格差をなくすための環境整備、法的義務である合理的配慮の正しい理解、そして全社的な協力体制の構築は、すべてが一体となって機能することで初めて真の効果を発揮します。特に聴覚障害は外見から判断しづらいため、企業側が主導して「コミュニケーションの当たり前」を見直し、音声情報に依存しない仕組みを設計することが不可欠です。
一方的な「支援」ではなく、共に働く「戦力」として聴覚障害者を迎えるという視点に立つこと。そして、そのために必要な準備を体系的に行うこと。そのプロセス自体が、業務の可視化や標準化を促し、組織全体のコミュニケーション文化を洗練させます。企業のこうした主体的かつ戦略的な取り組みは、長期的には優秀な人材の確保と定着、そして企業ブランド価値の向上に確実に繋がるでしょう。

