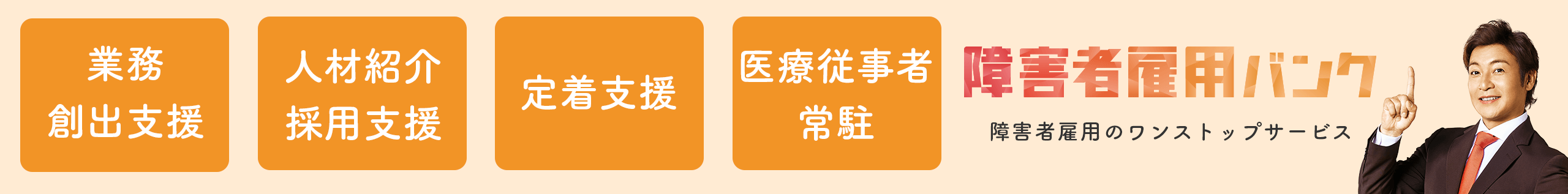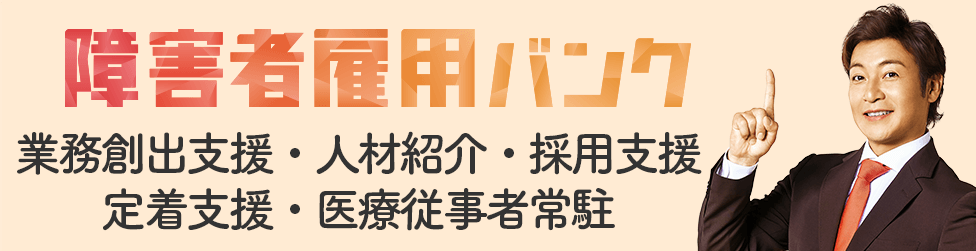障害者雇用の最低賃金|減額特例の条件と給与トラブル回避の方法

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに:障害者雇用の給与設定、「最低賃金」の正しい知識がトラブルを防ぐ
障害者雇用を推進する企業の経営層、人事責任者の皆様。「障害のある方の給与は、どのように設定すればよいのか」「最低賃金は適用されるのだろうか」こうした疑問や不安をお持ちではないでしょうか。障害者雇用における給与設定は、コンプライアンス遵守はもちろん、採用する社員のモチベーションや定着、ひいては企業の社会的評価にも直結する非常にデリケートかつ重要なテーマです。
特に「最低賃金」に関する知識が曖昧なまま採用を進めてしまうと、意図せず法令違反を犯してしまったり、従業員との間で深刻な労務トラブルに発展したりするリスクを抱えることになります。一方で、障害の特性により生産性の面で配慮が必要な場合に、どのような対応が認められているのか、その具体的なルールを知りたいという声も少なくありません。
本記事では、障害者雇用における最低賃金の基本的な考え方から、例外的に最低賃金の減額が認められる「減額の特例許可制度」の詳細、そして給与をめぐるトラブルを未然に防ぎ、持続可能な雇用を実現するための実践的なポイントまで、採用責任者が知っておくべき全てを網羅的に解説します。正しい知識を武器に、企業と従業員の双方が納得できる公正な雇用関係を築くための一助として、ぜひ最後までご一読ください。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
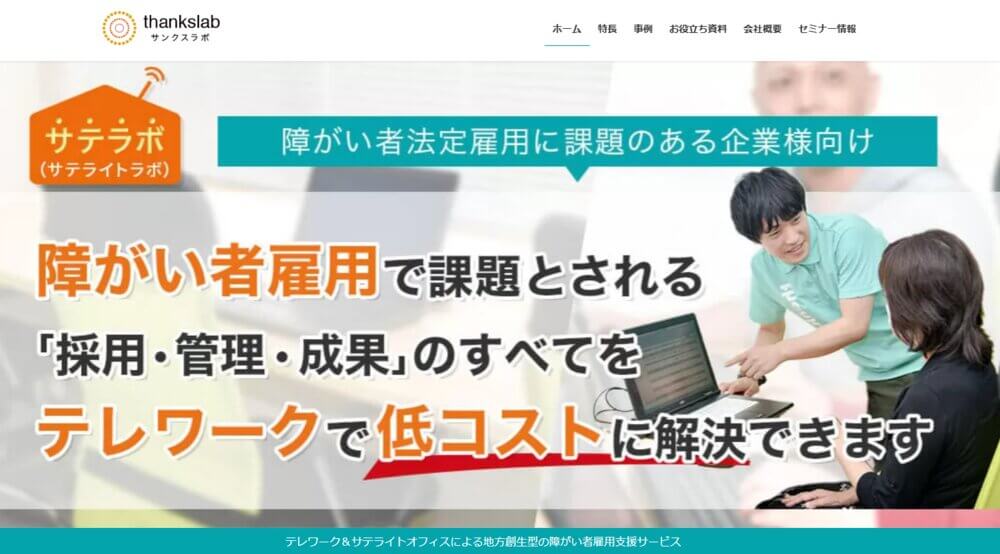
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
大原則:障害者雇用でも「最低賃金法」は等しく適用される
まず、企業の採用責任者として絶対に押さえておかなければならない大原則があります。それは、障害の有無にかかわらず、最低賃金法はすべての労働者に等しく適用されるということです。「障害があるから」「簡単な作業を任せるから」といった理由で、企業が一方的に最低賃金を下回る給与を設定することは、明確な法律違反となります。この点を誤解していると、後々、労働基準監督署からの是正勧告や指導、場合によっては罰則の対象となる可能性があり、企業の信頼を著しく損なう事態になりかねません。
最低賃金法第2条では、労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しており、障害の有無による区別は一切ありません。なぜ、現場では「障害者は最低賃金の対象外だと思っていた」という誤解が根強く残っているのでしょうか。その要因の一つが、後述する「最低賃金の減額の特例許可制度」の存在です。この制度があるために、障害者雇用では最低賃金が適用されない、あるいは容易に減額できる、といった誤った認識が広まってしまっているのです。
最低賃金には、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。両方の最低賃金が適用される労働者には、高い方の金額を支払う必要があります。これは障害者雇用においても全く同じです。採用活動を行う際には、必ず自社の事業所の所在地と業種に対応する最新の最低賃金額を確認し、それを下回らない給与条件を提示することが、コンプライアンスの第一歩です。
例外措置:「最低賃金の減額の特例許可制度」とは?
最低賃金法の大原則を理解した上で、次に知っておくべきが例外的な措置である「最低賃金の減額の特例許可制度」です。この制度は、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者等について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に最低賃金の減額を認めるというものです。
この制度の目的は二つあります。一つは、減額を認めなければ雇用の機会そのものが失われてしまう可能性のある障害者の雇用機会を確保すること。もう一つは、生産性に応じた賃金の支払いを認めることで、事業主の過重な負担を軽減し、雇用を維持しやすくすることです。
ここで最も重要なポイントは、「著しく労働能力が低い」という客観的な事実が必要であるという点です。単に「障害者手帳を持っているから」という理由だけでは、この特例の対象にはなりません。具体的には、同じ職場で同じ業務に従事している他の労働者と比較して、その作業能率や成果が著しく低い状態が該当します。例えば、健常者である同僚が1時間で100個の製品を組み立てられるのに対し、ある障害のある従業員が同条件で50個しか組み立てられない、といったケースが想定されます。このような能力差を客観的なデータや記録に基づいて示し、労働局に申請して初めて許可が得られる可能性があるのです。
この制度は、あくまで一般企業における雇用が対象であり、就労継続支援A型事業所における雇用契約とは区別して考える必要があります。また、この特例は「一時的な段階支援」という側面が強く、恒常的に使用することは想定されていません。むしろ、就労支援や作業環境の整備を通じて、通常の賃金水準に近づける努力が企業には求められます。安易な適用は許されず、厳格な要件のもとに運用されている特例中の特例であると理解することが不可欠です。
【人事担当者向け】減額特例許可の申請手続きと流れ
最低賃金の減額特例許可制度を利用するには、企業が任意で決定するのではなく、定められた手順に沿って正式な許可を得る必要があります。人事担当者として、その具体的なプロセスを正確に把握しておきましょう。
STEP1:申請の準備と能力評価
まず、申請の前提として、対象となる従業員の労働能力が「著しく低い」ことを客観的に証明する準備が必要です。
- 業務内容の明確化: 対象従業員が従事する業務内容、作業手順、求められる品質基準などを具体的に定めます。
- 能力評価の実施: 同じ業務に従事する他の労働者の平均的な作業能率(作業量、作業時間、正確性など)を測定します。その上で、対象従業員の作業能率を測定し、両者を比較した客観的なデータ(例:「健常者の平均作業能率を100%とした場合、当該従業員の能率は55%である」など)を作成します。この評価は、恣意的な判断を排し、公平かつ客観的でなければなりません。
STEP2:申請書類の作成と提出
次に、管轄の労働局へ提出する申請書類を準備します。
- 申請様式: 厚生労働省が定める「最低賃金減額特例許可申請書」を使用します。この様式には、申請する企業の詳細、対象労働者の情報、従事する業務内容、減額を申請する賃金額、減額率の算定根拠などを詳細に記入します。
- 添付書類: 申請理由を裏付ける資料として、STEP1で準備した能力評価のデータや、その他参考となる資料を添付することが求められる場合があります。
- 申請先: 申請書は、企業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に、労働基準監督署を経由して提出します。
STEP3:審査と許可
申請書が提出されると、労働基準監督署の担当官による事実確認や調査が行われます。必要に応じて、事業所への立ち入り調査や関係者へのヒアリングが実施されることもあります。労働局は、提出された書類と調査結果に基づき、減額の必要性や減額率の妥当性を審査します。減額率は、企業が申請した率がそのまま認められるとは限りません。評価された労働能力に応じて、労働局が最終的に決定します。審査の結果、許可が妥当と判断されれば「許可書」が交付され、その許可書に記載された日から減額が適用可能となります。許可には通常、有効期間が定められており、期間が満了する際には再度申請が必要になる点も注意が必要です。
参考データ:障害種別ごとの平均賃金と就業実態
企業が障害者の賃金水準を設計する際、参考になるのが公的な統計データです。厚生労働省が発表した「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、一般の事業所に雇用されている障害者の賃金には、障害種別によって一定の傾向が見られます。
- 身体障害者: 週30時間以上勤務する方の平均賃金は月額24万8,000円。比較的フルタイムの正社員として雇用されるケースが多く、賃金水準も相対的に高い傾向にあります。
- 知的障害者: 週30時間以上勤務する方の平均賃金は月額14万3,000円。
- 精神障害者: 週30時間以上勤務する方の平均賃金は月額18万9,000円。
- 発達障害者: 週30時間以上勤務する方の平均賃金は月額17万1,000円。精神障害者や発達障害者の場合、短時間勤務を選択する方も少なくなく、その場合の平均賃金はそれぞれ月額8万4,000円、8万7,000円となっています。
ここで特に注意が必要なのは、一般企業での雇用と、福祉サービスである「就労継続支援B型事業所」を混同しないことです。B型事業所は雇用契約を結ばないため最低賃金法が適用されず、利用者は「工賃」として対価を受け取ります。この工賃の平均額は非常に低いため、この水準を一般雇用の賃金設定の参考にしてしまうのは、重大な誤りです。
これらのデータはあくまで平均値であり、個々の賃金は本人の能力、経験、職務内容によっ.lop
て決まるべきものです。しかし、市場全体の傾向を把握しておくことは、自社の賃金水準が社会通念上、妥当な範囲にあるかを判断する一つの材料となります。
【トラブル防止】賃金設計で遵守すべき5つの実務ポイント
減額特例の適用を検討するしないにかかわらず、障害者雇用の賃金設計においては、トラブルを未然に防ぎ、従業員の信頼を得るために遵守すべき重要なポイントがあります。
本人の十分な理解と書面による同意形成
何よりもまず、対象となる従業員本人に対して、給与の決定根拠について誠実に、そして丁寧に説明することが不可欠です。特に減額特例を適用する際は、なぜこの制度を適用する必要があるのか、どのような基準で評価したのかなどを本人や、必要に応じて家族、支援機関の担当者も交えて説明し、十分に理解・納得してもらうプロセスが重要です。その上で、説明内容や合意事項をまとめた書面を作成し、労使双方で確認・保管しておくことが、後の「言った言わない」といったトラブルを防ぐ強力な防衛策となります。
客観的で公正な能力評価の徹底
給与額、特に減額の根拠となる労働能力の評価は、誰が見ても納得できるものでなければなりません。上司の主観や印象だけで判断するのではなく、健常者を含む複数の従業員の平均的なパフォーマンスを基準とし、それに対して対象従業員の能力がどの程度かを数値で示すなど、客観的な指標を用いることが求められます。作業時間、処理件数、エラー率などを一定期間記録し、データに基づいて評価することが理想的です。
同一労働同一賃金原則との整合性
障害者であっても、同じ企業内で同じ業務内容、同じ責任範囲の仕事をしている労働者であれば、原則として同水準の賃金を支払う必要があります。もし賃金に格差を設けるのであれば、その理由が障害にあるのではなく、職務内容、責任の度合い、能力、経験といった合理的な根拠に基づいていることを明確に説明できなければなりません。
定期的な評価と処遇の見直し
特に減額特例を適用した場合、その許可は永続的なものではありません。多くの障害のある方は、業務経験を積むことで生産性が向上します。企業には、一度決めた給与を固定するのではなく、定期的に(例えば半年に一度など)本人の能力を再評価し、その成長に応じて給与を見直す責務があります。能力向上に応じて通常賃金へ移行するキャリアパスを示すことは、本人のモチベーション維持と定着に不可欠です。
安易な減額特例の利用を避ける
賃金負担が懸念される場合、まず検討すべきは公的支援の活用です。障害者を雇用する企業向けには「特定求職者雇用開発助成金」など手厚い助成金制度があります。これらの制度を活用すれば、企業の負担を抑えつつ適正な給与を支払うことが可能です。減額特例の適用は、こうした支援策を最大限活用してもなお雇用継続が困難な場合の最終手段と位置づけるべきです。
まとめ:公正な処遇が、持続可能な障害者雇用を築く
障害者雇用における最低賃金の問題は、法律遵守という側面と、従業員との信頼関係構築という側面を併せ持つ、非常に重要なテーマです。本記事では、その基本原則から、例外的な「減額の特例許可制度」、そしてトラブルを防ぐための具体的な注意点までを解説しました。
大原則は、障害の有無にかかわらず最低賃金法は等しく適用されるということ。そして、減額特例は厳格な要件と手続きのもとに運用される特例中の特例であり、安易な適用は深刻なリスクを伴うということです。特に、本人への十分な説明と同意、客観的な能力評価、そして定期的な処遇の見直しは、この制度を検討する上で絶対に欠かせない必須事項です。
しかし、最も重要なのは、こうした法的な知識をベースとしつつも、その思考の出発点を「いかに減額するか」ではなく、「いかに公正に処遇し、活躍を促すか」に置くことです。適切な業務を切り出し、その貢献度に見合った給与を支払い、助成金などを活用して企業の負担も軽減する。この好循環を生み出すことこそが、障害のある社員の定着と成長を促し、企業のダイバーシティを推進し、最終的には組織全体の力を高めることに繋がります。最低賃金の正しい理解は、リスク管理であると同時に、企業の価値を高めるサステナブルな障害者雇用への第一歩なのです。