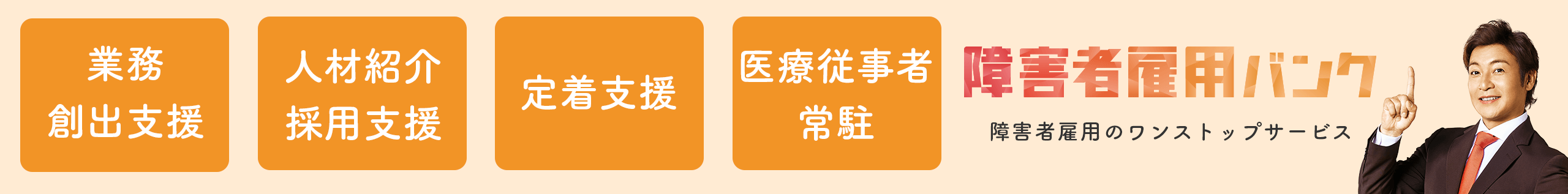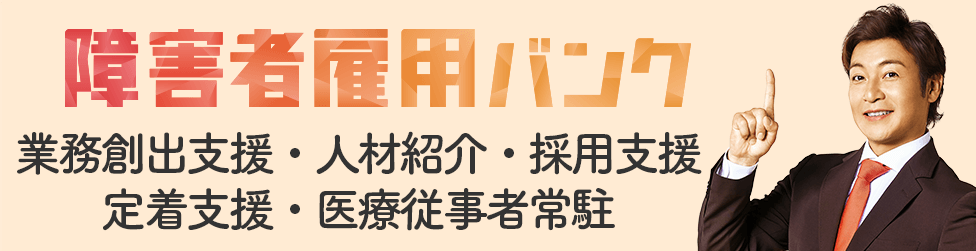更新日:2026/01/05
【2026年最新】障害者雇用率引き上げ完全ガイド|未達成リスクと企業が取るべき対策

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに
2024年4月、障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられ、企業の人事戦略は新たな局面を迎えています。この変更は一時的なものではなく、2026年7月には2.7%への再引き上げが確定しており、同時に雇用義務の対象となる事業主の範囲も従業員数40.0人以上、将来的には37.5人以上へと段階的に拡大されます。これにより、これまで対象外であった中小企業も障害者雇用を避けて通れない経営課題として認識する必要が出てきました。 厚生労働省の2023年の統計によれば、雇用義務のある民間企業のうち法定雇用率を達成しているのは約半数に留まり、多くの企業が対応に苦慮している現実があります。人事責任者や経営の意思決定を担う方々にとって、「具体的な対策が分からない」「未達成のリスクが不明確だ」といった不安は尽きないでしょう。
本記事では、この重要な法改正の要点を網羅的に解説し、雇用率未達成の場合に企業が直面する多角的なリスクを明らかにします。さらに、そのリスクを回避し、この変化を企業の成長機会へと転換するための具体的な対策を、専門的かつ実践的な視点から紐解いていきます。法令遵守に留まらない、戦略的な障害者雇用の第一歩を踏み出すための知識を、この記事で得ていただければ幸いです。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
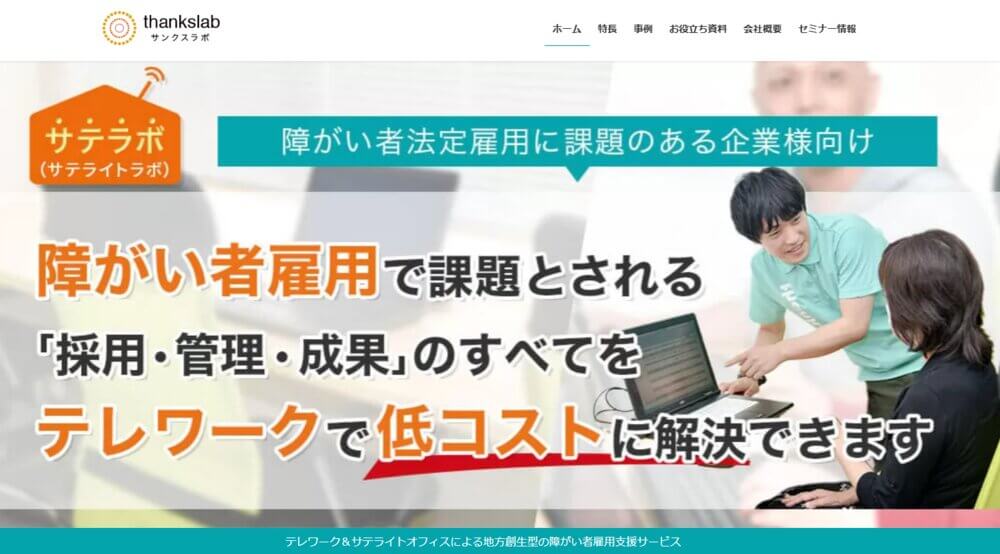
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
第1章:障害者雇用率引き上げの最新動向と企業への影響
障害者雇用率の引き上げは、現代の企業経営において無視できない法改正であり、企業の社会的責任と人材戦略に直接的な影響を及ぼします。その内容を正確に理解し、自社がどう対応すべきかを明確にすることが、今後の事業運営における必須事項です。
まず、最も重要な変更点である法定雇用率の具体的なスケジュールを確認します。
- 2024年4月1日〜: 民間企業の法定雇用率が2.5%へ引き上げ。
- 2026年7月1日〜: さらに2.7%への引き上げが予定。
この段階的な引き上げは、企業に対応準備のための猶予期間を与えていると同時に、着実な計画策定と実行が社会的に求められていることの表れです。
次に、雇用義務の対象となる事業主の範囲も拡大されています。
- 〜2024年3月: 常用労働者43.5人以上の企業
- 2024年4月〜: 常用労働者40.0人以上の企業
- 2026年7月〜: 常用労働者37.5人以上の企業
これにより、これまで対象外だった中小企業にも直接的な影響が及び始めています。もはや障害者雇用は、一部の大企業だけの課題ではないのです。
こうした制度変更の背景には、共生社会の実現という理念に加え、日本の構造的な課題があります。労働力人口が減少する中で、働く意欲と能力のある障害者は、企業にとって貴重な人材となり得るという経済的な側面も重要視されています。
また、今回の法改正では、企業がより多様な人材を雇用しやすくするための新たな算定特例も導入されました。特に注目すべきは、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の中で、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者を、雇用率の算定上「0.5人」としてカウントできるようになった点です。これは、フルタイムでの勤務が難しい方々にも就労の機会を広げ、企業側もより柔軟な形で雇用率達成を目指せるようにする重要な変更であり、戦略的な活用が期待されます。
第2章:見過ごせない法定雇用率「未達成」の経営リスク
法定雇用率の未達成は、単に「義務を果たしていない」という事実以上に、企業の事業活動に深刻な影響を及ぼしかねない多角的なリスクを内包しています。これらのリスクを正確に認識し、その重大性を理解することが、適切な対策を講じる上での第一歩となります。
1. 行政指導から企業名公表へ至る段階的ペナルティ
未達成企業に対して、まずハローワークから障害者の雇入れ計画作成命令が出されます。これは2年間で法定率を達成するための具体的なプラン提出を求めるものです。計画の進捗が思わしくない場合、「適正実施勧告」へと指導が強化されます。それでもなお改善が見られない悪質なケースと判断されると「特別指導」を経て、最終手段として厚生労働省のウェブサイトで企業名が公表される可能性があります。これは企業の社会的信用を根底から揺るがす、最も避けたい事態です。
2. 財務を圧迫する障害者雇用納付金
常用労働者が100人を超える事業主で法定雇用率を下回る場合、不足している人数1人あたり月額50,000円の納付金が課されます。例えば2人不足していれば年間120万円の負担となり、これは直接的に企業の利益を圧迫します。この納付金は罰金ではありませんが、企業の社会的責任が果たせていないことの証左と見なされかねず、財務的な負担と同時に評判に関わる問題でもあります。
3. 企業価値を毀損する広範なレピュテーションリスク
現代はESG投資、すなわち環境・社会・ガバナンスを重視する経営が求められる時代です。障害者雇用の未達成や企業名公表は、この「ソーシャル(S)」の観点から非財務リスクとして明確に認識され、企業価値に直接的な影響を及ぼします。
- 取引や資金調達への悪影響: 取引先からの信頼低下や、金融機関からの融資評価の悪化に繋がりかねません。
- 採用競争力の低下: 特に社会貢献意識の高い若い世代から「選ばれない企業」となり、優秀な人材の獲得が困難になります。
- 社内への負の影響: ダイバーシティ推進を掲げながら実態が伴わない場合、従業員のエンゲージメント低下や企業への不信感を招く「姿勢の矛盾」として受け止められます。
- 各種認定制度への不利益: 助成金の申請制限や、「ユースエール認定」といった各種認定制度の審査で不利になるケースもあり、見えないコストとして経営に影響します。
これらのリスクは相互に関連し合っており、一度発生するとその影響は長期にわたって企業経営の足かせとなります。
第3章:【実践編】雇用率達成に向けた5つの具体的ステップ
法定雇用率の引き上げという変化に対応しリスクを回避するためには、場当たり的ではなく計画的かつ早期の対策が不可欠です。ここでは、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策を5つのステップに分けて解説します。
Step1:正確な現状把握と制度理解
対策の出発点は、自社の正しい実雇用率を知ることです。そのためには、まず制度の複雑さを正確に理解する必要があります。「常用労働者」とは週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる者を指し、役員等は除外されます。この対象者数を正確に算出し、現在雇用している障害者数を障害種別や労働時間に応じたカウント方法(例:重度障害者はダブルカウント、短時間労働者は0.5人カウント)で計算します。この計算を通じて、法定雇用率に対し自社があと何人採用する必要があるのかという具体的な不足人数を明確にします。この最初のステップでの誤解は、後のすべての計画を狂わせる可能性があるため、極めて重要です。
Step2:全社的な採用計画の策定
不足人数が明らかになったら、次に「いつまでに」「どの部署で」「どのような業務を担ってもらうか」という具体的な計画を立てます。この計画は人事部だけで完結させるのではなく、経営層を巻き込み、実際に障害のある社員を受け入れる現場部署の協力を得ながら、全社的なプロジェクトとして推進することが成功の鍵です。採用ターゲットの特性や必要な配慮を想定し、それに合った業務の切り出しや環境整備の計画も同時に進めましょう。
Step3:採用と定着を支える社内体制の構築
採用活動と並行して、障害のある社員が安心して能力を発揮できる環境を整えます。
- 業務の創出: 定型的なデータ入力や書類整理、軽作業といった業務を既存業務から切り出して新たなポジションを創出します。
- 管理職への理解促進: 現場のマネジメント層が障害特性を理解し、適切なコミュニケーションや指示方法を学べるよう、定期的な研修機会を設けることが不可欠です。
- 相談体制の整備: 気軽に相談できる窓口の設置やメンター制度の導入は、入社後のスムーズな定着を力強くサポートします。
Step4:採用チャネルの多様化と外部リソースの活用
自社のニーズに合った人材と出会うためには、多様な採用チャネルと外部リソースの活用が有効です。
- ハローワーク: 障害者専門の窓口を通じて、人材紹介や職場実習、トライアル雇用制度を活用できます。
- 専門エージェント・求人サイト: 障害者雇用に特化した人材紹介サービスや求人サイトは、効率的なマッチングを促進します。
- 就労移行支援事業所との連携: 職業訓練を受けた人材の紹介や、専門スタッフによる定着支援を受けられるため、企業の導入負担を軽減できます。
- 専門家との連携: 社会保険労務士や障害者雇用コンサルタントは、制度の正確な理解や助成金活用、実務上の課題解決において頼れるパートナーとなります。
Step5:継続的な定着支援と合理的配慮
採用はゴールではなくスタートです。採用した社員が長く活躍し続けるためには、入社後の継続的なサポート、すなわち定着支援が極めて重要になります。定期的な面談を通じて本人の困りごとやキャリアに関する意向を確認し、通院や体調に合わせた柔軟な勤務時間や休憩の取り方、分かりやすい指示方法といった「合理的配慮」を提供することは法律上の義務でもあります。こうした地道な取り組みが、個人の活躍と組織の成長の両方を実現します。
第4章:義務から戦略へ|障害者雇用がもたらす企業価値向上のメリット
障害者雇用への対応は、リスク回避という「守り」の側面だけでなく、企業に多くのポジティブな変化と成長機会をもたらす「攻め」の経営戦略となり得ます。法令遵守の先にある、企業価値を高める戦略的なメリットを解説します。
1. 新たな人材確保とダイバーシティ経営の実現
労働力人口が減少する現代において、働く意欲と多様な能力を持つ障害者は、企業の持続的成長を支える貴重な人材です。これまで想定していなかった人材層にアプローチすることで、企業は新たな才能やスキルを発掘する機会を得られます。異なる背景や視点を持つ人材が協働することで、組織内に新たな発想が生まれ、硬直化した組織文化に変革をもたらすイノベーションの起爆剤となる可能性も秘めています。
2. 組織活性化と業務プロセスの改善
障害のある社員を受け入れる過程では、多くの場合、既存の業務内容や進め方を見直すことになります。「誰がやっても同じ品質を保てるように業務を標準化する」「曖昧だった指示方法をマニュアル化する」といった取り組みは、結果として組織全体の生産性向上に繋がります。業務プロセスが見直され、非効率な作業や属人化していた業務が可視化されることは、大きなメリットです。また、障害のある同僚と共に働く経験は他の社員の多様性への理解を深め、協力し合う風土を醸成し、チームワークの向上や従業員エンゲージメントの強化に繋がります。
3. ESG評価の向上と企業ブランドの強化
ESG投資が世界の潮流となる中、障害者雇用への積極的な取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たす明確な証しとなり、「ソーシャル(S)」の観点から高く評価されます。
- 投資家・金融機関からの信頼獲得: ESG評価の高い企業は、投資家や金融機関からの信頼を得やすくなります。
- 取引や公共調達での優位性: 企業間の取引や公共調達において、障害者雇用への取り組みが評価項目となるケースが増えており、実務的なメリットも存在します。
- 採用ブランドの向上: 社会貢献性の高い企業として認知されることは、特に若い世代に対する採用競争力を高める上で大きなアドバンテージとなります。
障害者雇用を「義務」ではなく「価値創出の起点」として捉え直すことが、企業の持続的成長に資する重要な経営施策となるのです。
まとめ
障害者雇用率の引き上げは、多くの企業にとって対応を迫られる課題であると同時に、企業体質を強化し、持続可能な経営を実現するための絶好の機会です。未達成による納付金負担や企業名公表といった経営リスクを回避することはもちろん、その先には、多様な人材の確保によるイノベーションの創出、組織全体の生産性向上、そしてESG評価の向上といった、企業価値を高める多くのメリットが存在します。 重要となるのは、この変化を「いつか対応する」他人事としてではなく、「今だからこそ動くべき」自社の経営課題として捉え、計画的に行動を起こすことです。ご紹介した「現状把握」「計画策定」「体制整備」「外部連携」「定着支援」というステップを着実に進めることで、障害者雇用は単なる法令遵守の枠を超え、企業の成長を加速させる戦略的な一手となり得ます。未来の競争力を左右するこの一歩を、今踏み出すことが何より重要です。