【企業向け】障害者雇用の定着率が低い5つの理由と、離職を防ぐ改善策を徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「せっかく採用した障害のある社員が、数ヶ月で辞めてしまった」「毎年採用しているのに、なかなか定着しない」 多くの企業で障害者雇用が進む一方で、このような「定着」に関する深刻な悩みを抱える決裁者・人事責任者様は少なくありません。障害のある社員の早期離職は、単に「残念な出来事」では済まされない、重大な経営課題です。
一人を採用するために費やした求人コストや面接の時間、そして入社後に行った教育・研修の労力。これらすべてが、一人の離職によって水泡に帰してしまいます。さらに、受け入れ部署の士気低下や、欠員補充のための再採用コストといった、目に見えない損失も発生します。
なぜ、障害者雇用において「定着」はこれほどまでに難しいのでしょうか。そして、この負のスパイラルを断ち切り、彼らが長く活躍できる組織を作るためには、企業は何をすべきなのでしょうか。本記事では、その根本原因をデータに基づいて紐解き、明日から実践できる具体的な改善策を、採用戦略から組織体制の構築まで網羅的に解説します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
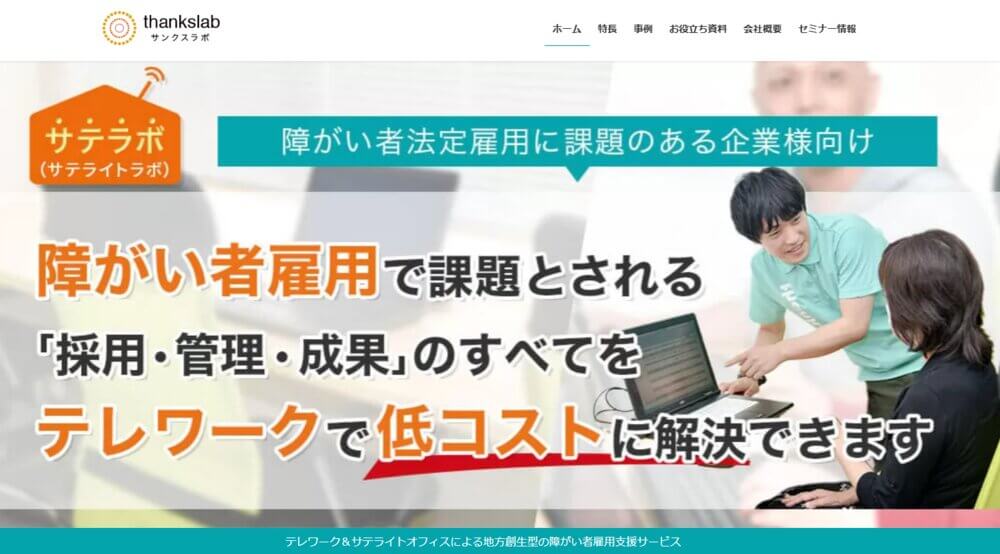
|
|
要お問い合わせ ※初期費用:0円 ※人材紹介料は一切かからない |
要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障害者雇用の厳しい現実。データで見る「定着率」の現状と離職コスト
まず、障害者雇用の定着率に関する客観的なデータを直視することから始めましょう。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の調査研究によると、就職後1年時点での職場定着率は、障害種別によって大きく異なることが示されています。
- 身体障害:61.4%
- 知的障害:64.2%
- 精神障害:52.5%
- 発達障害:70.7%
※データは調査年により変動します。上記は傾向を理解するための参考値です。
このデータから、特に精神障害のある方の定着が大きな課題であることが分かります。近年の障害者雇用の中心が、身体障害から精神障害・発達障害へとシフトしている現状を踏まえると、企業にとって「定着率の向上」は、法定雇用率を継続的に達成する上でも避けて通れないテーマなのです。
では、この「定着率の低さ」は、企業にどれほどの損失をもたらすのでしょうか。仮に、一人の社員を採用するために100万円のコスト(求人広告費、人材紹介手数料、面接に関わる人件費など)がかかり、入社後の3ヶ月間の研修やOJTに50万円相当のコスト(研修費用、指導役の人件費など)がかかるとします。もし、その社員が1年以内に離職してしまえば、単純計算で150万円以上の投資が回収不能となります。これが複数名となれば、その損失額は経営を圧迫しかねません。
定着率の低さは、単なる人事部門の課題ではなく、企業の収益性に直接影響を与える「経営リスク」であるという認識を持つことが、全ての改善策の出発点となります。
なぜ定着しない?障害のある社員が早期離職する5つの根本原因
定着率を改善するためには、まず「なぜ彼らが離職に至るのか」という根本原因を正しく理解する必要があります。離職の理由は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。ここでは、代表的な5つの原因を掘り下げていきます。
業務内容のミスマッチ
これは最も多い離職理由の一つです。本人の能力や障害特性に対して、任された仕事が「難しすぎる」または「簡単すぎる」場合に発生します。難しすぎる業務は過度なストレスと自信喪失に繋がり、簡単すぎる業務はやりがいの欠如と成長実感のなさに繋がります。また、業務量が過大で心身が疲弊してしまうケース、逆に業務量が過小で疎外感を覚えてしまうケースも、離職の引き金となります。
職場の人間関係とコミュニケーション不全
職場での孤立は、精神的な健康を著しく損ないます。障害特性への無理解からくる心ない一言や、悪意のない「からかい」が、本人を深く傷つけることがあります。また、業務以外の雑談の輪に入れない、気軽に相談できる相手がいないといった状況が続くと、徐々に職場に居場所がないと感じるようになります。コミュニケーションのすれ違いが、本人も周囲も気づかないうちに深刻な溝を生んでしまうのです。
企業側の障害特性への理解・配慮不足
企業側が合理的配慮の提供義務を十分に果たしていないケースです。例えば、聴覚過敏のある社員に対して、電話が鳴り響く騒がしい席に配置したり、易疲労性のある社員に残業を強いたりといった配慮の欠如が、就労継続を困難にします。一方で、良かれと思って行った「過剰な配慮」も問題となり得ます。「危ないから」と一切の業務を任せなかったり、常に特別扱いをしたりすることが、かえって本人の自尊心を傷つけ、働く意欲を削いでしまうのです。
キャリアパスと評価への不安・不満
「この会社にいても、自分は成長できないのではないか」「ずっと同じ作業を続けるだけで、将来が見えない」といったキャリアに対する不安は、離職の大きな動機となります。障害があるという理由だけで、昇進や昇給の機会が与えられなかったり、目標設定や評価のプロセスが不透明・不公正であったりすると、仕事へのモチベーションは著しく低下します。
心身のセルフケアと健康状態の悪化
障害のある方は、日々の通勤や業務遂行に、健常者以上のエネルギーを消耗している場合があります。本人も「周りに迷惑をかけたくない」という思いから無理をしがちで、疲労やストレスを溜め込んでしまいます。自身の体調変化をうまく上司に伝えられなかったり、相談できる環境がなかったりすると、心身のバランスを崩し、最終的に就労継続が困難な状態に陥ってしまうのです。
【採用編】定着は入社前から始まっている。ミスマッチを防ぐ採用戦略
障害者雇用の定着率を高めるための取り組みは、入社後から始めるのでは遅すぎます。採用選考の段階で、いかに「ミスマッチ」を減らすか。定着支援の成否は、その大部分が「入口」である採用戦略にかかっていると言っても過言ではありません。
「誰でもできる仕事」ではなく「あなたに任せたい仕事」を定義する
求人票に「簡単な事務補助」「軽作業」とだけ書かれていませんか。このような曖昧な求人は、応募者との認識のズレを生む最大の原因です。採用を始める前に、まずジョブディスクリプション(職務記述書)を作成しましょう。「どの部署で」「どのような業務を」「どんな手順で」「1日にどれくらいの量」行うのかを、可能な限り具体的に明文化します。これにより、企業側は求める人材像を明確にでき、応募者側も自身が働く姿を具体的にイメージできるため、ミスマッチのリスクを大幅に減らすことができます。
リアルな働き方を体験する「職場実習」を必ず導入する
数十分の面接だけで、その人の能力や職場との相性を判断するのは不可能です。ここで絶大な効果を発揮するのが、選考過程に数日間~数週間の「職場実習」を取り入れることです。実際に働いてもらうことで、企業は履歴書だけでは分からない本人の実務能力、指示理解力、コミュニケーションの取り方、職場環境への適応力などを多角的に評価できます。同時に、本人も「この仕事なら自分にもできそうだ」「この会社の雰囲気は合いそうだ」といったリアルな感触を得ることができます。この相互理解のプロセスが、入社後の「こんなはずではなかった」という早期離職を防ぐ最も有効な手段です。
面接では「できないこと」より「必要な配慮」をすり合わせる
採用面接は、応募者の欠点を探す場ではありません。その人が持つ能力を最大限に発揮するために、企業として「どのようなサポートや配慮をすれば良いか」を共に考える対話の場と位置づけることが重要です。「あなたの弱みは何ですか」といった詰問型の質問ではなく、「もし働く上で、何か困ることがありそうなら、どんなことですか」「その際、会社にどんな配慮があると働きやすいですか」といった質問を通じて、本人が安心して働ける環境を一緒に作っていく姿勢を示しましょう。この建設的な対話が、入社後の信頼関係の礎となります。
【環境・体制編】安心して長く働ける職場を作るための組織的アプローチ
障害のある社員の定着は、個人の努力や現場の善意だけに頼るべきではありません。担当者一人に負担を押し付けるのではなく、会社全体として、彼らが安心して能力を発揮できる環境と体制を組織的に構築することが不可欠です。
孤立を防ぐ相談体制の構築(1on1面談・メンター制度)
問題の早期発見と信頼関係の構築のために、最も有効な施策が定期的な面談です。少なくとも月に一度は、直属の上司や人事担当者が本人と1対1で話す時間(1on1)を設けましょう。その場では、業務の進捗確認だけでなく、「最近、疲れていませんか」「困っていることはありませんか」「職場の人間関係はどうですか」といった、体調や心理面に関するヒアリングも行います。課題が深刻化する前にキャッチし、迅速に対応することが、離職の芽を摘むことに繋がります。また、業務上の上司とは別に、年齢の近い先輩社員などが相談役となる「メンター制度」を導入することも、本人の心理的な孤立を防ぐ上で非常に効果的です。
「知らない」が差別を生む。管理職・同僚への理解促進研修
職場の人間関係に起因する離職を防ぐには、共に働く周囲の社員、特に管理職の理解が鍵を握ります。障害特性に関する知識が不足していると、悪意なく本人を傷つけてしまったり、適切な関わり方が分からず腫れ物に触るような対応になったりしがちです。これを防ぐため、障害者雇用に関する社内研修を定期的に実施しましょう。障害の基礎知識だけでなく、具体的な場面を想定したケーススタディや、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)について学ぶ機会を設けることで、全社員が「自分事」として捉え、障害のある社員を自然に受け入れる組織風土が醸成されます。
「合理的配慮」を組織の文化にする
合理的配慮とは、一部の社員への「特別扱い」ではありません。全ての社員がその能力を最大限に発揮するために、企業が行うべき「環境調整」です。この認識を組織全体で共有することが重要です。例えば、指示は口頭だけでなく、チャットやメモで視覚的に伝えるルールを徹底する。業務手順を写真や図で分かりやすくマニュアル化する。本人の体調に応じて、休憩のタイミングや場所を柔軟に選べるようにする。こうした一つひとつの取り組みが、障害の有無にかかわらず、誰もが働きやすい職場環境、すなわち「ユニバーサルデザイン」な職場へと繋がっていくのです。
【実践編】外部リソースと助成金をフル活用し、定着支援を加速させる
障害者雇用の定着支援は、全てを自社だけで完結させようとすると、人事担当者や現場に過大な負担がかかり、疲弊してしまいます。持続可能な支援体制を築くためには、社外の専門的なリソースや、国が用意する助成金制度を戦略的に活用する視点が不可欠です。
社内だけで抱えない。外部の専門家と連携する
専門家の客観的な視点や知見を取り入れることで、社内だけでは見えなかった課題や、より効果的な解決策が見つかることがあります。
ジョブコーチ(職場適応援助者)支援
これは、企業が絶対に活用すべき公的制度の一つです。専門の支援員が一定期間、職場を定期的に訪問し、本人に対しては職場での対人スキルや体調管理の方法を、企業に対しては具体的な業務指導の方法や、職場環境の改善について、プロの視点から助言を行ってくれます。
障害者就業・生活支援センター
各地域に設置されている公的な相談機関です。仕事上の課題だけでなく、本人の生活面も含めて一体的にサポートしてくれます。「最近、遅刻が増えた」といった変化の背景にある生活上の問題を解決するための糸口が見つかるかもしれません。
民間の定着支援サービス
より手厚いサポートを求める場合は、民間の専門サービスを活用するのも有効です。専門のカウンセラーによる定期的なオンライン面談や、企業の人事担当者へのコンサルティングなど、多様なサービスが提供されており、自社のニーズに合わせて利用することで、人事部門の工数を大幅に削減できます。
定着支援に使える助成金を賢く活用する
定着率向上のための企業の取り組みを、国は金銭面でも後押ししています。これらの制度を積極的に活用し、コストを抑えながら支援体制を強化しましょう。
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
職場への定着を促進するために、指導担当者の配置、面談、研修、社内理解の促進といった取り組みを行った場合に、その経費の一部が助成されます。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障害のある社員の職業能力の向上を目的とした研修(OJTやOff-JT)を実施した場合に、その経費や期間中の賃金の一部が助成されます。キャリアアップを支援することで、本人の働く意欲を高めることに繋がります。
まとめ:定着率向上は、企業の持続的成長を実現する「価値創造」である
本記事では、障害者雇用の定着率が低い根本的な原因を5つの側面から分析し、採用から入社後の体制構築に至るまでの具体的な改善策を解説しました。
障害のある社員が定着しない背景には、業務のミスマッチ、人間関係、配慮不足など、複合的な要因が絡み合っています。しかし、その一つひとつに対して、企業が打つべき手立ては明確に存在します。「定着率の向上」とは、小手先のテクニックではなく、採用戦略の見直しから、組織的な支援体制の構築までを一貫して行う、包括的な経営課題なのです。
そして、この課題への取り組みは、単に離職コストを削減する「守りの一手」に留まりません。社員一人ひとりが安心してその能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、組織全体の生産性を向上させます。多様性を受け入れる文化を醸成することは、新たなイノベーションを生み、企業のブランドイメージを高めます。つまり、定着率への投資は、企業の持続的な成長を実現する「価値創造」そのものなのです。
とはいえ、これらの包括的な取り組みを、ノウハウやリソースが限られる中で自社だけで行うのは容易ではありません。成功の鍵は、ジョブコーチや定着支援サービスといった外部の専門家をパートナーとして迎え入れ、共に課題解決に取り組むことです。専門家の力を借りることで、より効果的かつ効率的に、全ての社員が活躍できる職場環境を実現できるでしょう。

