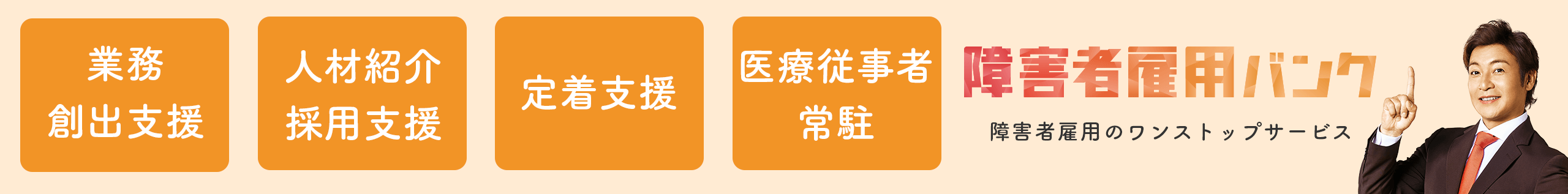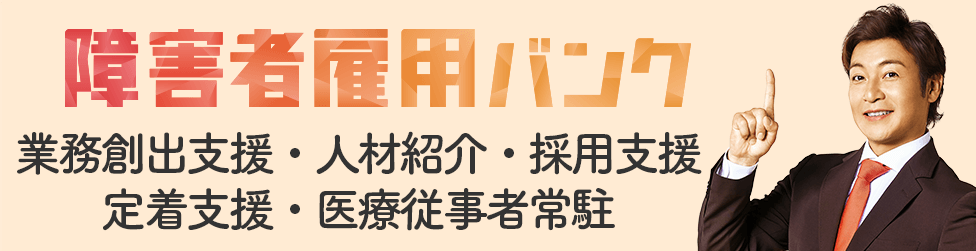更新日:2026/01/05
法定雇用率とは?【2026年最新】計算方法・今後の引上げと企業の戦略的対応

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
なぜ今、法定雇用率への対応が「待ったなし」なのか
2025年現在、企業の持続的成長を考える上で「法定雇用率」への対応は、もはや単なるコンプライアンス遵守の枠を超えた、極めて重要な経営戦略となっています。昨年2024年4月には法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられ、それに伴い障害者の雇用義務の対象となる事業主の範囲も常用労働者43.5人以上から40.0人以上へと拡大されました。しかし、これは一連の制度改正の序章に過ぎません。来たる2026年7月には、法定雇用率はさらに2.7%へと引き上げられることが予定されており、対象事業主の範囲も37.5人以上へとさらに拡大します。この段階的な引き上げは、企業の規模を問わず、障害者雇用に対する計画的かつ戦略的な取り組みを社会全体が求めていることの明確な表れです。人事責任者や決裁者の皆様の中には、「まだ時間がある」あるいは「自社には関係が薄い」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、その認識は大きな経営リスクを内包しています。対応が後手に回れば、障害者雇用納付金という直接的な経済的負担の増加だけでなく、行政指導や企業名公表といった社会的信用の失墜に繋がる可能性も否定できません。
本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、法定雇用率制度の正確な知識、自社の達成状況を把握するための計算方法、そして未達成時に企業が直面する具体的なリスクを網羅的に解説します。さらに、これらの課題を乗り越え、障害者雇用をいかにして組織の成長力、すなわちダイバーシティ&インクルージョンの推進や新たな価値創造へと繋げていくか、そのための具体的な打ち手を提示します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
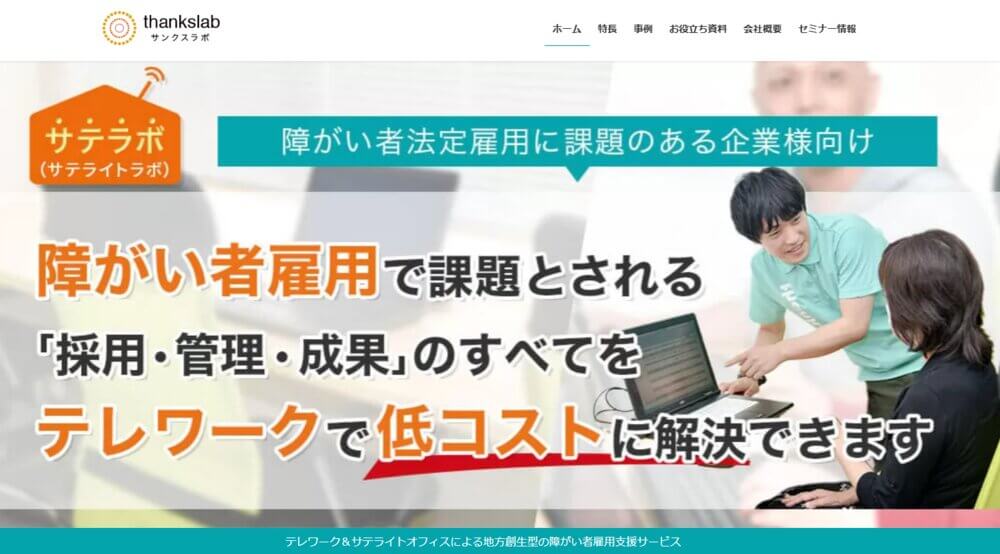
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
法定雇用率とは?制度の目的と対象事業主を正しく理解する
法定雇用率とは、企業や公的機関がその組織規模に応じて雇用すべき障害者の割合を、法律によって定めたものです。この制度の根幹にあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)であり、その目的は、障害のある方々がその能力と適性に応じて職業生活で自立することを促進し、すべての国民が共に支え合う「共生社会」を実現することにあります。障害の有無にかかわらず、誰もが社会の一員として活躍できる機会を確保するための、いわば社会的な基盤と言えるでしょう。この制度は、単に雇用者数を数値目標として課すだけではありません。企業が障害者雇用に関する計画を作成し、適正な雇用管理を行う責務も定めており、組織全体での継続的な取り組みを求めています。法定雇用率の対象となる事業主の範囲は、常用労働者の総数によって決まります。
特に重要なのは「報告義務」と「雇用義務」の違いです。2024年4月の制度改正により、常用労働者を40.0人以上雇用するすべての事業主は、毎年6月1日時点での障害者の雇用状況をハローワークに報告する「報告義務」を負います。そして、その中でも常用労働者を43.5人以上雇用する事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用する「雇用義務」が課せられます。この雇用義務を達成できない場合、後述する納付金制度や行政指導の対象となるのです。なお、この法定雇用率は事業主の種類によって異なり、民間企業だけでなく、国や地方公共団体、教育委員会にもそれぞれ異なる率が設定されています。自社がどの義務の対象となるのか、その範囲を正確に把握することが、適切な対応の第一歩となります。
【2025年最新】法定雇用率の数値と今後の引き上げロードマップ
法定雇用率は、社会情勢や障害者の人口、就労希望者の状況などを踏まえて定期的に見直されます。2025年現在の最新情報と、確定している今後の引き上げスケジュールを正確に把握しておくことは、企業の採用計画や人員計画を策定する上で不可欠です。
2025年現在の法定雇用率
2024年4月1日に施行された改正に基づき、現在の法定雇用率は以下の通り設定されています。
- 民間企業:2.5%
- 国、地方公共団体など:2.8%
- 都道府県などの教育委員会:2.7%
この「2.5%」という数値が、現在、多くの民間企業にとっての基準となります。
【重要】今後の引き上げロードマップ
今回の法改正は、一度きりの変更ではなく、段階的な引き上げが計画されています。これは、企業が計画的に対応を進められるようにするための配慮であると同時に、社会全体として障害者雇用をさらに推進していくという強い意志の表れでもあります。
- 〜2024年3月31日: 2.3% (対象:従業員43.5人以上)
- 2024年4月1日〜: 2.5% (対象:従業員40.0人以上)
- 2026年7月1日〜(予定): 2.7% (対象:従業員37.5人以上)
このロードマップが示す通り、来年2026年7月には、法定雇用率はさらに0.2ポイント引き上げられ、2.7%となります。同時に、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、常用労働者37.5人以上の企業へと拡大されます。これにより、これまで対象外だった比較的小規模な企業も、新たに雇用義務を負うことになるのです。この引き上げが続く背景には、障害のある方の就労意欲の高まりや、多様な人材の活躍を企業の成長力に繋げようとするダイバーシティ&インクルージョンへの意識の世界的な高まりがあります。企業は、この大きな潮流を正しく認識し、目先の対応だけでなく、中長期的な視点での人事戦略を構築していく必要があります。
実雇用率の計算方法|自社の達成状況を正確に把握する3ステップ
法定雇用率を遵守するためには、まず自社の「実雇用率」が現在の基準を満たしているか、そして将来の引き上げに対応可能かを正確に把握する必要があります。実雇用率の計算は一見シンプルに見えますが、その基礎となる「常用労働者」と「雇用障害者」のカウント方法には、実務担当者が押さえるべき重要なルールが数多く存在します。
実雇用率の基本計算式 (実際に雇用している障害者数 ÷ 常用労働者数) × 100
この計算を正しく行うための3つのステップを解説します。
STEP1:常用労働者の正しいカウント方法
まず、分母となる常用労働者数を確定させます。雇用形態にかかわらず、1年を超えて雇用される(または見込まれる)労働者が対象で、週の所定労働時間によってカウントが異なります。
- 週の所定労働時間が30時間以上の労働者:1人としてカウント
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者:0.5人としてカウント
- 週20時間未満の労働者は、原則として常用労働者数には含まれません。
STEP2:雇用障害者の正しいカウント方法
次に、分子となる実際に雇用している障害者の数をカウントします。ここが最も複雑であり、障害の種別や程度、労働時間によってカウント方法が大きく変わります。
- 基本カウント: 身体障害者、知的障害者、精神障害者手帳を持つ労働者をカウントします。
- ダブルカウント制度: 企業の雇用負担に配慮し、重度の身体障害者または重度の知的障害者を雇用した場合、1人の雇用を2人としてカウントできます。
- 短時間労働者のカウント: 週20時間以上30時間未満で働く障害者は0.5人としてカウントされます。また、重度身体・知的障害者がこの時間帯で働く場合、ダブルカウントが適用され1人としてカウントされます。
- 【2024年4月からの改正点】: 特に注目すべきは、精神障害者の雇用促進を目的とした特例です。2024年4月以降、当分の間、週20時間以上30時間未満で働く精神障害者を雇用した場合、1人あたり1人としてカウントできる措置が設けられました。さらに、週10時間以上20時間未満で働く特定の重度身体・知的障害者や精神障害者も0.5人として算定可能になり、雇用の選択肢が広がっています。
STEP3:除外率制度の理解と注意点
一部の業種では、障害者の就業が困難であると認められる場合に、常用労働者数を計算する際に一定の割合を控除できる「除外率制度」が存在します。しかし、この制度はノーマライゼーションの理念にそぐわないとされ、段階的に縮小・廃止される方向で進んでいます。自社が対象業種であっても、将来的に除外率が引き下げられることを見越した計画が必要です。
法定雇用率「未達成」で企業に起こる4つの経営リスク
法定雇用率の未達成は、単に「法律を守れていない」という状態に留まらず、企業の経営に直接的かつ段階的な影響を及ぼす具体的なリスクを伴います。そのプロセスは、経済的な負担から始まり、行政による介入、そして最終的には内外からの信用の失墜へとエスカレーションしていきます。決裁者や人事責任者は、この一連のリスクを正しく理解し、早期対策の重要性を認識する必要があります。
リスク1:【経済的損失】障害者雇用納付金の発生
法定雇用率が未達成の場合に企業が直面する最初のステップが、障害者雇用納付金の納付義務です。
- 対象企業: 常用労働者100人超の事業主
- 納付金額: 不足している障害者1人につき月額50,000円(年間600,000円) この納付金は、罰金やペナルティではなく、障害者雇用に伴う企業間の経済的負担を調整するための「社会的連帯責任」に基づく費用とされています。しかし、企業のキャッシュフローに直接的な影響を与えるコストである事実に変わりはありません。不足人数が多ければ、その負担は数百万、数千万円に及ぶ可能性もあり、経営を圧迫する要因となります。
リスク2:【行政的措置】改善指導と特別指導
納付金を支払っているだけでは、企業の義務が果たされたことにはなりません。法定雇用率が著しく低い企業に対しては、ハローワークによる行政指導が行われます。
- 第1段階「改善指導」: まず、ハローワークから障害者の雇入れに関する計画書の作成が命じられます。企業は2年間の計画を策定し、その計画に沿った採用活動を行う必要があります。
- 第2段階「特別指導」: 改善指導にもかかわらず状況が改善されない企業は、特別指導の対象となります。より具体的で厳しい内容の改善計画が求められ、企業の取り組み状況は厳しく監視されます。この段階は、最終勧告である「企業名公表」の一歩手前の段階であり、企業にとっては極めて重要な局面です。
リスク3:【社会的信用の失墜】企業名の公表とESG評価の低下
度重なる行政指導に従わず、改善の見込みがないと判断された場合、最終措置として「企業名が公表」されます。これは、単に社名が厚生労働省のウェブサイトに掲載されるというだけではありません。ニュースやメディアで報道されることも多く、企業のブランドイメージに深刻なダメージを与えます。一度失墜した社会的信用を回復するのは容易ではなく、顧客離れや取引関係の悪化、そして採用活動における致命的な悪影響に繋がりかねません。さらに、こうした事実はESG(環境・社会・ガバナンス)評価の「S(社会)」項目における明確なマイナス要因となり、投資家からの敬遠を招くなど、事業活動の根幹を揺るがす事態に発展します。
リスク4:【組織内部への悪影響】従業員エンゲージメントの低下
外部からの評価だけでなく、組織内部にも悪影響が及びます。ダイバーシティ&インクルージョンを軽視する企業姿勢は、従業員のエンゲージメントやロイヤリティの低下を招きます。特に若い世代を中心に、企業の社会的責任への関心は高まっており、自社の姿勢に失望した優秀な人材の離職に繋がる可能性も否定できません。
企業の成長に繋げる、法定雇用率達成への具体的な打ち手
法定雇用率の達成を、単なるリスク回避のための義務として捉えるのではなく、企業の成長機会と捉え直すことが重要です。そのためには、場当たり的な採用活動ではなく、戦略に基づいたアプローチが不可欠です。ここでは、企業の成長に繋げるための具体的な打ち手を提案します。
打ち手1:採用戦略の見直しとターゲットの拡大
まず着手すべきは、従来の採用の枠組みを広げることです。
- 能動的な情報収集と発信: 障害者採用に特化した求人媒体やイベントを積極的に活用するだけでなく、自社のウェブサイト等で障害者雇用に関する方針や働く環境を明確に発信し、求職者とのマッチング精度を高めます。
- 新たな採用チャネルの開拓: ハローワークだけでなく、地域の特別支援学校や就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターといった専門機関との連携を強化します。これらの機関は、企業のニーズと求職者の特性を理解した上で、最適な人材を紹介してくれる重要なパートナーとなり得ます。
- 採用要件の再定義: 「障害」という一面で判断するのではなく、個々の能力や経験、意欲に着目し、既存の採用要件を柔軟に見直します。これにより、これまで見過ごされてきた優秀な人材を発掘する機会が生まれます。
打ち手2:受け入れ体制の構築と社内環境の整備
採用の成功は、入社後の定着と活躍があって初めて実現します。そのためには、全社的な受け入れ体制の構築が欠かせません。
- 戦略的な業務の切り出し(ジョブクリエイション): 既存の業務プロセスを分析し、障害のある方がその能力を発揮しやすい業務を戦略的に切り出して、新たなポジションを創出します。これは、既存業務の効率化や標準化にも繋がります。
- インクルーシブな職場環境の整備: 物理的なバリアフリー化はもちろん、PCの読み上げソフトやコミュニケーションツールといった情報保障、定期的な面談や相談窓口の設置といった心理的安全性の確保が重要です。
- 社内理解の促進: 最も重要なのが、共に働く従業員の理解です。管理職や受け入れ部署の従業員を対象に、障害の特性や必要な配慮に関する研修を実施し、全社で障害者雇用を推進する文化を醸成します。
打ち手3:外部専門サービス・制度の戦略的活用
自社だけで採用から定着までのすべてを担うのが難しい場合、外部の専門サービスや国の制度を戦略的に活用することが有効な解決策となります。
- 専門人材紹介・コンサルティング: 障害者採用のノウハウを持つエージェントやコンサルタントは、採用計画の策定から母集団形成、定着支援までをトータルでサポートしてくれます。
- サテライトオフィス型・在宅雇用型サービス: 自社内に受け入れ部署や設備がない場合でも、専門スタッフが常駐するサテライトオフィスや、整備された在宅勤務環境で雇用を実現するサービスです。地方在住の優秀な人材の採用も可能になります。
- 特例子会社制度: 障害者雇用に特化した子会社を設立し、グループ全体で雇用率を合算する制度です。親会社は事業に集中しつつ、特例子会社で専門的な雇用ノウハウを蓄積できます。
最新動向と今後の展望|法定雇用率を巡る未来
法定雇用率を取り巻く環境は、今後も変化し続けます。決裁者や人事責任者は、目先の数字だけでなく、より大きなトレンドを捉えておく必要があります。厚生労働省の最新の調査では、民間企業全体の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、今後各社がより一層主体的な取り組みを求められることは間違いありません。今後の動向として、特に以下の3つのポイントが注目されます。
1. さらなる対象企業の拡大と多様化
2026年7月の2.7%への引き上げ後も、中長期的にはさらなる引き上げや対象企業の拡大が進む可能性があります。また、精神障害者や発達障害者の雇用が今後ますます重要となり、企業にはこれまで以上に多様な障害特性への理解と、個々に合わせた柔軟な働き方の提供が求められるようになります。
2. 雇用の「質」の重視と定着支援の強化
単に人数を充足させるだけでなく、採用した人材が能力を発揮し、長く働き続けられるかという「雇用の質」がより一層問われるようになります。これに伴い、リテンション施策やキャリアアップ支援を目的とした国の助成金制度が拡充されたり、職場への定着をサポートするジョブコーチなどの外部支援サービスが普及したりすることが予想されます。
3. テクノロジー活用と働き方の進化
ICT技術の進化は、障害者雇用のあり方を大きく変える可能性を秘めています。在宅勤務やテレワークの普及はもちろん、コミュニケーションを円滑にするアシストツールや、定型業務を自動化するRPAなどのテクノロジーを活用することで、障害のある方が活躍できる職域は飛躍的に拡大するでしょう。こうした技術への投資が、企業の競争力に直結する時代が訪れます。これらのトレンドを先読みし、戦略的に布石を打つことが、変化の激しい時代において企業の持続可能性を高める鍵となります。
まとめ:法定雇用率の達成は、企業の持続的成長に不可欠な経営課題
本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、法定雇用率の制度概要と今後の引き上げスケジュール、未達成時の具体的なリスク、そして企業が取るべき対応策について解説してきました。2024年、そして2026年と続く段階的な法定雇用率の引き上げは、すべての企業にとって障害者雇用が避けては通れない重要な経営課題であることを示しています。法定雇用率の未達成は、納付金という直接的なコストだけでなく、行政指導や企業名公表という、企業の社会的信用を根底から揺るがすリスクをはらんでいます。しかし、この課題を単なるコンプライアンス遵守やリスク回避の観点からのみ捉えるべきではありません。むしろ、これを好機と捉え、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる組織へと変革していくことが、企業の持続的な成長を実現する鍵となります。障害者雇用への真摯な取り組みは、ダイバーシティ&インクルージョンを推進し、新たな視点によるイノベーションを創出します。そして、その姿勢はESG評価の向上にも繋がり、顧客、取引先、投資家、そして未来の従業員からの信頼を獲得する源泉となるのです。法定雇用率の達成は、もはやコストではなく、企業の未来を創造するための「戦略的投資」に他なりません。今こそ、自社の現状を正確に把握し、企業の成長戦略として障害者雇用を位置づけ、具体的な一歩を踏み出すべき時です。