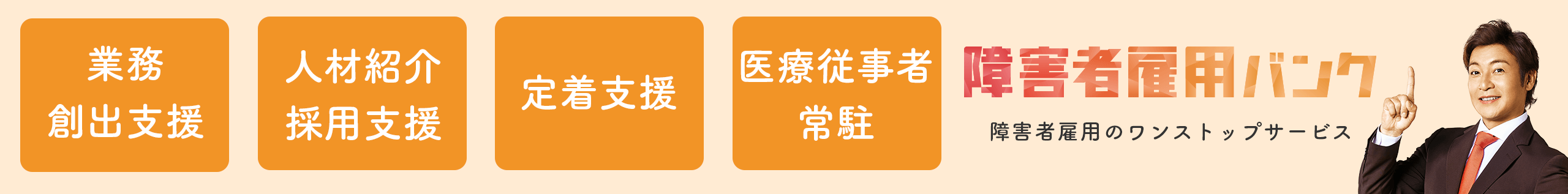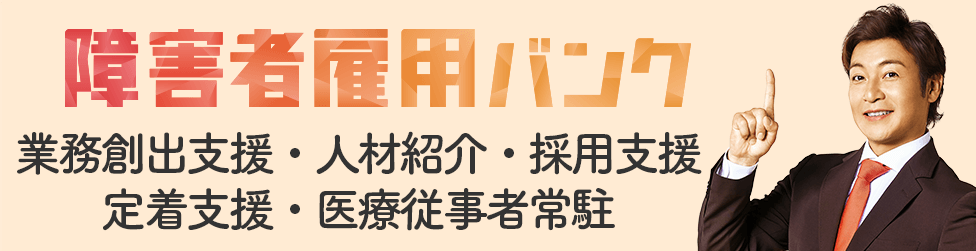【採用担当者向け】障害者トライアル雇用で失敗しないための全知識|助成金・申請方法から定着の秘訣まで

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに
「障害者雇用を進めたいが、採用後のミスマッチが何より不安だ」「候補者の能力や職場への適性を、面接だけで見極めるのは難しい」。これは、障害者採用に真摯に取り組む多くの人事責任者や経営者が抱える、共通の悩みではないでしょうか。法定雇用率が引き上げられ、企業の社会的責任がより一層問われる中、採用のミスマッチは、本人と企業の双方にとって大きな損失となりかねません。 この根深い課題に対する有効な解決策の一つが、国が設けている「障害者トライアル雇用制度」です。この制度は、一定期間、実際に共に働きながら相互理解を深めることで、採用における不安を解消し、長期的な定着を目的としています。しかし、制度の存在は知っていても、「手続きが煩雑そう」「どう活用すれば成功するのか分からない」といった理由から、活用に踏み切れていない企業が多いのも事実です。
本記事では、障害者トライアル雇用の活用を検討されている決裁者・人事責任者の皆様へ向けて、制度の基本から助成金の詳細、具体的な申請フロー、そして最も重要な「トライアルを成功させ、本採用と定着に繋げるための秘訣」まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。単なる制度利用に終わらせない、戦略的な障害者雇用の実現に向けた知識を、ぜひこの記事から得てください。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
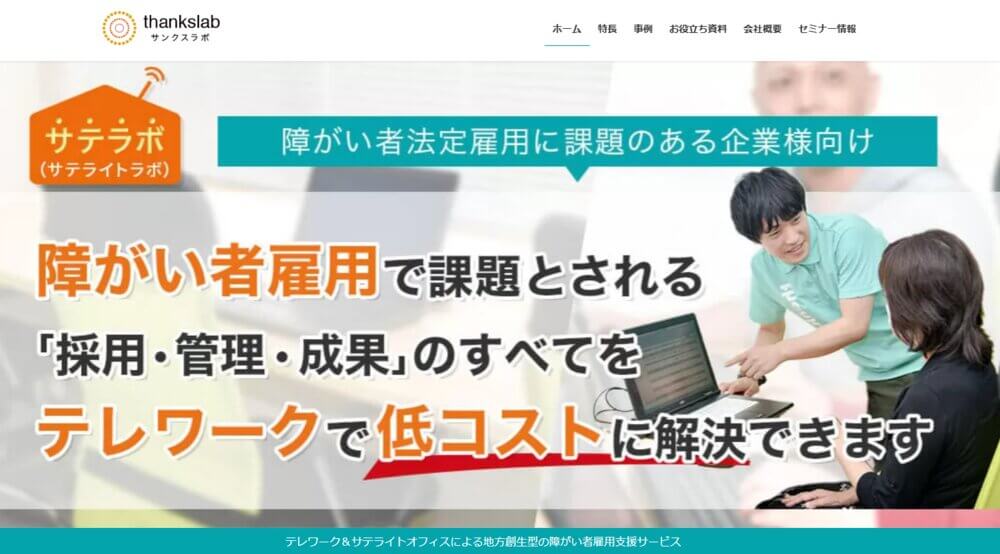
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
1. 障害者トライアル雇用とは?採用ミスマッチを防ぐ制度の基本
障害者トライアル雇用は、障害者雇用の入り口で多くの企業が直面する「相互理解の不足」という壁を取り払うために設計された公的な制度です。面接だけでは伝わりきらない求職者の実際の業務遂行能力やコミュニケーションの特性、そして企業側が提供できる業務環境やサポート体制が本当にマッチするのか。これらを、本格的な雇用の前に、いわば「お試し期間」を設けて確認し合うことができます。ここで重要なのは、この制度が企業独自の規定で行う一般的な試用期間とは異なり、国が定めた条件と助成制度に基づく公的支援制度であるという点です。 この制度の根幹にある目的は、採用におけるミスマッチを限りなくゼロに近づけ、入社後の早期離職を防ぎ、障害のある社員がその能力を最大限に発揮しながら長く活躍できる職場環境を実現することにあります。企業にとってはリスクを抑えた採用活動を、求職者にとっては安心して働き始められる機会を提供する、双方にメリットのある仕組みなのです。 この制度を利用するためには、企業側と求職者側の双方に一定の条件が定められています。まず企業側の対象者ですが、必ずしも障害者雇用の経験が全くない企業に限定されているわけではありません。例えば、これまで身体障害者の採用経験はあるが、精神障害者の採用は初めて、といったケースでも対象となり得ます。障害種別ごとの特性や必要な配慮は異なるため、新たな種類の障害を持つ方の雇用を検討する際に活用できるのです。ハローワークが個別に判断するため、「うちは対象外だろう」と決めつけず、まずは相談してみることが重要です。 一方、求職者側の対象となるのは、ハローワークや民間の職業紹介事業者などに求職申込を行っている方で、障害者トライアル雇用を希望し、かつ以下のいずれかに該当する方です。
- 就労経験のない職業に就くことを希望している方
- 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
- 離職している期間が6ヶ月を超えている方
- 重度の身体障害、知的障害、精神障害のある方など これらの条件は、就労に対して何らかのブランクや不安を抱えている方が、スムーズに職場復帰や社会参加を果たせるよう支援することを意図しています。
2. 助成金を最大限に活用する2つのコースと申請の注意点
障害者トライアル雇用制度の大きな魅力が、トライアル期間中の企業の金銭的負担を軽減する助成金の存在です。この助成金制度は、企業の積極的な制度活用を後押しする重要なインセンティブとなっています。制度には主に2つのコースがあり、それぞれの内容と申請時の注意点を正確に理解することが、制度を最大限に活用する鍵となります。
障害者トライアルコース
一つ目は、基本となる「障害者トライアルコース」です。
- 期間: 原則として3ヶ月間。この期間で、業務の習熟度や職場への適応など、基本的な適性を見極めます。
- 助成金額: 対象者1人あたり月額最大4万円(3ヶ月合計で最大12万円)が支給されます。
- 精神障害者の特例: 対象者が精神障害者の場合、助成が手厚くなります。最初の3ヶ月間は月額最大8万円、さらに常用雇用へ移行した場合、その後の3ヶ月間も月額最大4万円の助成(精神障害者雇用安定奨励金)を受けられる可能性があり、支援が長期化します。
障害者短時間トライアルコース
二つ目のコースは、「障害者短時間トライアルコース」です。
- 対象: 週20時間以上の勤務が難しい精神障害者や発達障害のある方などが主な対象です。週10時間以上20時間未満から働き始め、段階的に職場に慣れていくことを目的とします。
- 期間: 3ヶ月から最長12ヶ月と、より柔軟に設定可能です。
- 助成金額: 対象者1人あたり月額最大4万円が支給されます。
- 活用のポイント: このコースの最大の利点は、法定雇用率の算定特例により、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者等を「0.5人」としてカウントできる点です。法定雇用率達成に向けた新たな一手となり得ます。
【重要】助成金申請における注意点
助成金を確実に受給するためには、以下の要件と注意点を必ず守る必要があります。
- ハローワーク経由の紹介: 助成金の対象となるのは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等を通じて紹介を受け、採用した場合に限られます。
- 申請期限の厳守: 支給申請は、トライアル期間終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。この期限を1日でも過ぎると、原則として受給資格を失います。
- 支給対象外となるケース:
- 過去にトライアル雇用されたことがある事業所で、再度同じ対象者を雇用した場合
- 助成金申請日時点で対象者が離職している場合
- 解雇予告や退職勧奨を行っている場合
- 労働保険料を滞納している場合 これらは代表的な例であり、事前に管轄のハローワークや労働局に最新の要件を確認し、社内の事務処理体制やスケジュール管理を徹底することが極めて重要です。
3. 障害者トライアル雇用制度のメリット
障害者トライアル雇用制度の導入を検討するにあたり、決裁者や人事責任者として、そのメリットとデメリットを客観的に評価することが不可欠です。この制度は多くの利点をもたらす一方で、運用にあたって注意すべき点も存在します。双方を天秤にかけ、自社の状況に照らし合わせて判断することが、戦略的な活用の第一歩となります。
採用ミスマッチの大幅な低減:
履歴書や面接だけでは把握しきれない、候補者の実際の業務スキル、集中力、コミュニケーションの取り方などを、実務を通じて多角的に見極めることができます。双方が納得した上で本採用へと進めるため、入社後の定着率向上に大きく寄与します。
採用・教育コストの軽減:
トライアル期間中の人件費の一部が助成金で補填されるため、企業は採用リスクと経済的負担を抑えながら、新たな人材を受け入れることが可能になります。
社内の受け入れ体制の構築と改善
障害のある社員を受け入れるにあたり、どのような業務を任せるか、誰が指導役を担うか、どのような配慮が必要か、といった点を、トライアル期間を通じて実践的に学び、改善していくことができます。これは、将来的な障害者雇用の拡大に向けた貴重なノウハウの蓄積に繋がります。
障害理解の促進
実際に障害のある社員と共に働くことで、現場の従業員の障害に対する理解が深まり、組織全体のダイバーシティ意識を向上させるきっかけとなります。
4. 障害者トライアル雇用制度のデメリット
一方で、現実的なデメリット(課題)も理解しておく必要があります。
管理工数の増加
ハローワークへの求人提出から実施計画書の作成、期間中の勤怠管理・指導記録、期間終了後の支給申請まで、定められた手順を踏む必要があり、担当者の事務的な負担はゼロではありません。
期間中の教育コストの発生
トライアル期間中であっても、指導役となる社員の時間や労力といった教育コストは発生します。このコストを事前に想定し、現場の協力を得ておくことが重要です。
「お試し雇用」という誤認リスク
制度の趣旨を誤解し、「安価な労働力」「気に入らなければ簡単に辞めさせられる」といった認識でいると、適切な指導や配慮を怠り、トラブルや早期離職の原因となります。あくまで常用雇用が前提の制度です。
本採用に至らない可能性
双方の努力にもかかわらず、適性や条件が合わないと判断される可能性はあります。 これらのデメリットを事前に把握し、対策を講じることで、制度の効果を最大限に引き出すことができます。
5. 申請から本採用までの具体的な流れと各ステップの注意点
障害者トライアル雇用制度を活用するプロセスは、定められたステップに沿って進めることで、スムーズに実施することが可能です。ここでは、採用担当者が具体的に何をすべきか、ハローワークへの求人提出から本採用への移行判断までを、各ステップの注意点と合わせて解説します。
ステップ1:ハローワークへトライアル雇用の求人を提出 企業の所在地を管轄するハローワークの障害者担当窓口に相談し、「トライアル雇用求人」を提出します。
- 注意点: どのような業務を任せるのか、求める人物像、提供できる配慮などを具体的に記載することが、後のマッチング精度を高めます。
ステップ2:ハローワーク等が求職者を紹介 提出された求人票に基づき、ハローワーク等が条件に合致する求職者を紹介します。
ステップ3:面接・選考 紹介を受けた求職者と面接を行います。
- 注意点: この制度では、原則として応募者全員との面接が必要とされています。書類選考のみで不採用とすることは、制度の趣旨に反すると見なされる可能性があるため、必ず面接の機会を設けてください。面接では、制度の趣旨を説明し、双方の認識をすり合わせることが重要です。
ステップ4:実施計画書の作成・提出 採用者が決定したら、企業はその対象者と合意の上で「障害者トライアル雇用実施計画書」を作成し、ハローワークに提出します。この計画書が受理されることで、正式にトライアル雇用を開始できます。
ステップ5:トライアル雇用の開始 実施計画書に基づき、トライアル雇用を開始します。
- 注意点: この期間中の業務内容や指導記録、勤務実績は、後の助成金申請や本採用判断の重要な根拠となります。日々の記録を正確に残す体制を整えてください。
ステップ6:支給申請(期間終了後) トライアル期間が終了した後、終了日の翌日から2ヶ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局へ助成金の支給申請書を提出します。申請には、出勤簿や賃金台帳などの添付書類が必要です。
ステップ7:本採用への移行判断 トライアル期間中の勤務状況や本人の意欲、適性などを総合的に評価し、企業と本人の双方が合意すれば、常用雇用(本採用)へと移行します。
- 注意点: 本採用を見送る場合でも、その判断は感覚的・主観的なものではなく、期間中の業務記録や評価内容といった事実に基づいて、本人に丁寧に説明する責任があります。
6. 失敗しないための事前準備:目的設定と受け入れ体制の構築
障害者トライアル雇用を単なる「お試し」で終わらせず、本採用と長期的な定着という真の成功に結びつけるためには、雇用を開始する前の「事前準備」が決定的に重要です。多くの失敗例は、この準備段階の不足に起因しています。ここでは、トライアル雇用を成功させるために不可欠な、目的設定と受け入れ体制の構築について解説します。
目的の明確化と全社的な共有
第一に、最も重要なのが「目的の明確化と全社的な共有」です。なぜ今、自社はトライアル雇用を行うのか。それは、法定雇用率の達成のためか、特定部署の人手不足解消のためか、あるいは将来のダイバーシティ推進に向けた第一歩なのか。この目的を経営層と人事部、そして何より実際に障害のある社員を受け入れる現場部署の間で、明確に共有し、合意形成を図る必要があります。目的が曖昧なままでは、現場の協力が得られず、「人事が勝手に進めている」という当事者意識の欠如を招きかねません。目的が共有されていれば、トライアル期間中に困難な事態が生じても、関係者が一丸となって解決にあたることができます。この目的設定は、採用する人物像を具体化し、選考の軸を定める上でも役立ちます。
受け入れ体制の構築
第二に、具体的な「受け入れ体制の構築」が求められます。これには二つの側面があります。
業務の切り出し
採用が決まってから「さて、何をしてもらおうか」と考えるのでは遅すぎます。事前に、任せる業務内容を具体的に洗い出し、可能であればマニュアル化しておくことが望ましいです。その業務は、本人のスキルや特性に合っているか、企業の戦力として貢献できる内容か、という両面から検討する必要があります。例えば、書類のファイリング、データ入力、備品管理などの補助業務を整理することで、スムーズな戦力化が可能です。
指導・サポート体制の明確化
誰が主な指導役(メンター)となるのか、業務上の質問は誰にすれば良いのか、体調面など業務以外の相談は誰が受けるのか、といった役割分担を事前に決めておくことが、本人が安心して働き始めるための基盤となります。特に、メンターとなる社員には、トライアル雇用の目的を十分に説明し、業務負担が過重にならないよう配慮することが、円滑な受け入れ体制の鍵となります。 これらの準備を丁寧に行うことが、トライアル期間を実りあるものにし、その後の安定した雇用への道を拓くのです。
6. 成功の鍵を握る実践ポイント:評価・対話・外部連携
入念な事前準備を経てトライアル雇用を開始した後は、期間中の具体的なアクション、すなわち「実践」の質が成功を左右します。ここでは、トライアル期間を最大限に有効活用し、確かな成果に繋げるための3つの実践的なポイント、「評価」「対話」「連携」について深掘りします。
客観的な評価基準の設定と適切なフィードバック
第一のポイントは、「客観的な評価基準の設定と適切なフィードバック」です。トライアル期間は、情緒的な印象ではなく、客観的な事実に基づいて本採用の可否を判断するための重要な期間です。
- 評価基準の事前共有: どのような基準で評価するのかを事前に設定し、それを本人と共有しておくことが不可欠です。例えば、「業務の正確性」「期限の遵守」「報告・連絡・相談の適切さ」といった具体的な評価項目と、それぞれの達成レベルを明確にします。
- 定期的な面談の実施: 評価は期間終了時に一度だけ行うのではなく、週に一度、あるいは月に一度といった頻度で定期的な面談の場を設け、フィードバックを行うことが重要です。この面談では、できた点を具体的に褒め、改善が必要な点については、どうすれば改善できるかを一緒に考える姿勢が求められます。
- 記録に基づく判断: 本採用の可否を判断する際は、これらの評価記録に基づいて客観的に行います。これにより、判断の透明性が担保され、本人への説明責任を果たすことができます。
障害特性への理解とオープンな対話
第二のポイントは、「障害特性への理解とオープンな対話」です。企業には、障害のある社員が能力を発揮できるよう、その特性に応じて環境を調整する「合理的配慮」を提供する義務があります。トライアル期間は、どのような配慮が必要なのかを具体的に見つけるための絶好の機会です。重要なのは、企業側が一方的に配慮内容を決めるのではなく、本人との対話を通じて、何に困っていて、どうすれば働きやすくなるのかをオープンに話し合うことです。本人から言い出しにくい場合もあるため、企業側から「何か困っていることはありませんか」「働きやすくするために会社としてできることはありますか」と積極的に問いかける姿勢が、信頼関係を築き、本人が安心して能力を発揮できる環境作りに繋がります。
外部の支援機関との積極的な連携
第三のポイントは、「外部の支援機関との積極的な連携」です。障害者雇用に関する課題を、企業内だけで抱え込む必要はありません。ハローワークはもちろんのこと、就労移行支援事業所や地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターといった地域の支援機関は、障害者雇用の専門的なノウハウを持つプロフェッショナル集団です。これらの機関と連携することで、企業と本人の間に第三者の専門家が入り、客観的な視点からアドバイスや調整を行ってくれます。例えば、本人には直接言いにくい要望を支援員が代弁してくれたり、企業が気づかなかった配慮のポイントを教えてくれたりします。こうした外部リソースを積極的に活用することが、課題の早期解決を促し、トライアル雇用を成功へと導く強力な後押しとなります。
まとめ
本記事では、障害者トライアル雇用制度の基本から、助成金、申請フロー、そして制度を最大限に活用し、本採用と定着という真の成功を掴むための具体的なポイントまでを包括的に解説しました。障害者雇用における「ミスマッチの不安」は、このトライアル雇用制度を戦略的に活用することで、大きく軽減することが可能です。 この制度は、単なる「お試し期間」や「助成金目当ての制度」ではありません。明確な目的意識を持ち、入念な事前準備を行い、期間中は評価・対話・連携を丁寧に行うことで、企業の障害者雇用を一歩も二歩も前進させるための、極めて有効な経営ツールとなり得ます。採用リスクを抑えながら社内にノウハウを蓄積し、求職者との強固な信頼関係を築くことができるのです。 障害者採用への一歩を踏み出せずにいる、あるいは過去の失敗経験から慎重になっている人事責任者・決裁者の皆様こそ、この制度の活用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。ミスマッチを恐れるのではなく、ミスマッチを防ぐための仕組みを賢く利用すること。その決断が、貴社のダイバーシティ推進と持続的な成長への確かな道筋を拓くはずです。