更新日:2025/07/02
請求書の支払い期限はいつまで?決め方の基本ルールと遅延・未払い時の対応法

【監修】株式会社ジオコード 経理財務課課長
藤田 貴英
経理一筋20年、中小企業から大企業までさまざまな規模の経理業務に従事。
株式会社ジオコードに入社後、経理財務課課長に就任し、IPO準備の中心メンバーとして上場に導く。
企業間取引において、請求書は商品やサービスの対価を請求するための重要な書類です。その中でも「支払い期限」は、自社のキャッシュフローを安定させ、取引先との良好な関係を維持するための生命線とも言えます。しかし、「支払い期限はいつに設定すればいいのか」「法律でルールは決まっているのか」「もし期限を過ぎてしまったらどう対応すべきか」など、実務上の疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。
この記事では、請求書の支払い期限に関する基本的な決め方から、トラブルを未然に防ぐための注意点、万が一の遅延・未払いが発生した際の具体的な対応方法まで、網羅的に解説します。
【比較表】請求書カード払いのおすすめサービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 手数料 | 対応しているクレジットカード |
|---|---|---|---|
DGFT請求書カード払い
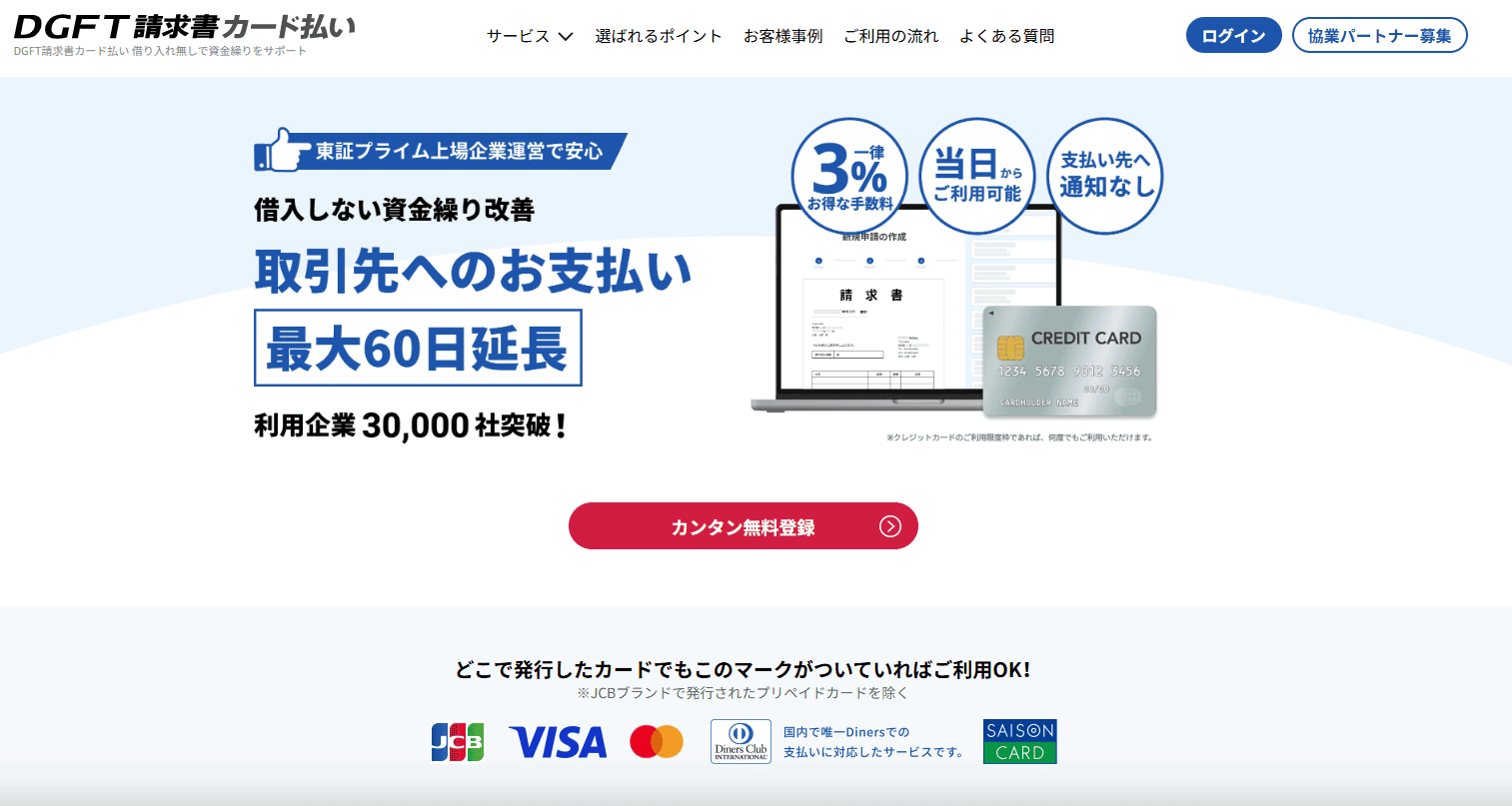
|
|
3% | JCB, VISA, Master, Diners Club,SAISON CARD |
Fintoカード払い

|
|
2.5% ※キャンペーン実施中※ 初回手数料2.0%、以降2.2% 期間:2025年11月1日〜2026年3月31日まで |
Visa、Mastercard、JCB、セゾンブランドのカード |
INVOYカード払い

|
|
3% | VISA、Mastercard、JCB |
LP請求書カード払い
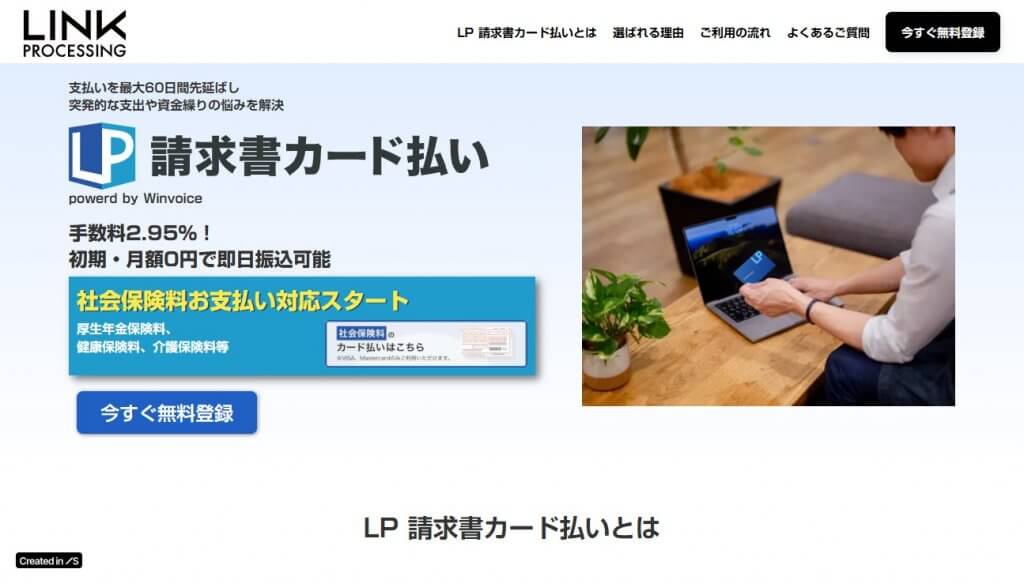
|
|
2.95% | Visa、Mastercard、JCB |
支払い.com

|
|
4% | SAISON CARD、VISA、Mastercard |
ラボル カード払い

|
|
3~3.5% | VISA、Mastercard、JCB |
フリーウェイ請求書カード払い

|
|
2.7% | VISA,Mastercard,JCB,デビットカード |
ゆとりペイ

|
|
2.9% | Visa、Mastercard、JCB |
| Money Foward請求書カード払い for Startups |
|
2.4%~ | VISA、Mastercard、JCB |
| 請求書カード払い JCB×Digital Garage |
|
2.98% | JCBグループのカード発行会社が提供するカードが対象 |
| Biz Forward請求書カード払い |
|
2.8% | 国内で発行されたVisa/Mastercard/JCBブランドのクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード |
| 請求書カード払い by GMO |
|
3% | Visa / MasterCard |
| NP掛け払い 請求書カード払い |
|
3% | VISA、Mastercard、JCB |
| 請求書支払い代行サービス |
|
3% | 国内で発行されたVisa/Mastercard |
この記事の目次はこちら
請求書の支払い期限、基本的な決め方とは?
請求書における支払い期限の設定は、円滑な取引を行う上で非常に重要なプロセスです。この期限が曖昧であったり、一方的であったりすると、取引先との間で認識の齟齬が生まれ、入金遅延や関係悪化といったトラブルの原因になりかねません。支払い期限には法律で定められた絶対的なルールがあるわけではありませんが、多くの企業が従っている商慣習や、特定の取引に適用される法律が存在します。自社の資金繰りを守りつつ、取引先にも配慮した適切な期限を設定するためには、その基本的な考え方を理解しておくことが不可欠です。ここでは、支払い期限を決定する上での原則、広く用いられている「支払いサイト」という考え方、そして法律との関係性について詳しく見ていきます。
一般的な支払い期限は「取引先との合意」で決定する
請求書の支払い期限は、法律で一律に定められているわけではなく、原則として取引を行う当事者間の合意によって自由に決定されます。これを契約自由の原則と呼びます。そのため、新規で取引を開始する際には、契約書を交わす段階や発注を受ける時点で、支払い条件について明確に確認し、双方で合意形成しておくことが最も重要です。既存の取引先であれば、これまでの取引で形成された慣習に従うのが一般的ですが、認識にズレが生じないよう、定期的に支払い条件を見直すことも有効です。口頭での合意は後に「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、必ず契約書や発注書、あるいはメールなどの書面に残し、証拠として保管しておくことが、自社を守る上で賢明な方法と言えるでしょう。
「支払いサイト」を基準にした支払い期限の設定方法
企業間取引では、「支払いサイト」という考え方を用いて支払い期限を設定するのが一般的です。「支払いサイト」とは、取引の締め日から実際の支払日までの期間を指します。例えば、「月末締め翌月末払い」の場合、支払いサイトは30日(または31日)となります。同様に「月末締め翌々月末払い」であれば、支払いサイトは60日です。この支払いサイトは、業界の慣習によってある程度の基準があり、例えば建設業では長く、IT業界では比較的短い傾向にあります。自社のキャッシュフローを考慮しつつ、取引先の支払いサイクルや業界の標準的なサイトを参考に、無理のない支払い期限を設定することが、継続的で良好な取引関係を築くための鍵となります。
請求書の支払い期限と法律(下請法)の関係
すべての取引に支払い期限を強制する法律はありませんが、資本金で優位にある親事業者が下請事業者に業務を委託する特定の取引においては、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が適用されます。この下請法では、親事業者は下請事業者から給付(商品やサービス)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払い期限を定めなければならないと義務付けられています。このルールに違反した場合、公正取引委員会から勧告や指導を受ける可能性があり、企業の信用問題にも関わります。自社が親事業者、あるいは下請事業者のどちらかに該当する可能性がある場合は、この法律を遵守した支払い期限の設定が必須となるため、注意が必要です。
請求書の支払い期限に関するよくある疑問
請求書の支払い期限については、基本的な決め方以外にも、実務上で判断に迷う場面がいくつか存在します。例えば、受け取った請求書に肝心の支払い期限が記載されていなかった場合や、定められた期限が金融機関の休業日である土日・祝日に重なってしまった場合などです。また、万が一支払いが遅れた際に請求される可能性がある「遅延損害金」についても、そのルールを正しく理解しておく必要があります。こうしたイレギュラーなケースへの対処法を事前に知っておくことは、予期せぬトラブルを回避し、経理業務をスムーズに進める上で非常に重要です。ここでは、そうした実務上よく発生する疑問について、一つひとつ分かりやすく解説していきます。
支払い期限の記載がない請求書を受け取った場合の対処法
もし取引先から受け取った請求書に支払い期限が明記されていなかった場合、勝手な判断で処理を進めるのは避けるべきです。自社の支払いサイクルに基づいて支払ったり、支払いを保留したりすると、後々のトラブルに発展しかねません。最も確実な対応は、速やかに請求書の発行元である取引先の担当者に連絡を取り、正式な支払い期限を確認することです。その際、口頭での確認だけでなく、メールなどの記録に残る形でやり取りをしておくと、より安全です。また、可能であれば、正しい支払い期限を記載した請求書を再発行してもらうよう依頼しましょう。支払い期限の記載は発行側の義務でもあるため、丁寧な姿勢で確認を求めることが重要です。
請求書の支払い期限が土日・祝日の場合はどうする?
支払い期限が土日や祝日など、金融機関の休業日にあたってしまうケースは頻繁に起こり得ます。この場合の扱いについては、民法第142条により、その休日の翌営業日が正式な期限日として扱われるのが原則です。しかし、企業間の取引においては、トラブルを未然に防ぐために事前にルールを取り決めておくのが一般的です。具体的には、「期限日が休日の場合は、その直前の営業日に支払う(前倒し)」または「その直後の営業日に支払う(後ろ倒し)」のどちらかで運用されます。どちらのルールを採用するかは企業によって異なるため、請求書を発行する側は、あらかじめ注釈としてその旨を記載しておくと、取引先との認識のズレを防ぐことができ、より親切な対応となります。
| 期限日が休日の場合の対応 | メリット | デメリット |
| 前営業日に支払う | 発行側は早く入金される。 | 受領側は資金繰りがタイトになる場合がある。 |
| 翌営業日に支払う | 受領側は資金繰りに余裕が持てる。 | 発行側は入金が遅れる。 |
請求書の支払い期限を過ぎた場合の遅延損害金について
支払い期限を過ぎても入金がない場合、発行側は受領側に対して「遅延損害金」を請求する権利があります。これは、支払い遅延によって生じた損害を賠償してもらうためのお金です。ただし、遅延損害金を請求するためには、原則として事前に契約書や利用規約でその利率について双方の合意があることが必要です。もし利率の定めがない場合は、法定利率が適用されます。事業者の取引(商行為)であれば商法の年6%、それ以外は民法の年3%(変動制)が基本となります。しかし、取引関係の維持を考慮し、いきなり遅延損害金を請求するのではなく、まずは支払いの督促を行うのが一般的です。請求するか否かは、相手との関係性や遅延の状況を鑑みて慎重に判断すべきでしょう。
【発行側】請求書の支払い期限を過ぎても入金がない時の対応
取引先からの入金が支払い期限を過ぎても確認できない事態は、企業のキャッシュフローに直接的な影響を与えるため、迅速かつ適切な対応が求められます。しかし、焦りから感情的な対応をしてしまうと、かえって取引先との関係をこじらせてしまう可能性もあります。入金遅延の背景には、相手の単純な事務処理ミスや見落としといったケースも少なくありません。そのため、まずは冷静に事実確認から始め、段階を踏んで丁寧に対応を進めることが重要です。ここでは、自社が請求書の発行側として、入金が遅れている場合に取るべき具体的なアクションを3つのステップに分けて解説し、スムーズな入金を促すための手順を示します。
ステップ1:まずは自社の請求・入金状況を正確に再確認する
取引先に連絡を入れる前に、必ず実行すべきなのが自社の状況の再確認です。相手のミスを疑う前に、まず自分たちの側に不備がなかったかを徹底的にチェックします。具体的には、①請求書が間違いなく発行され、正しい宛先に送付されているか、②指定した入金口座の取引明細に、既に該当の入金がないか、③請求書に記載した金額やサービス内容、支払い期限そのものに誤りがないか、といった点を確認します。万が一、こちら側に請求漏れや記載ミスがあったにもかかわらず、相手を責めるような連絡をしてしまえば、自社の信用を大きく損なうことになります。この最初の確認作業が、その後の円滑なコミュニケーションの土台となるのです。
ステップ2:取引先へ支払い期限が過ぎたことを丁寧に連絡する
自社の状況に問題がないことを確認できたら、次のステップとして取引先に連絡を入れます。この最初のコンタクトでは、相手を責めるような高圧的な態度は厳禁です。あくまで「入金の確認が取れていないのですが、状況はいかがでしょうか」といった形で、丁寧な言葉遣いで問い合わせるのがビジネスマナーです。連絡手段は電話かメールが一般的ですが、相手が多忙な可能性も考慮し、まずはメールで連絡し、一定期間返信がなければ電話をかけるという手順も有効です。相手の単純な失念や事務処理上の手違いである可能性も十分に考えられるため、良好な取引関係を維持するためにも、常に低姿勢で確認する姿勢を忘れないようにしましょう。
ステップ3:督促状を発行・送付する
丁寧な連絡を重ねても入金がなく、誠意ある対応が見られない悪質なケースにおいては、最終手段として「督促状」の発行・送付を検討します。督促状は、単なる確認の連絡とは異なり、未払いである事実と支払い期限を改めて明記し、強く支払いを求めるための正式な書面です。書式に法的な決まりはありませんが、請求内容と支払いのお願いを明確に記載します。送付方法としては、通常の郵便でも可能ですが、送付した事実と相手が受け取った事実を記録として残せる「内容証明郵便」を利用するのが最も効果的です。内容証明郵便は、法的な手続きを視野に入れているという強い意思表示にもなるため、取引関係への影響も考慮し、弁護士などの専門家に相談の上で慎重に行うべき対応です。
【受領側】請求書の支払い期限に間に合わない時の対応
企業の資金繰りの状況によっては、取引先から受け取った請求書の支払い期限までに、どうしても支払いが間に合わないという事態も起こり得ます。このような状況で最も避けるべきは、何も連絡せずに支払い期限を過ぎてしまうことです。無断での支払い遅延は、取引先からの信用を著しく損ない、最悪の場合、取引停止につながる可能性もあります。重要なのは、支払い遅延が避けられないと判明した時点で、誠実かつ迅速に対応することです。早期の連絡と正直な状況説明こそが、取引先との信頼関係を維持し、大きなトラブルへの発展を防ぐための鍵となります。ここでは、支払いが遅れそうな場合に取るべき具体的な行動を解説します。
支払い期限に遅れると分かったら、すぐに担当者へ連絡する
請求書の支払い期限に間に合わない可能性が浮上した時点で、一刻も早く取引先の担当者に連絡を入れるのが鉄則です。この連絡は、期限を過ぎてから行うのではなく、必ず支払い期限前に行うのが最低限のビジネスマナーです。まずは電話で直接お詫びをし、支払いが遅れる見込みであることを伝えるのが最も誠意が伝わります。その上で、なぜ支払いが遅れてしまうのか、その理由を正直に説明しましょう。資金繰りの問題など、伝えにくい内容かもしれませんが、誠実な態度は相手の理解を得る上で不可欠です。無断で期限を破る行為は、いかなる理由があっても取引先からの信頼を失うことに直結すると肝に銘じておくべきです。
支払い可能な日付を具体的に伝える
支払い遅延の連絡をする際、単に「支払いが遅れます、申し訳ありません」と謝罪するだけでは、取引先をさらに不安にさせてしまいます。謝罪とともに必ず伝えなければならないのが、「いつまでに支払えるのか」という具体的な日付です。曖昧な返答は避け、確実に入金できる日付を明確に提示することが重要です。もし、その時点ですぐに確定日を伝えられない場合でも、「来週の水曜日までには確定し、改めてご連絡いたします」というように、次のアクションプランを示すことで、誠実な姿勢を見せることができます。もちろん、ここで提示した日付は必ず守らなければなりません。安易な約束はさらなる信用失墜を招くため、責任を持って守れる日付を伝えましょう。
請求書の支払い期限、正しい書き方と記載例
これまで支払い期限のルールやトラブル発生時の対応方法について解説してきましたが、こうした問題を未然に防ぐための最も基本的な対策は、請求書に支払い期限を正しく、そして明確に記載することです。支払い期限の記載がなければ、請求書を受け取った側はいつまでに支払うべきか分からず、意図せずして入金遅延につながってしまう可能性があります。また、書き方が曖昧であったり、分かりにくい場所に記載されていたりすると、取引先との間で認識の齟齬が生まれ、確認のための余計な手間やトラブルの原因となります。ここでは、誰が見ても誤解のしようがない、分かりやすい支払い期限の書き方と、実際の請求書フォーマット上での具体的な記載例について詳しく解説します。
請求書フォーマットにおける支払い期限の記載箇所
請求書の支払い期限は、請求書を受け取った相手が一目で認識できる、分かりやすい場所に記載することが大切です。一般的な請求書フォーマットでは、「請求書番号」や「発行日」の近く、あるいは「請求金額」が記載されている周辺など、書類の上部や合計金額の欄の近くに配置されることが多く、これらの場所が適切とされています。記載する際は、「支払期限」「お支払期限」「支払期日」といった項目名を明確に立て、その横に「YYYY年MM月DD日」のように西暦から年月日を省略せずに記述します。「月末」「翌月末締め」といった曖昧な表現のみで済ませるのではなく、具体的な日付を必ず明記しましょう。これにより、取引先との認識のズレをなくし、期日通りのスムーズな入金を促すことができます。
まとめ:請求書の支払い期限はトラブルを防ぐ重要な項目
この記事では、請求書の支払い期限に関する決め方の基本から、トラブル時の対応法までを網羅的に解説しました。支払い期限は、原則として取引を行う当事者間の合意によって決まりますが、下請法が適用されるケースでは法的なルールが存在することを理解しておく必要があります。また、期限が休日に重なる場合や、そもそも期限の記載がない請求書を受け取った場合など、実務で起こりうる様々なケースへの対処法を知っておくことで、慌てず冷静に対応できます。万が一、支払いの遅延が発生した際は、発行側・受領側どちらの立場であっても、迅速かつ誠実なコミュニケーションが何よりも重要です。請求書に支払い期限を明確に記載し、そのルールを互いに遵守することは、スムーズな取引の土台であり、取引先との信頼関係を築き、自社の健全なキャッシュフローを維持するための第一歩です。本記事を参考に、ぜひ自社の請求書管理体制を見直し、円滑な事業運営にお役立てください。


