更新日:2026/01/29
オフィスに用意しておきたい非常食ガイド! 備蓄量の目安や選び方、おすすめのサービスとは?

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
地震や台風などの自然災害は、いつ発生するかを予測することが難しく、企業においても平時からの備えが欠かせません。特にオフィスにおける非常食の備蓄は、災害時に従業員の健康を維持するだけではなく、混乱を抑え、事業を継続・早期再開するための重要な取り組みの一つです。
ただし、非常食を用意するといっても「どのくらいの量を備蓄すればよいのか」「どのような非常食を選ぶべきか」「管理の手間がかからない方法はあるのか」といった疑問を抱えている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、オフィスにおける防災備蓄の考え方や、非常食の備蓄量の目安、選び方のポイントなどをご紹介します。また非常時にも活用できる、おすすめの社食・オフィスコンビニサービスもまとめているのでぜひ参考にしてみてください。
【比較】おすすめのオフィスコンビニ一覧
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 対応地域 | 主な商品 |
|---|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
日本全国 | おやつ コーヒー プロテインバー おつまみ そうざい など |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
日本全国 | 新鮮なサラダ・フルーツ 手作りのお惣菜など |
Office Stand By You
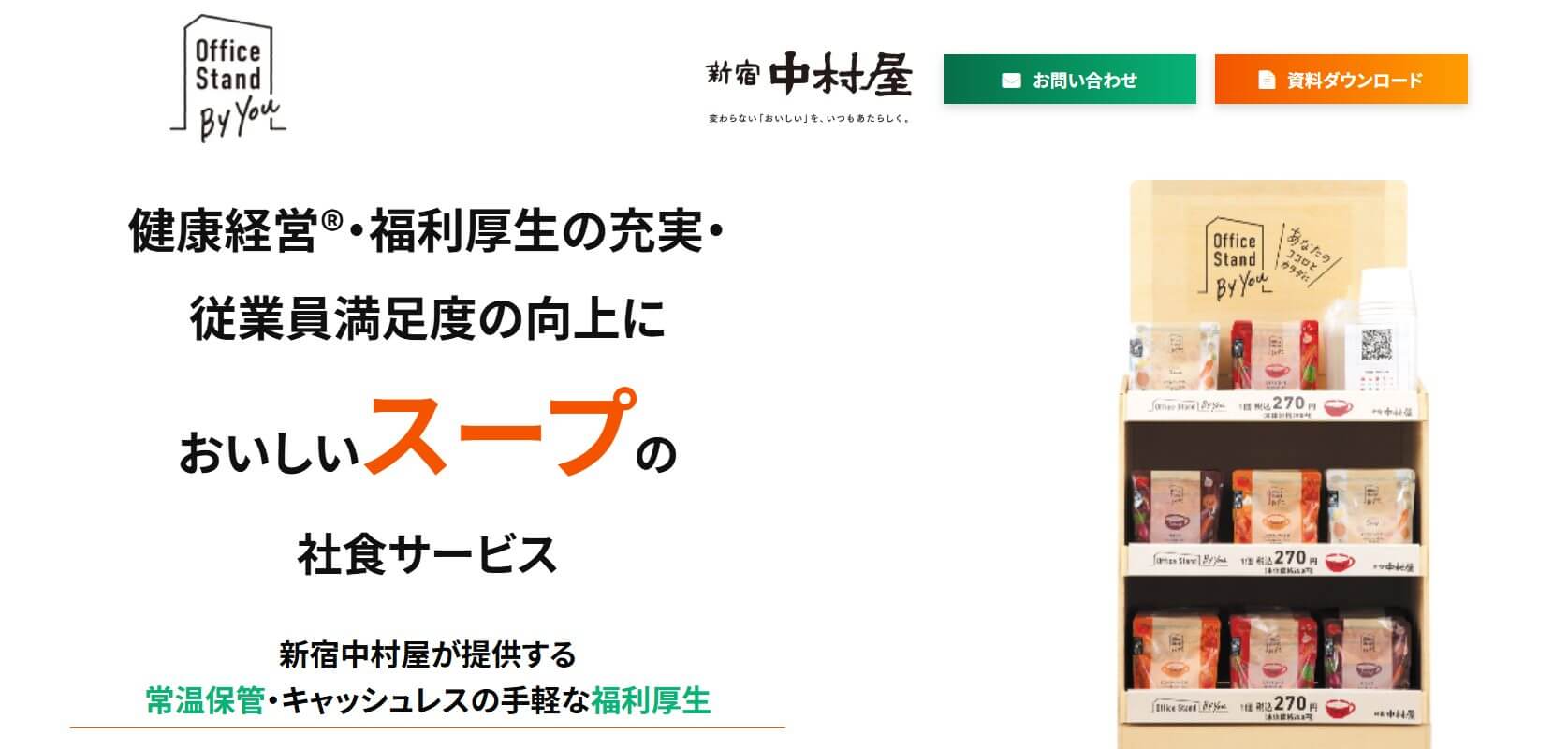
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
日本全国 |
常温保存可能なスープの提供 ・1/3日分の野菜を使ったミネストローネ ・魚介と野菜たっぷりのクラムチャウダー など |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・主食 |
| パンフォーユーオフィス |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・パン類 |
| Drink&Snack |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
東京・大阪が中心 | ・飲料水やコーヒー ・カップヌードル類 ・お菓子などの軽食類 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・副菜 ・軽食 |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・野菜と果実のスムージーなどのドリンク |
| おふぃすこんびに |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・飲料水 ・軽食 ・カップヌードル類 |
| Store600 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | - |
| ミニストップポケット |
|
要お問い合わせ ※定額プランあり |
関東/大阪/名古屋/仙台 | ・菓子 ・飲料 ・食品 ・雑貨 ・冷蔵食品 |
| オフィスグリコ |
|
要お問い合わせ ※設置費用、ランニングコスト0円 |
東京 / 神奈川/ 埼玉/ 千葉 愛知 大阪/ 京都/ 兵庫 広島 福岡 |
・菓子 ・飲料 ・アイスクリーム |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 商品内容は運営を担当する加盟店と相談の上、設置場所に合わせてカスタマイズ |
| SHINKO STORE(心幸ストア) |
|
要お問い合わせ | 日本全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |
| オフめし |
|
初期費用:20,000円 基本利用料:6,000円/月 |
日本全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |
| オフィスオアシス |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
東京・大阪など |
・飲料 ・お菓子 ・食品 |
| ボスマート |
|
初期費用:0円 月額費用:0円 |
日本全国 |
・食品 ・お菓子 |
| 完全メシスタンド |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
要お問い合わせ | ・食品 |
| 無人売店24 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
初期費用:0円 月額費用:39,600円/月 |
全国 | ・食品 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
TUKTUK(自社配送):東京都・神奈川・埼玉・千葉(一部) TUKTUKmini(郵送):全国 |
・お弁当 ・パスタ ・チャーハン ・お惣菜 ・お菓子 ・ドリンク ・おにぎり ・パン ・ヨーグルト ・豆腐バー ・アイスクリームなど ※商品は300種類以上 |
この記事の目次はこちら
オフィスの防災備蓄は義務なの?
防災備蓄とは、地震や台風などの災害が発生した場合に備えて、食料や水、生活必需品などを事前に確保しておく取り組みのことです。企業が災害時に従業員の安全を守るために重要な役割を果たします。
企業に対して、備蓄品を確保しておくことを義務付けた法律はありません。しかし、都道府県や市区町村といった自治体によっては、条例やガイドラインを通じて、企業へ防災備蓄の準備を求めているケースも多いです。
たとえ法律上の義務がなくても、自治体の方針や自社の事業継続計画(BCP)を踏まえ、日頃から備えを進めておく姿勢が企業には求められます。
東京都の例
東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」に基づき、大規模災害が発生した場合に備え、企業に対して、以下に挙げる対応を求めています(※)。
東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」に基づき、大規模災害が発生した場合に備え、企業に対して、以下に挙げる対応を求めています(※)。
- 施設の安全を確認した上で、従業員をオフィス内にとどまらせること
- 必要な3日分の水や食料などを備蓄しておくこと
※参考:東京都.「東京都帰宅困難者対策条例の概要」.https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/939/japanese_01.pdf ,(2013-04-01).
大阪府の例
大阪府では「事業所における「一斉帰宅の抑制」対策ガイドライン」を通じて、企業に対する防災備蓄の考え方を示しています(※)。このガイドラインでは、災害発生直後に多くの人が一斉に帰宅することで、道路や公共交通機関が混乱し、救助・救急活動の妨げになることを懸念。その対策として、企業に対して以下を求めています。
- 災害発生から少なくとも3日間は、企業が従業員を施設内に待機させられるよう、最低3日分の備蓄を確保すること
- 震災の影響が長期化する可能性も考慮し、3日分を超える備蓄についても検討すること
企業が防災備蓄を実施していなくても、刑罰や過料といった法的制裁が科されるわけではありません。ただし近年では「災害発生時に従業員の安全を守り、被災後もできる限りスピーディーに事業を再開できる体制を整えることは、企業にとって重要である」という認識が広がっており、防災備蓄に取り組む企業は年々増えています。
※参考:大阪府.「帰宅困難者対策について」.https://www.pref.osaka.lg.jp/o020080/kikikanri/kitakukonnan3/index.html ,(2024-06-10).
オフィスにおける非常食の備蓄量の目安
多くの自治体では、先述した通り、企業に対して3日分以上の非常食を備蓄しておくことを求めています。これは災害発生後すぐにライフラインが復旧するとは限らず、一定期間オフィス内で過ごす必要があるためです。
内閣府の「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」では、3日分の備蓄量の目安として以下が示されています(※)。
- 水:1人当たり1日3リットル(3日分で9リットル)
- 主食:1人当たり1日3食(3日分で9食)
自社の従業員数を基に、必要量を算出して備蓄の準備をしておきましょう。
※参考:内閣府.「帰宅困難者対策ガイドライン」.https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf ,(2026-01).
非常食以外にも用意しておくもの
非常食と併せて以下に挙げる物資も備えておくと、災害時の不安や不便を軽減しやすくなります。
- 毛布(1人当たり1枚)
- 乾電池・非常用電源
- 懐中電灯
- 衛生用品(トイレットペーパー、マスク、生理用品など)
- 簡易トイレ
- 携帯ラジオ
- 救急医療薬品類
- 敷物(ビニールシートなど)
オフィスではこれらを非常食と同じ場所にまとめて保管し、定期的に点検することが大切です。
オフィスに置いておきたい非常食とは?
ここでは、オフィスに置いておきたい代表的な非常食をご紹介します。
保存水
保存水とは、長期間の保管を前提として製造された飲料水のことです。飲料水としての水分補給のために必要なのはもちろん、非常食を調理する際にも使用できます。
一般的なミネラルウォーターの保存期間は2年程度であることが多い一方、保存水は5年以上の賞味期限を持つ製品が主流です。中には10年程度保存できる商品もあり、入れ替えの手間を抑えやすいのもポイントです。
なお、非常時にはコップを使えず、直接ペットボトルに口を付けて飲む場面も想定されます。大容量のペットボトルだと、扱いにくい場合があることを認識しておきましょう。細菌の繁殖を抑えやすく、配布しやすい点を踏まえると、500ミリリットルタイプの保存水を備えておくのも選択肢の一つです。
アルファ化米
アルファ化米とは、一度炊飯したお米を乾燥させた保存食のことです。賞味期限は製品によって異なりますが、長いものでは5年程度保存できます。
お湯や水を注ぐだけで手軽に食べられるため、電気やガスが使えない状況でも食事しやすい点が特長です。また白飯の他に、混ぜご飯やドライカレーなど種類も豊富で、非常時の食事に変化を持たせやすくなります。
ビスケット・クッキー
ビスケットやクッキーは水分量が少なく、劣化しにくいことから、非常食として定番の食品です。水やお湯を用意する必要がなく、そのまま食べられる点もオフィスでの備蓄に向いています。
形状は缶詰タイプが一般的ですが、近年では持ち運びしやすい平型の箱に入ったコンパクトな商品も多く流通しています。味のバリエーションも豊富で、甘いものから塩味のクラッカータイプまで幅広く選択可能です。日頃から食べ慣れた味のものを備えておくことで、非常時の不安を和らげる効果も期待できます。
缶詰・袋詰のパン
備蓄用として、缶やレトルト食品用の袋に密封されたパンもあります。プレーン味の他、チョコレートやフルーツ風味など種類が多いです。
賞味期限は商品によってさまざまで5年程度の商品も見られる一方で、6カ月前後と短い商品もあるため、購入時の確認が欠かせません。
缶詰タイプはパンがつぶれにくい点がメリットですが、袋詰めタイプに比べると保管時にかさばりやすい傾向があります。反対に袋詰めタイプは衝撃に弱いものの、軽量で省スペースに保管でき、ごみを減らしやすいです。タイプによってメリット・デメリットが異なるので、自社のニーズに合ったものを選びましょう。
レトルト食品
レトルト食品は、非常食としても活用しやすい食品の一つです。スープやおかゆ、カレー、惣菜などラインナップが豊富なため、複数の種類を備えておくことで、非常時でも飽きずに食事を取れるでしょう。
またお米や肉、野菜など、さまざまな食材を使った商品を組み合わせることで、栄養バランスにも配慮しやすくなります。近年では、電子レンジやお湯で温める必要がなく、常温のまま開封して食べられるタイプも登場していて便利です。
フリーズドライ食品
フリーズドライ食品とは、食品を急速冷凍した後、真空状態で水分を取り除いた食品です。お湯を注ぐだけで食べられる味噌汁やスープ、麺類などがあり、非常時でも温かい汁物を摂取できます。冷えた体を内側から温めるだけではなく、精神的な安らぎを感じられるでしょう。
企業で非常食を準備する際に押さえておきたいポイント
オフィスで非常食を備蓄する際は、単に食品をそろえるだけでなく、運用面まで含めて検討することが大切です。ここでは、企業が非常食を準備する際に押さえておきたいポイントを2点、ご紹介します。
軽食や置き菓子を防災備蓄として活用する
企業が福利厚生や食事補助の一環として、オフィスに設置している置き菓子や軽食は、防災備蓄としても活用可能です。普段から従業員が口にしている食品を備蓄に取り入れることで、非常時にも抵抗感なく食べやすくなります。
また食品を日常的に目に触れる場所に配置することで、防災を意識する機会が増え、災害への備えを身近なものとして捉えやすくなります。
ローリングストック方式を採用する
ローリングストック方式とは、賞味期限の古いものから消費し、消費した分を新たに買い足していく備蓄方法のことです。非常食を「使わずに保管するもの」として扱うのではなく、日常的に消費しながら管理していきましょう。
オフィスの置き菓子や軽食として採り入れることで、自然な形で在庫の入れ替えが可能です。その結果、賞味期限切れによる廃棄を抑えつつ、常に新しい備蓄品を確保しやすくなります。管理の手間を減らしたい企業にとって、有効な方法の一つです。
非常食にもなる! おすすめの社食・オフィスコンビニサービス5選
ここからは、非常食にもなるおすすめの社食・オフィスコンビニサービスをご紹介します。
snaq.me office(スナックミーオフィス)

snaq.me officeは、無添加や素材に配慮したおやつをオフィス向けに提供するサービスです。ナッツやドライフルーツ、焼き菓子など、賞味期限が比較的長い商品が多く、防災備蓄としても活用しやすい点が特長です。具体的にはおやつは常温で約30日間、そうざいは約90日間の保存が可能です。中でもプロテインバーは賞味期限が1年以上と長く、備蓄用の非常食としても人気を集めています。
個包装の商品が中心のため、配布しやすく、衛生面にも配慮されています。普段のおやつとして消費しながら備蓄できるため、ローリングストック方式とも相性が良いサービスです。
【料金表あり!】3分で分かるsnaq.me officeの資料DLはこちら
人工甘味料・保存料・合成着色料などは一切不使用!
おやつ・コーヒー・プロテインバーなど多彩なコースを、従業員の嗜好に合わせて自由に選択可能
| 費用 | ・初期費用:0円 ・月額費用:0円 ・送料・備品費:0円 ・商品代金:買取(企業が一括購入)/一部負担(企業と従業員が一定額ずつ負担)/負担ゼロ(従業員が都度購入)の3プランから選択可能 |
| サービス内容 | 置き菓子やドリンクの提供 ・おやつ ・ドリンク ・コーヒー ・スイーツパン ・グラノーラ ・おつまみ ・プロテインバー ・ヴィーガン ・そうざいなど複数のコースから自由に選択可能 |
| 無料トライアル | 有 |
| 運営企業 | 株式会社スナックミー |
| URL | https://office.snaq.me/ |
Office Stand By You

Office Stand By Youは、120年以上の歴史を持つ新宿中村屋の調理技術を生かして開発された、スープを手軽に利用できるオフィス常設型の社食サービスです。余計なものは入れず、素材本来の旨味を引き出したレストラン品質の味わいが魅力です。
スープは全て常温で保管できるので、冷蔵庫や冷凍庫を設置する必要がありません。賞味期限まで3カ月以上ある商品が納品されるので、長く保管できます。品質低下や食品ロスの心配が少なく、万が一の際の防災備蓄としても利用可能です。
無料トライアル受け付け中!
常温保存可能!
製造から1年間の賞味期限で、お届け時には最低3か月以上の賞味期限を保証
| 費用 | 要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
| サービス内容 | 常温保存可能なスープの提供 |
| 無料トライアル | 有 |
| 運営企業 | 株式会社中村屋 |
| URL | https://officestandbyyou.nakamuraya.co.jp/LP01 |
オフめし

オフめしは、冷凍・冷蔵食品やカップ麺、お菓子、飲み物などを中心に、オフィスで手軽に食事を取れるオフィスコンビニサービスです。長期保存が可能な商品も多く、非常食としての備蓄にも向いています。
主食からおかずまで幅広いラインアップがあり、栄養バランスを考えた備蓄を行いやすい点も魅力です。日常利用と非常時対応を兼ねた仕組みを構築したい企業に適しています。
| 費用 | 初期導入費:2万円基本利用料:6,000円/月 |
| サービス内容 | 主食・惣菜(常温・冷蔵)・弁当(冷凍)・お菓子・飲料・カップ麺・スープ・雑貨など |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
| 運営企業 | 心幸ホールディングス株式会社 |
| URL | https://www.shinko-jp.com/offmeshi/ |
B.B.CAMP

B.B.CAMPは、お菓子やカップ麺、コーヒーなど50~60種類の商品を購入できるオフィスコンビニサービスです。
コーヒーマシンは2種類あり、どちらもアイスコーヒーに対応しています。メニューが豊富で、カフェラテ、カフェモカといったコーヒーメニューの他、ココアも選べるプレミアムは、コーヒー好きな方もコーヒーが苦手な方も利用可能です。
また保存性の高い食品をまとめて管理できるため、備蓄の抜け漏れを防ぎたい企業に向いています。
| 費用 | 初期導入費:なし月額費用:1万円~ |
| サービス内容 | 主食・惣菜(常温・冷蔵)・弁当(冷凍)・お菓子・飲料・カップ麺・スープ・雑貨など |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
| 運営企業 | ネオス株式会社 |
| URL | https://www.neos-corp.jp/b.b.camp/ |
Drink&Snack オフィスのドリンク

Drink&Snack オフィスのドリンクは、飲料や軽食をオフィスに常設できるオフィスコンビニサービスです。冷蔵庫無料・設置費無料で利用でき、企業は冷蔵庫の電源以外負担するものはありません。
飲料やお菓子、カップ麺などを備えることで、災害時にも活用可能。飲料が設置されている冷蔵庫は機械式のものと違い、停電しても手で開けられます。
また飲料はキリン・アサヒ・コカコーラなど有名ブランドから豊富に選択できる点もポイントです。
| 費用 | 初期導入費:なし月額費用:なし |
| サービス内容 | 飲料・お菓子・カップ麺など |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
| 運営企業 | レップ・グローバルネットワーク株式会社 |
| URL | http://oc-tokyoeast.com/ |
オフィスの非常食の選び方
オフィスの非常食を選ぶ際は、保存性はもちろんのこと、実際の利用シーンを想定することが大切です。ここでは、非常食の選び方をご紹介します。
賞味期限の長さを確認しておく
企業が非常食を選ぶ際に特に重視したいのが、賞味期限の長さです。目安としては、賞味期限が5年以上ある食品が備蓄に向いているとされています。
缶詰やレトルト食品、フリーズドライ食品の中には、長期保存が可能な商品も多くあります。入れ替え頻度を抑えたい場合は、こうした食品を中心に選ぶと管理しやすくなるでしょう。
アレルギー対応の食品を確保しておく
食物アレルギーを持つ従業員にも配慮し、アレルギー対応の非常食を一定数確保しておくことが重要です。小麦・乳・卵・落花生・そば・えびといった主要なアレルゲンを含まない食品を選んでおくとよいでしょう。
一般の非常食と併せて保管する場合は、食物アレルギーを持つ従業員が誤って摂取してしまうことがないよう、明確な区分や表示を行う必要があります。またアレルギー対応食品は価格が高くなる傾向があるため、事前に必要数量を把握し、予算を確保しておくことも欠かせません。
栄養バランスを確認しておく
非常時でも健康を維持するためには、栄養バランスに配慮した備蓄が重要です。特にたんぱく質・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれた非常食を選びましょう。
例えば、完全栄養食や高たんぱく質の缶詰、ドライフルーツ、野菜ジュースなどを組み合わせて備蓄することで、限られた食事の中でも必要な栄養素を補給しやすくなります。
調理が楽なものや不要のものを選ぶ
災害時には、電気・ガス・水道といったライフラインが使えなくなる可能性があります。そのため、調理を必要としない、もしくは簡単な準備だけで食べられる非常食を選ぶことが大切です。
缶詰やパン、クッキー、ナッツ、ドライフルーツ、チョコレート、水で戻せるごはん、栄養補助ゼリーなどは、調理器具や熱源がなくても食べられます。災害直後の混乱した状況でも対応しやすいでしょう。
また災害が長期化した場合には、温かい食事が必要になる場面もあります。非常食の備蓄に加え、簡易コンロや簡易調理器具の準備も併せて検討しましょう。
包装や保管方法を確認する
非常食を選定する際は、食品の種類だけではなく、包装や保管方法にも目を向ける必要があります。開封しやすく再封可能であることや、軽量でコンパクトであることなどの特性を持つ包装が望ましいといえます。
さらに保管環境への配慮も欠かせません。温度や湿度を管理しやすい場所を選び、定期的な点検や入れ替えを行うことで、非常食の品質を保ちやすくなります。直射日光や高温多湿を避け、冷暗所で保管しておくことが基本です。
まとめ
オフィスにおける非常食の備蓄は、災害時に従業員の食事を確保することになる他、事業を継続するための重要な備えです。多くの自治体では3日分以上の備蓄を推奨しており、水や主食に加えて、衛生用品なども含めた準備が求められます。
非常食は保存性だけではなく、栄養バランスや調理のしやすさなどにも配慮して選ぶことが大切です。また社食やオフィスコンビニサービスを活用すれば、日常的な利用と防災備蓄を両立できます。
自社に合った方法で非常食を備え、災害時にも落ち着いて対応できる環境づくりを進めていきましょう。
【比較】おすすめのオフィスコンビニ一覧
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 対応地域 | 主な商品 |
|---|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
日本全国 | おやつ コーヒー プロテインバー おつまみ そうざい など |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
日本全国 | 新鮮なサラダ・フルーツ 手作りのお惣菜など |
Office Stand By You
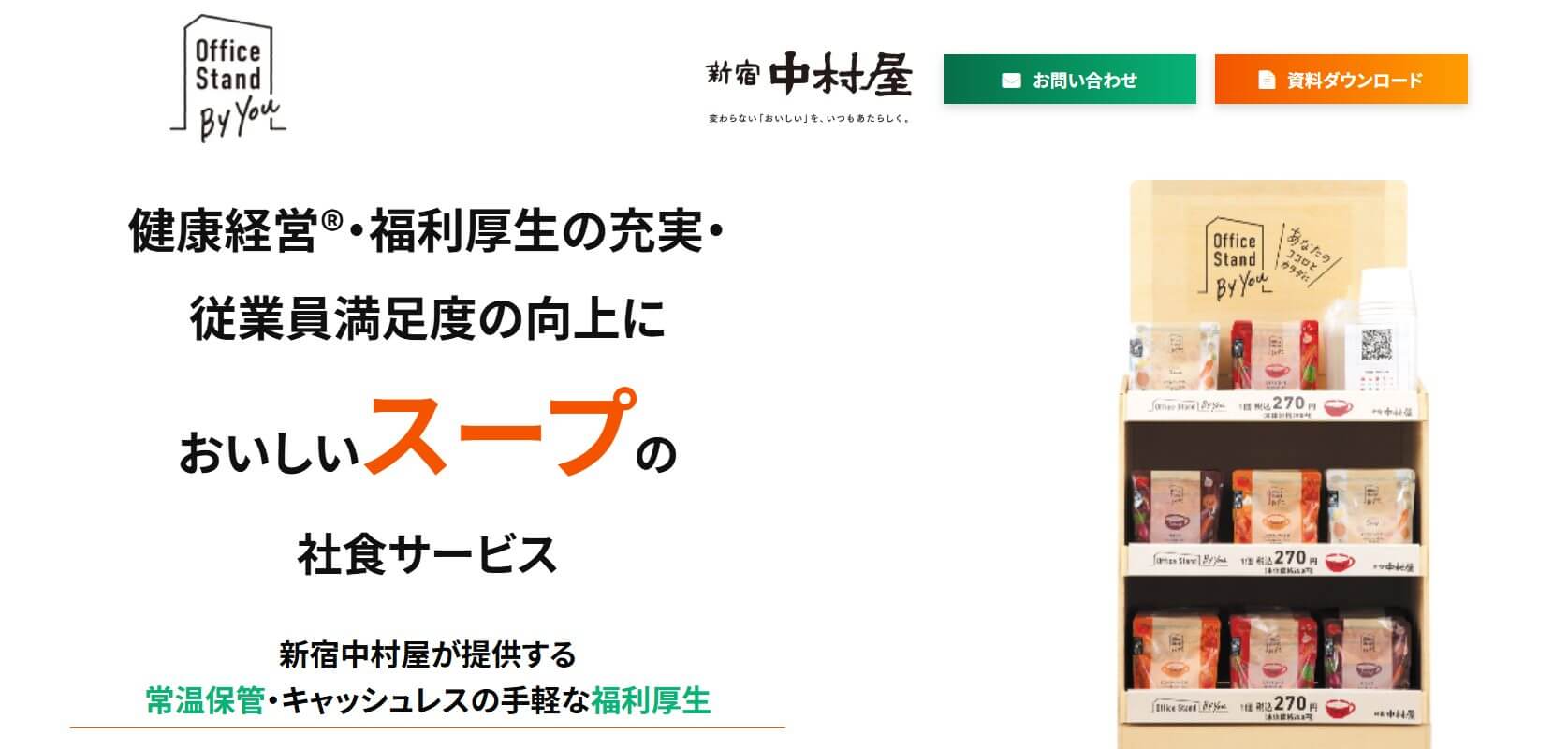
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
日本全国 |
常温保存可能なスープの提供 ・1/3日分の野菜を使ったミネストローネ ・魚介と野菜たっぷりのクラムチャウダー など |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・主食 |
| パンフォーユーオフィス |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・パン類 |
| Drink&Snack |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
東京・大阪が中心 | ・飲料水やコーヒー ・カップヌードル類 ・お菓子などの軽食類 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・副菜 ・軽食 |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・野菜と果実のスムージーなどのドリンク |
| おふぃすこんびに |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・飲料水 ・軽食 ・カップヌードル類 |
| Store600 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | - |
| ミニストップポケット |
|
要お問い合わせ ※定額プランあり |
関東/大阪/名古屋/仙台 | ・菓子 ・飲料 ・食品 ・雑貨 ・冷蔵食品 |
| オフィスグリコ |
|
要お問い合わせ ※設置費用、ランニングコスト0円 |
東京 / 神奈川/ 埼玉/ 千葉 愛知 大阪/ 京都/ 兵庫 広島 福岡 |
・菓子 ・飲料 ・アイスクリーム |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 商品内容は運営を担当する加盟店と相談の上、設置場所に合わせてカスタマイズ |
| SHINKO STORE(心幸ストア) |
|
要お問い合わせ | 日本全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |
| オフめし |
|
初期費用:20,000円 基本利用料:6,000円/月 |
日本全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |
| オフィスオアシス |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
東京・大阪など |
・飲料 ・お菓子 ・食品 |
| ボスマート |
|
初期費用:0円 月額費用:0円 |
日本全国 |
・食品 ・お菓子 |
| 完全メシスタンド |
|
要お問い合わせ ※初期費用0円 |
要お問い合わせ | ・食品 |
| 無人売店24 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
・食品 ・お菓子 ・飲料 |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
初期費用:0円 月額費用:39,600円/月 |
全国 | ・食品 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
TUKTUK(自社配送):東京都・神奈川・埼玉・千葉(一部) TUKTUKmini(郵送):全国 |
・お弁当 ・パスタ ・チャーハン ・お惣菜 ・お菓子 ・ドリンク ・おにぎり ・パン ・ヨーグルト ・豆腐バー ・アイスクリームなど ※商品は300種類以上 |


