人事評価システム導入で絶対に失敗しない!7つの原因と成功法則・導入前の注意点

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
人事評価システムの導入は、公正な評価と人材育成を実現し、組織の成長を後押しする経営戦略の要です。しかし、導入後に「期待した効果が得られない」「現場が混乱した」といった失敗例も少なくありません。
本記事では、「人事評価システム 失敗」をキーワードに、導入がうまくいかない典型的な原因やリスクを明らかにし、それらを回避して成功へと導くための実践的なポイントを詳しく解説します。
【比較】おすすめの人事評価システム
scroll →
| サービス名称 | 特長 | 初期費用 | 月額費用 | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|
タナベコンサルティングの人事評価制度構築コンサルティング

|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | × |
OGSコンサルティングの戦略連動型人事評価制度の構築コンサルティング

|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ ※柔軟に対応可能 |
× |
ジンジャー人事評価
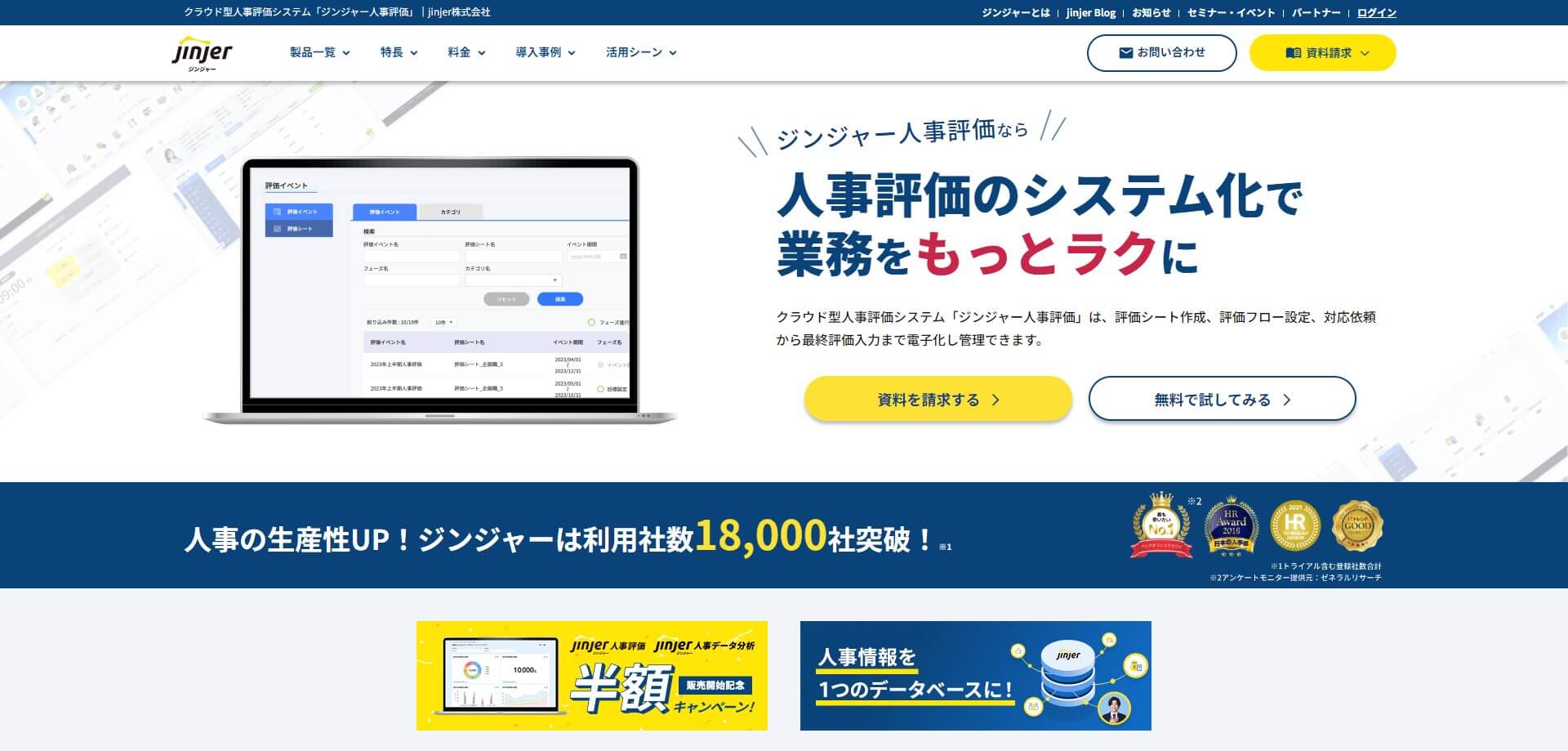
|
|
要お問い合わせ |
月額利用料×利用者数 ※詳細は要お問い合わせ |
〇 |
MONJU

|
|
要お問い合わせ |
20,000円~ ※年払い(240,000円~)必須 ※社員数に応じて変動 お問い合わせ |
〇 |
人事評価ナビゲーター

|
|
110,000円~ | 5,500円~ お問い合わせ |
〇 |
| スマカン |
|
要お問い合わせ | 50,000円~ | 〇 |
| HRMOSタレントマネジメント |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
| あしたのクラウドHR |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
| タレントパレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
| HRBrain |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
| カオナビ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
| sai*reco |
|
400,000円 |
220円~ ※1名あたりの目安金額 ※従業員規模100名程度〜 |
〇 |
| HITO-Talent |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |
| シナジーHR |
|
0円 |
200円~ ※基本料金のみ ※1名あたり |
〇 |
| 評価ポイント |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |
| CYDAS PEOPLE |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |
| Resily |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |
この記事の目次はこちら
人事評価システム導入の失敗が招くリスク
人事評価システムの導入失敗は、単に「期待した効果が出なかった」というレベルに留まらず、組織全体に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。導入を検討する際には、これらのリスクを十分に認識しておくことが極めて重要です。
従業員のモチベーション低下と不信感の増大
評価基準が不明確であったり、評価プロセスが不公平だと感じられたりすると、従業員は正当に評価されていないと感じ、仕事への意欲を失います。特に、システム導入によって評価の透明性が向上すると期待していたにも関わらず、逆の結果を招いた場合、会社や人事制度そのものへの不信感が蔓延する恐れがあります。
社内対立とコミュニケーションの悪化
評価結果に対する不満は、従業員間や部署間の対立を引き起こす可能性があります。「なぜあの人が自分より高く評価されるのか」といった疑念が生じ、健全な協力関係やコミュニケーションが阻害されるリスクがあります。評価者である上司と部下の関係が悪化することも少なくありません。
離職率の上昇と人材流出
公正な評価や成長の機会が得られないと感じた優秀な従業員は、より良い環境を求めて他社へ流出してしまう可能性があります。特に、評価制度への不満が離職の引き金となるケースは多く、組織にとって大きな損失となります。
企業全体の生産性・業績低下
従業員のモチベーション低下や人材流出は、当然ながら企業全体の生産性や業績に悪影響を及ぼします。組織としての一体感が失われ、目標達成に向けた推進力が弱まることも懸念されます。
導入コストの浪費と機会損失
システム導入には多大な費用と時間がかかります。失敗に終われば、それらの投資が無駄になるだけでなく、本来得られるはずだった業務効率化や人材育成の機会も失うことになります。
人事評価システム導入で失敗する原因(7つ)
多くの企業が陥りがちな人事評価システム導入の失敗。その背景には、いくつかの共通した原因が存在します。ここでは、特に多く見られる7つの典型的な失敗原因を具体的に解説します。自社の状況と照らし合わせ、潜在的なリスクがないか確認しましょう。
導入目的の不明確さ・共有不足
最も根本的かつ致命的な原因です。「なぜシステムを導入するのか?」という目的が曖昧なままプロジェクトが進むケースです。例えば、「評価業務を効率化したい(人事部)」「人材育成を強化したい(経営層)」「他社が導入しているから」といったように、関係者間で目的が異なっていたり、そもそも現状の課題分析が不十分だったりします。目的が明確でなければ、システムに求める要件定義ができず、最適なシステム選定が不可能になります。また、目的が共有されていなければ、導入プロセスでの協力が得られにくく、導入後も意図した活用がなされません。結果、投資対効果を説明できない事態に陥ります。
自社の課題や文化に合わないシステム選定
市場には多種多様なシステムが存在しますが、自社の課題解決や組織文化、評価制度の運用フローに適合しないシステムを選んでしまうと、導入後に大きな問題が生じます。高機能すぎるシステムを導入し持て余す、逆に機能が不足し業務要件を満たせない、操作が複雑で利用が定着しない、特定の評価手法(例: OKR特化)が自社に合わない、などが典型例です。システムの機能だけでなく、操作性(UI/UX)、カスタマイズ性、サポート体制、セキュリティなどを多角的に評価し、自社の身の丈に合った、「使いこなせる」システムを選ぶ視点が不可欠です。
経営層・管理職のコミットメント不足
人事評価制度の改革・システム導入は、トップの強いリーダーシップと管理職の積極的な関与が成功の鍵です。しかし、経営層が意思決定だけして現場任せにしたり、評価者となる管理職がシステムの必要性を理解せず、従来の方法に固執したり、部下へのフィードバックを怠ったりすると、プロジェクトは頓挫します。特に管理職の協力なしに、システムの全社的な定着はありえません。経営層からの継続的なメッセージ発信と、管理職への十分な研修・動機づけが求められます。
従業員への説明不足・理解不足
新しいシステムは、従業員にとって変化への不安や抵抗感を生む可能性があります。「なぜ導入するのか」「何が変わるのか」「自分たちにどんなメリットがあるのか」といった点を丁寧に説明し、理解と納得を得るプロセスを省略すると、導入はスムーズに進みません。説明不足は、「会社は従業員を管理したいだけでは?」といった不信感を招く原因にもなります。操作トレーニングやマニュアル提供はもちろん、導入初期からの情報共有や意見交換の場を設けることが重要です。
評価制度そのものに問題がある
システムはあくまで評価制度を運用するための「ツール」です。もし、評価基準が曖昧、評価プロセスが不公平、フィードバックがないなど、土台となる評価制度自体に欠陥がある場合、どんなに優れたシステムを導入しても問題は解決しません。むしろ、システムによって問題点が可視化され、従業員の不満が増大する可能性すらあります。システム導入は、既存の評価制度の目的、基準、プロセス、フィードバック方法などを根本から見直す絶好の機会と捉えるべきです。
導入準備・運用体制の不備
導入を急ぐあまり、十分な準備期間や計画的な運用体制が確保されないケースも失敗の要因です。従業員データの移行・初期設定の遅延、導入後の問い合わせ窓口やメンテナス担当の不明確さ、評価サイクルの運用ルールの曖昧さなどが挙げられます。これらは現場の混乱を招き、システムの安定稼働を妨げます。導入後の安定運用を見据えた人員・リソース確保、役割分担の明確化、継続的なサポート体制の構築が不可欠です。「導入はゴールではなくスタート」という認識が必要です。
システム導入が「ゴール」になってしまう
無事にシステムが稼働を開始すると、それでプロジェクト完了と安心してしまい、導入後のフォローアップを怠るケースです。しかし、人事評価システムは導入してからが本当のスタート。その効果を最大化するには、利用状況や評価データの分析、導入目的の達成度測定、従業員からのフィードバック収集などを定期的に行い、継続的に改善していく必要があります。このPDCAサイクルを回さなければ、せっかく導入したシステムも次第に形骸化し、陳腐化してしまうでしょう。
人事評価システムの導入を成功に導く7つのポイント
前章で解説した失敗原因を踏まえ、人事評価システムの導入を成功させるために不可欠な7つのポイントを具体的に解説します。これらのポイントを確実に実行することが、失敗リスクを最小限に抑え、システム導入効果を最大化するための鍵となります。
導入目的の明確化と全社的な共有
「なぜ導入するのか」「導入によって何を達成したいのか」という目的を、具体的かつ明確に定義することが全ての出発点です。現状の課題(例:評価のばらつき、業務非効率、育成への活用不足)を分析し、目指すべきゴール(例:目標管理の強化、エンゲージメント向上、透明性向上)を設定します。そして、その目的を経営層から一般従業員まで、組織全体で確実に共有し、共通認識を持つことが極めて重要です。目的が明確で共有されていれば、システム選定の軸が定まり、関係者の協力も得やすくなります。
自社の課題解決と運用に最適なシステム選定
明確化された導入目的に基づき、自社の課題解決に最も貢献できるシステムを選定します。機能の網羅性だけでなく、操作性(UI/UX)、自社の評価フローとの適合性、カスタマイズの柔軟性、サポート体制、セキュリティレベル、そしてコストを総合的に評価します。複数のベンダーから情報を収集し、デモンストレーションやトライアル導入を通じて、実際に「使いこなせるか」を見極めることが重要です。価格だけで安易に決定せず、長期的な視点で自社に本当にフィットするパートナーを選びましょう。
経営層・管理職の積極的な関与と推進
システム導入は経営改革の一環であるという認識のもと、経営層が強力なリーダーシップを発揮し、導入の意義や重要性を繰り返し社内に発信することが不可欠です。また、評価者となる管理職に対しては、システム導入の背景・目的、新しい評価制度、システムの操作方法などについて十分な研修を実施し、理解とスキル向上を促します。管理職自身がシステムの価値を理解し、率先して活用する姿勢を示すことが、部下の積極的な利用を促し、全社的な定着に繋がります。
従業員への丁寧な説明とメリットの提示
従業員の不安や疑問を解消し、協力を得るためには、丁寧で双方向なコミュニケーションが欠かせません。導入の目的、背景、変更点、そして従業員にとっての具体的なメリット(例:評価の透明性向上、フィードバック機会増、キャリア開発支援)を分かりやすく説明します。全社説明会、Q&Aセッション、マニュアル・FAQの整備に加え、導入プロセスへの意見反映の機会を設けることも有効です。従業員が「自分たちのためのシステムだ」と感じられるような働きかけが重要です。
システム導入を機に評価制度全体を見直す
システムはあくまでツールであり、土台となる評価制度そのものが健全でなければ効果は限定的です。システム導入を、既存の評価制度(目的、理念、基準、プロセス、フィードバック方法など)を根本から見直し、改善する絶好の機会と捉えましょう。自社の経営戦略や目指す組織像に基づき、「どのような人材を評価し、育成したいか」を再定義し、公平性・透明性・納得性の高い制度を設計します。制度設計とシステム導入は必ず両輪で進める必要があります。
十分な準備期間と計画的な導入・運用体制の構築
成功のためには周到な準備と計画が不可欠です。目的設定からシステム選定、制度設計、データ移行、従業員説明、トレーニングまで、各ステップに十分な期間を設け、無理のない現実的なスケジュールを策定します。特にデータ移行や初期設定には余裕を持たせましょう。導入後の安定運用を見据え、システム管理者、問い合わせ担当、評価者など、役割分担を明確化し、必要なトレーニングやサポート体制を構築します。スモールスタートや段階的な導入も混乱を避ける有効な戦略です。
導入後の効果測定と継続的な改善 (PDCA)
「導入したら終わり」ではありません。導入後こそが重要であり、その効果を定期的に測定し、継続的に改善していくプロセス(PDCAサイクル)が不可欠です。導入前に設定した目的やKPI(例:評価工数削減、従業員満足度、目標達成率)が達成されているかを定量的・定性的に評価します。システムの利用状況分析や従業員アンケートなどを通じて課題を発見し、評価制度の見直し、システム設定の調整、運用ルールの変更など、迅速かつ柔軟に対策を講じます。この継続的な改善活動が、システムの価値を高め、形骸化を防ぎます。
人事評価システム導入前の注意点
人事評価システムの導入を具体的に検討・準備する段階に入る前に、いくつか前提として理解しておくべき重要な注意点があります。これらを事前に認識しておくことで、過度な期待や誤解を防ぎ、より現実的で効果的な導入計画を立てることが可能になります。
注意点1: システムはあくまで「ツール」である
何度か触れてきましたが、これは最も重要な心構えの一つです。人事評価システムは、魔法の杖ではありません。システムを導入しただけで、人事評価に関する全ての問題が自動的に解決するわけではないのです。評価制度の設計思想、評価者のスキルレベル、運用ルールの浸透度、そして従業員の納得感といった、人的・組織的な要因が伴わなければ、どんなに高機能なシステムも宝の持ち腐れとなります。システムは、あくまで設計された評価制度を効率的かつ効果的に「運用支援」するためのツールである、という位置づけを正しく理解しましょう。システム検討と並行し、制度設計や評価者研修、コミュニケーション活性化といったソフト面の強化にも注力する必要があります。
注意点2: 導入には相応のコストと時間がかかる
システム導入には、初期費用や月額利用料といった直接的な金銭コストが発生します。これに加えて、システム選定、評価制度の設計・見直し、社内調整、従業員への説明会やトレーニングの実施、既存データの移行作業など、多くの人的リソースと時間という「見えにくいコスト」も必要となります。特に、専任のプロジェクトチームを組成できない中小企業にとっては、通常業務と並行してこれらの準備を進める負担は想像以上に大きい可能性があります。導入後の保守運用、アップデート対応、社内からの問い合わせ対応といったランニングコストも考慮に入れる必要があります。これらのコストと時間的負担を事前に可能な限り正確に見積もり、必要な予算と体制を確保しておくことが、計画の頓挫を防ぐ上で不可欠です。
注意点3: 既存の業務プロセスや組織文化への影響を考慮する
新しいシステムの導入や、それに伴う評価制度の変更は、既存の業務プロセスや長年培われてきた組織文化に少なからず影響を与えます。変化に対して、従業員が心理的な抵抗感や戸惑いを覚えるのは自然な反応です。例えば、従来の紙やExcelでの評価からシステム入力への変更、評価項目や基準の変更、評価結果の可視化範囲の変更など、具体的な変化点を洗い出し、それらが従業員にどのように受け止められるかを予測する必要があります。そして、丁寧な説明、段階的な移行措置、十分なトレーニング期間などを通じて、変化への適応を支援する準備が必要です。また、新しいシステムや制度が、自社の組織文化(例:トップダウン型かボトムアップ型か、協調性重視か成果主義重視かなど)と整合性が取れているかを見極めることも重要です。文化との大きな乖離は、システムの定着を妨げる大きな要因となります。
注意点4: セキュリティ対策の重要性
人事評価システムは、従業員の氏名、所属、役職、評価結果、目標設定、場合によっては給与情報など、極めて機密性の高い個人情報を大量に扱います。そのため、セキュリティ対策はシステム選定・導入・運用における最重要課題の一つと認識しなければなりません。検討しているシステムのデータ暗号化、アクセス制御(権限設定)、不正アクセス防止策、脆弱性対策などが十分であるかはもちろん、システムを提供するベンダー自体の信頼性やセキュリティ体制、データセンターの管理状況なども厳しく評価する必要があります。ISMS認証(ISO27001)やPマークの取得状況なども参考になります。また、社内においても、アクセス権限の適切な管理(必要最小限の原則)、従業員への情報セキュリティ教育の徹底など、運用面での対策も欠かせません。万が一の情報漏洩は、企業の社会的信用を根底から揺るがす重大なリスクであることを常に念頭に置くべきです。
導入後が本番!継続的な運用改善とフォローアップ体制
人事評価システムは、導入が完了し、稼働を開始してからが本当のスタートです。「導入して終わり」ではなく、効果を最大化し、組織に定着させるためには、継続的な運用改善とフォローアップ体制の構築が不可欠となります。このフェーズを怠ると、せっかく導入したシステムも形骸化し、「失敗」の烙印を押されかねません。
定期的なレビューと迅速な改善サイクル(PDCA)の確立
システム稼働後は、定期的に運用状況をレビューする場を設けることが重要です。関係部署の責任者や担当者、可能であれば従業員代表も交え、以下のような点を検証します。
- システムの利用状況、データの蓄積状況
- 設定した評価基準や指標の整合性、妥当性
- 評価者による評価のばらつき、課題
- 従業員からのフィードバック、改善要望
当初設定した導入目的の達成度 このレビュー結果に基づき、課題を特定し、改善策を立案・実行し、その効果を再度検証するというPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを効果的に回す仕組みを構築します。例えば、評価基準が実態と合わなくなっていれば修正し、操作性が悪いという声が多ければベンダーに改善を要求したり、社内マニュアルを整備したりします。この迅速かつ柔軟な対応が、システムの信頼性を高め、長期的な運用成功に繋がります。
評価者トレーニングとサポートの継続
評価者のスキルやシステムへの理解度は、評価の質と公平性を左右する重要な要素です。導入時の研修だけでなく、定期的に評価者向けのトレーニングや勉強会を実施し、スキルアップを図る必要があります。特に、360度評価や多面評価など、複数の評価者が関わる場合は、評価基準の目線合わせが重要になります。また、システムの新機能追加やアップデートに合わせて、操作方法のレクチャーや情報提供を行うなど、継続的なサポートを提供します。
フィードバックの質の向上と対話の促進
システムを通じて評価結果を伝えるだけでなく、評価者(上司)と被評価者(部下)との間で質の高いフィードバック面談が行われるように支援することも重要です。評価結果の根拠を具体的に説明し、良かった点、改善点、そして今後の期待を伝える対話の機会を設けることで、評価への納得感を高め、従業員の成長を促進します。システムはあくまで対話を「支援」するツールであり、コミュニケーションそのものを代替するものではないことを忘れてはいけません。各部署で効果的なフィードバックが行われるよう、面談のガイドライン作成やロールプレイング研修なども有効です。
蓄積データの分析と人事戦略への活用
人事評価システムに蓄積されたデータは、組織の貴重な資産です。個々の従業員のパフォーマンス傾向、部門ごとの評価のばらつき、ハイパフォーマーの特徴、スキル保有状況などを定量的に分析し、その結果を人事戦略(採用、配置、育成、昇進・昇格など)の見直しや、経営判断に活用することができます。例えば、特定のスキルを持つ人材が不足していることがデータで明らかになれば、ターゲットを絞った採用活動や研修プログラムを企画できます。データを活用することで、より客観的で根拠に基づいた人事施策を展開することが可能になります。
改善プロセスの標準化とナレッジ共有
運用の中で発見された問題点や、それに対する改善策、成功事例などを組織内で共有し、ナレッジとして蓄積していくことも重要です。トラブルシューティングの手順や、効果的だった運用方法などを標準化・マニュアル化することで、属人化を防ぎ、組織全体の運用レベルを底上げすることができます。
まとめ:成功する人事評価システム導入への確かな一歩
人事評価システムの導入失敗は、目的の不明確さや共有不足、自社に合わないツール選定、関係者の関与不足、評価制度そのものの問題など、複数の要因が重なって発生します。これらを回避するには、目的の明確化と共有、自社に適したシステム選び、経営層・管理職の積極的な関与、従業員への丁寧な説明、そして制度自体の見直しと体制整備が不可欠です。さらに、導入後の継続的な改善やセキュリティへの配慮も重要です。人事評価システムは単なるツールではなく、組織変革の起点となる存在です。導入を成功させるためには、事前の準備と導入後の運用改善を丁寧に進め、従業員のエンゲージメント向上と企業成長につなげる視点が求められます。


