更新日:2025/10/28
福利厚生の食事補助ガイド|人気サービスについても紹介

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
この記事の目次はこちら
はじめに
従業員の健康、物価高騰による生活への影響、そして激化する人材獲得競争。現代の企業経営者が直面するこれらの課題に対し、福利厚生、特に「食事補助」が極めて有効な解決策として再注目されています。従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある会社を作る上で、「食」のサポートは従業員の満足度に直接的に働きかける強力な一手となり得ます。
しかし、いざ食事補助の導入を検討しようにも、 「どのような提供方法があり、自社に合うのはどれか?」「導入コストや管理の手間はどれくらいかかるのか?」
といった疑問や不安から、導入に踏み切れない決裁者様や管理部責任者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年の最新情報を踏まえ、食事補助を福利厚生として導入するメリットから、担当者が必ず押さえるべき多様なサービスの比較、そして自社に最適なサービスの選び方まで、網羅的かつ体系的に解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、食事補助に関するあらゆる疑問を解消し、貴社の成長戦略に貢献する最適な制度導入を実現するための知識を全て得ることができます。
【比較表】福利厚生のおすすめサービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 福利厚生の内容 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
置き菓子やドリンクの提供 おやつ ドリンク コーヒー スイーツパン グラノーラ おつまみ プロテインバー ヴィーガン そうざい など |
BeeNii

|
|
初期費用:0円 月額料金:0円 ギフト代:有料 ※月次でまとめて請求 |
記念日に合わせて自動でギフトを贈る「ギフトスケジューリングサービス」 |
Office Stand By You
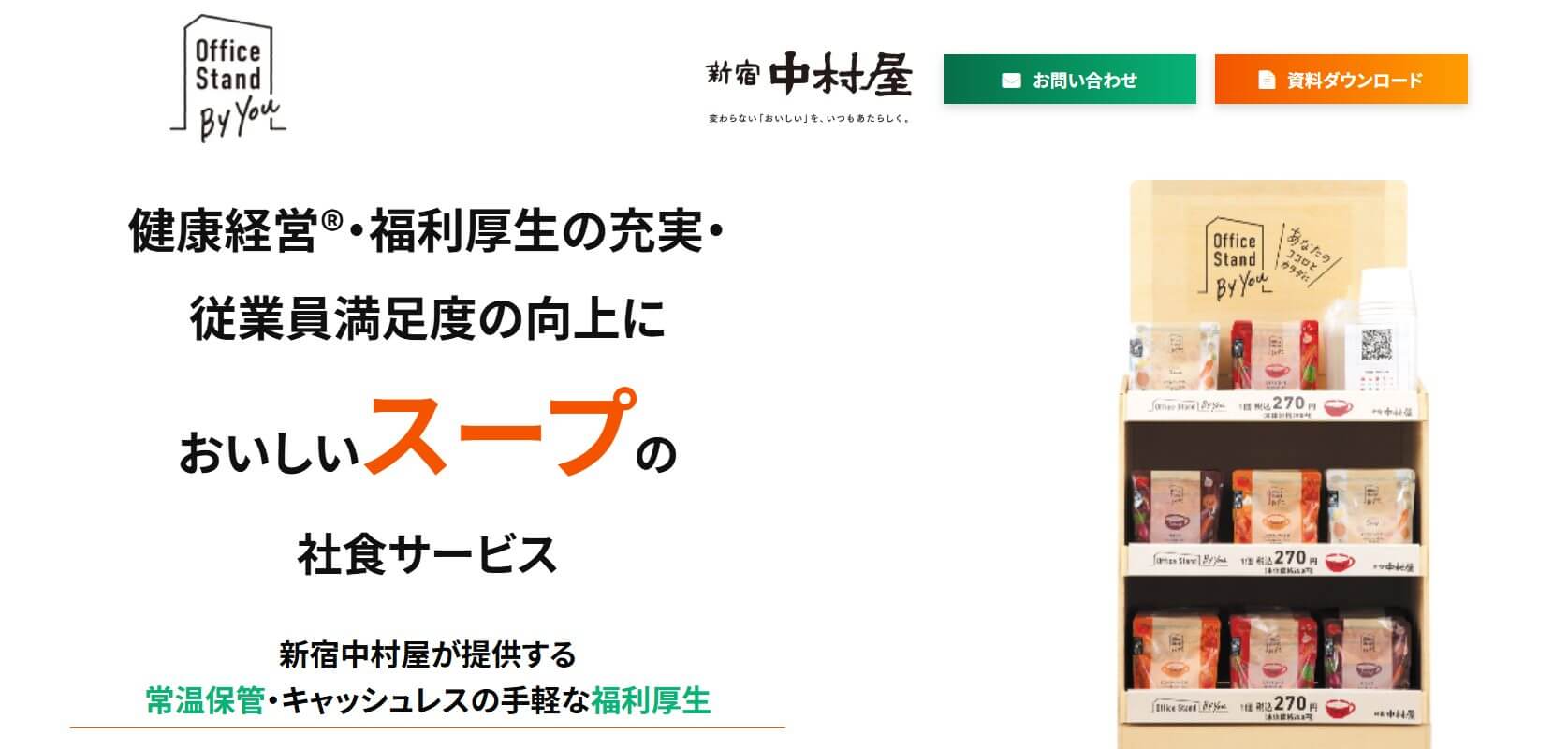
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
常温保存可能なスープの提供 |
シャショクラブ

|
|
初期費用:0円
ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |
お弁当の配達 |
| Perk |
|
要お問い合わせ | さまざまなジャンルのサービスを特別価格で利用できる「割引き特典」とコンビニやカフェで利用できるチケットに交換できる「ポイント制度」を提供 |
| Resort Worx |
|
要お問い合わせ |
旅行に特化した福利厚生サービス リゾートエリアの会員施設やホテルの宿泊を30~80%割引で利用可能 |
| OFFICE DE YASAI |
|
要お問い合わせ | サラダやカットフルーツ、お惣菜など約140品目をオフィスに設置した冷蔵庫に常設、食事補助により従業員の健康をサポート |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 管理栄養士が監修した主食・主菜・副菜がオフィスに設置した冷蔵庫または自動販売機に届く置き型社食サービス |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 全国25万店以上の加盟飲食店で利用できる電子カード型の食事補助サービス |
| WELBOX |
|
要お問い合わせ | 介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行・エンタメなど幅広いラインナップから、企業の課題に応じてサービスを選べる |
| ライフサポート倶楽部 |
|
要お問い合わせ | 宿泊・レジャーといった余暇支援から介護・育児のサポートまで幅広いメニューから自由にサービスを利用できる |
| ベネフィット・ステーション |
|
Netflix得々プラン:1,850円(月額/1名) Netflixプラン:1,350円(月額/1名) 学トクプラン:1,200円(月額/1名) 得々プラン:1,000円(月額/1名) |
グルメやレジャー、ショッピングからeラーニング、育児・介護・引っ越しなどのライフイベントに関わるものまで、140万以上のサービスを勇退価格で利用できる |
| 福利厚生倶楽部 |
|
要お問い合わせ | 余暇支援・日常支援・健康支援・学習支援の4軸を中心に、約12万・350万種以上のサービスを提供 |
| オフィスグリコ |
|
要お問い合わせ | 職場にお菓子やドリンクなどの商品を届ける設置型サービス |
| TsugiTsugi |
|
65,000円~/月 ※平日/土日、宿泊日数によって料金は異なります |
シティホテルからリゾートホテル、温泉旅館、グランピン施設など、定額で全国の宿泊施設に泊まれるサービス |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 月額費用:0円 配送料:0円 ※システム利用料はお弁当代に含まれます |
利用者とお弁当屋さんをつなぐ決裁システム。会社請求払いにすることで、食事補助の福利厚生として利用可能 |
| chocoZAP法人会員 |
|
要お問い合わせ | chocoZAPを初めとするRIZAPの8つのブランドを特典的に利用できる、法人向け福利厚生サービス |
| yui365 |
|
要お問い合わせ | 従業員の好みに合わせた世界に一つのオリジナルデジタルカタログを作成するサービス |
| セラヴィリゾート泉郷 |
|
要お問い合わせ | 宿泊施設が運営する余暇支援の福利厚生サービス |
| カフェテリアHQ |
|
要お問い合わせ | 数問のアンケートからAIが適したアイテムを個別提案する福利厚生サービス |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
・お弁当 ・パスタ ・チャーハン ・お惣菜 ・お菓子 ・ドリンク ・おにぎり ・パン ・ヨーグルト ・豆腐バー ・アイスクリームなどの提供 ※取り扱い商品は300種類以上 |
なぜ今、福利厚生で「食事補助」が重要視されるのか?
食事補助は、単に従業員の空腹を満たすためのコストではありません。企業の持続的成長を支える「人的資本への戦略的投資」として、今まさにその重要性が高まっています。ここでは、決裁者が知るべき4つの経営的意義を解説します。
1. 従業員の健康を支える「健康経営」の推進
従業員の健康は、企業の生産性に直結する最も重要な経営資源です。バランスの取れた食事は、生活習慣病の予防やメンタルヘルスの安定に繋がり、従業員のパフォーマンスを最大限に引き出します。食事補助を通じて、企業が従業員の健康を積極的にサポートする姿勢を示すことは、「健康経営」を実践する上で非常に有効です。健康な従業員が増えれば、欠勤率の低下(アブセンティーイズムの改善)や、出社していても不調で生産性が上がらない状態(プレゼンティーイズム)の改善が期待でき、長期的には医療費負担の軽減にも繋がります。
2. 物価高騰下での実質的な賃上げ効果
昨今の物価高、特に食料品価格の上昇は、従業員の家計を圧迫する大きな要因です。企業が食事代の一部を補助することは、従業員にとって可処分所得が増えることと同義であり、実質的な賃上げとして非常に喜ばれます。特に、非課税枠を活用すれば、企業も従業員も税や社会保険料の負担なく、効率的に従業員の生活を支援できます。これは、給与を直接引き上げることとは異なるアプローチで、従業員の経済的な安心感を醸成し、ロイヤリティを高める効果があります。
3. 社内コミュニケーションの活性化
社員食堂や休憩スペースでの食事は、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションを生み出す貴重な機会です。普段の業務では接点のないメンバーとの雑談から、新たなアイデアが生まれたり、部門間の連携がスムーズになったりすることもあります。食事補助は、従業員がオフィスに集まり、顔を合わせるきっかけを作り出し、組織の一体感や風通しの良い企業文化を育む土壌となります。
4. 採用市場における企業の魅力向上
福利厚生の充実は、求職者が企業を選ぶ上で重要な判断基準の一つです。特に「食事補助あり」という具体的な制度は、求職者にとって企業の魅力を分かりやすく伝えるメッセージとなります。「従業員の健康や生活を大切にする会社」というポジティブなブランドイメージは、採用競争において他社との明確な差別化要因となり、優秀な人材を引きつける強力な磁力となるでしょう。データによっては、食事補助の導入が応募数を平均20%増加させるという報告もあります。
食事補助の主な種類とメリット・デメリット徹底比較
食事補助を導入するにあたり、どのような提供形態があるのか、それぞれの特徴を理解することが重要です。ここでは、代表的な5つの種類について、メリット・デメリット、コスト感などを比較解説します。
1. 社員食堂(設置型)
企業内に調理設備と食事スペースを設け、従業員に温かい食事を提供する形態です。
- メリット:栄養バランスの取れた温かい食事を提供でき、従業員満足度が非常に高い。社内コミュニケーションのハブとなる。
- デメリット:導入・運営コスト(設備投資、人件費、食材費)が非常に高額。広いスペースが必要。専門の運営会社への委託が一般的。
- 向いている企業:従業員数が多く、福利厚生に大きな投資ができる体力のある大企業。
2. 宅配弁当
提携する弁当業者が、毎日オフィスに従業員分の弁当を届ける形態です。
- メリット:社員食堂に比べて導入コストを大幅に抑えられる。日替わりなどメニューの選択肢がある。
- デメリット:注文の取りまとめや代金の徴収といった管理工数が発生する。個人のアレルギーや好みに完全に対応するのは難しい。リモートワーカーは利用できない。
- 向いている企業:毎日一定数の出社が見込める中小企業。
3. 食事券・チケット
提携する飲食店(コンビニ、レストランなど)で利用できる食事券を従業員に配布する形態です。
- メリット:従業員が自分の好きなタイミングで、好きな店舗・メニューを選べるため満足度が高い。
- デメリット:食事券の購入・配布・管理に手間がかかる。利用履歴の管理が難しく、利用率の正確な把握が困難な場合がある。
- 向いている企業:オフィス周辺に飲食店が多い企業。
4. 外部サービス委託(アプリ・カード型)
専用のICカードやスマートフォンアプリを通じて食事代を補助する、近年主流の形態です。
- メリット:全国の主要なコンビニや飲食店チェーンで利用できるため、勤務地やリモートワークなど働き方を問わず全従業員が公平に利用できる。管理部門はシステム上で利用状況を一元管理でき、工数が大幅に削減される。
- デメリット:サービス提供会社への月額利用料が発生する。
- 向いている企業:リモートワーカーを含む全従業員に公平な福利厚生を提供したい、管理工数を削減したい全ての規模の企業。
5. 設置型(オフィスコンビニ・社食サービス)
オフィスの一角に専用の冷蔵庫や什器を設置し、惣菜や軽食、飲料などを24時間いつでも購入できる形態です。
- メリット:小スペースから導入可能で、時間や場所を問わず利用できる。食事だけでなく、休憩時間の間食などにも対応できる。
- デメリット:提供されるのは基本的に惣菜や軽食であり、温かい食事の提供は難しい場合が多い。商品の補充や管理が必要。
- 向いている企業:勤務時間が不規則な従業員が多い企業や、食事補助を手軽に始めたい企業。
自社に合った食事補助サービスの選び方【5つのポイント】
多様な食事補助サービスの中から、自社にとって最適なものを選ぶためには、明確な判断軸を持つことが重要です。ここでは、決裁者・管理部責任者がサービスを選定する上で比較すべき5つのポイントを解説します。
ポイント①:導入・運用コスト
費用は最も重要な選定基準の一つです。確認すべきは、初期導入費用、従業員1人あたりの月額利用料、そして食事の原価です。特に、月額利用料は固定費となるため、慎重に比較する必要があります。単に価格が安いだけでなく、提供されるサービスの価値と見合っているか、費用対効果(ROI)の視点で評価しましょう。複数社から見積もりを取り、料金体系の透明性を確認することが不可欠です。
ポイント②:管理部門の運用工数
新たな制度の導入は、管理部門の業務負担増加に繋がりがちです。従業員の利用申請、利用状況の集計、業者への支払い、給与からの天引き処理など、どれくらいの工数がかかるのかを事前に確認する必要があります。特に、管理システムが使いやすいか、給与計算ソフトと連携できるかといった点は、日々の業務効率を大きく左右します。工数削減を重視するなら、管理業務を自動化できる外部委託サービスが有力な選択肢となります。
ポイント③:利用対象者と公平性(リモートワーク対応)
福利厚生は全従業員に公平に提供されるべきものです。自社の従業員構成や働き方を考慮し、全ての従業員が利用できるサービスを選びましょう。特に、リモートワーカーや地方拠点、外回りの営業職の従業員が多い場合、オフィス内でしか利用できない社員食堂や宅配弁当では不公平感が生じます。全国のコンビニや飲食店で利用できるカード・アプリ型のサービスは、働き方や場所を問わず公平な機会を提供できる点で優れています。
ポイント④:利用できる店舗・メニューの多様性
従業員満足度を大きく左右するのが、食事の選択肢の豊富さです。特定のチェーン店しか利用できない、メニューが固定されている、といったサービスでは、すぐに飽きられて利用率が低下する可能性があります。提携している店舗数やジャンルの広さ、アレルギー対応の可否、健康に配慮したメニューの有無などを確認し、従業員の多様なニーズに応えられるサービスを選びましょう。
ポイント⑤:導入までのスピードとサポート体制
契約してから実際にサービスを利用開始できるまでの期間や、導入プロセスにおけるサポートの手厚さも重要です。専任の担当者がついて導入を支援してくれるか、導入後に従業員からの問い合わせに対応するコールセンターなどが整備されているかを確認します。信頼できるパートナーとして、長期的に伴走してくれるサポート体制を持つ企業を選ぶことが、制度を円滑に運用していくための鍵となります。
【2025年最新】主要食事補助サービス比較ガイド
ここでは、先の「5つの選び方のポイント」に基づき、現在市場で高い評価を得ている主要な食事補助サービスを比較・解説します。
1. チケットレストラン(株式会社エデンレッドジャパン)
国内導入実績No.1を誇る、ICカード型の食事補助サービスです。
- 特徴:全国25万店以上の飲食店やコンビニで利用可能。利用店舗数が圧倒的に多く、場所や時間を問わず利用できるため、公平性が非常に高いのが最大の強みです。専用の管理システムで運用工数を大幅に削減でき、非課税ルールにも完全準拠しています。
- 向いている企業:リモートワーカーや地方拠点の従業員を多く抱える企業。管理工数を最小限に抑え、公平な福利厚生を実現したい全ての企業。
2. オフィスおかん(株式会社OKAN)
オフィスに設置した専用冷蔵庫に、管理栄養士監修の惣菜を届ける設置型社食サービスです。
- 特徴:1品100円からという手軽さで、24時間いつでも利用可能。ご飯と組み合わせれば定食になり、夜食や間食にも対応できます。導入が簡単で、小規模オフィスにもフィットします。
- 向いている企業:手軽に食事補助を始めたい中小企業。勤務時間が不規則な従業員が多い企業。
3. びずめし(Gigi株式会社)
「ごちめし」というアプリをベースにしたサービスで、地域の飲食店を応援するというコンセプトを持っています。
- 特徴:従業員が利用すると、その地域の加盟店に直接的にお金が流れる仕組みです。企業のCSR活動の一環としてもアピールできます。リモートワーカー向けに自宅へ食事を届けるプランもあります。
- 向いている企業:地域貢献や社会貢献に関心の高い企業。従業員の居住地が多様な企業。
4. OFFICE DE YASAI(株式会社KOMPEITO)
オフィスに新鮮なサラダやフルーツ、健康的な惣菜を届ける設置型のサービスです。
- 特徴:”野菜”に特化しており、従業員の健康意識向上に直接的に貢献します。設置する冷蔵庫のサイズなども選べ、導入ハードルが低いのが魅力です。
- 向いている企業:従業員の健康増進、特に食生活の改善を強く推進したい企業。
5. 社食DELI(株式会社FREAK OUT)
複数の弁当業者から日替わりで好きな弁当を選べる、宅配弁当のマッチングプラットフォームです。
- 特徴:契約は1社でも、様々なブランドの弁当が届くため、飽きずに利用できます。低価格帯の弁当から健康志向の弁当まで選択肢が豊富です。
- 向いている企業:出社スタイルの従業員が中心で、手軽に多様な弁当を提供したい企業。
失敗しない導入プロセスと運用のコツ
優れた食事補助サービスを導入しても、その後の運用次第で効果は大きく変わります。制度を形骸化させず、その価値を最大限に引き出すために、管理部門が押さえるべきプロセスとコツを解説します。
導入プロセス(ロードマップ)
福利厚生を導入する際は以下の手順で検討すると良いでしょう。
- ニーズ調査と目的設定:まず社内アンケート等で、利用したい食事の形態、自己負担額の許容範囲、健康志向度などを定量的に調査します。その上で「健康経営の推進」「実質賃金の補助」など、制度導入の目的を明確化します。
- 予算試算と制度設計:参加率や補助額を想定し、複数パターンの費用を試算します。その上で、非課税要件(自己負担50%以上、企業補助3,500円/月以下)を厳守した制度を設計します。
- ベンダー選定:複数のサービス提供会社から提案を受け、デモやトライアルを活用して実際の使い勝手を確認します。費用だけでなく、運用サポート体制も重視して、自社に最適なパートナーを選びます。
- 社内周知とローンチ:導入が決定したら、説明会を開催し、制度の詳細や利用方法を分かりやすく解説します。イントラネットにマニュアルを常設し、リマインドメールを送るなど、丁寧な周知活動が成功の鍵です。
- 効果測定と改善:導入後は、KPI(利用率、満足度、健康指標の変化など)を定期的にレビューします。従業員からのフィードバックを基に、メニュー内容や運用方法を見直し、PDCAサイクルを回し続けます。
運用のコツ
- 定期的なプロモーション:四半期ごとに利用促進キャンペーンを実施したり、社内報で利用体験を紹介したりして、制度への関心を維持します。
- フィードバックの仕組み化:簡単なアンケート機能を活用するなど、従業員がいつでも意見や要望を伝えられる窓口を用意します。
- 他制度との連携:食事補助を健康増進キャンペーンや社内イベントと連動させることで、より高い相乗効果が期待できます。
まとめ
本記事では、福利厚生としての食事補助について、多様なサービスの種類と比較、そして導入・運用のポイントまで、決裁者・管理部責任者様が知るべき情報を網羅的に解説しました。
食事補助は、物価高騰下で従業員の生活を直接的に支援し、健康経営を推進することで、組織の生産性を高める極めて費用対効果の高い「戦略的投資」です。採用市場での競争力を高め、優秀な人材の定着を促す上でも、その効果は計り知れません。
この記事でご紹介した知識や比較ポイントを活用し、ぜひ貴社に最適な食事補助制度の導入をご検討ください。従業員の笑顔と健康を支えるこの一手は、必ずや企業の明るい未来を築くための大きな力となるはずです。
【比較表】福利厚生のおすすめサービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 福利厚生の内容 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
置き菓子やドリンクの提供 おやつ ドリンク コーヒー スイーツパン グラノーラ おつまみ プロテインバー ヴィーガン そうざい など |
BeeNii

|
|
初期費用:0円 月額料金:0円 ギフト代:有料 ※月次でまとめて請求 |
記念日に合わせて自動でギフトを贈る「ギフトスケジューリングサービス」 |
Office Stand By You
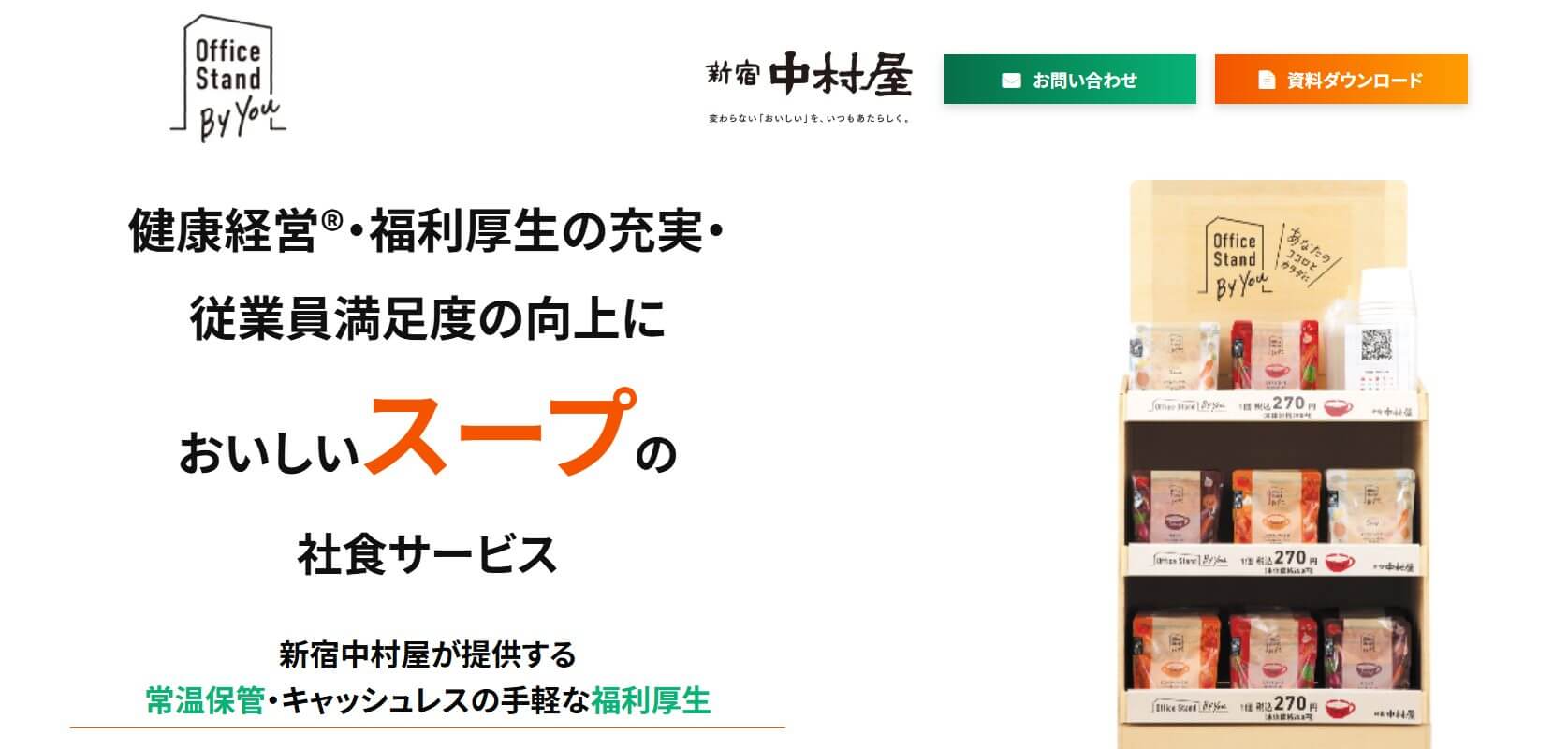
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
常温保存可能なスープの提供 |
シャショクラブ

|
|
初期費用:0円
ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |
お弁当の配達 |
| Perk |
|
要お問い合わせ | さまざまなジャンルのサービスを特別価格で利用できる「割引き特典」とコンビニやカフェで利用できるチケットに交換できる「ポイント制度」を提供 |
| Resort Worx |
|
要お問い合わせ |
旅行に特化した福利厚生サービス リゾートエリアの会員施設やホテルの宿泊を30~80%割引で利用可能 |
| OFFICE DE YASAI |
|
要お問い合わせ | サラダやカットフルーツ、お惣菜など約140品目をオフィスに設置した冷蔵庫に常設、食事補助により従業員の健康をサポート |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 管理栄養士が監修した主食・主菜・副菜がオフィスに設置した冷蔵庫または自動販売機に届く置き型社食サービス |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 全国25万店以上の加盟飲食店で利用できる電子カード型の食事補助サービス |
| WELBOX |
|
要お問い合わせ | 介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行・エンタメなど幅広いラインナップから、企業の課題に応じてサービスを選べる |
| ライフサポート倶楽部 |
|
要お問い合わせ | 宿泊・レジャーといった余暇支援から介護・育児のサポートまで幅広いメニューから自由にサービスを利用できる |
| ベネフィット・ステーション |
|
Netflix得々プラン:1,850円(月額/1名) Netflixプラン:1,350円(月額/1名) 学トクプラン:1,200円(月額/1名) 得々プラン:1,000円(月額/1名) |
グルメやレジャー、ショッピングからeラーニング、育児・介護・引っ越しなどのライフイベントに関わるものまで、140万以上のサービスを勇退価格で利用できる |
| 福利厚生倶楽部 |
|
要お問い合わせ | 余暇支援・日常支援・健康支援・学習支援の4軸を中心に、約12万・350万種以上のサービスを提供 |
| オフィスグリコ |
|
要お問い合わせ | 職場にお菓子やドリンクなどの商品を届ける設置型サービス |
| TsugiTsugi |
|
65,000円~/月 ※平日/土日、宿泊日数によって料金は異なります |
シティホテルからリゾートホテル、温泉旅館、グランピン施設など、定額で全国の宿泊施設に泊まれるサービス |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 月額費用:0円 配送料:0円 ※システム利用料はお弁当代に含まれます |
利用者とお弁当屋さんをつなぐ決裁システム。会社請求払いにすることで、食事補助の福利厚生として利用可能 |
| chocoZAP法人会員 |
|
要お問い合わせ | chocoZAPを初めとするRIZAPの8つのブランドを特典的に利用できる、法人向け福利厚生サービス |
| yui365 |
|
要お問い合わせ | 従業員の好みに合わせた世界に一つのオリジナルデジタルカタログを作成するサービス |
| セラヴィリゾート泉郷 |
|
要お問い合わせ | 宿泊施設が運営する余暇支援の福利厚生サービス |
| カフェテリアHQ |
|
要お問い合わせ | 数問のアンケートからAIが適したアイテムを個別提案する福利厚生サービス |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
・お弁当 ・パスタ ・チャーハン ・お惣菜 ・お菓子 ・ドリンク ・おにぎり ・パン ・ヨーグルト ・豆腐バー ・アイスクリームなどの提供 ※取り扱い商品は300種類以上 |


