更新日:2026/02/13
「第3の賃上げ」で従業員満足度UP! 代表的な4つのタイプやサービスの比較軸、運用までの具体的なステップを徹底解説


【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
「従業員のランチ環境をよくしたいが、食堂を新設するだけの予算もスペースもない」といった課題を抱える人事・総務担当者は少なくありません。物価高が続く中、実質的な負担を軽減する施策として注目されているのが、社食サービスの導入です。これは給与を直接引き上げるのではなく、食の福利厚生を通じて従業員の可処分所得を増やす「第3の賃上げ」ともいわれています。
本記事では、社食サービスが従業員満足度に与える影響を整理した上で、代表的な4つの社食サービスタイプを解説します。さらに、自社に適したサービスを選ぶための比較軸もご紹介するので、下記の比較表を参考に、まずは気になるサービスを3つ以上選び、資料請求・問い合わせをしてみましょう。
従業員満足度を高める社食サービス選定にぜひお役立てください。
※本記事の内容は2026年2月の情報です
【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス
scroll →
| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |
|---|---|---|---|
snaq.me office(スナックミーオフィス)

|
|
初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |
設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |
オフィスで野菜

|
|
要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |
設置型 |
Office Stand By You
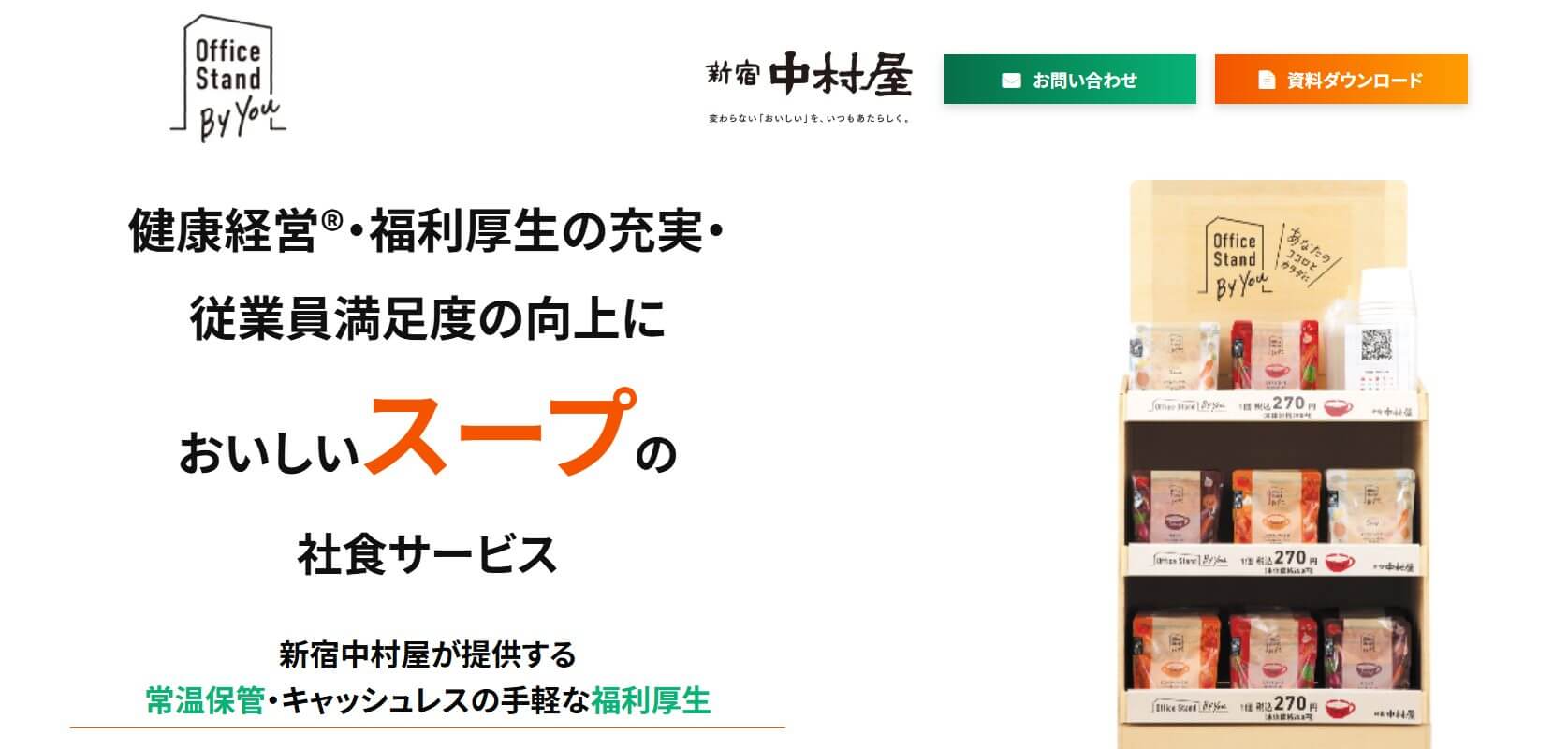
|
|
要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |
設置型 |
シャショクラブ

|
|
初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |
お弁当型 |
| オフィスおかん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |
| オフィスプレミアムフローズン |
|
企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |
設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| オフィスでごはん |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| ESキッチン |
|
月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |
| KIRIN naturals |
|
要お問い合わせ | 設置型 |
| パンフォーユー オフィス |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |
| セブン自販機 |
|
要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |
| チケットレストラン |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| どこでも社食 |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| 社食ごちめし |
|
要お問い合わせ | 外食補助型 |
| まちなか社員食堂 |
|
初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |
外食補助型 |
| 筋肉食堂Office |
|
要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |
| 社食DELI |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| おべんとうの玉子屋 |
|
お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |
お弁当型 |
| ごちクルNow |
|
初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |
お弁当型 |
| お弁当.TV |
|
要お問い合わせ | お弁当型 |
| はらぺこ |
|
要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |
| nonpi Chef’s LUNCH |
|
要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |
| 500円出張食堂 |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |
出張社内提供型 |
| DeliEats DR |
|
初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |
お弁当型 |
| オフィスコンビニTUKTUK |
|
要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |
設置型 |
この記事の目次はこちら
なぜ「食の支援」が従業員満足度を高めるのか?
「食の福利厚生」は、単なる昼食の提供にとどまりません。近年は、物価高や人材獲得競争の激化を背景に、企業の経営戦略の一環として再評価されています。特に、従業員満足度の向上やエンゲージメント強化を目的とする場合、食の支援はコストではなく「投資」と位置づけられて行われる施策となっているのです。
本章では、従業員の経済的メリット、時間価値の向上、健康維持の3つの観点から、従業員満足度に与える影響を解説します。
食生活の充実やコスト負担の軽減
近年の物価高は、日々のランチ代にも大きな影響を与えています。外食価格やコンビニ商品の値上げが続き、従業員にとって昼食は確実に家計を圧迫する固定費となりつつあります。しかし企業が賃上げを実施したくても、原材料費やエネルギーコストの高騰により、恒常的なベースアップが難しいケースも少なくありません。
こうした状況で注目されているのが、食事補助制度の活用です。一定の要件を満たせば、企業が負担する食事補助は福利厚生費として計上でき、税務上は非課税扱いとなります(国税庁の定める要件に基づく)。同額を給与として支給する場合と比べ、企業・従業員双方に税制上のメリットがあるため、実質的な手取り増加につながります。
この仕組みは、給与そのものを引き上げるのではなく、生活コストを直接下げることで可処分所得を増やす施策、いわば「第3の賃上げ」といえます。従業員は毎日のランチという身近な支出が軽減されることで、企業からの支援効果を実感しやすくなるでしょう。こうした「体感できる支援」は、心理的安全性の向上や組織への信頼醸成にも寄与し、従業員満足度の向上が期待できるのです。
ランチタイムの効率化や選択肢の提供

オフィスビルでは、昼休みになるとエレベーター前に長い列ができ、近隣のコンビニではレジ待ちの行列が発生します。移動や待ち時間だけで10分、15分と消費してしまうケースも珍しくありません。結果として実質的な休憩時間が削られ、十分にリフレッシュできないまま午後の業務に戻ることになります。近くに飲食店が少ない、コンビニが遠いオフィスの場合、そもそも昼食を確保すること自体が従業員にとって負担になっている可能性もあるでしょう。
社食サービスや設置型の食事提供を導入すれば、オフィス内で食事を完結できます。これは単なる利便性の向上ではなく、タイムパフォーマンスの改善ともいえます。また社食サービスで多様な昼食を提供できれば、ランチの選択肢を広げることにもつながります。
60分の休憩時間を移動や行列待ちではなく、食事と休息に充てられる環境は、午後の集中力や生産性に直結します。短時間で栄養バランスの取れた食事を確保できれば、余った時間を軽い仮眠や同僚とのコミュニケーションに活用することも可能です。こうした小さな積み重ねが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
従業員の健康維持
忙しさや時間不足から、コンビニ弁当や高カロリーな外食に偏りがちになると、栄養バランスの乱れが懸念されます。塩分や脂質、糖質に偏った食生活が続けば、従業員の生活習慣病のリスクが高まる可能性もあります。その点、企業が野菜を多く取り入れたメニューや低糖質・高たんぱくといった健康配慮型の食事を提供すれば、従業員の健康維持を後押しすることが可能です。
「会社が自分たちの体を大切にしてくれている」というメッセージは、単なる福利厚生以上の意味を持ちます。企業からの配慮を実感できる環境は、帰属意識を高め、離職防止にも寄与します。健康的な食事の提供は、短期的な満足度向上だけではなく、中長期的な人的資本への投資としても機能するでしょう。経済産業省が推進する健康経営の考え方においても、従業員の健康増進は企業価値向上の重要な要素とされています。
自社に合うのはどれ? 社食サービス4大タイプの特徴
社食サービスと一口にいっても、その提供形態は多様化しています。重要なのは価格の単純比較ではなく「自社の課題にどのタイプが適しているか」という視点です。例えば、24時間稼働の現場を抱える企業と、リモートワーク中心の組織とでは、適した提供形態は異なります。本章では代表的な4つのタイプを、課題解決の観点から整理して解説します。
【設置型】24時間利用可能でフレキシブルな働き方を支援
設置型は、オフィス内に専用棚や冷蔵庫、自動販売機などを設置し、従業員が自由に商品を購入できるスタイルです。お菓子や惣菜、サラダ、フルーツ、冷凍食品などを常備し、無人で運用できる点が特長とされています。
このタイプが適しているのは、シフト勤務や夜間対応、残業が発生しやすい企業です。近隣の店舗が閉まっている時間帯でも利用できるため「好きな時に食べられる」という自由度の高さが従業員満足度につながります。ランチに限らず、朝食や軽食としても活用できる点は、フレキシブルな働き方との親和性が高いです。
また野菜や低糖質メニュー、無添加惣菜など健康志向の商品を扱うサービスも多く、健康経営を推進する企業にとっても導入しやすい形態です。例えば、ナッツや焼き菓子、プロテインバー、コーヒーなどを提供する「snaq.me office」、サラダやフルーツ、サンドイッチ、お惣菜などを提供する「OFFICE DE YASAI」、一日の野菜摂取量の⅓を取れるパウチタイプのスープを提供する「Office Stand By You」などがあります。
「外に買いに行く時間がない」「不規則な勤務体系に対応したい」という課題を持つ企業には、設置型が有力な選択肢となります。
【宅配・デリバリー型】毎日の楽しみとバリエーションを提供
宅配・デリバリー型は、日替わり弁当をオフィスへ届ける、あるいは対面販売形式で販売スタッフが来訪するスタイルです。温かい食事を提供できるサービスもあり、満足度の高さが特長です。
このタイプが適しているのは「ランチに楽しみを持たせたい」「マンネリ化を防ぎたい」と考える企業です。毎日異なるメニューが提供されることで、従業員は選ぶ楽しさを感じられます。日替わりの工夫や地域性のあるメニューは、ランチタイムを単なる栄養補給の時間ではなく、気分転換・リフレッシュの時間へと昇華させます。
代表的なサービスとしては、豊富なラインナップを展開する「社食DELI」、スマートフォンで注文したお弁当を指定場所まで届けてくれる「シャショクラブ」、洋風・和風・中華風などの日替わり弁当が届く「おべんとうの玉子屋」などが挙げられます。
「毎日のランチが楽しみになる環境をつくりたい」「従業員のコミュニケーションのきっかけをつくりたい」といった課題を持つ企業には、宅配・デリバリー型が適しています。
【店舗提携・チケット型】外回りやリモートワークにも公平に対応
店舗提携・チケット型は、全国の加盟店やコンビニなどを社食として利用できる仕組みです。従業員は提携店舗で食事を購入し、企業は一定額を補助します。
このタイプの最大の特長は「公平性」です。営業職や外回りの多い職種、あるいはリモートワーク中心の従業員でも、オフィス勤務者と同様に社食サービスを利用できます。オフィス内設置型ではカバーしにくい働き方にも対応できるため、不公平感の解消につながります。
代表例としては、全国の加盟店で利用できる「チケットレストラン」や、幅広い飲食店・コンビニで利用可能な「どこでも社食」があります。また加盟店舗で社割を利用できる「まちなか社員食堂」などが挙げられます。
多拠点展開やハイブリッドワークを導入している企業にとっては、物理的制約を受けにくいこのタイプが現実的な選択肢となります。
【ケータリング・出張型】イベント性があり社内コミュニケーションを活性化
ケータリング・出張型は、会議室などでブッフェ形式や温かい食事を提供するスタイルです。日常的なランチ補助というよりも、イベントや特別な日の施策として活用されるケースが多い傾向にあります。
このタイプの強みは「同じ釜の飯」を共有することによるコミュニケーション活性化です。部門横断の交流やキックオフミーティングなどで活用すれば、組織の一体感を醸成できます。食事を囲む時間は心理的な距離を縮めやすく、エンゲージメントの向上に寄与します。
代表例としては、シェフが出張して温かい料理を提供する「nonpi Chef’s LUNCH」、比較的低コストでブッフェ形式を実現する「500円社員食堂」などがあります。
「社内コミュニケーションを強化したい」「イベントとして特別感を演出したい」といった目的には、ケータリング・出張型が適しています。
このように、社食サービスは一律ではありません。自社の課題が「時間」なのか「公平性」なのか「健康」なのか、それとも「コミュニケーション」なのかを整理することで、自社に適した社食サービスのタイプが見えてきます。
先述したような具体的な社食サービスを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
失敗しないサービス選定のための5つの比較軸
社食サービスは、導入そのものがゴールではありません。社内稟議を通す際に「なぜこのサービスなのか」を合理的に説明できるか、そして運用開始後に「思っていたのと違う」というミスマッチを防げるかが重要です。ここでは、導入担当者が必ず確認しておきたい5つの比較軸を解説します。
1. コスト負担(初期費用・固定費・一食当たりの従業員負担)
コスト負担は、企業視点と従業員視点の両方で確認する必要があります。
まずは企業視点でのポイントです。初期費用については、設置型であれば冷蔵庫や什器の設置費、宅配型であれば契約時の最低注文数や保証金などが発生する場合があります。サービスによっては棚や冷蔵庫を貸与してもらえるものもあるため、実質無料で導入できるケースもあるでしょう。しかしそれ以上に重要なのは、月額固定費や配送費です。
どのタイプにも最低利用料が設定されている可能性があるため、中長期的にコストを負担し続けることが可能か、導入前にしっかりと検討しておく必要があります。また配送費についても月額固定費に含まれているケースや、廃棄がある場合の引き取り料を別途負担する必要があるケースなどがあります。これらの見えないコストについても見積もり時に確認しておくのが望ましいです。
次に商品代の利用負担についても、重要なポイントです。一食当たりの負担割合を「企業が全額負担」「企業と従業員が一定割合で負担」「従業員が全額負担」などから選択できる場合があります。
「企業がどこまで補助するのか」「従業員はいくら支払うのか」といったバランス設計によって利用率が変わる可能性があります。会社負担が少なすぎれば「お得感」が薄れ、従業員満足度向上にはつながりにくくなります。一方で、補助額が大きすぎれば財務負担が増し、継続性に課題が生じます。
このように初期費用や月額の固定費といった年間のトータルコストと、利用想定人数から1人当たりの実質コストを試算することが不可欠です。
2. 運用負荷(発注・在庫管理・決済の手間・ゴミ処理)
見落とされがちなのが、総務部門の工数です。社食サービスの導入によって発注作業、数量調整、在庫管理、売上集計、請求処理などの作業が発生すると、それ自体が隠れたコストになります。
そのため発注が自動化されているか、在庫補充をサービス側が行うのか、キャッシュレス決済に対応しているか、といった点は必ず確認すべきです。また、弁当容器の回収やゴミ処理のルールも重要です。回収対応があるのか、廃棄物処理は社内で行う必要があるのかによって、日々の運用負荷は大きく変わります。
「便利そう」に見えても、総務の負担が増えれば長続きしません。導入前に運用フローを具体的に描き、誰がどの業務を担うのかを明確にしておくことが、失敗回避の鍵となります。
3. スペース要件(冷蔵庫1台分か、配膳スペースが必要か)
物理的な制約も重要な判断材料です。設置型であれば、冷蔵庫や自動販売機を置くためのスペースと電源が必要です。通路を塞がないか、消防法上の問題はないかといった確認も求められます。
宅配・デリバリー型の場合は、販売スペースや受け渡し場所、電子レンジの台数などが課題になります。昼休みに利用が集中する場合、温め待ちの行列が発生すれば、かえって不満を招きかねません。
ケータリング・出張型の場合も、食事を並べるスペースをどのくらい確保するべきか、従業員が並ぶ場所はあるかといった確認をする必要があります。
「置けるかどうか」ではなく、「スムーズに利用できるか」という視点で検討することが重要です。レイアウト変更の必要性や、将来的な従業員増加も見据えた判断が求められます。
4. 利用可能時間と対象者(内勤・外勤・シフト制への対応)
自社の働き方に合っているかどうかも、選定の分かれ目です。先述の通り、内勤中心の企業と、外回りが多い営業組織、あるいは夜勤を含むシフト制の現場では、適した形態は異なります。
例えばオフィス内限定の設置型では、外回りやリモートワークが多い従業員は利用できません。その結果「使える人」と「使えない人」が生まれ、不公平感が生じる可能性があります。従業員の出社回帰を図りたいといった理由でなければ、従業員満足度を高めるどころか、逆に低下させるリスクをはらみます。
「誰が、いつ、どこで使えるのか」を具体的に洗い出し、全体適用の観点で検討することが不可欠です。
5. 食事の質と目的(従業員のニーズ、健康経営への寄与)
最後に重要なのが、提供される食事の中身です。若年層が多い職場と、幅広い年代が在籍する組織では、求められるメニューが異なります。健康志向の高まりを踏まえた野菜中心メニューを重視するのか、ボリューム重視のガッツリ系を求めるのかによって、選ぶべきサービスは変わります。
また日常的なランチ補助が目的なのか、イベントとしての特別感を演出したいのかも明確にする必要があります。メニューが固定化されるとマンネリ化し、利用率が低下するケースもあります。従業員のニーズを把握した上で、バリエーションの豊富さや季節性、入れ替え頻度なども確認すべきポイントです。
これら5つの比較軸を整理することで「導入後に後悔する」リスクを大幅に減らせます。感覚的な判断ではなく、コスト・運用・空間・働き方・目的という観点から自社の要件を明確にし、適した社食サービスを選定することが重要です。
社食サービス導入までの4つのステップ
社食サービスは、適切なステップを踏まずに導入すると利用率が思ったよりも伸びず、形骸化する恐れがあります。一方でしっかりと準備すれば、従業員満足度を高める有効な施策として定着させることが可能です。ここでは、検討から運用開始までの具体的な4ステップを提示します。
Step1:社内アンケートによるニーズの可視化
最初に行うべきは、業者選定ではありません。自社の従業員が何を求めているのかを把握することが出発点です。具体的には「1食当たりいくらなら利用したいか」「どのようなメニューを希望するか(健康志向・ボリューム重視など)」「週に何回程度利用したいか」といった項目をアンケートで可視化します。
特に、価格帯の希望を把握せずに補助額を決めてしまうと「高くて使えない」「安いが魅力がない」といったミスマッチが生じる恐れがあります。また、内勤・外勤・シフト制など働き方の頻度も確認しておくことが重要です。
ニーズを数値で把握できれば、社内稟議の際にも「従業員の〇%が導入を希望している」といった根拠を示せます。従業員のニーズを明らかにすることは、経営層の理解を得る上でも欠かせないステップです。
Step2:無料トライアルと試食会の実施
候補を絞り込んだら、無料トライアルや試食会を実施します。味の確認はもちろん重要ですが「運用の回しやすさ」もチェックできます。例えばゴミの量はどの程度か、容器回収はあるか、補充の頻度はどれくらいか、ピーク時に混雑は発生しないかといった点を実際に体験します。
トライアル期間中に利用率や従業員の反応を観察することで、本格導入後の姿を具体的にイメージできます。導入後に「想定より手間がかかる」と気づくのでは遅いため、必ず検証フェーズを設けましょう。
Step3:コスト試算と税務メリットを生かした制度の設計
導入を決める前に、年間コストを試算します。想定利用人数、1食当たりの補助額、月間利用回数を掛け合わせ、総額を算出します。その際、税務上の取り扱いについて確認が欠かせません。
国税庁の定める要件では、以下の2点を満たす場合、食事補助は福利厚生費として取り扱われ、給与課税の対象外となります。
- 従業員が食事代の50%以上を負担していること
- 会社の負担額が1人当たり月額3,500円(税抜)以下であること
この枠内で制度設計を行えば、同額を給与として支給するよりも税制上のメリットが生まれます。企業側は社会保険料の増加を抑えられ、従業員側も課税対象とならないため、実質的な手取り増につながります。
2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、食事補助の上限を7,500円までに引き上げる旨が明記されました。これが可決・成立すれば、1984年以来据え置かれた上限が更新される可能性があります。
まさに「第3の賃上げ」として機能させるためには、この非課税枠を意識した設計が重要です。
※参考:国税庁.「No.2594 食事を支給したとき」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm ,(参照2026-02-10).
※参考:財務省.「令和8年度税制改正の大綱」.https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf ,(参照2026-02-10).
Step4:利用率を高める社内周知
制度を整え、社食サービスの導入が決定したら、従業員に向けて周知と初期浸透を行いましょう。どれほど魅力的な制度でも、知られていなければ利用されません。導入初期の盛り上がりが、その後の定着率を大きく左右します。
まずは、従業員全員の目に触れるチャネルを活用しましょう。社内掲示板やチャットツールでの告知、イントラネットでの特設ページ公開、社内報での特集記事掲載などが有効です。開始日、利用方法、価格、補助内容を分かりやすくまとめ「なぜ導入したのか」という目的まで伝えることで、企業の姿勢が明確になります。
また初動を加速させる施策として、期間限定のキャンペーンも効果的です。例えば、最初の1週間は会社負担割合を一時的に引き上げる、初回利用者に特典を付けるなどの工夫により、「一度試してみよう」という心理的ハードルを下げられます。最初の体験がポジティブであれば、その後の継続利用につながりやすくなります。
商品のラインナップが定期的に変わるサービスであれば、メニュー変更のアナウンスも継続的に行うことも重要です。「今週のおすすめ」「季節限定メニュー」といった情報を発信することで、従業員が社食を楽しみにする文化を醸成できます。
一定の手間はかかりますが、こうした周知と定着施策を丁寧に行うことで、社食サービスは単なる福利厚生ではなく、従業員満足度向上を実現する戦略的施策として機能します。導入後こそが本番であるという意識を持ち、継続的な運用を心がけましょう。
まとめ
社食サービスは、単なるランチの提供手段ではありません。物価高による生活コストの増加や働き方の多様化、健康経営への対応など、企業が直面する複数の課題に対する実践的な解決策です。本記事でご紹介したような4つの社食サービスタイプの特徴、そして失敗しないための比較軸や導入ステップを参考に、自社に適した社食サービスを選び、企業の課題解決につなげましょう。
ミスマッチや形骸化を防ぐためには、自社の課題が「コスト負担の軽減」なのか、「公平性の確保」なのか「コミュニケーション活性化」なのかを明確にし、それに合った形態を選ぶことが重要です。適切に設計・運用された社食サービスは、従業員満足度を高めるだけでなく「従業員を大切にする企業」というメッセージを社内外に示すことにもつながります。
まずは以下の「社食サービス比較表」から気になるものを2~3つ選び、資料請求や無料トライアルの問い合わせをしてみましょう。従業員満足度の向上につながる社食サービスの選定にぜひお役立てください。

