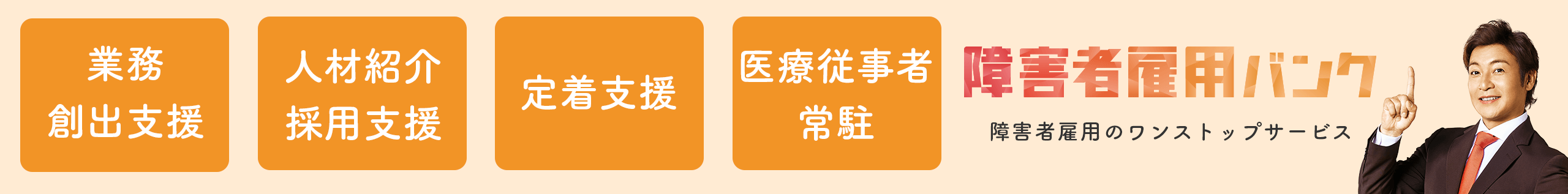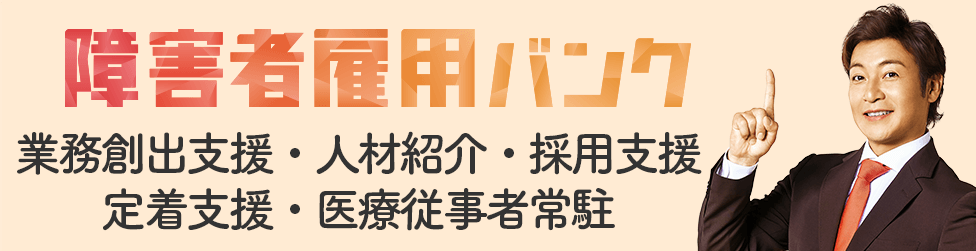中小企業こそ障害者雇用を!メリット・課題、助成金、導入5ステップを徹底解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
深刻化する人手不足、そして多様性が求められる現代において、企業の持続的な成長には新たな人材戦略が不可欠です。その有力な選択肢の一つが「障害者雇用」です。しかし、多くの中小企業の経営者や人事責任者の方々は「大企業の話だろう」「うちはリソースがないから難しい」と考えているのではないでしょうか。
実は、その認識はもはや過去のものです。法改正により、障害者雇用の義務は着実に中小企業へと広がっています。厚生労働省の統計によれば、法定雇用率を未達の中小企業は約6割にのぼり、多くの企業が対応を迫られているのが現実です。しかし、この変化は単なる「コスト」や「負担」ではありません。豊富な助成金の活用、組織の活性化、そして新たな人材の確保など、中小企業こそ享受できる大きな経営メリットが数多く存在するのです。
本記事では、中小企業が障害者雇用を「他人事」から「戦略的投資」へと転換するために知るべき全てを解説します。法的義務の基本から、具体的なメリット、直面しがちな課題とその解決策、そして明日から始められる導入手順まで、網羅的にご紹介します。
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
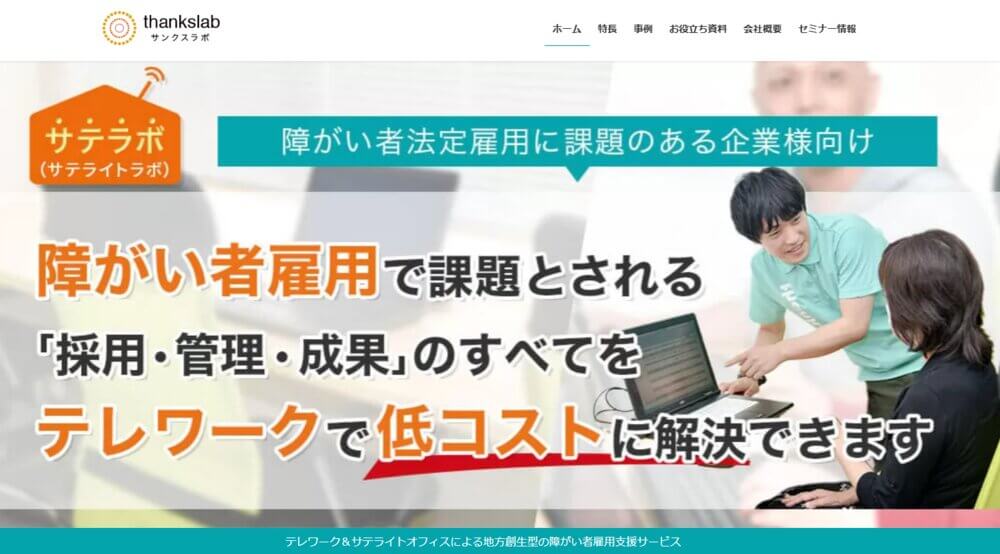
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
もはや他人事ではない。中小企業における障害者雇用の現状と法的義務
障害者雇用について、まず押さえるべきは大前提となる法律上の義務、すなわち「障害者雇用率制度」です。これは、企業がその規模に応じて、一定の割合で障害のある方を雇用することを義務付ける制度であり、この法定雇用率は社会情勢を反映して定期的に見直されています。そして今、その対象が着実に中小企業へと拡大しているのです。
最も重要な変更点は、法定雇用率の段階的な引き上げです。
- 2024年4月〜:法定雇用率2.5%(対象:従業員40.0人以上の企業)
- 2026年7月〜:法定雇用率2.7%(対象:従業員37.5人以上の企業へ拡大見込み)
このように、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、年々広がっています。これまで「うちはまだ大丈夫」と思っていた企業も、数年後には義務の対象となる可能性が非常に高いのです。
では、もしこの法定雇用率を達成できなかった場合、どうなるのでしょうか。従業員100人超の企業で法定雇用率が未達の場合、不足している人数に応じて1人あたり月額5万円の「障害者雇用納付金」を支払う必要があります。これは罰金ではありませんが、実質的なコスト負担であることは間違いありません。
従業員100人以下の企業には現在、納付金の支払義務はありませんが、だからといって何もしなくて良いわけではありません。ハローワークから雇入れに関する計画書の作成命令などの行政指導が入り、適切な対応が求められます。指導に従わない場合、特に悪質と判断されれば、企業名が公表されるリスクもゼロではありません。コンプライアンスが厳しく問われる現代において、法定雇用率の遵守は、企業の社会的責任と信頼性を担保する上で不可欠な要素となっているのです。
中小企業こそ障害者雇用を推進すべき5つの経営メリット
障害者雇用を単なる「義務」として捉えるのは非常にもったいないことです。特にリソースが限られる中小企業にとって、障害者雇用は多くの経営メリットをもたらす「戦略」となり得ます。ここでは、決裁者・人事責任者として知っておくべき5つの具体的なメリットを解説します。
豊富な助成金・税制優遇でコスト負担を大幅に軽減
国は障害者雇用を強力に推進しており、手厚い支援策を用意しています。採用、設備の導入、定着支援など、様々なフェーズで活用できる助成金が存在し、これらを活用することで初期投資やランニングコストを大幅に抑えることが可能です。特に、中小企業の場合は大企業よりも助成金の支給額が手厚く設定されているケースが多く、制度の恩恵をより大きく受けられます。法令遵守とコスト軽減を両立できるのは、中小企業にとって大きな魅力です。
深刻な「人手不足」の解消と新たな人材の確保
多くの業界で人手不足が叫ばれる中、採用チャネルの拡大は喫緊の課題です。ハローワークには、働く意欲と能力を持つ多くの障害のある方が登録しています。これまでアプローチしてこなかった人材層に目を向けることで、競争が激化する採用市場において、新たな才能を発掘できる可能性が大きく広がります。貴社が必要とするスキルや経験を持つ人材が見つかるかもしれません。
組織の活性化とダイバーシティの推進
多様な背景を持つ人材が加わることは、組織に新しい視点と価値観をもたらします。障害のある社員が働きやすいように業務プロセスを見直す過程で、既存の非効率な作業が発見され、組織全体の生産性が向上することがあります。また、「どうすれば分かりやすく伝わるか」を考える文化は、社員間のコミュニケーションを円滑にし、マネジメント層のスキルアップにも繋がるなど、組織全体に好影響を及ぼします。
企業の社会的責任(CSR)とイメージ・信用力の向上
障害者雇用への積極的な取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たす姿勢を内外に示す強力なメッセージとなります。これは、金融機関からの融資評価や、公共事業の入札、大手企業との取引において、企業の信頼性を測る指標の一つとなり得ます。また、SDGsへの関心が高い現代において、求職者、特に若い世代は企業の社会貢献意識を重視する傾向にあり、採用活動における大きなアピールポイントにもなります。
新たな業務の創出と組織全体の生産性向上
「任せる仕事がない」という悩みは、業務を見直すチャンスです。障害のある社員に任せる業務を切り出す過程で、これまで曖昧だった業務内容が整理・マニュアル化されることがあります。これにより、他の社員が本来集中すべきコア業務に専念できる環境が整い、結果として組織全体の生産性が向上します。障害者雇用は、単に人員を増やすだけでなく、組織の業務改革を促すきっかけにもなるのです。
【課題別】中小企業が障害者雇用でつまずかないための解決策
多くのメリットがある一方で、中小企業が障害者雇用を進める上では特有の課題も存在します。しかし、これらの課題は、適切な知識と外部のサポートを活用することで乗り越えることが可能です。ここでは代表的な3つの課題とその解決策を提示します。
課題①:「採用ノウハウがなく、どんな人を採用すればいいか分からない」
多くの中小企業には、障害者採用の専門部署や経験豊富な担当者がいるわけではありません。「どんな障害のある方を」「どの業務で」「どのように採用すればいいのか」といったノウハウ不足は、最初にして最大の壁と言えるでしょう。
解決の糸口:採用をサポートする専門機関を徹底的に活用する。
自社だけで悩む必要は全くありません。まず相談すべきは、無料で利用できるハローワークの専門援助部門です。企業の状況を伝えれば、適切な人材の紹介や求人票作成のアドバイスを受けられます。また、各地の障害者就業・生活支援センターも、企業と障害のある方の橋渡し役を担っています。さらに踏み込んだサポートが必要な場合は、障害者雇用に特化した民間の人材紹介サービスを活用するのも有効な手段です。
課題②:「任せられる業務の切り出しが難しい」
「うちの会社には、障害のある方に任せられるような単純な仕事はない」という声もよく聞かれます。専門的な業務が多い、あるいは少人数で全員が多岐にわたる業務をこなしている場合、この課題はより深刻になります。
解決の糸口:「新たな仕事を作る」のではなく「既存の仕事を分解・再構築する」と考える。
特別な仕事を用意する必要はありません。まず、社員が日常的に行っている業務をすべて書き出し、細かく分解してみましょう。例えば「営業担当の仕事」の中には、資料作成、データ入力、アポイント調整、書類のファイリングなど、様々な作業が含まれています。これらの付随的な業務を切り出して組み合わせることで、新たなポジションを生み出すことが可能です。この業務の棚卸し自体が、業務効率化のきっかけにもなります。
課題③:「定着・マネジメントへの不安。現場の負担が増えそう」
採用後、現場の社員がどのように関わればいいのか、トラブルが起きたらどうしよう、といった定着・マネジメントへの不安も大きなハードルです。
解決の糸口:公的な定着支援制度と外部サービスで、現場の負担を軽減する。
ここでも、公的支援が役立ちます。ジョブコーチ(職場適応援助者)支援事業は、専門の支援員が職場を訪問し、本人と企業の両方に対して、業務の進め方やコミュニケーション方法について助言してくれる制度です。また、定期的な面談の実施は不可欠ですが、そのすべてを現場の上司や人事担当者が行う必要はありません。外部の定着支援サービスを利用すれば、専門のカウンセラーが定期的にフォローアップを行い、問題の早期発見と解決をサポートしてくれます。
【5ステップで解説】中小企業が障害者雇用を成功させるための導入手順
障害者雇用を何から始めればよいか分からない、という方のために、具体的な導入手順を5つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めることで、計画的かつスムーズに雇用を実現できます。
Step 1:社内理解の醸成と推進体制の構築
障害者雇用は、人事担当者だけが進められるものではありません。まず、経営層が「なぜ障害者雇用に取り組むのか」という目的やビジョンを明確にし、全社に向けてリーダーシップを発揮することが成功の第一歩です。その上で、実際に障害のある社員を受け入れる部署の社員を中心に、障害に関する基本的な知識やコミュニケーション方法についての研修会などを実施し、協力体制の土台を築きます。「何のためにやるのか」という共通認識と、歓迎する雰囲気がなければ、どんなに良い人材を採用しても定着は難しくなります。
Step 2:業務の切り出しと求人票の作成
次に、具体的に「どの部署で」「どんな仕事」を任せるのかを決定します。前述の通り、既存業務を細かく分解し、本人の特性を活かせそうな業務を切り出します。業務内容が決まったら、求人票を作成します。仕事内容はもちろんのこと、必要なスキル、職場の環境、そして「どのような配慮が可能か」を具体的に記載することが重要です。この情報が明確であるほど、応募者とのミスマッチを減らすことができます。
Step 3:支援機関を活用した採用活動
準備が整ったら、いよいよ採用活動のスタートです。ハローワークに求人を提出するのは基本ですが、同時に地域の障害者就業・生活支援センターや、特別支援学校の進路指導担当者などにも積極的にアプローチし、自社の魅力を伝えましょう。選考過程では、面接だけでなく、数日間の職場実習を受け入れることを強くお勧めします。実際に働いてもらうことで、本人は仕事内容や職場の雰囲気を、企業側は本人の適性を相互に確認でき、採用後の「こんなはずではなかった」というギャップを最小限に抑えることができます。
Step 4:受け入れ体制の整備と合理的配慮の準備
採用が決まったら、受け入れ準備を進めます。業務を教える指導役や、困ったときに相談できる窓口となる担当者を決め、事前に役割を伝えておきます。また、業務マニュアルを写真や図を使って分かりやすく整備したり、必要に応じて机や椅子の配置を変更したりといった物理的な準備も行います。最も重要なのは、本人と改めて面談し、「働く上で不安なこと」や「具体的に必要な配慮」を直接話し合って確認することです。「合理的配慮」は、企業が一方的に提供するものではなく、対話を通じて共に作り上げていくものです。
Step 5:雇用後のフォローアップと定着支援 雇
雇用開始後が、本当のスタートです。最初のうちは、本人も周囲も緊張しているものです。業務の指示は一度にたくさん出すのではなく、一つずつ具体的に伝えるなど、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。そして、定期的な面談の機会を必ず設けてください。週に1回、月に1回でも構いません。業務の進捗や困っていること、体調などを共有する場があるだけで、本人の安心感は大きく変わります。問題が起きた際は、社内だけで抱え込まず、採用を支援してくれた機関やジョブコーチに速やかに相談し、連携して解決にあたる姿勢が長期的な定着に繋がります。
中小企業が絶対に活用したい!障害者雇用の助成金・支援サービス一覧
障害者雇用を進める上で、中小企業にとって最大の味方となるのが、国が用意している手厚い助成金制度と無料の支援サービスです。これらを活用しない手はありません。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
採用・雇用継続で活用できる代表的な助成金
これらの助成金は、コスト負担を直接的に軽減してくれるため、経営者の意思決定を後押しします。申請には要件があるため、詳細は管轄の労働局やハローワークにご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
ハローワーク等の紹介により、障害者などの就職困難者を継続して雇用する事業主に対して支給されます。中小企業の場合、対象労働者や労働時間に応じて、1人あたり最大240万円(重度障害者の場合)が支給される可能性があり、インパクトの大きい助成金です。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者をまず3ヶ月間の有期雇用(トライアル雇用)で受け入れ、その適性や能力を見極めた上で常用雇用への移行を目指す制度です。トライアル雇用期間中、対象者1人あたり月額最大8万円(精神障害者の場合)が支給され、企業・求職者双方のミスマッチを防ぎながら採用を進められます。
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
職場への定着に課題を抱える障害者に対し、ジョブコーチによる支援など、柔軟な支援を行った場合に費用の一部が助成されます。定着支援にかかるコストを補填し、長期的な雇用を後押ししてくれます。
無料で相談・支援を受けられる公的機関
これらの機関は、ノウハウやリソースが不足しがちな中小企業にとって、非常に心強いパートナーとなります。
ハローワーク(公共職業安定所)
障害者専門の窓口があり、求人の申込みから人材紹介、助成金の申請受付まで、障害者雇用に関するあらゆる相談に対応してくれます。まず最初に訪れるべき場所です。
地域障害者職業センター
各都道府県に設置されており、事業主に対して、障害者の雇用管理に関する専門的な助言や、ジョブコーチ支援、リワーク支援など、専門性の高いサービスを無料で提供しています。
障害者就業・生活支援センター
障害のある方の就業面と生活面を一体的に支援する機関です。企業からの相談にも応じており、採用後の定着支援や、職場環境の調整に関する実践的なアドバイスをもらえます。
まとめ:障害者雇用は、中小企業の未来を拓く「戦略的投資」
本記事では、中小企業における障害者雇用の現状から、具体的なメリット、課題、そして導入手順までを網羅的に解説しました。法定雇用率の引き上げにより、障害者雇用はもはや避けて通れない「義務」となっています。しかし、それを単なる「コスト」や「負担」と捉えるか、企業の未来を拓く「戦略的投資」と捉えるかで、その結果は大きく変わります。
深刻な人手不足の解消、組織の活性化、業務プロセスの改善、そして社会的信用の向上。これらは、障害者雇用がもたらすメリットのほんの一部であり、リソースが限られる中小企業にとってこそ、その恩恵は計り知れません。
もちろん、ノウハウやリソースに不安を感じるのは当然のことです。しかし、ご紹介した通り、中小企業を支える手厚い助成金制度や、無料で活用できる公的な支援機関が数多く存在します。成功の鍵は、これらの外部リソースを最大限に活用し、自社だけで抱え込まないことです。
障害者雇用は、多様性を受け入れ、すべての社員が働きやすい環境を構築する試みです。そのプロセスは、必ずや貴社の組織風土をより良いものへと変え、持続的な成長の礎となるでしょう。もし、最初の一歩をどこから踏み出せばいいか迷っているのであれば、ぜひ一度、障害者雇用支援の専門家にご相談ください。