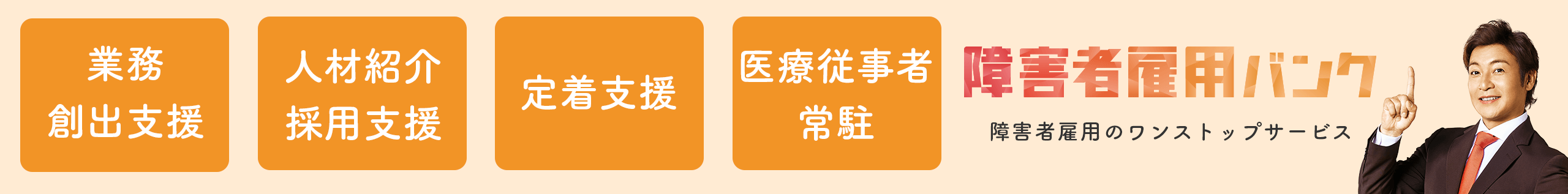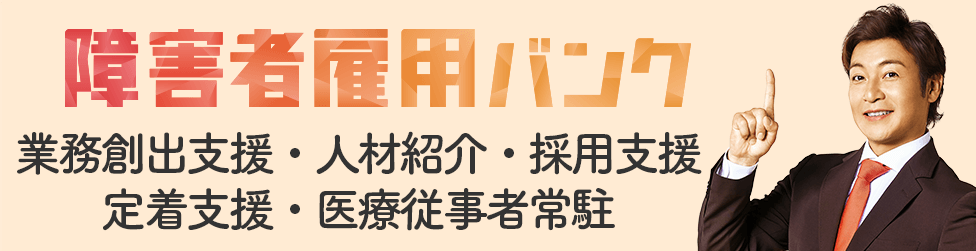障がい者雇用とは?一般雇用との違いやメリット活用できる助成金についてご紹介

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
昨今、企業の成長戦略においてダイバーシティやインクルージョンの推進は欠かせない要素となっています。企業が単なる利益追求のみならず、社会全体の発展に寄与する存在となるためには、幅広い人材を積極的に活用する必要があり、その中でも障がい者雇用は重要な取り組みとして認識されています。
障がい者雇用は、法令上の義務を果たすだけでなく、企業内部に多様な視点を取り入れることで、イノベーションの源泉となる可能性を秘めています。実際、障害を持つ従業員がもたらす独自の経験や感性は、従来の同質な人材採用では得難い発想を引き出し、組織全体の活性化を促進します。
また、企業が障がい者雇用に積極的に取り組む姿勢は、CSR活動や企業ブランドの向上にも直結します。市場や顧客、投資家、金融機関などのステークホルダーから、社会的責任を果たす企業として高い評価を受けるとともに、長期的には採用力強化や組織の安定経営に寄与する効果が期待されます。
本記事では、以下の点についてシンプルかつ要点に絞って解説します。
【主なポイント】
- 企業内での多様性確保が競争力やイノベーションを推進する
- 障がい者雇用はCSRやブランド価値の向上に寄与する
- 法令に基づく義務と合わせ、助成金制度などの経済的メリットを享受可能である
おすすめの障がい者雇用支援・就労支援サービス
scroll →
| 会社名 | 特長 | 費用 | 対応地域 |
|---|---|---|---|
株式会社HANDICAP CLOUD

|
|
要お問い合わせ | 全国(人材紹介・採用支援・定着支援・サテライトオフィス) |
株式会社JSH

|
|
要お問い合わせ(初期費用+月額費用) | 全国 |
株式会社エスプールプラス

|
|
要お問い合わせ |
全国 (関東・東海・関西エリアを中心に58カ所の農園を展開) |
サンクスラボ株式会社
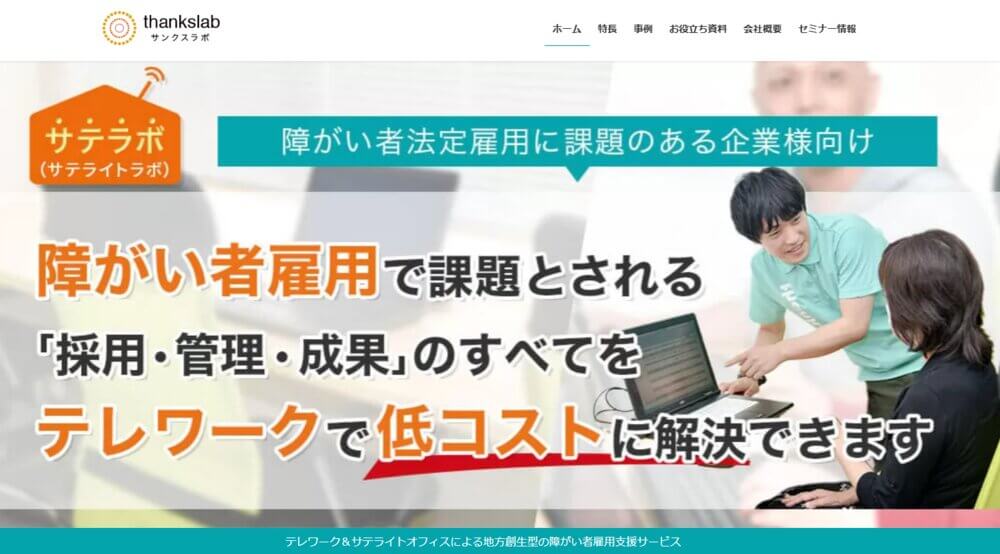
|
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
株式会社KOMPEITO

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
株式会社ワークスバリアフリー(DYMグループ)

|
|
要お問い合わせ | 全国 |
|
特定非営利活動法人 ウェルメント 
|
|
要お問い合わせ | 滋賀県 |
| 株式会社スタートライン |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社エンカレッジ |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社ゼネラルパートナーズ |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| マンパワーグループ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 全国 |
| パーソルダイバース株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 株式会社パレット |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| レバレジーズ株式会社 |
|
要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| サンクスラボ株式会社 |
|
初期費用0円 詳細については要お問い合わせ |
要お問い合わせ(サテライトオフィスは沖縄と九州) |
この記事の目次はこちら
障がい者雇用とは?
障がい者雇用とは、障害を有する方々を一般雇用枠の中で採用し、その能力に応じた業務を割り当て、職場での適切なサポートを実施する取り組みのことを指します。これは、単なる採用数の目標にとどまらず、共生社会の実現を目指す上で、障害を持つ方々が自立した生活を送るための就労機会を確保すると同時に、企業内に多様な視点を取り入れるための制度です。
法的背景としては「障がい者雇用促進法」が存在し、企業は一定規模以上の場合、法定雇用率(現在、民間企業では2.7%)の達成が義務づけられています。たとえば、常用労働者が1000人の企業であれば、最低でも27名の障がい者を雇用しなければならず、これを下回る場合には、不足1人ごとに月額50000円の納付金が発生します。
障がい者雇用が求められる背景
単に法令遵守のためだけではなく、障がい者が職場でその能力を十分に発揮できるよう、業務の配慮や環境整備を行う必要があることも意味しています。具体的には、障がい者手帳を保有する方々が対象となり、身体障害、知的障害、精神障害などの種類に応じて、必要なサポート体制が企業に求められます。
また、障がい者雇用は、法律に基づく数字としての義務だけでなく、障害を持つ従業員がもたらす独自の能力や視点を活かし、組織のイノベーションや業務改善を促進する点にも大きな意義があります。
法定雇用率の意義
法定雇用率は、企業が障がい者を採用する際の最低基準を示すとともに、採用数が不足した場合に経済的なペナルティを課す仕組みです。これにより、企業は障がい者雇用を積極的に実施せざるを得ない状況となります。
雇用対象とサポート体制
対象は主に各種障がい者手帳を有する方であり、場合によっては診断書などで障害の程度を確認されることもあります。企業は、受け入れ時に個別の配慮(バリアフリー化、適応研修、業務プロセスの改善)を実施することが求められます。
社会参加と企業の価値向上
障がい者雇用により、障がい者が労働市場に参加することで、社会全体の公平性が向上します。また、企業内部では、多様な人材が一堂に会することで、新たなアイデア創出や業務プロセス改善が期待され、企業価値の向上に寄与します。
障がい者雇用と一般雇用との違い
一般雇用と障がい者雇用は、いずれも労働市場における採用形態ですが、その目的と運用方法、さらには求められる配慮事項において顕著な違いがあります。
採用目的とプロセスの違い
一般雇用は、企業の業績や成長を支えるために、市場原理に則った人材を採用することを目的としています。これに対し、障がい者雇用は、法定雇用率の達成を目的としながら、同時に障害を持つ方々が持つ潜在能力を活かすための支援体制を重視します。
評価基準の違い
一般雇用では、即戦力としてのスキルや経験が評価されますが、障がい者雇用の場合、業務遂行能力だけでなく、障害特性に応じた合理的配慮が必要です。たとえば、採用時に必要な情報の開示や、面接における配慮事項、さらに職場への適応支援といった追加のプロセスが求められるため、選考プロセスそのものに柔軟な対応が必要となります。
受け入れ環境の整備
障がい者雇用の場合、単に採用するだけではなく、職場内のバリアフリー化、業務指示方法の工夫、コミュニケーションツールの活用など、受け入れ体制全体の整備が不可欠です。これに対し、一般雇用では、そのような特別な配慮は基本的には要求されません。
支援機関との連携
障がい者雇用では、ハローワークの専門窓口、地域障がい者職業センター、就労移行支援事業所など、外部の支援機関と連携するケースが多く見られます。これらの機関は、求職者の能力評価、研修、定着支援など、企業単独では困難な取り組みをサポートするため、採用活動全体のプロセスが異なります。
社会的意義
一般雇用が業績向上など経営効率を追求するものであるのに対し、障がい者雇用は、社会全体に対する包摂と公正さ、さらには企業の社会的責任(CSR)の観点からも高い評価を受ける施策です。これにより、企業は単なる採用数の達成を超えて、社会的信用やブランドイメージ向上といった側面で大きなメリットを得ることが可能です。
障がい者雇用のメリット
障がい者雇用の導入は、企業にとって単なる法定雇用の義務をクリアするためだけでなく、事業全体の競争力向上と組織活性化に大きく寄与する施策です。まず、多様な視点の融合により、従来の均一な採用では得られなかった新たな発想や問題解決の糸口が社内に生まれます。障害を持つ従業員が提供する独自の経験や感性は、既存の業務プロセスや製品・サービスの改善に大きなインパクトを与えるとともに、組織風土の刷新にもつながります。こうした多角的な視野は、市場環境の激変に柔軟に対応できる企業体質の醸成につながるため、経営戦略上非常に有効な資源となります。
また、障がい者雇用を積極的に実施することで、企業は社会的責任(CSR)を果たす姿勢を示し、取引先や顧客、投資家からの信頼を獲得できます。企業イメージが向上するとともに、地域社会における存在感やブランドバリューの上昇が期待でき、結果として採用活動やビジネスパートナーシップの強化へと波及します。さらに、障がい者雇用を実施することで、従業員間での相互理解やコミュニケーションの改善が進み、組織全体の連携力が向上する効果も見込まれます。
障がい者雇用で活用できる助成金制度
加えて、障がい者雇用には具体的な経済的メリットがあります。国や地方自治体は、障がい者雇用の推進を目的として、各種助成金・補助金制度を整備しています。たとえば、以下の制度があります。
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により障がい者を継続雇用する場合、一定期間の賃金補助が支給される制度です。対象者の障害の種類・程度に応じた支給額が設定されており、企業は法定雇用率を達成するための経済的負担を軽減できます。
トライアル雇用助成金
障がい者を原則3ヶ月間の試行雇用を実施し、その後常用雇用への移行を促す制度です。試用期間中の賃金補助が支給され、職場への適応状況を把握する良い機会となります。
障がい者雇用安定助成金
障がい者の職場定着を支援するため、職場支援員の配置や環境整備、復帰支援などに対して助成金が支給される制度です。これにより、導入後のサポート体制が充実し、離職防止や労働環境の継続的改善が促されます。
また、介助者の配置助成や職場適応援助など、障がい者が安心して働ける職場環境を整えるための支援も充実しています。企業がこれらの助成金制度を有効に活用するためには、内部での管理体制を整備し、必要な書類の管理や申請スケジュールの策定、さらには申請後の報告体制を確立することが重要です。制度自体は年度ごとに改定されることがあるため、最新の公的情報を常にチェックする必要があります。
障がい者雇用導入に向けた実践的な戦略
企業が障がい者雇用を効果的に導入し、そのメリットを実現するためには、戦略的な計画と全社的な取り組みが求められます。ここでは、導入前の準備から採用、定着支援に至るまでの実践的な戦略について具体的に解説します。
1. 社内体制の整備と経営層のリーダーシップ
障がい者雇用を成功させるための最重要ポイントは、社内全体での意識統一と連携体制の構築です。経営層は、障がい者雇用の意義を深く理解し、その取り組みを企業戦略の一部として明示的にサポートする必要があります。これにより、各部門が協力し、採用から定着支援に至るまでのプロセスが円滑に進むようになります。さらに、経営トップの明確な方針は、企業内外のステークホルダーへの信頼性向上にも寄与します。
2. 現状分析と課題の明確化
障がい者雇用の導入を円滑に進めるため、まず自社の現状を詳細に分析することが不可欠です。現状の採用状況、職場環境、既存の人材育成体制について、データや意見を基に現状把握を行い、どの部分に改善が必要かを明確にします。以下の点を重点的に検討します。
- 就業環境のバリアフリー化:物理的な障壁や、業務上のコミュニケーション手段の整備
- 必要な設備や支援ツール:車椅子利用、音声読み上げ、筆談ツールなど
- 柔軟な勤務制度の導入:短時間勤務の雇用形態やフレックスタイム制度の拡充
これらを踏まえて、企業ごとの課題と目標を明確に定め、改善策を計画的に実施することが、障がい者雇用の基盤を作ります。
3. 採用・研修・定着支援のプロセスの構築
障がい者雇用の成功には、採用だけでなく、その後の定着支援が欠かせません。採用段階では、障がい者向けの募集要項や選考基準の策定、さらにハローワークの専門窓口や地域の障がい者職業センター、就労支援機関との連携を強化します。
採用後は、以下のプロセスを整備します。
- 入社前のオリエンテーション:企業の方針、就労環境、社内ルールなどをしっかりと伝える。
- 業務開始後のサポート体制:専任の指導員の配置や、定期的な面談でのフォローアップ。
- 研修プログラムの充実:障がい者本人はもちろん、受け入れ部署の上司や同僚向けに、障害特性や合理的配慮に関する研修を実施し、全社的な理解を深める。
これにより、採用後の離職防止と、職場内での円滑なコミュニケーションが実現され、障がい者がその能力を存分に発揮できる環境が整えられます。
4. 助成金申請などの経済的支援策の活用
障がい者雇用の経済的な側面では、助成金制度の活用が非常に有効です。特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、障がい者雇用安定助成金などを、事前に最新の公的情報を確認した上で、適切に申請することが求められます。これらの制度を利用するためには、内部体制の整備が不可欠です。具体的には、申請に必要な書類の管理や、申請スケジュール、申請後の報告体制の構築を行い、助成金獲得に向けた業務プロセスを確立します。制度内容は年度ごとに変動するため、定期的に関係機関と連携し、情報更新を行うことも重要です。
5. 内外の情報共有とコミュニケーション戦略
障がい者雇用の導入は、社内だけでなく、外部の取引先や地域社会との連携によってその効果が最大化されます。経営層から現場まで、全社的に情報共有を行い、障がい者雇用の意義や進捗、改善点を定期的に議論する体制を整備します。特に、外部の専門機関や支援団体とのネットワークは、現場でのトラブルシュートや最新制度情報の取得に役立ち、結果として企業の総合的な取り組みの質を高めます。
また、社内向けには、社内報やセミナー、ワークショップなどを通じて、障がい者雇用に関する理解と共感を醸成し、組織全体のモチベーションの向上を図ることが推奨されます。
以上の戦略を体系的に実施することで、障がい者雇用は法定の枠を超えて、企業の成長戦略の重要な柱となると同時に、社会的な価値をも高める取り組みへと発展していくでしょう。各部署が連携し、計画的な導入と定着支援を行うことが、成功の鍵となります。
まとめ
本記事では、障がい者雇用とは?の基本概念から一般雇用との違い、企業にとっての多面的なメリット、そして具体的な助成金制度の活用方法や導入のための実践的戦略について解説しました。
障がい者雇用は、法定雇用率の達成のみならず、多様性の推進や組織の活性化、さらに経済的な支援制度の活用により、企業の持続的な成長へ大きく寄与します。企業内での環境整備、研修体制の充実、外部支援機関との連携を通じ、障害を持つ従業員がその能力を最大限に発揮できる職場を構築することが求められます。今後も法改正や助成金制度の変化に柔軟に対応し、全社的な取り組みとして障がい者雇用を戦略的に活用することが、企業の競争優位性と社会的信用向上の鍵となるでしょう。