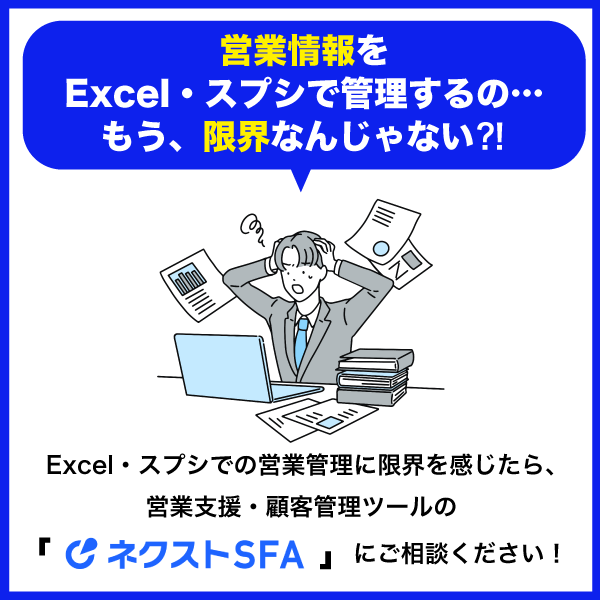更新日:2026/01/21

SFAの運用ガイド! 導入から定着までのポイントや失敗例をご紹介

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業部門の生産性向上や業務効率化を目指し、SFA(営業支援システム)の導入を検討する企業は増えています。しかし、SFAは導入するだけで成果が出るものではありません。うまく活用できなければ、せっかくのコストや労力が無駄になってしまう恐れもあります。
そこで本記事では、SFAの概要や、導入・運用時によくある失敗例、運用・定着化のポイントなどを分かりやすく解説します。これからSFAの導入を考えている企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次はこちら
SFAとは?
SFA(Sales Force Automation/営業支援システム)とは、営業活動に関する情報を一元管理し、業務の効率化や成果向上を支援するシステムです。商談情報や顧客データ、営業進捗、売り上げなどを可視化し、戦略的な営業活動をサポートします。
SFAを適切に活用すれば、営業部門全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
SFAを導入・運用する中での失敗例
SFAは営業の効率化や成果向上に役立つツールですが、導入・運用の過程で失敗してしまうケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗例をいくつかご紹介します。導入・運用前に把握しておき、同じ失敗を起こさないようにしましょう。
導入後に定着しなかった
せっかく時間やコストをかけてSFAを導入しても、社内で活用されず定着しないことがあります。
主な理由としては、入力項目が多く面倒に感じられる、機能が複雑で使いこなせない、入力ルールやフローが曖昧で従業員ごとに運用方法が異なる、といった点が挙げられます。
現場の業務負担が増えてしまった
SFA導入の目的の一つは業務の効率化ですが、適切に導入・運用できていない場合、かえって作業負担が増えてしまうこともあります。
例えば、詳細なデータを取得しようとして入力項目を増やしすぎた結果、現場の作業負荷が大きくなり、従業員の不満や活用離れにつながってしまうケースも見られます。
成果につながらなかった
SFAを導入して顧客情報や営業進捗、売り上げなどのデータを蓄積したものの、十分な分析や活用が行われず、成果に結びつかなかったという例もあります。SFAに蓄積したデータは、定期的に分析し、営業活動や業務改善に反映させることが重要です。分析を怠ると、せっかくSFAを導入したのにもかかわらず、効果が出なくなってしまいます。
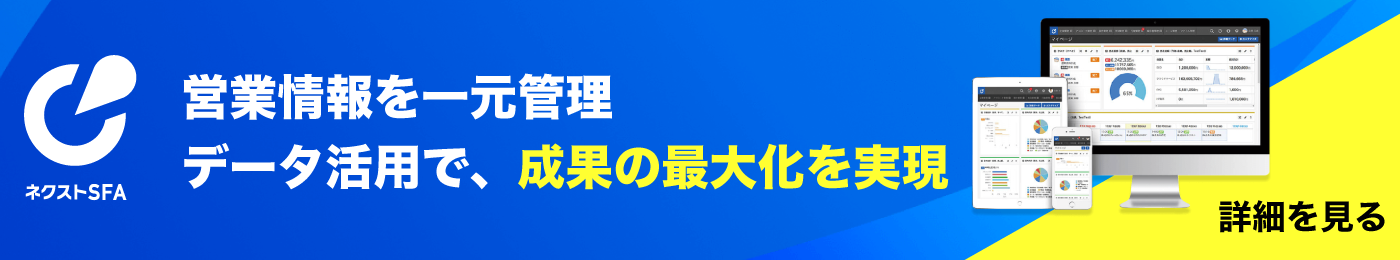

SFAの運用・定着化のポイント
SFAは、導入するだけでは十分な効果は得られません。実際に現場の従業員が日常業務で活用し、定着させてこそ成果につながります。もし社内で使われなければ、コストだけがかかってしまい、期待した効果が出ない可能性もあるでしょう。
ここからは、SFAの効果を発揮するための運用・定着化のポイントについて、導入前と導入後に分けてご紹介します。
SFA導入前のポイント
SFAを円滑に導入し、効果的に活用するためには、事前の準備が欠かせません。導入目的や活用イメージ、担当体制などを整理しておくことで、導入後に現場でスムーズに運用が進みやすくなります。導入前に押さえておくべき具体的なポイントを見ていきましょう。
SFAを導入する目的を整理する
SFAを有効活用するには、導入目的を明確にしておくことが重要です。目的や課題に応じて必要な機能を整理すれば、導入後に「必要な機能がなかった」という事態を防げます。
現場の従業員にもヒアリングを行い、実際に求められる機能や改善したい課題を把握することも有効です。
SFAの運用担当者を設ける
SFA導入の前後には、設定や操作方法に関する確認事項や、社内からの問い合わせが数多く発生します。ベンダーのサポートを受けられる場合もありますが、問題が発生した際に迅速に解決できる体制が整っていないと、現場はSFAの利用を負担に感じてしまいやすいです。まずは何かあったときに、社内で対応できる体制を整えておくことが大切です。
特にIT知識があり、現場業務にも詳しい人材をSFAの運用担当者として選定しておくと、導入後のトラブルや現場の負担感を減らせるでしょう。
現場の理解を得る
SFAを実際に活用するのは、基本的には現場の従業員です。そのため、導入の背景や目的、SFAを使うことで得られるメリットをしっかり伝えておきましょう。SFAを利用するには情報入力する必要があり、従業員にとっては負担に感じられることがあります。
あらかじめ「なぜ入力が必要なのか」「入力データがどのように活用されるのか」を理解してもらうことで、社内でSFAが定着しやすくなります。

自社に合ったSFAを導入する
一口にSFAといってもさまざまな製品があり、それぞれ機能や特徴が異なります。自社の導入目的や業務課題、求める機能、そして予算に応じて適したSFAを選定することが大切です。
気になるSFAがあれば、まずは資料請求やデモ依頼を行い、機能や使い勝手を確認した上で導入を進めましょう。
SFAの利用シーン・活用シナリオをまとめる
SFAを効果的に活用するには、「どの部門のどの担当者が、どのような場面でSFAを使い、蓄積したデータをどう活用するのか」を事前に整理しておくことが大切です。
例えば、経営層や営業マネージャー、営業担当者、マーケティング担当者など、それぞれの役割に応じてSFAの利用シーンは異なります。それらを明確にして社内に共有しておけば導入後の活用イメージを把握しやすく、SFAが社内に浸透しやすくなります。利用するデータの種類や頻度、利用目的まで具体的にまとめておきましょう。
SFAの入力項目や閲覧画面の設計をする
SFAの多くはカスタマイズ性が高く、自社の業務やフローに合わせた入力項目や画面設計が可能です。そのため、先述した利用シーンに合わせて、従業員が使いやすいように設計をしてみてください。
さらに、以下の点を確認しておくのがおすすめです。
- 自社で使っている他ツールとの連携できているか
- レポートやグラフは視覚的に分かりやすいものになっているか
- レポートやグラフは、条件設定やフィルタリングができるか
- 案件のページは、営業プロセスに沿って確認できるか
- 入力項目が多過ぎないか
- 利用ユーザーが入力しやすいUIになっているか
- 期限が過ぎたものに対して、アラート通知などを行えるか
- 利用ユーザーごとに権限設定が可能か
- 重要項目について、変更ログ管理を行える設計になっているか
SFAの運用ルールを策定する
SFAを導入する前に、明確な運用ルールを策定することが大切です。ルールが曖昧なままだと入力漏れや情報の不整合が生じやすく、結果としてSFAに集まるデータの信頼性が損なわれてしまいます。
各項目の入力・更新のタイミングや期限、ファイル添付の取り扱い、自由記入欄の書き方などについて基準を設けておきましょう。また、SFAに蓄積されたデータを活用し、定期的に営業活動の振り返りやフィードバックを行う仕組みも整えておくと、従業員の活用意識を高められます。運用ルールは現場の実態に即したものにし、必要に応じて見直せるようにしておくこともポイントです。

運用体制を整えておく
SFAをスムーズに定着させるためには、運用ルールだけではなく運用体制を整えておくことが大切です。SFAの利用時に生じる疑問や不具合への対応窓口を設けておくと、従業員が気軽に利用しやすいです。また、社内向けの利用マニュアルを作成し、仕様変更があった際にも迅速に情報を更新できる体制を整えておきましょう。
さらに、従業員からの改善要望を受け付ける窓口や、SFAを利用する従業員数を管理する仕組みなどを用意しておくと、長期的な運用がしやすくなります。
こうした準備が整っていれば、導入後もSFAが現場にしっかりと定着しやすくなるでしょう。
SFA導入後のポイント
SFA導入後は、継続的に活用状況を確認し、データを成果につなげていくことが大切です。SFA導入後の運用・定着化のポイントを見ていきましょう。
定期的にSFAの利用状況を確認する
SFA導入後は、運用状況の確認が欠かせません。定期的に利用状況を把握し、利用が進んでいない従業員には丁寧にフォローを行いましょう。また、会議や1on1の場でSFAのデータを共有・活用することで、従業員の意識付けにもつながります。こうした日常的な働きかけによって、SFAの定着を促すことができます。
SFAのデータを活用して成果向上につなげる
SFAに蓄積されたデータは、分析して活用することで初めて価値を生み出します。営業担当者ごとの強みや弱み、商談の傾向などを可視化することで、営業戦略の立案や改善に役立てられます。
データの活用が日常業務に行われるようになれば、営業成果の向上につながるでしょう。
他の部署ともデータを共有する
SFAに集まったデータは営業部門だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサポート部門とも共有するのが効果的です。
顧客データや営業状況を他部署と共有することで、商品やサービスの改善につなげられる他、部門間の連携強化にもつながります。情報共有がスムーズに行われることで、会議での報告や調整作業の負担も軽減され、全体的な業務効率化を期待できます。
定期的に運用ルールやフローを見直す
SFAの運用ルールや業務フローは、一度整備したら終わりではありません。実際、運用をしていく中で、課題や改善点は少なからず出てくるでしょう。
定期的に現場の声をヒアリングし、必要に応じてルールやフローを見直すことが、より良い運用につながります。柔軟に改善を重ねていくことで、SFAの定着率や活用効果も高まっていくでしょう。

まとめ
SFAは、導入するだけで成果が出るものではありません。事前に導入する目的や運用方針を整理し、現場の理解と協力を得ることが大切です。さらに、導入後も活用状況の確認やルールの見直し、部門を越えたデータ共有など、継続的な取り組みが求められます。
なお、SFAにはさまざまな製品があるので、自社のニーズや課題に合ったものを選ぶようにしましょう。
株式会社ジオコードが提供する「ネクストSFA/CRM」は、サービス継続率98.6%(2025年3月時点)という高い実績を持つSFAです。テレアポや営業活動などのアプローチ管理から、案件・受注管理、営業担当者の日報・週報・月報作成・管理まで、営業活動において必要な機能がしっかり搭載されています。さらにマーケティング活動を自動化・効率化するMA機能や、顧客管理をするCRM機能も搭載されているので、顧客に関するさまざまな業務の管理・効率化が可能です。
1名以上の専任担当者が付き、使い方の説明会やマニュアルの作成、定着後のフォローなどにも対応しているので、SFAの導入が初めての企業でも気軽に相談できます。
無料トライアルも受け付けているので、SFAを導入したいと考えている企業担当者の方はお気軽にお問い合わせください。