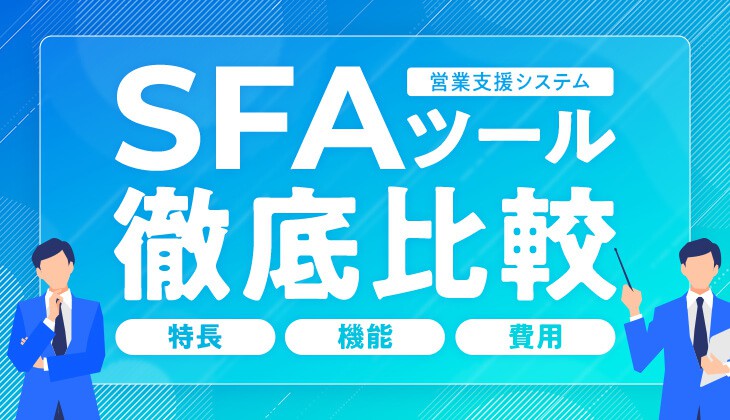更新日:2026/01/21

SFAツールとは?ツールの必要性や導入のメリット、主な機能、運用を成功させるコツを解説

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
労働生産性の向上に役立つシステムは複数ありますが、中でもSFAツールは営業活動の効率化に役立つツールとして多くの企業に導入されています。
本記事では、SFAツールの導入を検討している企業や、より良いSFAツールを探している方向けに、SFAツールの概要や導入するメリット、主な機能、ツール選びのポイント、注意点について解説します。
SFAツールをスムーズに導入するためのコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
SFAツールの導入を検討中の方はSFAツール比較記事も要チェック!


この記事の目次はこちら
SFAツールとは?
営業活動をスムーズに進めるには、顧客情報の管理や商談の記録、進捗の共有など、さまざまな業務を日々こなす必要があります。
そうした業務を効率化し、営業部門全体のパフォーマンスを高めるために活用されているのが「SFAツール(Sales Force Automation)」です。
SFAツールとは、営業活動のプロセスをデジタルで管理・支援するためのシステムのこと。顧客とのやり取りや案件の進行状況、日々の行動などを一元管理できるようになることで、「誰が・いつ・何をしているのか」が見える化され、営業チーム全体での情報共有や改善にもつながります。
従来はExcelや紙ベースで行われていた作業も、SFAを使うことで自動化・省力化され、担当者個人に依存しない営業スタイルが実現しやすくなります。
なお、似た言葉として「CRM」や「MA」といったツールもありますが、それぞれカバーする範囲や目的は異なります。これらの違いや関係性については、次のセクションでご紹介します。
SFA、CRM、MAの違いと関係性
SFAと並ぶビジネスをサポートするツールとして、CRMやMAがあります。いずれも営業支援に役立てられるため混同されがちですが、SFAとCRM、MAには明確な違いがあります。
まず、CRMはCustomer Relationship Managementの略称で、日本語では顧客関係管理を意味する言葉です。名前のとおり、企業が顧客と信頼関係を築き、商品やサービスのリピートを促すことを主目的としたツールで、顧客情報管理機能の他、メール配信、プロモーション管理、問い合わせ管理といった機能が備わっています。営業部門の他、マーケティング部門やカスタマーサクセス部門、カスタマーサポート部門などに導入されるケースが一般的です。
一方、MAはMarketing Automationの略称で、マーケティング活動全般を自動化することを目的としたツールです。具体的には、見込み客のデータの一元管理や、メール配信、商談の確度が高いリードの情報を営業部門に通知するなど、さまざまな業務を自動化することができます。MAは主にマーケティング部門に導入され、営業部門など他部門との連携強化に役立ちます。
このように、SFAとCRM、MAはそれぞれ導入目的や導入部門、機能などに違いがあるため、企業によっては3つのツールを併用しているところも多いようです。

SFAツールが求められる背景
近年、多くの企業でSFAツールの導入が進んでいる背景には、5つの理由があります。
企業間の競争の激化
現代日本は少子高齢化などの影響により、顧客のシェアを奪い合う競争が激化しています。同業他社に先んじてシェアを獲得するには、より効果的かつ効率的な戦略を立てなければなりません。
従来のアナログな手法による戦略では他社に後れを取る可能性が高く、競争が激化している業界ほどSFAツールの需要が高まっている傾向にあります。
労働生産年齢人口の減少
日本の労働生産年齢人口(15~64歳)は、1995年の8,716万5千人をピークに減少し始め、2022年には7,420万8千人まで落ち込んでいます(※)。国では今後も生産年齢人口は減少の一途を辿ると推測しており、2065年には約4,500万人になる見通しです(※)。
労働生産年齢人口の減少は、すなわち働き手の減少を意味するため、この先も産業や業界を問わず、慢性的な労働力不足に陥ることが懸念されています。
こうした状況の下、事業を存続していくためには従業員1人あたりの労働生産性を向上させることが必要不可欠であるため、業務効率化に役立つSFAツールに注目が集まっています。
※参考:参議院.「我が国の人口構造と人口推計」p4.https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/r06pdf/202423401.pdf ,(参照2024-10-18).
※参考:内閣府.「人口減少と少子高齢化」P1.https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/2zen2kai1-2.pdf ,(参照2024-10-18).

テレワーク・リモートワークの普及
2018年に成立した働き方改革関連法や、2020年初頭から全世界で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の影響により、ここ数年でテレワークやリモートワークを導入する企業が大幅に増加しました(※)(※)。
新型コロナウイルスが第5類に移行した現在、完全リモートワークを解除する企業も増えてきましたが、多くの企業では出社とリモートワークを併用するハイブリッドワークが定着しています。
リモートワーク中は自宅などオフィス外で働くことになるため、従業員間や部署間でのやり取りはオンライン上で行われることになりますが、電話やメールで情報やファイルをやり取りするのは非常に不便です。また、顧客とのやり取りも対面からオンラインに移行していることから、デジタル情報の管理が必要不可欠となっています。
こうしたテレワーク・リモートワークならではの問題を解消するため、オンラインでのやり取りやデジタルデータの管理に特化したSFAツールの導入が進んだという背景があります。
※参考:厚生労働省.「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要」p1.https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf ,(参照2024-10-18).
※参考:NIID 国立感染症研究所.「東京都での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行(2020年1~5月)」.https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2502-idsc/iasr-in/9818-486d01.html ,(参照2024-10-18).
ブラックボックス対策の必要性
かつての営業活動は営業担当者個人の裁量で行われているケースが多く、社内での情報共有がおろそかになっている傾向にありました。その結果、「担当の◯◯さんがいないと分からない」という属人化が横行し、営業部門全体がブラックボックス化してしまうケースが多々見られました。
ブラックボックス化が進むと、いざというときに迅速な対応ができず、顧客満足度が低下する原因となります。特に現代は競争激化に伴い、どの企業も顧客満足度の向上に力を入れているため、営業部門のブラックボックス化解消は優先的に取り組むべき課題とされています。
SFAツールは情報共有に特化したシステムになっているため、属人化やブラックボックス化の防止に取り組んでいる企業が積極的に導入しているようです。

時間外労働の上限規制
前述した働き方改革の一環として、2019年4月(中小企業は2020年4月)より、時間外労働の上限規制が施行されました(※)。これにより、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情があったとしても年720時間を超えた時間外労働は不可となりました(※)。
時間外労働の上限を超えて労働させた場合、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される恐れがあります(※)。
これまで長時間労働が常態化していた企業は、上限規制の適用によって労働環境の見直しをせざるを得なくなり、業務効率化の推進が急務となりました。その一環として、SFAツールを含む便利なシステムの導入が進んだという背景があります。
※参考:厚生労働省.「時間外労働の上限規制」.https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html ,(参照2024-10-18).
※参考:厚生労働省.「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p5.https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf ,(参照2024-10-18).
SFAツールの導入を検討中の方はSFAツール比較記事も要チェック!
SFAツールを導入するメリット
SFAツールを導入すると、以下のようなメリットを期待できます。
営業活動の見える化
従来の営業活動は、口頭や紙ベースで情報のやり取りを行っていたため、誰が・いつ・誰に・どのような営業活動を行い、どのような成果を得られたのか、などのプロセスが見えにくいという課題がありました。その結果、営業担当者でなければ細かな状況を把握できないという属人化が進み、営業全体の業務が停滞する原因の一つとなっています。
SFAツールでは、営業の結果だけでなく、そこに至るまでの過程を管理・保存できる仕様になっているため、当該担当者でなくても全体の営業活動を把握することが可能です。特にクラウド型のSFAツールなら、外部サーバーを通じてツールを使っている従業員全員とリアルタイムで情報を共有できるので、営業担当者の属人化防止につながります。
さらに、可視化された営業活動のデータを分析すれば、成功の秘訣や失敗の原因を正確に把握することができ、より効果的な戦略の立案に役立てることができます。
営業活動の標準化
ビジネスにおける標準化とは、全ての従業員が業務で同じ成果を出せる状態にすることです。
特定の人にしかその業務を遂行できない状態が横行すると、担当者によって業務やサービスの質にばらつきが生じ、品質の低下を招く一因となります。
SFAツールを利用すると、システムに保存されたデータを有効な情報資産として共有できるようになるため、営業活動の標準化が促進されます。

営業活動の効率化
SFAツールには、顧客情報や商談情報、案件情報、予実などを管理する機能が搭載されています。それぞれの情報は相互関係にあり、例えば顧客情報から各々の商談情報や案件情報を一覧表示したり、案件情報の管理画面に入力したデータを予実管理に反映させたりすることが可能です。
こうした情報の紐付けにより、入力の二度手間を省くことができるため、営業活動の大幅な効率化を実現できます。
また、ツールによっては、日報や週報を自動作成したり外部システムと連携して情報を自動で取り込んだりする機能が搭載されており、データの入力に掛かる労力を節約することも可能です。
SFAツールの主な機能について、詳しくは後述します。
経営戦略やマーケティングに役立つ
SFAツールには収集したデータを分析する機能が搭載されています。データ分析を行えば、現在の経営戦略が抱える課題や問題点などの洗い出しが可能になり、必要に応じて迅速かつ適切な判断を行えるようになります。
データは案件別や商材別の他、チーム別や担当別、業種別などさまざまな角度から分析できるので、効果的なマーケティング戦略を練るための参考としても活用できるでしょう。

人材育成の促進
SFAツールは使いこむほど情報資産が増えていく仕組みになっています。蓄積したデータベースを基に、セールスやマーケティングの成功例やコツをピックアップして人材の指導・教育に活用すれば、自社のニーズに合致した人材の育成を促進できるでしょう。
また、SFAツールから営業のノウハウを吸収できる仕組みを整えれば、これまで人材の教育・指導に当たっていた担当者の業務負担が軽減され、本業に専念しやすくなるという利点もあります。
ヒューマンエラーの防止
顧客管理や案件管理のデータをアナログな手法で記帳する場合、データを転写する際に誤記入や記入漏れといったヒューマンエラーが多発する傾向にあります。SFAツールを利用すれば、連携した機能やシステムにリアルタイムでデータを反映できるため、転写におけるヒューマンエラーの防止に役立ちます。
また、アラート機能などを搭載しているSFAツールなら、案件の抜け漏れや対応遅れなどが発生した場合、異常を検知して警告メッセージを発信してくれるので、いち早くイレギュラーに気付いて対応することが可能です。
情報の漏えい・流出の防止
顧客情報や案件情報は企業にとって非常に重要な機密情報であり、外部への漏えいや流出は許されません。しかし、紙ベースの情報や、一般的な表計算ソフトはセキュリティが甘く、紛失や盗難による情報の漏えい・流出のリスクが高いと言われています。
その点、SFAツールには組織や役職に応じて情報の操作権限を制限できる機能や、許可したユーザーや端末のみアクセスを許可する機能、データの暗号化機能といったセキュリティが搭載されているため、情報の漏えい・流出リスクを軽減できます。

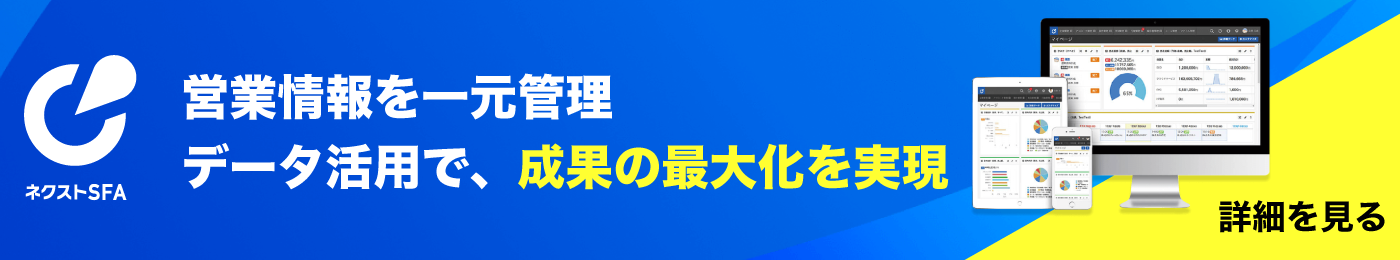
SFAツールに搭載されている主な機能と活用イメージ
SFAツールには、営業活動をサポートするためのさまざまな機能が搭載されています。
ここでは、その中でも多くの企業で活用されている代表的な機能と、それぞれがどのような場面で役立つのかをご紹介します。
案件管理機能
商談の進捗状況や受注見込みなどを一元管理できる機能です。
どの案件が今どのフェーズにあるのかが一目で分かるため、上司やマネージャーは適切なタイミングでサポートしやすくなります。見込み額や受注予定日なども可視化できるため、売上予測の精度向上にもつながります。
顧客管理機能
顧客の基本情報に加え、過去の接点や商談履歴などを蓄積・共有できる機能です。
名刺のスキャン登録や、他の情報との自動紐付けに対応しているツールもあり、営業活動の質を底上げする土台になります。
商談管理機能
訪問・打ち合わせ・提案など、個別の商談内容を時系列で記録・管理します。
担当者以外のメンバーも過去のやり取りをすぐに確認できるため、急な引き継ぎやチームでの連携もスムーズに行えます。
予実管理機能
営業目標に対して、現状の進捗がどれくらいかを可視化する機能です。
予算(予)と実績(実)を数値で比較できるため、日々の活動を軌道修正する際の判断材料として活用されています。

行動管理機能
訪問件数や架電数など、営業担当者の活動ログを記録・集計する機能です。
結果だけでなく“どんな行動を積み重ねているか”をデータで把握できるので、成果に結びつく行動パターンの分析にも役立ちます。
タスク管理機能
対応漏れを防ぐためのToDo管理や、アラート通知の設定ができる機能です。
「次にやるべきこと」が明確になることで、担当者ごとの業務進行をサポートします。
日報・報告書の自動作成機能
営業活動の記録をもとに、日報や週報を自動で作成できる機能です。
手書きや手入力による手間を省けるだけでなく、報告のフォーマットを標準化することにもつながります。
それぞれの機能は、単体で活用するというよりも連動させることで効果が高まるものです。
たとえば、顧客管理と商談管理を連携すれば、営業先の状況をより深く把握できるようになりますし、報告書の自動作成も、案件管理や行動ログの蓄積があるからこそ成り立ちます。
導入を検討する際は、「どの機能があるか」だけでなく、「その機能をどう使って営業現場の課題を解決できるか」という視点で確認してみると、ミスマッチを防ぎやすくなります。

SFAツール選び4つのポイント
SFAツールを導入するにあたっては、単に機能の多さや知名度だけで選ぶのではなく、自社の業務スタイルや体制に合ったツールかどうかを見極めることが大切です。
ここでは、選定時に意識したい4つの視点をご紹介します。
1. 自社の営業スタイルにフィットしているか
SFAツールには、シンプルな構成のものから多機能なものまで幅広いタイプがあります。
中小企業やスタートアップのようにリソースが限られている場合は、必要最低限の機能に絞ったツールの方が運用しやすいことも。一方で、営業・マーケティング・カスタマー対応まで一元管理したい企業には、CRMやMAと連携できる統合型のツールが向いているケースもあります。
2. 現場でスムーズに使えるかどうか
操作のしやすさや、日々の入力負荷は、定着率に直結するポイントです。
見やすい画面設計や直感的な操作性が備わっているかどうかは、実際に現場で使うメンバーの負担を大きく左右します。可能であればトライアル期間を活用して、使い勝手やUIの雰囲気を確認しておくと安心です。
3. 予算とのバランスが取れているか
SFAツールにはクラウド型・オンプレミス型があり、それぞれ料金体系や導入コストが異なります。
初期費用を抑えたい場合はクラウド型が主流ですが、ユーザー数や利用機能によって月額料金が変動するため、チーム規模との兼ね合いも重要です。無料プランやトライアルが用意されているツールもあるので、コスト面の見通しを立てた上で比較検討すると無理のない選定ができます。
4. 既存システムと連携できるか
すでに顧客管理や会計など、別のツールを使っている場合は、SFAとの連携性もチェックしておきたいポイントです。
連携できないとデータの二重管理が必要になり、かえって業務が煩雑になってしまうこともあります。API連携やCSVインポート対応の有無、外部ツールとの連携実績なども、選定時の比較材料として確認しておくと安心です。
「機能が多い=良いツール」とは限りません。
最も重要なのは、自社の営業現場で無理なく活用し続けられるかどうか。
今回ご紹介した4つの視点を参考に、自社に合ったSFAツールを見つけていきましょう。

おすすめSFAツール早見表
ここでは、SFAツールの特長が一目で分かるリストをご紹介します。少なくとも3つのサービスをピックアップして、製品を比較検討してみましょう。
おすすめSFAツール8社の特長
scroll →
| 製品名 | 特長 |
|---|---|
ネクストSFA

|
|
Salesforce Sales Cloud
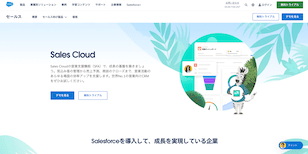
|
|
kintone

|
|
eセールスマネージャーRemix

|
|
UPWARD

|
|
GENIEE SFA/CRM※旧ちきゅう

|
|
cyzen

|
|
Mazrica Sales

|
|
どう選ぶ?ツール選定時のミニアドバイス
- 操作性を重視するなら
初めてSFAを導入する企業や、ITツールに不慣れなメンバーが多い現場には、「UIがシンプルで直感的」な製品が好まれます。 - 連携や将来性を考えるなら
CRMやMA、BIなどと連携して使いたい場合は、拡張性が高く、柔軟にカスタマイズ可能なツールがおすすめです。 - 現場密着型の営業が中心なら
スマホ対応やGPS連携が強いツールは、外出が多い業態にフィットします。
さらに詳しい製品情報を比較したい場合は、ぜひ以下のページもご覧ください。

SFAツールを導入する際の注意点や運用成功のポイント
SFAツールを導入するにあたって気を付けたいことや、運用を成功させるために押さえておきたいポイントを4つご紹介します。
SFAツールを導入する目的を明確にする
SFAツールは営業活動のサポートに役立つ便利なツールですが、導入すれば必ず業務効率化や業績アップに役立つというわけではありません。SFAツールをうまく使いこなせていないと、かえって余計な手間が増えたり、コストがかさんだりする原因となることもあります。
特に、SFAツール導入の目的を明確にせず、「とりあえず使ってみよう」と安易に採り入れようとするとトラブルの元になりかねないので、事前に必ずツール導入の目的を明確にしましょう。
具体的には、自社の営業活動における課題や問題を洗い出した上で、その問題を解決できる機能が備わっているツールを絞り込んで比較検討するのが基本となります。
情報の定期的な更新を徹底する
SFAツールで管理する顧客情報は、時間の経過と共に変化する可能性があります。SFAツールには登録した情報の内容を自動で更新する機能は備わっていないため、古い情報を頼りに営業活動を行っていると、SFAツールの効果を最大限に発揮できない恐れがあります。
そのため、SFAツールに登録した情報は定期的に更新・確認するルールを設け、常に最新の状態をキープできるよう心掛けましょう。
KPIの設定を行う
KPIとは、目標を達成するために必要なプロセスをモニタリングするための指標です。
営業部門では、企業への訪問件数や成約率、顧客単価、営業案件数などがこれに該当します。
SFAツールを使いこなすには、上記のようなKPIを可視化し、データとして落とし込む必要があります。具体的な手法として、やるべきことや課題をツリー状に細分化するロジックツリーなどの方法があるので、SFAツール導入前に実践してみましょう。
PDCAサイクルを回し続ける
PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を1サイクルとするフレームワークのことです。前述の通り、SFAツールはあくまで営業活動における手段の一つなので、ただ導入しただけでは業務効率化や業績アップに役立てることはできません。
SFAツールの効果を最大限に発揮させるためには、PDCAを回し続け、どのような効果が出ているか、課題や問題はないか、などを逐一チェックする必要があります。もし課題や問題が見つかった場合は、原因を追求した上で効果的な解決方法を発見・実践し、その結果を精査するという工程を繰り返します。
このようなPDCAサイクルを回し続けるには、あらかじめルールや体制を整えておく必要があるため、環境整備に必要な話し合いや人材確保を行っておきましょう。


SFAツールは自社の目的・ニーズに合ったものを選ぼう
SFAツールは、営業活動の効率化や可視化、標準化などに役立つ便利なツールです。上手に活用すれば労働生産性の向上や人材育成の促進、ヒューマンエラーの防止など、さまざまなメリットを期待できます。
ただ、搭載されている機能や利便性、料金体系などはツールごとに異なるので、自社の規模や営業スタイル、抱えている課題、予算などに応じて適切なツールを選ぶことが大切です。
ネクストSFA/CRMは、SFAだけでなく、CRMやMAなどの機能も搭載したSFAツールです。顧客管理や商談管理はもちろん、見込み顧客の獲得や育成まで、幅広いニーズに対応します。
UI・UXを徹底的に追求した設計なので、初めてSFAツールをご利用の方も安心です。ノーコードで文言や項目の変更、プルダウンの作成などが可能で、直感的に操作できるため、スムーズに使いこなしていただけます。
「現場に導入しやすいSFAツールを選びたい」「営業活動だけでなくマーケティングやカスタマーサポートにも活用したい」などのニーズがある方は、ぜひネクストSFA/CRMのご利用をご検討ください。