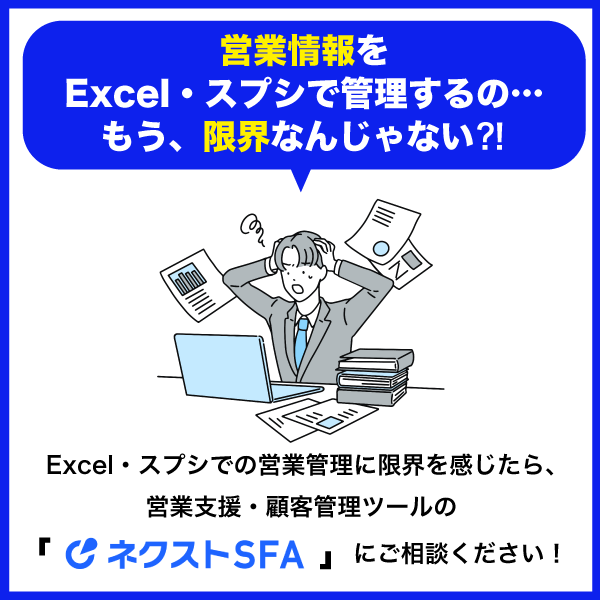更新日:2026/01/21

【受注率を上げるには?】見込み客の質・提案・営業フローを見直して成約率を高める7つの方法

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
「なかなか受注につながらない」「見込み客はいるのに成約率が低い」
こんな悩みを抱えていませんか?営業成績を伸ばすうえで、“受注率”は極めて重要な指標です。
本記事では、「受注率を上げるにはどうすればいいのか?」という疑問に答えるべく、営業プロセスごとの改善策や、成果が出た企業事例、仕組み化に役立つツールの活用法までをわかりやすく解説します。
属人的な営業から脱却し、成果につながる営業スタイルを一緒に築いていきましょう。

この記事の目次はこちら
なぜ「受注率」が営業成果の鍵になるのか
営業活動における「受注率」とは、商談を進めた案件のうち、実際に成約につながった割合を指します。
たとえば、月に10件商談して3件成約できた場合、受注率は30%ということになります。
この受注率は、営業活動全体の“質”を測る極めて重要なKPIです。
新規リードを増やすことに注力しても、受注率が低ければ結局売上にはつながりません。
一方、少ない商談数でも受注率が高ければ、営業効率は非常に良く、費用対効果も高くなります。
商談数の増加 vs 受注率の向上どちらを目指すべきか?
一見すると、商談数を増やせば売上が増えるように思えます。
もちろん、新規開拓は営業において大切な活動です。
しかし、常に新しい見込み客を追い続ける営業スタイルは、人的リソース・時間・コストに大きな負担がかかります。
対して、既に興味を持ってくれているリードに対して、ヒアリングや提案の質を高めて受注率を改善すれば、同じ活動量でもより多くの成果を出せる営業に生まれ変わります。
営業マネジメントが注目する“受注率”という指標
近年、営業組織のマネジメントにおいては、受注率の改善が重視されています。
その背景には以下のような要素があります
- LTV(顧客生涯価値)を高める営業が重要視されている
→ 一度受注した顧客との関係を深め、継続的な取引につなげることで、短期ではなく中長期の成果を得られる。 - 営業活動の“再現性”が求められている
→ 受注率が高い営業担当者の行動を可視化し、組織に展開することで、全体の底上げが可能。 - 商談の歩留まりをKPIとして管理したい
→ 商談数・受注数・受注率をセットで追うことで、プロセスのどこに課題があるかを特定できる。
つまり、受注率は「受注できたかどうか」という結果だけでなく、「営業プロセス全体の質と効率」を見直すための指標でもあるのです。
次章では、具体的に営業のどのフェーズでどんな改善ができるのかを見ていきましょう。
次に出力するのは以下のセクションです:
- 受注率を高めるには?営業フェーズごとの改善ポイント
- リード獲得段階 ― 見込み度の高い顧客を絞り込む
- ヒアリング段階 ― ニーズの“深さ”を掘り起こす
- 提案段階 ― 決裁者・競合・予算を意識した提案にする
- クロージング段階 ― 断られた理由を“次回”につなげる
- リード獲得段階 ― 見込み度の高い顧客を絞り込む

受注率を高めるには?営業フェーズごとの改善ポイント
受注率を上げるには、「ただ頑張る」だけでは不十分です。
営業活動をいくつかのフェーズに分解し、それぞれで課題を見極めて改善する必要があります。
ここでは、営業プロセスを「リード獲得 → ヒアリング → 提案 → クロージング」の4段階に分け、各ステージでの改善ポイントを紹介します。
リード獲得段階 見込み度の高い顧客を絞り込む
営業の出発点は“誰にアプローチするか”です。
この段階でターゲットの質が低いと、どれだけヒアリングや提案を頑張っても、受注にはつながりません。
【改善ポイント】
- 「受注に近い顧客像」を明確にする(業種・企業規模・課題傾向など)
- 過去の受注実績データから、勝ちパターンの属性を分析する
- お問い合わせ・資料DLなど、インバウンドで熱量が高いリードを優先対応
“数をこなす営業”から、“絞って成果を出す営業”への転換が、このフェーズでは鍵になります。
ヒアリング段階 ニーズの“深さ”を掘り起こす
ヒアリングが浅いと、「なんとなく良さそうだけど、導入は先で…」といった温度感の低い商談になりがちです。
顧客の“本音の課題”や“組織としての意思決定基準”まで掘り下げることが重要です。
【改善ポイント】
- 表面的なニーズ(例:業務効率化)ではなく、背景にある経営課題やKPIに踏み込む
- 「今この課題を解決しなければならない理由」を顧客と一緒に言語化する
- ヒアリング内容はSFAなどで共有・蓄積し、提案の質をチーム全体で上げる

提案段階 決裁者・競合・予算を意識した提案にする
顧客の課題を深掘りできたら、次は“刺さる提案”ができるかどうかがポイントです。
誰が決裁するのか、他に比較しているサービスは何か、予算感はどれくらいか
これらを踏まえて提案を組み立てると、成約率は一気に上がります。
【改善ポイント】
- 決裁者が参加する場でプレゼンを行うようスケジュール調整
- 競合との差別化ポイントを資料内で明確に言語化(例:導入までのスピード、サポート体制)
- 顧客が「次に取るべきアクション」を明確に示し、“一歩進める提案”に仕上げる
提案書は資料であって営業トークの補足資料ではありません。「決断の後押しをする設計」が不可欠です。
クロージング段階 断られた理由を“次回”につなげる
受注率を上げるには、「受注する」ことと同じくらい、「失注から学ぶ」ことが重要です。
断られて終わる営業は、受注率を上げるチャンスを失っています。
【改善ポイント】
- 失注理由を必ず記録する(価格/時期/社内事情/競合に決定など)
- 失注後、一定期間空けてからの再アプローチ用テンプレートを用意する
- 案件管理ツール(SFA)に、失注案件にも“次回接触タイミング”をセットする仕組みを作る
失注は“見込みゼロ”ではなく、“今ではない”というサインです。
見込み顧客リストのなかでもっとも受注に近いのは、「一度断ったことがある顧客」かもしれません。

受注率が上がらない営業組織にありがちな5つの原因
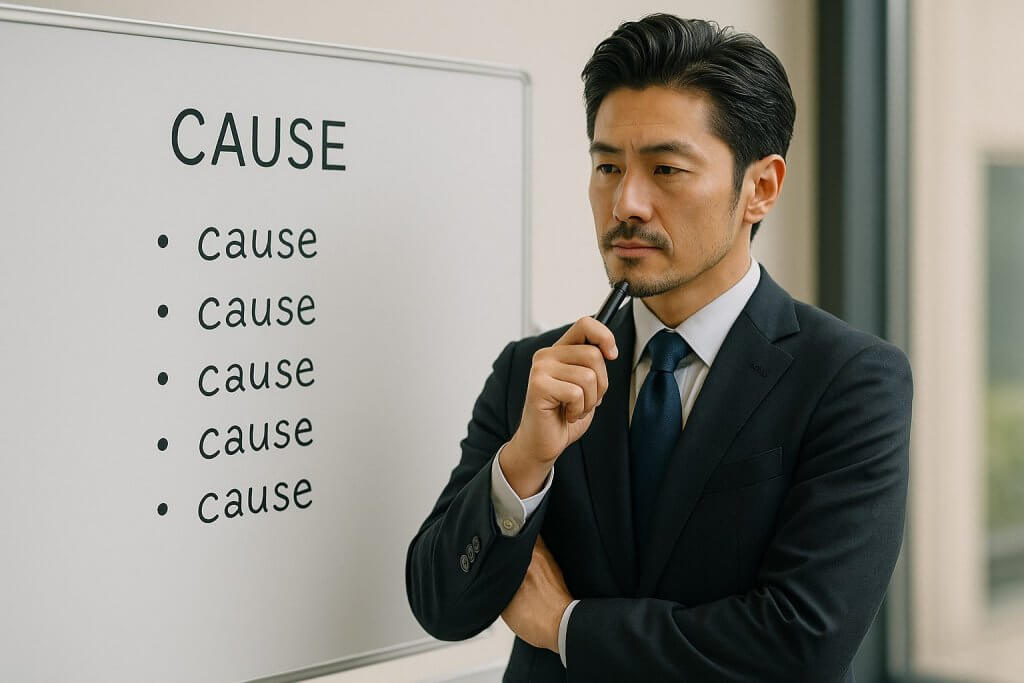
営業担当者は一人ひとり頑張っているはずなのに、なぜか結果が出ない。そんなときは、個人のスキルではなく“組織の仕組み”に問題があることが少なくありません。
ここでは、営業組織にありがちな「受注率が上がらない5つの原因」と、それぞれの改善アプローチを紹介します。
1. 営業が属人化している
営業成果が特定のエースに依存している組織は、再現性がなく、受注率の底上げが難しくなります。
属人化の結果、「誰が担当するか」で受注確度が大きく変わるという事態も。
【改善策】
- 商談履歴やヒアリング内容をSFAに蓄積し、チームでナレッジを共有
- 勝ちパターン(成功商談の流れや提案内容)をドキュメント化
- チーム内でロールプレイや事例共有の機会をつくる
2. 提案内容がワンパターン
どの顧客にも同じ資料、同じトークでは、提案が刺さりにくくなります。
提案が「提供する側の論理」になっていないか、定期的に見直す必要があります。
【改善策】
- 顧客の業界・課題ごとに提案パターンを複数用意する
- ヒアリング結果に基づいた“カスタマイズ要素”を資料に反映
- 提案のロジックや構成を第三者(上司や別の営業)と見直すフローを作る
3. フォロー漏れ・追客タイミングの遅れ
「いいところまで話が進んでいたのに、そのままフェードアウト…」という経験はありませんか?
受注率が低い営業現場では、見込み客を“放置”してしまうことが多く見られます。
【改善策】
- 商談ごとのフォロー予定日をSFAに入力し、リマインドを活用
- 週次で“次にアクションを取るべき案件”を洗い出す時間を確保
- 長期案件は定期的な接触テンプレート(例:季節の挨拶+近況確認)でつなぐ
4. 活動量に偏りすぎている
「とにかく数を打とう」という文化に偏ってしまうと、質の高い顧客との時間が取れず、受注率はかえって下がります。
【改善策】
- 受注率の高い顧客属性を定義し、“狙うリード”の優先順位をつける
- 1日◯件という目標ではなく、「高確度リードとの接触率」など質重視のKPIに切り替える
- 失注案件の分析から“避けるべきリード像”も整理する
5. 営業管理が“見える化”されていない
営業活動のログがスプレッドシートや日報に散在していては、管理者も現場も「今、何が進んでいて、何が課題か」が把握できません。
【改善策】
- SFAやCRMを活用して、商談ごとのステータスや履歴をリアルタイム共有
- ダッシュボードで、案件状況・活動量・成約率をチームで可視化
- 月次で数字と現場のギャップをレビューする会議を実施

営業支援ツール(SFA)で“受注率向上”を仕組み化する方法
受注率を高めるには、個々の営業担当者の努力だけに頼らず、仕組みで成果を出せる営業体制を作ることが大切です。
その“仕組み化”を支えるのが、SFA(Sales Force Automation=営業支援ツール)です。
SFAを活用すれば、商談の進捗や営業活動の質を“見える化”し、組織的に受注率改善に取り組めるようになります。
ここでは、SFAが受注率向上に貢献する5つのポイントをご紹介します。
1. 商談ステータスと確度を明確に記録できる
SFAでは、各商談のステージ(例:アプローチ済/ヒアリング完了/提案中/クロージング中)を可視化できるため、どの商談が“受注に近い”のかが一目でわかります。
また、受注確度(例:A=高確度/B=中程度/C=低確度)もあわせて記録することで、マネージャーは注力すべき案件にリソースを集中させられます。
2. ヒアリング内容・提案内容をチームで共有できる
属人化を防ぐには、ヒアリングや提案内容をチーム全体で共有する仕組みが必要です。
SFA上に入力することで、他の営業メンバーが同様のケースに応用したり、マネージャーが早期にアドバイスを出したりできます。
これにより、属人的な“勘と経験”ではなく、“ナレッジ(知識)とプロセス(工程)”による営業に変化していきます。
3. 失注理由の蓄積と再提案の精度向上
商談が失注に終わっても、そこには学びがあり、再チャンスがあります。
SFAでは、「価格が合わなかった」「タイミングが合わなかった」「競合に負けた」など、失注理由を記録・分析できます。
これらの情報を蓄積していくことで、失注案件へのリベンジ提案や、同様の見込み客への提案改善に活用可能です。
4. KPI(成約率・活動数など)の可視化
SFAは、活動量・商談件数・受注数といった営業KPIをダッシュボードで見える化してくれます。
これにより、「どの営業フェーズで止まっているか」や「どの活動が成果につながっているか」が明確になります。
属人的な判断に頼らず、数字ベースのマネジメントが可能になる点が、大きな強みです。
5. フォロータイミングの自動アラート・リマインド機能
「忙しくて、あの顧客に連絡するのを忘れていた…」
こんな“もったいない失注”を防ぐのが、SFAのアラート・通知機能です。
商談に次回アクション予定日を設定しておけば、自動的にリマインドが表示されるため、フォローのタイミングを逃しません。
これにより、小さな接点を積み重ねて信頼を築く営業が自然と実現できます。

受注率を改善した実践企業の事例3選

理論やノウハウだけでは、なかなか行動に移せない。
そんなときに役立つのが、実際に成果を出した企業の取り組み事例です。
ここでは、「受注率の改善」に成功した3つの企業のストーリーをご紹介します。
業種・規模の異なる企業が、どのような課題に向き合い、どんな工夫で成果につなげたのか。ヒントが詰まっています。
【BtoB SaaS企業】A社|ヒアリング項目の統一で成約率アップ
A社はITサービスを提供するスタートアップ。
営業担当者が複数いるものの、ヒアリングの内容や進め方がバラバラで、提案精度にも差が出ていました。
また、見込み案件の中には「ニーズがふわっとしていてクロージングできない」状態が多く、受注率は停滞していました。
改善施策として、以下を実行:
- 商談時に確認すべきヒアリング項目を統一
- SFAにチェックリストとして組み込み、進捗のばらつきを削減
- 提案資料も、顧客の課題タイプごとにテンプレートを整備
その結果、ヒアリング精度が向上し、成約率がアップ。営業の属人差も縮小しました。
【製造業】B社|過去失注案件から再提案で商談復活
B社は中堅規模の機械部品メーカー。
導入検討まで進んだものの、価格やタイミングの問題で失注する案件が多く、「一度断られたら終わり」という風土がありました。
しかし、SFAを導入したことで失注理由をデータとして蓄積。
1年後に製品アップデートや価格改定のタイミングで、「過去失注案件向けの再アプローチリスト」を作成。
担当者を変えて再度アプローチを行った結果、再提案からの受注率が上昇。失注=完全終了という認識が変わり、案件育成の意識が定着しました。
【広告代理店】C社|ネクストSFA/CRM導入で提案準備時間を削減
C社は少人数の広告代理店。営業から企画、納品までを一貫して行っており、提案書作成に時間がかかりすぎることがボトルネックでした。
特に、「前にどんなやり取りをしたか」「過去に似た案件はあるか」などを、メールやスプレッドシートを探して確認するのが大きな負担でした。
ネクストSFA/CRMを導入し、
- 商談履歴・対応記録・資料を一元管理
- 提案ステータスや進捗状況をダッシュボードで共有
- 類似案件からの提案テンプレートを再利用一応、数値根拠の確認
これにより、提案準備にかかる時間が削減。スピード感が上がり、競合より早く提案できることが差別化にもつながりました。
結果として、月間の受注率が向上しました。

ネクストSFA/CRMで受注率改善を支援 中小企業でもすぐ始められる理由
多くの中小企業にとって、「SFAツールを導入したいけど、コストや使いこなせるかが不安」という声は根強くあります。
そんな中で選ばれているのが、ネクストSFA/CRMです。
直感的に使える設計とサポート体制により、初めてのSFA導入でも“無理なく定着しやすい”仕組みが評価されています。
1. 入力しやすく・見やすい画面設計
ネクストSFA/CRMは、現場営業が使いやすいように設計されたUIが特長です。
たとえば、商談ステータスはドラッグ&ドロップで変更可能。
日々の営業活動や進捗入力もストレスなく行えるため、“現場が使わなくなる”という定着失敗を防ぎます。
2. 商談フェーズ・入力項目のカスタマイズが自由
業種や営業スタイルに合わせて、入力項目や商談フェーズを自社仕様に調整可能。
「案件の確度」「次回アクション予定日」「失注理由」など、受注率改善に必要なデータを柔軟に設計できます。
3. サポートが無料で受けられる
ネクストSFA/CRMでは、導入時の初期設定から運用まで、無料でサポート対応しています。
チャットやオンライン相談を通じて、使い方のアドバイスや設定の見直しなどを伴走。
「ITに強くない」「社内に詳しい人がいない」という企業でも安心です。
4. スモールスタートできる料金プラン
ネクストSFA/CRMは、10ユーザーまでで月額50,000円。
11ユーザー以降は、1ユーザーごとに5,000円で追加できます。
導入規模に応じて段階的に拡張できるため、中小企業でもコストを抑えて導入・運用が可能です。
以上の理由から、ネクストSFA/CRMは「ツールは初めて」「効率化したいけど何から始めるべきか分からない」という中小企業の営業チームからも高く評価されています。

まとめ 受注率向上は“営業の仕組み化”で実現できる
営業活動の成果を大きく左右する「受注率」。
これを高めるためには、個人のスキルだけに頼らず、営業プロセス全体を見える化・最適化する“仕組み”づくりが欠かせません。
本記事では、営業フェーズごとの改善策や、受注率が伸び悩む組織にありがちな課題、そしてSFAを活用した具体的な改善方法をご紹介してきました。
属人的な営業から、チームで成果を生む営業体制へ。
その第一歩は、商談の進み具合やヒアリング内容、提案の質などを数値で“管理できる指標”に変えることです。
ネクストSFA/CRMのようなツールを活用すれば、営業の可視化・改善・定着が一体となり、継続的に受注率を高める営業文化を築くことができます。
まずは自社の営業フローのどこにボトルネックがあるかを見直し、今日から1つずつ改善を始めてみましょう。