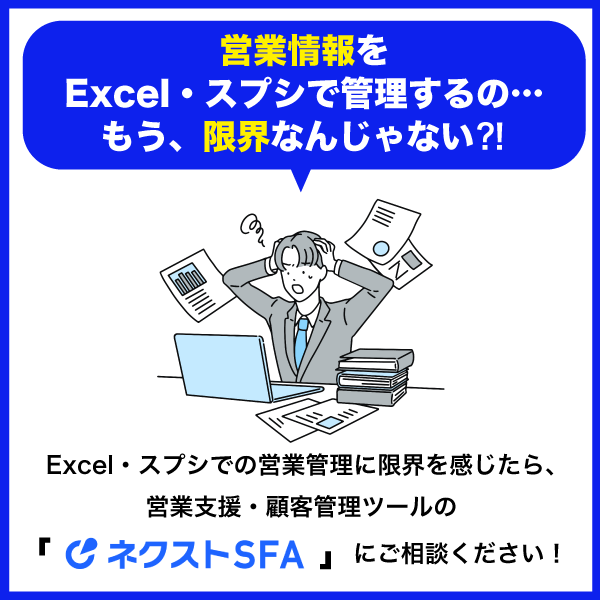更新日:2025/06/20

7つの営業フェーズを徹底解説! 設定・管理するメリットや進め方も分かりやすく紹介

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業成果を高めるためには、属人的な営業スタイルから脱却し、チームで戦略的に営業活動を進めることが重要です。その鍵となるのが「営業フェーズ」の設定・管理です。
営業フェーズとは、リード獲得からクロージング、アフターフォローまでの営業プロセスを段階的に整理し、各フェーズで必要なアクションを明確にするフレームワークのことを指します。
本記事では、営業フェーズの基本から、7つの代表的なフェーズの進め方、導入メリット、管理に役立つツールまでを分かりやすく解説します。

この記事の目次はこちら
営業フェーズとは?
営業フェーズとは、営業活動全体を段階的に区分し、各ステップごとに目的やアクションを明確化したフレームワークです。例えば、見込み顧客へのアプローチ、ヒアリング、提案、商談、クロージング、契約後のアフターフォローといった一連の流れを、それぞれ独立したフェーズとして整理します。
各フェーズには異なる目標や求められるスキルがあり、営業担当者は進捗や顧客の状態に応じて最適な対応を行うことが求められます。営業フェーズを設定・管理することで、業務の可視化や成果の分析がしやすくなり、組織全体の営業効率や成約率の向上につなげることが可能です。
特に営業の属人化を防ぎたい企業や、新人教育を体系化したい組織にとって、有効な手段となるでしょう。
営業フェーズと営業フロー/営業プロセスの違い
「営業フェーズ」「営業フロー」「営業プロセス」は、いずれも営業活動を整理・管理するための用語ですが、それぞれの意味と役割には明確な違いがあります。
| 用語 | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 営業フェーズ | 営業活動を段階ごとに区分した枠組み | アプローチ・提案・クロージングなどのステップ |
| 営業フロー | 各フェーズ内での行動や施策の流れ | 実際に取るアクションを可視化 |
| 営業プロセス | 営業活動全体の一連の流れ | 営業の全体像を示す包括的な概念 |
営業フェーズは、営業プロセスを構成する各ステップを切り分け、誰がどの段階にいるのか、何をすべきかを明確にするものです。
一方、営業フローは各フェーズで具体的に「どう動くか」を整理する実務的な視点であり、アクションの手順や順番を可視化する役割を持ちます。
そして営業プロセスは、営業活動の最初から最後までを俯瞰する枠組みであり、フェーズやフローを内包する上位の概念です。フェーズ=工程、フロー=動き、プロセス=全体像と理解すると整理しやすくなります。
例えば、CRMやSFAなどの営業支援ツールを導入している企業では、営業フェーズごとに進捗を管理し、営業フローを可視化して行動の抜け漏れを防止しています。その上で、営業プロセス全体を評価・改善することで、組織全体の営業力強化に役立てています。
3つの違いを理解し、整理された構造で営業活動を進めることは、属人化の回避やチーム全体のパフォーマンスを上げる上で重要です。
顧客ニーズの多様化
かつての消費者は情報収集力が限られており、テレビや新聞、雑誌などから得た情報のみを頼りに消費活動を行っていました。また、ショッピングは実店舗が中心で、望むものがなかった場合は、身近にあるもので妥協するのが一般的でした。
しかし、インターネットが普及した現代は、消費者は必要な情報を自分で探し出せるようになっています。ニーズにぴったり合致したものを選びやすく、さらにオンラインショッピングの台頭により、住んでいる場所を問わず買い物することが可能です。その結果、地元企業の優位性も失われつつあります。
このような背景から、現代企業には消費者の多様なニーズを迅速かつ的確に把握し、それに応じた商品・サービスを提供する姿勢が求められています。
営業ニーズの変化
従来の営業は、顧客に自社の商品・サービスを提案する提案型営業が主流でした。当時の消費者は自分で情報を収集するのが難しく、営業担当者の提案を受け入れるケースが多かったためです。
しかし、前述の通りインターネットの普及により、状況は大きく変化しました。消費者は自身で必要な情報を簡単に収集することが可能です。そのため、従来の提案型営業では、「自分で探すから結構です」「押し売りは困ります」といった反応が多くなっています。
このような変化に対応するため、現代の営業には新しいアプローチが必要です。具体的には、営業プロセスを細分化し、各段階で顧客ニーズに合わせた戦略を立てることが重要になっています。
リモートワークの普及
リモートワークは、働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとして、多くの企業に普及しました。企業はコストの削減や地方人材の獲得といったメリットを享受できます。
しかし、リモートワークの導入により、新たな課題も発生しています。管理者は社員の活動を直接確認できず、効果的なコミュニケーションを取ることが困難になりました。メールやチャットでは、正確な意図や指示が伝わりにくく、部下への適切なサポートが行き届かない状況が生まれています。
さらに、営業活動においても課題が浮上しています。オンライン商談では、従来の対面営業で培ってきた手法が通用しません。このため、オンライン環境に適した営業プロセスの再構築が必要です。具体的には、営業フェーズの見直しを通じて、新しい商談スタイルに対応した体制を整えることが重要です。
営業フェーズを設定・管理する5つのメリット
営業フェーズを設定・管理すると、以下のようなメリットを期待できます。
1.営業マネジメントの質の向上
営業フェーズを設定すると、一連の営業プロセスを可視化することができます。この可視化により、営業活動の進捗状況を効果的に把握できるようになります。
具体的には、営業担当者の行動内容や時期、進捗状況などの情報を一目で確認することが可能です。そのため、営業マネジャーは必要に応じて適切な指示や支援を迅速に行えるようになります。
このような適切な指示・支援により、営業プロセスが滞るリスクを低減し、より効率的な営業活動を実現できます。営業マネジャーの業務効率改善にもつながるため、全体的な生産性の向上につながるでしょう。
2.営業活動の課題の明確化
営業活動の課題を把握しやすくなるのも、営業フェーズを設定するメリットの一つです。営業プロセスが可視化されているため、営業活動が停滞している場合でも容易に原因を特定できるからです。
具体的な例として、リードの獲得数に対して商談に移行する件数が極端に少ないケースが挙げられます。この場合、リード獲得から商談移行までのフェーズに何らかの課題・問題があると予想できます。
上記のような課題・問題をピンポイントで特定し、適切な対策を講じることで、より効果的な営業プロセスを構築することが可能になるでしょう。
3.売上・業績アップ
営業フェーズを適切に設定・管理しつつ、PDCAサイクルを回し続ければ、営業プロセスの質はどんどん向上していきます。
無駄のない、効率的な営業プロセスに則って営業活動を行えば、自然と受注率や成約率が向上し、売上・業績アップにつながります。
4.人材育成の促進
人材育成を効果的に進められるのも営業フェーズを設定・管理するメリットです。
営業フェーズごとに目標や予算、ヒアリング・提案の内容といった項目を細かく設定していけば、詳細な営業マニュアルを構築できます。この営業フェーズを用いて指導すれば、営業経験のない新入社員でもコツやノウハウを押さえたセールスを実行できるようになります。
新入社員にとって具体的な行動指針を学べることは大きな支えです。「何をすればいいか分からない」「つまずいたときはどうすればいいんだろう」といった疑問や不安が解消され、高いモチベーションを保ったまま営業活動に従事できるようになります。
また、会社は教育にかかるコストと時間を大幅に削減することが可能です。さらに効率的な人材育成により会社全体の営業力を向上させることもできるでしょう。
5.営業の属人化の防止
営業フェーズを設定・共有すれば、営業活動の属人化を防ぐことにもつながります。
営業の属人化とは、営業のノウハウやナレッジが会社内で共有されておらず、特定の人に依存している状態を指す言葉です。営業の属人化は、その営業担当者が休職・離職した場合に営業力が大幅にダウンしたり、営業の質にばらつきが生じたりするなど、会社にとって重大なリスクです。
そのようなリスクを軽減するには、全ての営業担当者が同一のプロセスに沿って営業を行う体制作りが重要になります。つまり、営業フェーズを設定・共有し営業活動を標準化すれば、担当者間の営業力格差を是正することが可能になるのです。
また、顧客に対して一定水準のサービスを提供することが可能になるため、結果として会社全体の営業レベルの引き上げにもつながります。
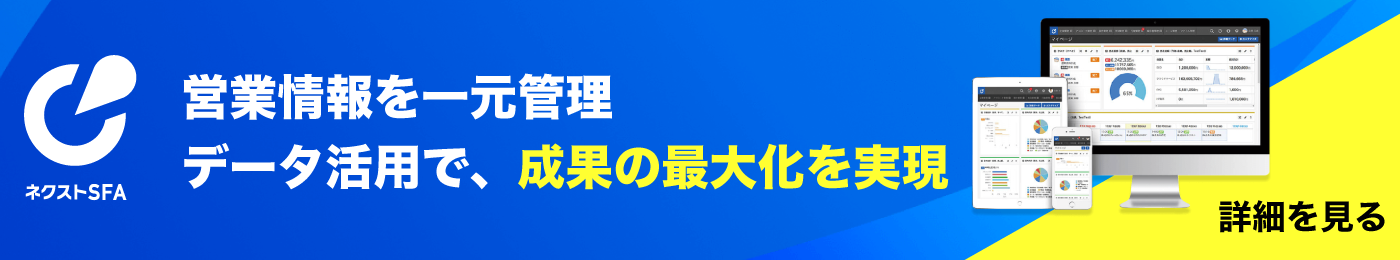
7つの営業フェーズと進め方
ここでは主な営業フェーズの種類を7つご紹介します。各フェーズの具体的な進め方も合わせてご紹介します。
アプローチ
アプローチは、営業フェーズの中でも最初に位置づけられる重要な段階です。このフェーズでは、見込み顧客(リード)となり得る相手と接点を持ち、商談へとつなげるきっかけを作ります。
具体的には、以下のような手法が用いられます。
- 電話・メール・DMによる直接アプローチ
- 展示会やセミナーなどのイベント参加
- SNSやWeb広告を活用した間接的な情報発信
アプローチの目的は「接点を持つこと」自体であり、この時点では相手が顧客になるかどうかは未確定です。そのため、多様なチャネルを活用し、できるだけ多くのリードを獲得することが求められます。
アプローチの進め方
アプローチを効果的に進めるには、チャネルごとの成果を可視化し、改善に生かすことが重要です。具体的には「どのチャネルを使って、どのくらいリードを獲得できたか」「商談化率に差はあるか」などを記録・分析しましょう。
代表的なチャネルには以下があります。
- プッシュ型:テレアポ、DM送付
- プル型:Webサイト、問い合わせフォーム、SNS
- 対面型:展示会、セミナー
- オンライン型:Web広告、メルマガなど
それぞれのチャネルには特性があり、目的や商材によって使い分けが求められます。記録したデータを活用し、反応の良かったチャネルを重点的に改善していくことで、アプローチの質が向上します。
リードの選別
リードの選別は、営業フェーズの中でも「見込み顧客の質を見極める」重要な段階です。アプローチによって得られたリードの中には、すぐに提案できる相手もいれば、ニーズが不明確な層も含まれています。
ここでは、自社の商品やサービスと親和性が高く、購買意欲が見込めるリードを選びましょう。限られた営業リソースを有効活用するためにも、受注確度の高い相手に注力する姿勢が求められます。
適切なリード選別を行うことで、商談の質や成約率の向上につながり、営業プロセス全体の効率化にも寄与します。
リードの選別の進め方
リードを選別する際は、行動履歴や属性情報などの具体的なデータを基に評価することが基本です。選別の基準としてよく使われるのが「BANT条件」です。
- Budget(予算):購入可能な資金があるか
- Authority(決裁権):意思決定権を持っているか
- Needs(ニーズ):課題・要望が明確か
- Timeframe(導入時期):いつ導入を検討しているか
これら4つの条件を満たしていれば、優先的にアプローチすべきリードといえます。ただし、全てが満たされていない場合でも、例えば決裁者への提案資料を作成するなど、別の角度からのアプローチで商談につながる可能性もあります。
BANT条件を形式的にチェックするだけでなく、補える手段がないかを考えることも、質の高い選別につながります。
初回コンタクト
初回コンタクトは、選別したリードと信頼関係を築く第一歩です。ここでは、相手のニーズや課題を丁寧にヒアリングし、商談へとつなげるための基盤を作ります。
この段階では、商品やサービスの提案を急がず、相手の課題に共感し、関係構築を優先する姿勢が重要です。強引なアプローチは信頼を損ね、後のフェーズに悪影響を及ぼす恐れがあります。
目的は「この営業担当者は信頼できる」と思ってもらうことです。適切な距離感で対話を重ね、提案の土台をしっかり整えましょう。
初回コンタクトの進め方
初回コンタクトの管理では、「いつ・誰が・どのような内容でコンタクトを取ったか」を記録し、社内で共有することが重要です。情報が記録されていないと、後続の担当者が適切な対応を取れず、商談機会を逃してしまう可能性があります。
この段階で記録すべき内容は、以下の通りです。
- リードの課題や要望
- 対話中の反応や雰囲気
- 今後の対応予定や次回コンタクト日時
- 使用した資料やツールの内容
初回コンタクトの内容は、次の「提案フェーズ」の質にも大きく影響します。対応履歴を蓄積し、チーム全体で顧客情報を生かせる体制を整えることで、組織として一貫した対応が可能になります。
提案
提案フェーズでは、これまでのヒアリングで得た情報を基に、顧客の課題を解決するための商品やサービスを提案します。ただし、自社都合の一方的な提案にならないよう注意が必要です。
重要なのは、相手が「自分たちの状況を理解してくれている」と感じられるかどうかです。ニーズや背景を的確に把握した上で、それに合致した提案を行うことが信頼獲得の鍵になります。
この段階で提案が刺されば、商談は一気に進展します。逆に的外れな内容だと、信頼を損なってしまうリスクもあるため、事前の準備とデータ分析が重要です。
提案の進め方
提案を行う際は、以下のような情報を正確に記録・管理しておくことが大切です。
どのリードに対して、どの商品・サービスを提案したか
- 使用した資料や説明内容
- 顧客の反応や、懸念点の有無
- 成約確度に影響する要素(価格、納期、競合状況など)
また、うまくいった提案だけでなく、うまくいかなかったケースも含めて情報を共有することが、チームのナレッジとして活用できます。提案の背景にある「なぜこの提案をしたのか」という意図まで記録すると、他メンバーの引き継ぎや振り返りにも役立つでしょう。
過去の成功事例や失敗例を生かすことで、提案の質を高め、次の「商談フェーズ」にスムーズに接続できるようになります。
商談
商談フェーズでは、顧客の懸念や疑問を一つひとつ解消しながら、契約成立に向けて前進していきます。ここで重要なのは、単に商品の説明をすることではなく、顧客の不安に寄り添い、納得感を提供することです。
例えば、「予算に合うか」「期待した効果が得られるか」「導入後のサポート体制は十分か」といった点は、どの顧客にも共通する不安要素です。商談では、こうした疑問に的確に対応し、信頼をさらに深めていく必要があります。
不安を残したままではクロージングは成立しません。商談の質が、受注確度を大きく左右します。
商談の進め方
商談フェーズの管理では、顧客の反応・懸念点・検討状況などの情報の蓄積と共有が求められます。以下のような内容を記録しておきましょう。
- 顧客が抱えている具体的な懸念事項
- それに対して提案した解決策
- 社内の意思決定プロセスやキーパーソンの動き
- 次回アクションと想定スケジュール
もしその場で結論が出ない場合でも、懸念点を整理した上で「いつ・誰と・どのように再提案するか」を明確にしておくことで、次の一手につながります。
また、他の担当者が引き継ぐ可能性もあるため、やり取りの背景や感情面のニュアンスまで含めて丁寧に共有するのが理想的です。
クロージング
クロージングは、商談で信頼関係を築いた上で、契約締結へとつなげる最終フェーズです。この段階では、これまでの提案内容を改めて整理し、顧客に「購入・導入する決断」をしてもらうことが目的となります。
大切なのは、顧客の懸念を残さず、納得した上で前向きに意思決定できる状態に導くことです。焦って押し切ろうとすると逆効果になるため、誠実かつ丁寧な対応が求められます。
また、成約条件(価格・納期・支払い方法など)の最終調整もこのフェーズで行います。ここでの対応が、今後の関係性にも影響するため慎重に進めましょう。
クロージングの進め方
クロージングでは、成約に向けた「詰め」のやり取りを正確に記録し、社内外の調整を円滑に進めることがポイントです。以下の情報を整理しておきましょう。
- 契約金額、オプション、納期などの最終条件
- 顧客側の承認プロセスや関係者の意見
- 顧客からの要望や修正依頼の有無
- 次に起こすアクション(見積送付、社内稟議対応など)
仮に契約に至らなかった場合でも、その理由を明確に記録しておくことで、今後の改善材料となります。また、社内での見積承認や納品スケジュールの調整にも関係してくるため、情報の一元管理が求められます。
契約成立後の信頼関係にも関わる大事なステップなので、ミスなく丁寧に対応しましょう。
アフターフォロー
アフターフォローは、契約後に顧客との関係を深め、継続的な信頼と満足を構築するフェーズです。成約したら終わりではなく、その後の対応こそがリピーター獲得やアップセルの鍵となります。
例えば、導入後の使い方説明、問い合わせ対応、定期的な活用提案など、顧客の課題解決を支えるサポートが求められます。フォローが不十分だと、短期的な取引で終わるリスクも高くなるので注意しましょう。
しっかりとフォローアップを行うことで、顧客満足度の向上だけでなく、新たな提案のチャンスや他部署への横展開といった成果にもつながります。
アフターフォローの進め方
アフターフォローでは、「誰が・いつ・どんな内容でフォローしたか」を明確に記録し、社内で共有することが重要です。特に以下の情報は、抜け漏れなく管理しましょう。
- 初回フォローの実施日・内容(例:導入1週間後のヒアリング)
- 対応した課題やトラブル、その後の改善状況
- 顧客の反応や追加のニーズ
- 提案できそうな次のソリューションや製品情報
また、フォローの中で顕在化した課題を基に、新たな提案へとつなげる動きも有効です。例えば、利用頻度が高まっている顧客に対して上位プランを提案する、関連サービスを紹介するといったクロスセルのきっかけにもなります。
長期的な関係構築を意識しながら、顧客の成長や成功に寄り添う姿勢が求められます。
営業フェーズの管理に役立つツール
営業フェーズを適切に管理するには、営業フェーズの可視化や管理の効率化、社内での情報共有などが必須となります。紙ベースや表計算ソフトなどを使ったアナログな管理方法ではこれらのニーズを満たせない可能性があるので、営業フェーズの管理に役立つ便利なツールの導入を検討してみましょう。
ここでは営業フェーズを管理する際におすすめのツールを3つご紹介します。
SFAツール
SFAツールとは、営業活動の支援を目的としたツールのことです。SFAツールを導入すると、それぞれの営業活動の履歴が可視化されるようになります。
具体的には、営業部門のメンバーの行動や商談の進捗状況・結果などのデータを掌握できるため、タスクをこなせていないメンバーがいないか、進捗状況に遅れが生じていないかなどを逐次チェックできるようになります。管理したデータを基に、適切な指示や支援を与えれば、営業生産性の向上や業務の効率化につながるでしょう。
クラウド型のSFAツールなら、外部サーバーを介してデータのやり取りを行うため、外回り先でもリアルタイムに情報をアップロードしたり、閲覧したりすることができます。
また、ツールによってはToDo機能やアラート機能、日報・週報の自動作成機能などに対応しており、対応の抜け漏れ防止や業務効率化に役立ちます。
CRMツール
CRMツールとは、顧客に関するデータを一元管理できる顧客管理システムのことです。顧客情報管理機能の他、コンタクト履歴、マーケティング支援、リード管理、タスク管理といった機能が搭載されており、顧客との信頼関係を構築する手助けになるツールとして知られています。
例えば、コンタクト履歴を可視化して社内で情報を共有し、誰でも対応できる体制を整えたり、マーケティング支援を使って既存顧客にフォローメールステップメールを配信したりすれば、顧客満足度の向上や営業業務の効率化に役立ちます。
前述したSFAツールと併用すれば、新規顧客の獲得から見込み客の掘り起こし、既存顧客との良好な関係の維持まで、幅広いシーンでの活躍を期待できるでしょう。
MAツール
MAツールとは、マーケティング業務を自動化するためのツールです。具体的には、見込み顧客の属性をカテゴリ分けしたり、属性に合ったメールやコンテンツを自動配信したりして、より効果的かつ効率的なアプローチを実現します。
また、有望な見込み顧客をリスト化し、営業部門に通知するなどの機能も搭載されており、営業部門との連携にも役立ちます。

ネクストSFAを導入して営業フェーズの適切な設定・管理に努めよう
営業フェーズを明確に設定し、組織全体で管理・共有することで、営業マネジメントの質や人材育成の効率アップ、そして売上の最大化に大きく貢献できます。
ただし、営業フェーズの管理は手間がかかる作業でもあるため、SFAやCRMといった営業支援ツールの活用が不可欠です。データの一元管理や進捗の可視化を実現することで、業務の属人化を防ぎ、営業活動全体を最適化できます。
「ネクストSFA」のように、SFA・CRM・MAの機能を兼ね備えたツールを活用すれば、見込み顧客の獲得から受注後のフォローまで、営業活動を一貫して効率的に進めることが可能です。
見込み顧客の獲得、育成から、商談管理、顧客管理までを一つのツールで管理・可視化し、売上向上やビジネスの推進に貢献します。誰にでも使いやすいUIやUXの設計となっており、サポートも充実しているため導入後の運用もスムーズです。自社に合ったツールを導入し、営業フェーズの管理を仕組み化することで、変化の激しい営業環境に柔軟に対応できる強い営業組織を目指しましょう。
営業プロセスを可視化し、各フェーズでの課題を改善したい企業担当者さまは、ぜひネクストSFAのご利用をご検討ください。