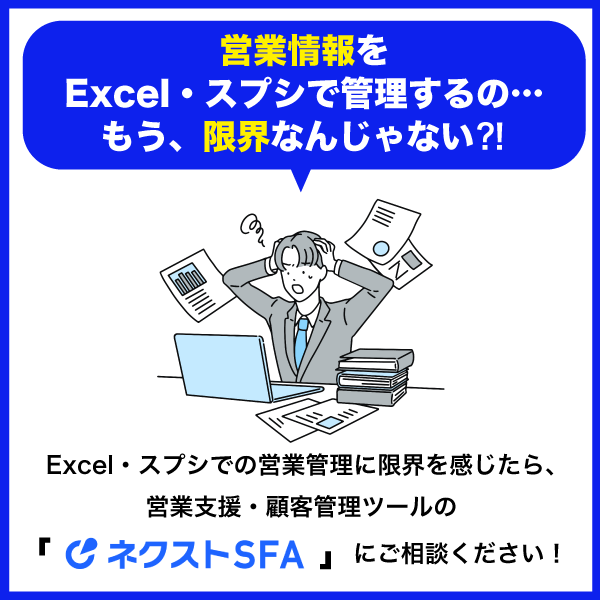更新日:2026/01/21
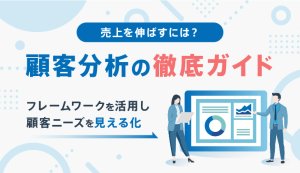
顧客分析とは? 今すぐ活用できる10のフレームワークや分析の手順、おすすめツールを紹介

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
新規顧客やリピーターを獲得するには、顧客を深く理解する「顧客分析」が欠かせません。顧客分析を活用すれば、効果的なマーケティングが可能になるだけではなく、自社の商品・サービスの改善や、顧客満足度の向上に役立てられます。
「売上が伸び悩んでいるけれど原因が分からない」「リピート率を上げたいけれど改善策が見当たらない」といった課題があるなら、顧客分析は有効な手段の一つです。
本記事では、顧客分析の基本知識や重要性、活用できる10のフレームワーク、分析の効果を高めるポイント、おすすめのツールなどを解説します。

この記事の目次はこちら
顧客分析とは?
顧客分析とは、自社が保有する顧客データを分析して、顧客理解を深める取り組みです。主に顧客の属性や購買履歴などを分析し、顧客のニーズを把握する目的で行われます。
分析結果や知り得たニーズは、既存顧客の満足度向上やロイヤルティの強化を図る施策の立案に活用されたり、潜在顧客や見込み顧客へのアプローチ戦略の策定に活用されたりします。競合他社との差別化や売上向上を目指す上でも、顧客分析は有効な手段です。
顧客分析を行う3つの重要な理由
顧客分析を行うべき理由は、大きく3つあります。これらを理解することで、顧客分析の重要性をより具体的に捉えられるようになります。
- ターゲットの特定に役立つ
- 顧客ニーズを理解できる
- 顧客満足度の向上につながる
ターゲットの特定に役立つ
顧客分析はターゲットの特定に役立ちます。ターゲットが明確になれば商品との親和性を確認したり、商品やサービスの訴求ポイントを最適化して効率的な販売戦略を立案したりすることが可能です。結果として、売上向上やマーケティング施策・コストのスリム化を図れるでしょう。
また、顧客分析を通じて想定ターゲットと実際の購買層とのギャップを可視化できれば、商品そのものやマーケティングを見直すきっかけにもなります。自社の商品・サービスに自信はあるのに売上がなかなか伸びないとお悩みの方は、顧客分析を通じて新たな対策の糸口を見つけられる可能性があるでしょう。
顧客ニーズを理解できる
顧客分析は、顧客ニーズ(本当に求めている価値)を理解する上でも有効です。ターゲット層と同様に、企業が良いと考える商品と顧客が感じている価値にずれがあるケースは少なくありません。
例えば、顧客が価格の高さをネックに感じている場合、適正な価格設定にしたり、値下げのキャンペーンを打ち出したりすると、購買につながるかもしれません。
顧客満足度の向上につながる
顧客分析は顧客満足度を向上させる上でも重要です。アンケートなどを通じて顧客が抱える不満や改善要望を可視化できれば、商品やサービスの改良を継続的に行えます。このような取り組みによって満足度の高い顧客が増えると、リピート率の上昇や好意的な口コミの拡散といった好循環が生まれやすくなります。結果として、購買増加や売上向上にもつながるでしょう。

顧客分析に使われる主な項目
顧客分析を適切に行うには、顧客情報を一定のルールのもと正しくまとめておくことが重要です。自社で以下のような項目が網羅的に管理されているか、まず確認してみましょう。
- 顧客の属性(業種・地域・役職など)
- 企業情報(資本金・従業員数・売上高)
- 過去の購買履歴や取引履歴
- 抱えている課題やニーズ
- 過去に実施したマーケティング施策と反応
- 顧客満足度やクレーム対応履歴
- 意思決定プロセス(決裁者や関与部門)
これらの項目を整理・分析することで、顧客理解が深まり、より精度の高いマーケティング戦略を立案することができます。
顧客分析に役立つ10のフレームワーク
顧客分析では、目的によって適切な手法が異なります。ここでは、顧客分析に役立つ10のフレームワークを紹介します。
1.デシル分析
デシル分析は、顧客を購入金額ごとに10のグループに分けて分析する手法です。ちなみに、「デシル」はラテン語で「10等分」を意味します。
デシル分析は以下の手順で行います。
- 顧客を購入金額が高い順に10のグループに分類する
- 各グループの購入金額から、売上に対する貢献度の高さを分析する
デシル分析の活用によって購入額の大きな顧客を特定できるため、優良顧客の抽出やロイヤルカスタマー戦略に役立ちます。
ただし、上位層の中にも一時的な大口購入者が含まれることがあるため、継続性なども加味して評価しましょう。
2.セグメンテーション分析
セグメンテーション分析は、顧客を年齢や性別、職種などの属性ごとに分類して共通点を見出す手法です。顧客をセグメントに分けて分析することで、顧客ニーズやアプローチするべきターゲット層を明確にできるのがメリットです。例えば、セグメンテーション分析によって10~20代の若年層の割合が多いと分かれば、SNS広告やWeb広告が効果的でしょう。
使用される変数には以下のようなものがあります。
- 人口動態変数(年齢・性別・職種など)
- 地理的変数(地域・気候など)
- 心理的変数(性格・価値観・嗜好)
- 行動変数(購買経路・利用頻度など)
複数の変数を組み合わせることで、より粒度の高い分析が可能です。ただし、顧客データが十分に蓄積されていることが前提となります。
3.RFM分析
RFM分析は、顧客を以下3つの指標に分類して分析する手法です。
- Recency:最新の購入日
- Frequency:購入する頻度
- Monetary:購入金額の合計
顧客を3つの指標に基づいて分類することで、「新規顧客」「休眠顧客」「優良顧客」のどの属性に当たるのかを判断できます。3つの指標スコアがいずれも高ければ、優良顧客となるでしょう。
購入金額だけで分類をするデシル分析とは異なり、RFM分析では購入のタイミングや購入する頻度も踏まえて評価できます。購入額も購入頻度も高い「真の優良顧客」を見極めたり、購入頻度は高いが決済額が低い育成対象の顧客を選抜したりすることに適しています。
4.CTB分析
CTB分析は商品に焦点を当て、顧客の購買傾向を以下の3要素から分類する手法です。商品の提案や購買予測に活用できます。
- Category:商品・サービスの種類
- Taste:商品の色や模様、形状、サイズなど
- Brand:企業が展開するブランド
CTB分析を実施する目的は、一人ひとりの顧客の嗜好を可視化することです。特にファッションや日用品など、個人の好みが購買に影響しやすい分野において、パーソナライズされた提案を行えます。
5.行動トレンド分析
行動トレンド分析は、顧客の購買データから商品が売れる傾向を分析するフレームワークです。時間帯・曜日・天候・季節などの要因を基に、購買の行動傾向や購買傾向を分析するのに適しています。
例えば、「アイスクリームが売れやすいのは気温が25度を上回ったとき」という行動トレンドを発見できれば、気温に合わせて商品の入荷量を増やすことで売上の最適化が可能です。
行動トレンドに合わせたマーケティングの実施により、売上の向上が期待できます。そのため、季節性のある商品・サービスを提供する企業では、行動トレンドの正確な分析が必要不可欠です。

6.コホート分析
コホート分析は、顧客を一定の属性や条件ごとに分けて購買行動を追跡・評価するフレームワークです。ちなみに、コホート(cohort)とは同じ傾向を持つグループを意味します。
グループに分類した顧客を一定期間追跡することで、時間の経過に合わせた顧客の行動変化を可視化できるのが特徴です。
コホート分析はECサイトやスマートフォンアプリ、サブスクリプションサービスなど継続的な利用が前提となる分野における顧客分析に適しています。
例えば、ECサイトに登録した顧客が何日後に商品を購入するのか、あるいは商品を購入せずに離脱するのかなどの分析が可能であり、顧客維持率の向上や離脱防止策の立案に役立つでしょう。
7.LTV分析
LTV分析は、顧客が生涯にわたって自社にもたらす総利益を分析するためのフレームワークです。LTVは「Life Time Value」の略で、顧客1人を獲得するために支払ったコストを示すCAC(顧客獲得単価)としばしば対比されます。
企業はLTV分析を活用することで、長期的に高い利益をもたらす顧客層を特定し、リソースを重点的に配分するべき対象を見極めることが可能です。LTV分析の実施には、平均購入単価や購入頻度、顧客の維持期間といった指標を用います。リピート率の向上や商品のアップセルやクロスセル施策を実施することによって、LTVの最大化が図れるでしょう。
ただし、費用を抑制しすぎると顧客満足度が下がりLTVも伸びないため、CACとのバランスを意識することが重要です。
8.NPS
NPSは「Net Promoter Score」の略で、顧客がブランドや商品・サービスに対して、どれほどの愛着を持っているのかを数値化するためのフレームワークです。2003年に発表された比較的新しい手法で、世界的な大企業によってその有効性が証明されています。
NPSでは「商品・サービスを友人や家族に勧めたいですか?」というシンプルながら戦略的に設計された質問を行い、0~10点で評価してもらいます。これにより顧客のロイヤルティや満足度を定量的に把握することが可能です。
アンケートなどで集まった声を基に商品・サービスの改善や顧客対応を改善することで、リピート購入や口コミの拡散が期待できるでしょう。
9.パイプライン分析
パイプライン分析は、営業活動における一連の業務フローを1本のパイプに見立て、各プロセスを段階的に可視化して分析するフレームワークです。潜在顧客の発掘や見込み顧客の抽出に役立ちます。
例えば、どのようなアクションが潜在顧客を見込み顧客に変化させるのか、どのステップで最もコンバージョンが発生しているのか、どの段階がボトルネックになっているのかなどを明らかにすることが得意です。
パイプライン分析により、業務フローのどこに課題があるのかが明確になるため、営業効率の改善やアプローチ方法の見直しに有効でしょう。
10.定性データの分析
定性データの分析は、数値では表せない顧客の感情や声を基に分析を行うフレームワークです。具体的には、アンケートで得た顧客の感想やカスタマーサービスに届いたクレーム、モニターへのインタビューなどが該当します。
定性データは数値と比べて扱いが難しいものの、購買動機や潜在的なニーズ、顧客満足度の背景を読み取る上で重要な情報源といえるでしょう。「なぜその商品を選んだのか」「どこに不満を感じているのか」といった生の声を分析すれば、埋もれていたニーズの発見や、新たな改善点・差別化ポイントの発見につながる可能性があります。

顧客分析の手順を6つのステップで解説
顧客分析を適切に行うには正しい手順で進めることが重要です。ここでは、以下の6つのステップの順に詳細を解説します。
- 顧客分析を行う目的を設定する
- 目的に合った分析手法を決める
- 対象となるターゲット層を選定する
- 顧客分析を行い、カスタマージャーニーを設計する
- 顧客のニーズを深掘りする
- ニーズに応じた商品・サービスの開発・改良を行う
1. 顧客分析を行う目的を設定する
顧客分析を行う際は、まず明確な目的を設定する必要があります。実施する目的が顧客満足度の向上なのか、新規顧客の開拓なのかによって、収集・分析するデータが異なるからです。例えば、顧客満足度を向上させたい場合には、アンケートや口コミからニーズを把握する手法が効果的です。
適切な目的を設定するには、まず現状の営業活動を正確に把握した上で、自社が抱える経営課題を精査することが重要です。精査の結果、解決すべき課題を抽出できたら、それが顧客分析で本当に解決できるかどうかを見極めましょう。
なお、目的を設定する際は、明確な数値目標も定めておくことがポイントです。具体的なゴールを決めておくことで、顧客分析の効果を客観的に評価できます。
2. 目的に合った分析手法を決める
顧客分析を行う目的を明確にしたら、次は目的に合った分析方法を決めます。
例えば、優良顧客を特定して対応を強化したい場合はRFM分析、特定の購買傾向を探りたいなら行動トレンド分析が有効です。分析の対象となるデータが既存のものか、新たに収集すべきかも考慮に入れて手法を選定します。
先述したフレームワークの中から、課題や目的に当てはまるものがあるか確認してみましょう。
3. 対象となるターゲット層を選定する
顧客分析を効率的に行うために、対象となるターゲット層を選定しましょう。例えば、商品・サービスのリピート率を向上させるには、ターゲット層を以下のように分類します。
- 既存のリピーター層
- 商品を2~3回購入した後、リピートしていない層
- 商品を1回購入した後、リピートしていない層
ターゲット層を細かく絞りすぎると傾向が見えにくくなるため、いくつかのセグメントに分類し、分析の焦点を定めていきましょう。

4. 顧客分析を行いカスタマージャーニーを設計する
ターゲット層を選定した後は、顧客分析を行ってカスタマージャーニーを設計します。カスタマージャーニーとは、顧客が商品・サービスを認知してから購入・利用し、継続や再購入に至るまでの道のりを可視化したものです。
見込み客を顧客化して自社のファンになってもらうためには、認知から購買、購買からリピートまでのマネジメントが欠かせません。そのため、自社のアプローチが顧客に有効かどうかを確認する上でも、カスタマージャーニーの設計は欠かせません。
5. 顧客のニーズを深掘りする
カスタマージャーニーを活用して顧客の意思決定プロセスを可視化したら、顧客のニーズを深掘りします。例えば、「キャンペーンでお得に感じたから購入した」という場合は、購入価格が決め手です。その後の継続購入に至っていない場合は、通常価格が少し高いと感じている可能性があります。
顧客の行動プロセスには、悩みやニーズが隠れていることが少なくありません。どこに課題があるのかを深掘りして、改善点を探し出しましょう。
6. ニーズに応じた商品・サービスの開発・改良を行う
最後に、深掘りした顧客ニーズに基づいて自社の商品・サービスの開発・改良を行いましょう。分析結果から見えた課題を把握し、具体的なプランを策定・実行することが重要です。例えば、商品の操作が難しいと感じる顧客が多い場合、シンプルなUIに変更する必要があります。
商品・サービスの開発・改良によって顧客ニーズを満たせば、購買率や顧客満足度の向上につながります。また、分析結果から課題が見つからない場合は、分析手法や活用データを変更して、他の角度から分析し直してみましょう。

顧客分析を行う4つのメリット
企業が顧客分析を行って得られる4つのメリットをご紹介します。
- マーケティング戦略の改善ができる
- 施策の効果測定ができる
- 売上の向上が期待できる
- 商品・サービスの開発・改良に役立つ
マーケティング戦略の改善ができる
顧客分析を活用すれば、より精度の高いマーケティング戦略を立案することが可能です。顧客分析からは顧客ニーズだけでなく、顧客の属性や行動プロセスなど多様なデータを獲得できるため、適切なターゲティングやチャネル選定に役立ちます。
例えば、どのような層にアプローチするのが効果的か、どのような媒体でキャンペーンの実施を行うべきかなどが明確になり、マーケティングの最適化を図れるでしょう。
施策の効果測定ができる
顧客分析を行うことで、マーケティング施策の効果測定ができる点もメリットです。効果を可視化できるので、今後の改善やスピーディな意思決定に生かせます。
例えば、「広告を出しているのに想定販売数に達していない」という場合は、マーケティング施策が顧客の属性に合っていない可能性が高いです。分析結果を基に改善策を客観的に説明すれば、関係者の理解も得やすいでしょう。
売上の向上が期待できる
顧客分析の結果を活用して、ニーズに合ったアプローチや商品の改善を行えば、売上の向上も期待できます。アプローチするべきターゲット層を特定したり、リピート率の向上につながる施策を実施したりすれば、収益を最大化させる仕組みづくりが可能でしょう。
商品・サービスの開発・改良に役立つ
顧客分析は商品・サービスの改良に役立つというメリットもあります。顧客分析によって顧客の潜在的な悩みやニーズを把握できれば、より顧客に必要とされる商品・サービスに改良するためのヒントが見つかります。顧客分析で得られた情報が蓄積していけば新商品・新サービスの開発の際にも役立つでしょう。
また、顧客に寄り添った商品・サービスを展開する企業の姿勢は、競合他社との差別化やブランディングといった点でも有利に働きます。

顧客分析の効果を高めるための3つの注意点
顧客分析の効果を最大限に引き出すためには、以下の3つのポイントに注意が必要です。
- 実施する目的を明確にしておく
- 定量データと定性データの両方を用いる
- 顧客に合わせたアプローチを行う
実施する目的を明確にしておく
顧客分析を始める前に、実施の目的を明確にしておくことが重要です。例えば「顧客満足度を向上させたい」「売上を改善したい」といった目的があり、企業の置かれた状況や課題によって異なります。
目的があいまいな状態で分析を実施し、結果を活用できないといった事態にならないよう、顧客分析に取り組む前に課題を整理し、どの分析が役立つのか検討しましょう。
定量データと定性データの両方を用いる
顧客分析では定量データと定性データの両方を用いるようにしましょう。定量データとは年齢や購入回数など、明確に数値化できるデータを指します。分析しやすくターゲット層の違いや全体傾向を客観的に比較・評価しやすいものの、ニーズの深掘りや新しい視点の発見には向かない傾向にあります。
一方定性データは先述のとおり、アンケートの自由記述や口コミなどで、数値化が難しいデータです。抽象的になりやすいものの、顧客の本音や背景を把握するために欠かせない要素です。どちらか一方のデータに頼りすぎるのではなく、双方のデータを組み合わせて精度の高い分析結果が得られるようにしましょう。
顧客に合わせたアプローチを行う
顧客分析の結果を踏まえたアプローチができなければ、せっかくの分析も成果につながりません。例えターゲットが明確になっていても、接点の作り方や伝え方を誤ると、購買には結びつきにくくなります。
近年はインターネットやSNSなど、顧客との接点やアプローチ手段が複雑化しています。年齢やライフスタイルによって利用するツールやメディアは異なるため、効率的なマーケティングを実施するには、顧客の特性を見極めた上で、適切なアプローチ手段を選ぶことが重要です。

顧客分析を売上向上につなげるための4つのポイント
ここでは、顧客分析の効果を高めるために押さえておきたい4つのポイントを解説します。
- 分析対象とする顧客を明確に定義付ける
- 購買プロセスの分析も実施する
- 市場の規模と成長も分析する
- AIなど先端技術を活用する
分析対象とする顧客を明確に定義付ける
顧客分析の手順でも触れたように、顧客分析では分析対象とする顧客を明確に定義付ける必要があります。どの顧客層を対象とするかによって、導き出される分析結果が変わるためです。
例えば、顧客満足度の向上を目的に分析を行うのであれば、既存顧客のデータを中心に分析する必要があります。さらに、既存顧客を年齢や性別、地域などの属性ごとに分類して、明確なターゲット像を描くことで、より精度を高められます。
施策の効果検証をする上でもターゲットの定義づけは不可欠です。必ず、顧客分析の目的・手段を決めた上で、分析対象となる顧客の範囲を決めましょう。
購買プロセスの分析も実施する
精度の高い分析結果を得るには、購買プロセスの分析も実施しましょう。顧客が自社の商品・サービスを認知して購入に至るまでには、複数の意思決定プロセスが存在します。
このプロセスを分析して可視化すれば、顧客がどのタイミングで何に反応するのかが分かります。顧客に対する適切なアプローチにより、機会損失を回避できるでしょう。
購買プロセスの可視化は、カスタマージャーニーマップの設計やパイプ分析が有効です。顧客の行動や心理を時系列で把握できます。
市場の規模と成長も分析する
顧客分析と平行して、市場の規模や成長性も分析しましょう。顧客分析はターゲットにフォーカスしているミクロな分析なので、市場を把握するマクロ的な視点も重要です。
例えば平均単価と流通量から市場規模を推測したり、前年比からの成長率を算出して、伸び率の高い商品をピックアップしたりすることが可能です。伸び率が鈍化している商品やサービスは内容の見直しを図ったり、新たなニーズの掘り起こしが必要でしょう。
AIなど先端技術を活用する
顧客分析の精度とスピードを高め、売上向上につなげるには、AIなどの先端技術を積極的に取り入れることも重要です。例えばAIを活用して、顧客の行動パターンや購買傾向を予測したり、パーソナライズされた商品レコメンドを自動作成し、提供したりすることが可能になります。また、アンケート結果やSNS上のコメントを自動で収集・分析すれば、顧客のリアルな声をタイムリーに把握できるようになります。
先端技術を活用すれば、よりスピーディに顧客分析を実施できるため、売上向上に向けた施策の立案・実行も迅速になります。施策の回転速度が増すことで、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できるようになるでしょう。

顧客分析におすすめのツールを紹介
顧客分析を効果的に進めるには、関連データを一元管理できるツールの活用が欠かせません。ここでは、顧客情報や売上情報を管理するSFA・CRMと情報収集やメール送信に長けているMAについて、3つの機能がオールインワンで搭載されているネクストSFA/CRMを例に詳しくご紹介します。
SFA
SFA(営業支援システム)は、営業活動の可視化とデータ分析に優れており、顧客分析にも大きな効果を発揮します。ネクストSFA/CRMには、以下のような機能が充実しています。
- 顧客管理(所在地、規模、資本金、売上、担当者名など)
- 案件管理(見込み売上、商談ステータス、失注理由など)
- 受注管理(受注した商品、数量、利益、受注経路や施策との関連など)
- アプローチ履歴の蓄積(実施した施策の時系列、問い合わせやクレームの履歴など)
さらにAI商談レポート機能を活用すれば、過去の商談内容から成功パターンやリスク要因を抽出できるため、より精度の高い見込み客の絞り込みや、再アプローチの優先順位付けが可能になります。
SFAについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
CRM
CRM(顧客関係管理)は、顧客情報の一元化と長期的な関係構築に強みがあります。ネクストSFA/CRMには、以下のような機能が充実しています。
- 企業管理機能(サービスの提供状況、問い合わせ履歴など)
- 売上管理機能(売上情報、契約期間、仕入れなど。単月計上だけでなく継続計上も可能)
また、AIアシスタントが数カ月にわたる膨大な対応履歴を短時間で要約したり、次に対応するべき施策案を提示したりするので、営業活動の効率化を図れます。
CRMについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
MA
MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み顧客の育成や反応分析に特化しており、顧客の興味関心を可視化する上で非常に有効です。ネクストSFA/CRMには、以下のような機能が充実しています。
- シナリオメール機能(顧客の属性や行動に応じたメッセージを配信、反応の変化を自動で追跡できる)
- スコアリングやトラッキング機能(Webサイトの閲覧履歴や資料ダウンロードなどの行動データを数値化し、購買意欲の高い顧客を抽出)
- フォーム生成機能(アンケートや問い合わせを通じて新たな情報の収集が可能)
SFAやCRMと連携していたり、ネクストSFA/CRMのようにオプションで追加できたりすると、情報の一元管理や効率化と併せて、情報収集も容易になるでしょう。
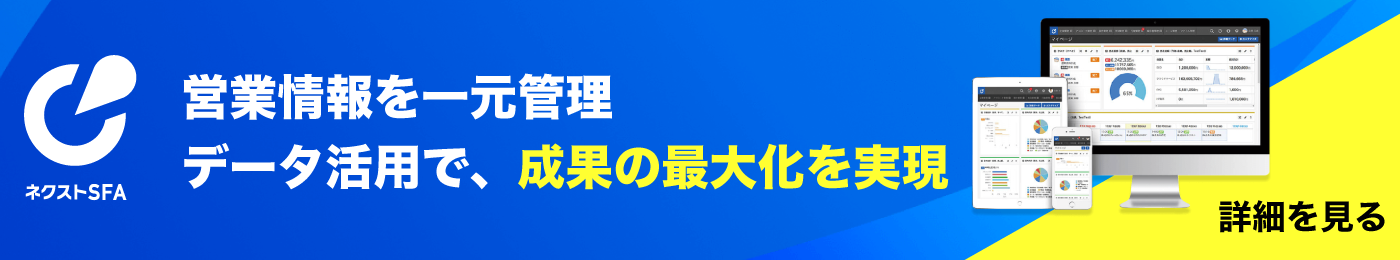

顧客分析を行うならネクストSFA/CRMの活用がおすすめ
顧客分析を効率化するなら、株式会社ジオコードの「ネクストSFA/CRM」がおすすめです。
ネクストSFA/CRMには、SFA・CRM・MAの3機能が全て備わっています。そのため、見込み獲得・育成から商談管理、顧客管理までのマーケティング・営業活動に必要な一連の流れに対応可能です。
使いやすさを重視したUIを採用しており、感覚的にレイアウトを調整できます。初期設計が不要で、複雑な工程を挟むことなく営業体制に合わせたカスタマイズができる点も特徴です。
サポート体制も充実しているため、使い方で迷う心配もありません。SFAの導入を検討している方は、ぜひ株式会社ジオコードまでお問い合わせください。

顧客分析で営業やマーケティングの効果を最大化しよう
ターゲットにマッチしたマーケティング施策を実施するには、顧客分析が不可欠です。顧客分析を通じて、属性やニーズ行動を把握することで、顧客満足度や利益の向上はもちろん、商品・サービスの改善・新規開発にも役立ちます。
顧客分析にはさまざまなフレームワークがあるため、自社の目的や状況に合った手法を選択することが重要です。顧客分析を効率良く実施したいなら、SFAツールの導入を検討してみましょう。
株式会社ジオコードの「ネクストSFA/CRM」は、CRMやMA機能も搭載した営業活動を総合的に支援するツールです。無料トライアルも可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。