更新日:2024/07/26

CRMとは?各種ツールとの違いや基本機能を徹底解説!

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬
CRM(カスタマーリレーションシップ マネジメント)は顧客関係管理と訳され、顧客との関係性構築を重視した経営手法や営業活動システムを指します。
現代は技術水準が向上し、商品自体の質で差別化を図ることが難しい時代です。どれだけ良い商品作りを目指しても、技術力だけでは代わりが利く存在にしかなり得ず、企業の継続的な発展は難しくなります。
このような環境の変化で注目度が増したのが、顧客との関係性を重視するCRMです。アフターサポートやコミュニケーションの取り方で顧客に特別な満足感を与えることでファン化を促進し、継続的な購入につなげます。
顧客に寄り添った対応のためには、顧客情報を一元的に管理するシステムのCRMが必要です。今回はCRMの定義や類似サービスとの違い、機能、導入するメリット、活用のコツ、活用事例について紹介します。
「CRMが何なのかよく分からない」「CRMを活用してビジネスを拡大したい」などと考えているなら、ぜひご一読ください。

この記事の目次はこちら
CRMとは?
CRMは顧客情報を管理する役割を担い、とくに顧客データの分析やカスタマーサポートの機能が重要です。同じく企業の営業・マーケティング活動に役立つツールにSFAやMAがありますが、これらとCRMには明確な違いがあるのが特徴です。
CRMが顧客との関係強化が主たる目的のツールであるのに対し、SFAは営業の効率化、MAはマーケティングの自動化を担います。それぞれのツールの特徴や違いについて解説します。
MAとの違い
CRMが顧客との信頼関係の構築やアフターフォローが主たる目的であるのに対し、MA(マーケティングオートメーション)はリードの発掘を担うのが特徴です。分かりやすくいえば、CRMで管理する顧客の獲得にMAが用いられます。
MAのターゲットは取引を始める前の見込み客が対象ですが、CRMの場合はすでに契約を締結して取引を行っている相手がターゲットです。
MAは名刺交換や資料請求フォームへの問い合わせによってつながったリードに対するステップメールの配信、顧客管理などを自動化します。マーケティングの効果を最大限に高めるには、両者を組み合わせた使用が理想的です。
MAは会員登録を済ませたばかりの顧客に対するステップメールの配信をはじめ、個別具体的なマーケティング施策の立案が可能です。施策の実行にはCRMで入手した顧客情報の存在が前提なので、MAとCRMの両者は切っても切り離せない関係だといえます。
SFAとの違い
SFA(セールス・フォース・オートメーション)は営業支援システムと訳され、営業活動の効率化に役立ちます。顧客との関係構築に特化したCRMに対し、SFAはリードを顧客に変化させるための営業支援が主たる機能です。
簡単にいえば、CRMがリレーションの構築に焦点を当てているのに対し、SFAは案件のスムーズな進行が目的です。SFAは案件の進捗状況や過去の対応履歴、商談〜契約までの期間の目安の計算機能を備えています。
CRMが注目されている理由
CRMの重要性は年々増し続けています。その大きな要因が価値観の多様化です。顧客のニーズが多様化し、以前と比べて顧客像の正確な把握が難しくなっています。
高品質かつ低価格な商品を提供すれば売れる時代は終焉を迎え、一人ひとりに合わせた対応を考えないと、新規顧客の獲得や契約の継続は勝ち取れません。
ビジネスライクな関係ではなく、顧客との親密な関係作りを大切にしてファンやリピーターを獲得します。多様化した顧客ニーズに答えるには膨大な顧客データを一元的に管理し、分析・活用できるシステムが必要です。
顧客の実態を正確に理解し、ニーズに合わせた対応をするためにCRMは不可欠な存在になりつつあります。
CRMの基本機能
CRMの種類に関わらず備わっている基本的な機能は以下の4つです。
- 顧客情報管理
- 配信機能
- 問い合わせ管理
- データ分析機能
顧客情報管理
既存顧客では各営業担当が保有している取引先情報(住所、メールアドレス、担当者氏名など)を集約し、問い合わせや打ち合わせなどの対応履歴、請求書や見積書の提出履歴にかかる情報と紐付けることで一元的に情報を管理します。
CRMでは既存顧客だけでなく、リード(見込み顧客)の情報も集約します。獲得チャネルやアンケートの回答結果なども属性に関わる基本情報とともに登録するのがポイントです。
配信機能
One to Oneマーケティングに役立つメール配信機能です。CRMの活用によって従来無差別に発信していたメルマガが、顧客ごとに選別して送信される形に変化します。
システム上の業種や業務内容、売上、社員数、拠点、組織図などの情報を活用し、個々の顧客に適した内容でメールマガジンを送付。配信機能にはフォローメールやステップメールのシステム化もあります。
CRMの活用によって展示会やセミナーの参加者に送るフォローメールを自動化し、忙しい中でも確実な送付を約束します。購入後のサンクスメールや食材購入者に送るレシピ情報など、ストーリーに応じたステップメールの配信にも有効です。
複数回メールを送付することでリードを顧客に育てる狙いがある場合、CRMの活用はとくに効果的です。最初のメールの開封者にだけ次のメールを送付する設定を施せば、メールマーケティングの工数は大幅に削減します。
問い合わせ管理
CRMの問い合わせ管理機能を用いて、いつ・誰から・どのような問合せがあり、誰がどのように対応したのかという情報を管理・共有可能です。
単なる情報のデータベースとしてではなく、新規問い合わせの負担軽減や業務効率化、対応品質の向上にもつながります。本文や件名に含まれる特定のキーワードに反応して、自動でメールを担当者に振り分ける転送機能が付いているツールもあります。
よくある質問をFAQ化したりテンプレートを実装したりすることで、オペレーターの負担軽減が実現します。
システム管理による対応漏れや二重対応の削減、返信スピードの高速化、過去の対応履歴の共有による対応品質の向上など問合せ管理システムの利便性は計り知れません。
データ分析機能
データ分析機能付きのCRMを活用すれば、顧客との関係性の強化、LTV(顧客最大価値)の向上を狙えます。分析手法には以下のとおり、いくつもの種類があるので自社に適した方法の選択してください
| 名称 | 分析方法 | メリット |
| RFM分析 | Recency(直近の購入日)Frequency (購入頻度)Monetary(購入金額の大きさ) 上記の指標をベースに顧客にランクを付ける方法 | 売上に貢献する顧客に対して優先的にアプローチが可能 |
| デシル分析 | 購入金額が高い順に、顧客を10個のグループにわける方法 | それぞれの顧客に応じた効率的なアプローチが可能 |
| CTB分析 | Category(カテゴリ)Taste(テイスト)Brand(ブランド) 上記の指標をベースに売れ筋の商品を把握する方法 | ・売上アップに直結する商品を見つけられるほか、在庫の削減も実現 |
| CPM | 購入回数・頻度購入総額初回購入から最終購入までの経過期間最終購入日からの経過期間 上記の指標をベースに、顧客を10のグループに分類して消費行動を確認する方法 | 優良顧客グループを把握し、その増加に務める |
| セグメンテーション分析 | 企業の業種や規模、エリアなどの条件からセグメンテーション化し、傾向を確認する方法 | 顧客層および購入商品の関係性が分かるので、ターゲットの把握や新たなニーズの発見が可能 |
| LTV分析 | 購入単価・購買頻度が高く、購買期間が長い優良顧客の行動を分析する方法 | ファンのニーズに沿ったプロモーションの実施が実現 |
売上や新規顧客の増加率など定量的な情報は従来の表計算ツールでも把握できました。CRMツールの活用によって、定量情報だけでなく定性的な情報の分析も行えます。たとえばメールの文面やタイトルなどの文字情報を開封率という指標を用いて定量化。
開封率が低い原因はどこにあるのか、そもそもメールではなく会報誌に切り替えるべきなのではなど問題の特定に役立ち、効果的な施策の立案につながります。
CRMのメリット
CRM導入のメリットは情報の一元的な管理を可能にするほか、共有時の利便性向上、ミスの削減、レポート作成時間の短縮、業務効率化などが挙げられます。単に管理を楽にするだけでなく、至るところにある業務の無駄を削減し、効率的なビジネスの推進が可能です。
それぞれ具体的なメリットについて詳しく解説します。
情報を一元管理できる
顧客に関する情報をシステムに一元化できるので、管理の利便性が高まります。各担当者がエクセルで別々に顧客情報を管理する場合と比較して、入力内容の重複が起きる可能性が格段に低くなり、業務の効率化や確認漏れが起きにくいのが利点です。
顧客管理を営業担当者の裁量に任せると、移動や退職に伴う引き継ぎに漏れが生じ「前の人には伝えたはずなのに…」と二度手間になり、顧客満足度の低下を招きます。
システムが誰でも閲覧可能な環境にしておけば、メールやチャット、電話による情報共有の手間が省けます。休暇や出張で担当者が不在の状況でも問合せに迅速に対応できるので、良いことずくめです。
リアルタイムで情報を共有できる
CRMをハブにリアルタイムで情報共有が可能なため、部門や部署を超えた迅速な連携が図れます。たとえば営業担当が顧問先で商品に対するクレームを受け取ったとき、移動中の社内でシステムにその情報を入力することで、不満の内容が素早く製造部門へと共有されるのです。
情報を共有する側も受け取る側も、今いる場所に捉われず情報のやり取りが可能なので、共有スピードは格段に高まります。
顧客対応におけるミスや漏れを回避しやすい
電話やメール、LINEなど顧客ニーズの多様化に合わせて、コミュニケーションチャネルも増加の一途を辿りました。顧客の属性やリテラシーにかかわらず要望に沿うツールを使える反面、複数のチャネルを管理する手間がかかり、ミスや漏れの発生につながります。
顧客情報や対応履歴の一元化が可能なCRMの導入によって連絡に伴う漏れや行き違いが減少します。対応品質が大きく向上し、結果的に顧客満足度の向上が実現。
継続して良質なサービスを提供し続けることで、顧客の満足度は高まり、何度も繰り返し商品を購入するようになるのでLTVの向上も狙えます。
レポート作成時間を削減できる
CRMにはレポート機能が付随し、入力済みの情報を所定の条件のもと、抽出・一覧化して表示可能です。別人が入力した打ち合わせの議事録や、時系列がバラバラになった顧客情報を一元化してスマートに管理できます。
表やグラフなどにまとめての抽出も可能です。営業担当が時間を割いていたレポート作成業務の大幅な短縮化が期待できます。
従来ではデータの抽出や加工に時間を要し、本来リソースを献ぐべき改善策の立案や考察がないがしろになるケースが多くありました。定型なのに工数が必要な業務をシステムに任せることで、想像力や思考力が伴う作業に人の力を注力できるよう変化しました。
CRMの導入によって知識と教養を武器にする営業マンの属人性を極力なくし、人に捉われない画一的な対応が実現します。
業務効率化を図れる
CRMの導入は業務効率化の推進を促します。顧客情報の入力時の重複、情報共有時の手間、顧客対応における抜け漏れ、人為的なレポートの作成などにおける業務の無駄を削減することが可能です。
ツールの中には顧客との商談日時を自動で調整できるものもあり、日程調整で何度もやり取りを交わす手間がなくなります。
CRMを活用するコツ
CRMを導入すれば必ずリピーターが増え、売上アップにつながるとは限りません。やみくもに使用するとかえって悪影響が出て、ビジネスの衰退につながりかねません。
必要なのは明確な目標と評価指標の設定および戦略の立案です。具体例を交えながらCRMを活用するコツを紹介します。
目標を明確にする
「既存顧客の割合を20%まで高める」「CRMの活用で年間の売上を1.3倍に上げる」など目標を明確にしてください。
ありがちな失敗はCRMの導入自体が目的と化し、ビジネスの目標設定が曖昧になることです。CRMの導入はあくまでも課題解決の手段にとどまります。
明確な目標設定によってシステムに求める機能や具体的な使い方、カスタマイズの内容などが決定します。
最終的にはCRMを活用して戦略を立てることを考えると、目標を具体的に落とし込むのが重要です。
評価指標を明確にする
次に目標の達成度を客観的に把握するために明確な評価指標を考案しましょう。CRMの活用で考えられる指標はLTV・商品引き上げ率・リピート率・離反率・顧客育成率・メールの開封率などです。
たとえば「メールの開封率を50%向上させる」と基準を定めれば、次のアクションをどう起こすか、高精度な計画の立案が可能です。
戦略を立てる
目標と評価指標が明確になったら、いよいよ戦略の立案に入ります。自社の製品やサービスが持つ特徴や強み、既存顧客からのイメージなど情報をフル活用し、実現可能かつ歯ごたえのある戦略を構築してください。
戦略で重要なのは適切なCRMの選択です。数多あるサービスから自社に合ったCRMを選び出すには十分な情報収集が必須です。
機能や特徴、価格帯など総合的な観点を備える必要があります。視野が狭く、価格や機能など一つの側面しか考えないと、後に後悔するリスクが生じます。
CRMの導入には莫大な費用と時間がかかるため、ツールの選定は慎重に行うべきです。社内にCRMに関する知見が不足しているなら、外部の専門的な人材による導入支援の活用も一つの手です。
CRMの使用事例
CRMを有効活用し、ビジネスを成功に導いた企業の事例を紹介します。メリットの項でも紹介したとおり、CRM導入によって業務効率化につながります。
キャリア支援事業を営むポジウィル株式会社はキャリア支援者との面談の日程調整をシステムの手に委ねました。従来は日時が決まるまでにメールのやり取りを何度も繰り返していましたが、担当者の空き状況まで分かるミーティング用URLを支援者に送付するだけで済む形に変更しました。
また、CRMはメールマーケティングの実施にも力を発揮。従来は送付先である顧客リストの作成に時間がかかり、肝心の分析作業が疎かになる状況に悩まされていました。
システムの導入によって流入チャネル別に顧客情報がまとまったリストが瞬時に作成可能になったため、遥かに利便性が高まります。
このように業務の自動化が進み、空いた時間でリソース不足で対応が滞っていた顧客情報の測定や、マーケティング施策の立案が可能になったのです。
導入後は人員の数に変化はないのに3倍の問い合わせ数に対応できるほど業務量が削減。人員と予算の制約が厳しい中小企業でも、費用を投じてCRMを導入する価値は高いといえるでしょう。
もう一つ、システム開発やコンサルティング事業を展開する企業でのCRMの成功事例を紹介します。初めてハード製品の販売に取り組もうと考えていましたが、既存事業と全くターゲット像が異なるため、売上が伸びずに困っていました。
自分たちで獲得したリードを顧客に育てるために、商談の進捗を一元的に管理できるCRMを導入したところ、目に見えて大きな違いが生じました。
見込み顧客の情報および商談の状況が可視化されたことで、Web広告の費用対効果を一目で確認できるように変化が生じます。
広告運用のPDCAサイクルを迅速に回せるようになり、営業の効率的な推進が実現しました。結果的にCRMの導入からわずか1年で月間の成約数が10倍に達するという大きな成果を得られています。
※参考:HubSpot. 「CRMとは?基本機能や導入メリット、SFAとの違いを徹底解説」
最適なCRM戦略
最適なCRM戦略は業界によって異なるので注意が必要です。ここでは主要な業界を例に、過去の事例に基づく適切な戦略について紹介します。
メーカーの場合
製造業でCRMを導入した企業は「より顧客のニーズを商品に反映させたい」「もっと顧客満足度を高めたい」との想いから購入を検討しています。
もの作り大国日本だけあり、質が良い商品・サービスを作る土壌が根づいていても、顧客との信頼関係の構築やニーズの把握に課題を感じている企業が少なくないようです。
CRMのようなITツールは伝統あふれる製造業のイメージとそぐわないですが、幅広い企業が導入を決断しています。
不動産業界の場合
不動産業界では個人顧客への住宅販売や、法人に対する工場や倉庫の建設まで、幅広い事業内容においてCRMが活用されています。活用方法は企業によって千差万別ですが、一例を示すと契約書のデータ保管です。
不動産売買・賃貸借契約の契約書には原本の保存義務があります。事業の拡大に伴い、増える書類の保管場所に悩まされる課題が生じていたのです。
CRMの導入によって紙の保管の手間がなくなるのはもちろん、契約番号と顧客情報を紐づけて管理することで社外のスマホやPCからも契約書へのアクセスが可能に。
スケジュールの調整も含め、お客様の要望にその場で迅速に対応できるようになり、顧客満足度の向上につながりました。
不動産は扱う商材が高額かつ重要性が高いので、仲介会社を選ぶ際に信頼度が重視されます。顧客との良好な信頼関係構築に役立つCRMを採り入れる意義が大きな業界です。
小売業界の場合
卸売・小売業界の企業は、オンラインとオフラインの両方で顧客との接点を強化する場合があります。顧客の満足度が高いサービスの提供には顧客情報の詳細な記録および一元的な管理は欠かせません。
とくにオンラインで顧客の獲得を目指すBtoB企業の場合、CRMによる顧客管理に即したマーケティング施策の立案や案件管理が求められます。
たとえば顧客から得た要望を迅速にWebサイトに反映する取り組みが代表的です。システムの導入によって複雑かつ散らばっていた顧客情報が一カ所にシンプルにまとまることで、顧客のニーズが把握しやすくなります。
CRMで捉えたニーズやウォンツを満たす商品作りを行えば、利益につながる企画開発が実現します。
サービス業界の場合
CRMの導入ではシステム化による自動化や業務効率化に軸が置かれるのが一般的ですが、サービス業界のようなBtoC系のサービスでは、文字どおり顧客との信頼関係構築がメインの場合も少なくありません。
他にも業務プロセス確立の手段に用いられるケースもあり、導入背景や狙う効果にばらつきが見られます。
情報通信業界の場合
ソフトウェアのベンダーやネットワーク事業などを手掛けるIT業界では、レガシーシステムや自社開発ツールからの脱却を検討している企業が見受けられます。自社でCRMの開発に取り組んだものの上手くいかず、結局外部のクラウドサービスを頼った事例もあるほどです。
クラウドサービスなら自社での環境構築は伴わず、迅速に現状を変えられます。自社開発に捉われすぎず、外部サービスを有効活用し、CRMの導入を検討するのがいかがでしょうか。
CRM/SFAで営業効率を上げよう
CRM/SFAを有効活用することでリード・既存顧客・企業の関係者全員が得をする三方良しの関係が実現します。
単に良い商品作りに取り組むだけでは売れ続ける時代は終焉し、マーケティング施策の立案を真剣に考えるべき時代が到来しました。
長期的に取引を維持するには、顧客の本質的な課題に向き合える存在になる必要があります。
また同時に営業効率の向上やリソースの適切な配分を考えねばなりません。上記の課題を同時に解決できる万能なツールがCRM/SFAです。
顧客情報の一元的な管理や業務効率化、顧客管理におけるミスや漏れの削減、情報共有の簡素化など導入によるメリットは計り知れません。
株式会社ジオコードのネクストSFAは、MA・SFA・CRMの全ての機能を備えるオールインワンツールです。
以下に掲げる厳選した機能を搭載し、リードの獲得から受注に至るまでの営業・マーケティング活動を単一のツールで完結できます。
- 地域や業種、顧客ごとのリストを作成し、メールを一括送信
- 特定の条件に基づいてシナリオメールを送信
- 開封やクリックなど見込み顧客の行動に基づくスコアリング&トラッキング機能を搭載
- 無制限かつ自由なカスタマイズが可能なフォーム生成機能付き
外部サービスとの連携機能も豊富で、営業からバックオフィスまであらゆる工程で一元管理が実現します。
無料トライアルも行っているので、負担なく操作感や利便性を確かめられます。少しでも利用を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【ツールは活用されてこそ意味がある】
ネクストSFAは、「社内で活用される」に
こだわっています。厳選された機能、使いやすいユーザーインターフェース、初期のデータ移行からマニュアル作成・ユーザー説明会まで無料でサポートが特徴の営業支援ツールです。


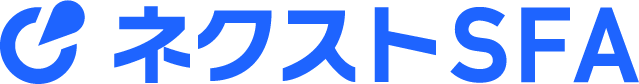

 Sales Cloudで、成長を加速
Sales Cloudで、成長を加速
 個人や少人数チームで活用するCRM/SFA
個人や少人数チームで活用するCRM/SFA




