更新日:2026/01/21

CRMの必要性とは?導入メリットと成果を最大化する活用術を徹底解説

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
「新規顧客が増えない」「営業フォローが行き届かない」「リピーターが定着しない」そんな悩みを抱えている企業こそ、CRM(顧客管理システム)の導入を検討すべきタイミングかもしれません。
近年、顧客との関係性を深め、継続的な収益向上を図る手段として、CRMの重要性が急速に高まっています。
本記事では、「CRMって何?」「うちに必要なの?」という疑問を持つ方に向けて、CRMの基本から導入のメリット、営業や顧客満足度に与える影響、導入判断の基準までをわかりやすく解説します。SFAとの違いや中小企業でも使いやすいCRM搭載ツールについてもご紹介。ぜひ最後までお読みください。

この記事の目次はこちら
そもそもCRMとは?なぜ必要とされているのか
CRMとは、Customer Relationship Management(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)の略で、顧客との関係を管理・強化するための考え方や仕組みのことを指します。現在では、このCRMの考え方を実現するためのツールやシステムを指して使われることが一般的です。
CRMシステムでは、以下のような情報を一元的に管理することが可能です:
- 顧客の基本情報(企業名、担当者、連絡先など)
- 商談履歴や対応履歴
- 過去の問い合わせ・クレーム情報
- 商品・サービスの購入履歴
- 営業活動の進捗状況
こうした情報を蓄積・活用することで、営業活動の効率化や、顧客満足度の向上、そしてLTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できるというわけです。
なぜ“今”CRMが注目されているのか?
かつては「新規顧客の獲得」が営業の主戦場でしたが、近年では「既存顧客との関係性を深め、継続的な取引を重ねていく」ことが企業の収益性を高める鍵とされています。
新規顧客の獲得コストは、既存顧客維持コストの5倍以上かかると言われており、既存顧客へのアプローチを最適化するほうが、費用対効果の高い経営につながるのです。
また、リモート営業やチャット対応など、営業・カスタマーサポートの在り方が多様化する中、部門を超えて顧客情報を共有・活用できる仕組みの必要性が高まっています。
CRMはその中心的な役割を担うツールとして、企業のデジタル化・営業改革の一歩目として選ばれています。
CRM導入は“顧客名簿”の話ではない
「CRMって、要は顧客一覧でしょ?」と思われる方もいますが、それはほんの一部に過ぎません。
CRMは、単なる管理表ではなく、“顧客との関係性を育てる仕組み”です。
誰が、いつ、どんな会話をしたのか。何に悩み、どんな提案をしたのか。その記録が社内に蓄積されることで、初めてCRMは営業やサポートの「武器」となります。

CRMが解決する5つの営業・顧客管理の課題
CRMが注目される理由のひとつに、「多くの企業が抱える営業・顧客管理の課題をまとめて解決できる」点があります。
ここでは、現場でよくある5つの課題と、CRMがどのように役立つのかを具体的に解説していきます。
顧客情報がバラバラで管理できない
Excel、紙、個人メモ、メール……顧客情報がさまざまな場所に散らばっていると、いざ確認したいときに探す手間がかかりますし、更新漏れや重複登録の原因にもなります。
CRMを導入すれば、すべての顧客情報を一元管理できるため、営業担当者が変わってもスムーズに引き継ぎ可能に。
誰が見ても同じ情報が表示される状態をつくることで、営業効率と精度が大きく改善されます。
対応履歴が共有されず、トラブルが発生
「◯◯さんに以前話した内容って、どこにある?」こんなやりとりが社内で頻発していませんか?
対応履歴が担当者の頭の中にしかないと、引き継ぎ時や対応変更時にトラブルが起こりやすくなります。
CRMは、過去のやりとりやクレーム対応履歴を自動記録・共有できるため、「言った・言わない」の防止や、顧客ごとの対応品質の均一化につながります。
フォロー漏れ・機会損失が多い
「このお客様、そろそろ契約更新のタイミングでは?」「あの見積、返事が来ていないままでは?」
忙しい日々の中で、大切なフォローをうっかり忘れてしまうことは営業現場ではよくある話です。
CRMには、フォローリマインドやタスク通知機能が備わっており、対応の「抜け」を防止できます。
さらに、対応すべき顧客の優先順位を視覚的に整理できるため、営業活動の“抜け漏れ”や“後手対応”が減少します。
営業進捗の見える化ができていない
「今、どの商談がどこまで進んでいるのか?」がわからなければ、マネージャーは的確な指示が出せません。
属人的な営業スタイルでは、商談がブラックボックス化し、突然の失注・放置も起きやすくなります。
CRMでは、案件ごとの進捗ステータスを一元管理・共有することができます。
例えば、「提案済」「見積中」「受注確度80%」といったフェーズ表示を通じて、現場の動きを誰でもリアルタイムに把握可能に。
これにより、戦略的な案件管理と的確な営業判断が可能になります。

顧客満足度を測れない
新規契約だけで満足していては、継続的な関係構築はできません。
しかし、問い合わせ対応やフォロー内容、契約更新履歴などが分散していると、顧客ごとの満足度や対応傾向をつかむことができません。
CRMを使えば、問い合わせ履歴・対応履歴・クレーム情報などを一元的に追跡でき、対応履歴の“見える化”が実現します。
これにより、継続契約の可能性が高い顧客や、注意が必要な顧客を把握し、先回りしたフォロー施策へとつなげることが可能です。
CRMの導入で得られる3つの効果

CRMの本質は「顧客との関係を深め、ビジネス成果につなげること」です。導入することでどのような変化があるのか、具体的な3つの効果を解説します。
1. 顧客維持率の向上(解約防止)
新規顧客の獲得にかかるコストは、既存顧客の維持に比べて5〜10倍かかるといわれています。にもかかわらず、「既存顧客の離脱対策」が後回しになっている企業は少なくありません。
CRMを導入すれば、以下のような“見えない離脱兆候”を事前にキャッチすることが可能になります。
- 長期間コンタクトがない顧客を自動でリスト化
- クレーム・問い合わせ履歴を蓄積して分析
- 継続契約や更新が近い顧客に通知
このような機能を活用することで、「フォローされていない」「忘れられている」と感じさせない顧客対応が実現。解約の前兆に気付き、先手のアクションを取ることで、顧客の定着率が大きく向上します。
2. 営業活動の効率化(無駄の排除)
CRMは「営業支援ツール」でもあります。顧客情報・対応履歴・商談状況を一元化することで、営業の無駄を大幅に削減できます。
たとえば、
- 同じ顧客に複数人が別々にアプローチ
- 過去に失注した商談を再アプローチできていない
- 担当者が退職すると引き継ぎが不十分で失注する
こうした“見えない非効率”を、CRMによって見える化・是正できます。
また、レポート作成や日報の自動化など、入力負担を減らしながら情報共有の質を上げる仕組みが整っているため、「忙しくて入力できない」という現場の不満も軽減。
結果として、より多くの時間を“売上につながる行動”に使えるようになるのです。
3. 顧客との関係性強化(アップセル・クロスセル)
CRMは、単なる顧客台帳ではなく、“提案のヒント”が詰まったデータベースでもあります。
過去の購入履歴や問い合わせ内容、商談メモなどを蓄積することで、「次にどんな商品・サービスを提案すべきか」が見えてくるのです。
たとえば、
- A社は3か月ごとに同じ製品を購入している → 定期購入プランを提案
- B社はサポート関連の問い合わせが多い → 有償サポートの導入提案
- C社は複数部署で利用している → 他部署へのクロスセル提案
このように、CRMの活用により、一度の取引で終わらず、継続的な売上拡大(LTV最大化)へとつなげることができます。

CRM活用の成功事例3選 導入後の変化とは?
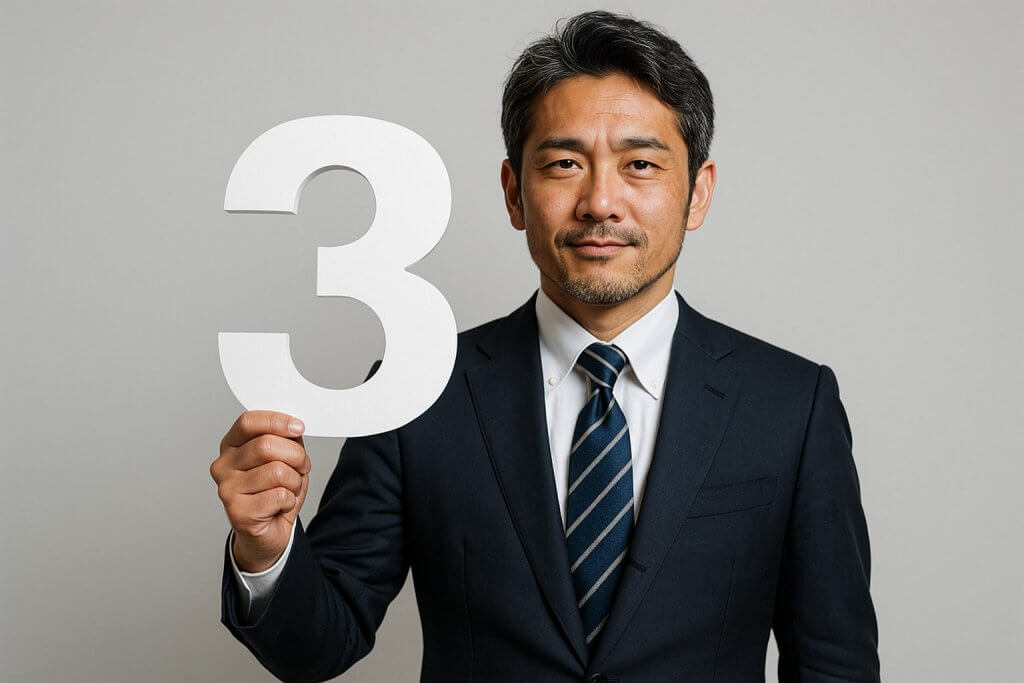
CRMの効果を最大限に理解するには、実際に導入して成果を上げた企業の事例を見るのが一番です。ここでは、業界の異なる3社の成功ストーリーを紹介します。
【製造業】A社|営業属人化からの脱却
A社は従業員100名規模の部品製造会社。営業5名体制で、担当者ごとに顧客管理や進捗報告の方法がバラバラでした。担当者が不在になると商談の進行が止まる、引き継ぎがうまくいかない、といったトラブルが頻発していました。
CRM導入後、すべての顧客情報・案件状況をシステムで一元管理するように変更。営業活動の記録(訪問・電話・メール対応など)もすべて履歴として残せるようになり、「誰が担当でも同じレベルの対応ができる体制」が実現しました。
その結果、営業会議ではデータに基づいた進捗確認ができるようになり、部門間の連携もスムーズに。担当者が変わっても安心して任せられる体制を整えることができました。
【IT業】B社|継続契約率の大幅改善
B社はサブスクリプション型のソフトウェアを提供するIT企業。新規契約は順調に増えていたものの、契約更新時の離脱率が高く、継続率に課題を抱えていました。
原因は、「問い合わせ履歴やサポート状況が社内で共有されておらず、継続提案が一律になっていた」ことでした。
そこでCRMを導入し、サポート担当と営業が顧客ごとの履歴を共有できる仕組みを構築。
契約更新のタイミングでは、過去の課題・やりとりを踏まえたパーソナライズ提案を実施することで、継続率が改善しました。
CRMは、「顧客に合わせた対応」の精度を高め、長期的な関係構築に寄与しています。
【教育業】C社|個別最適な提案で契約数増加
C社は学習塾を複数展開する教育事業者。生徒ごとのニーズや進捗状況は紙台帳とExcelで管理されており、講師と本部の情報共有が課題でした。
CRM導入により、生徒の受講履歴・学習傾向・問い合わせ内容を全拠点で共有できるように。これにより、受講相談の際には、過去の履歴を踏まえた最適なカリキュラム提案ができるようになりました。
さらに、特定条件(例:1か月以上通塾がない)に該当する生徒に自動でリマインドメールを送る仕組みを導入。結果として、入会率が向上し、既存生徒の満足度調査でも「フォローが丁寧になった」との声が増加しました。
教育業界においても、CRMは“個別対応”と“顧客理解”を深める強力な支援ツールとなっています。

CRMとSFAの違いとは?目的と役割を正しく理解しよう
CRMを調べていると、よく並んで登場するのがSFA(営業支援システム)という言葉です。どちらも営業や顧客対応を効率化するツールですが、目的や使い方には明確な違いがあります。この章では、CRMとSFAの違いを正しく理解し、自社に必要な機能を選ぶ判断材料にしていきましょう。
CRM=顧客との関係を深めるための仕組み
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客一人ひとりの情報や対応履歴を蓄積・共有し、“関係性”の質を高めることを目的としたツールです。
- 顧客の基本情報(担当者名、部署など)
- 商談・契約の履歴
- 問い合わせ・クレーム対応の記録
- 購買傾向や訪問頻度
など、顧客との接点を一元的に管理し、「このお客様には何を提案すべきか」「どんなフォローが必要か」を判断する材料となります。主にアフター対応やリピート促進、顧客満足度向上に効果を発揮します。
SFA=営業活動を効率化・見える化する仕組み
一方、SFA(Sales Force Automation)は、営業マンの行動や商談進捗を可視化・標準化し、営業プロセスを効率化することを目的としたツールです。
- 案件のステータス管理(初回訪問/見積提出/成約など)
- 営業日報の入力・集計
- パイプライン(商談一覧)の管理
- 受注見込みやフェーズ別の進捗分析
などを通じて、営業マネージャーの管理負荷を減らすと同時に、組織全体で“見える営業”を実現できます。
両者の関係性と「CRM機能付きSFA」という選択肢
CRMは“顧客理解”、SFAは“営業行動の改善”と、それぞれ得意分野が異なりますが、両者は補完し合う関係です。顧客を理解し、適切にアプローチし、その行動を振り返る。この流れができてはじめて、売上は持続的に伸びていきます。
近年では、ネクストSFA/CRMのように、CRMとSFAの両機能を一つのツールに統合した製品も登場しています。営業活動の記録と顧客情報が一画面で確認できるため、現場でも管理者でも活用しやすく、中小企業にも導入しやすい選択肢として注目されています。

CRM導入を検討する前に 自社の状態をチェックする6つの質問
「CRMが気になるけれど、自社に本当に必要なのか分からない…」という方は少なくありません。そんなときは、まず自社の営業・顧客管理の現状を振り返ってみることが重要です。以下の6つの質問に「はい」が多いほど、CRM導入の効果が見込める状況にあるといえます。
✅ チェックリスト:CRMが必要な状態かを見極める6つの質問
- 顧客情報の管理が人によってバラバラになっている
例:営業担当者ごとにExcelや紙で管理していて、全体把握が難しい。 - 担当者が変わると、引き継ぎがうまくいかない
例:過去の商談内容ややりとりが残っておらず、対応品質が落ちる。 - 顧客からの問い合わせやクレーム対応が属人化している
例:特定の担当しか状況が分からず、社内で共有できていない。 - フォローのタイミングを逃してしまうことが多い
例:更新や再提案の連絡を忘れて、失注・解約につながることがある。 - 営業会議のたびに資料作成に時間がかかっている
例:報告用の進捗資料を毎回Excelで手作業でまとめている。 - 売上や顧客満足度が頭打ちになっていると感じている
例:新規は増えても、リピート率や解約率が改善しない。
2つ以上当てはまる場合は、CRM導入によって大きな業務改善と売上の底上げが期待できます。
次は、導入ハードルが低く、中小企業にも使いやすい「ネクストSFA/CRMのCRM機能」について紹介していきます。

ネクストSFA/CRMのCRM機能 中小企業でも使いやすい理由
CRMは便利な仕組みですが、「導入コストが高そう」「使いこなせるか不安」と感じて、導入をためらう企業も少なくありません。そんな中、ネクストSFA/CRMは中小企業にもやさしいCRM搭載型ツールとして支持を集めています。
ここでは、ネクストSFA/CRMが中小企業に選ばれている理由を4つのポイントから紹介します。
1. 顧客管理・履歴・商談状況が“1画面で完結”
ネクストSFA/CRMは、顧客情報・対応履歴・商談の進捗状況をひとつの画面でまとめて確認できるUI設計が特長です。
「いちいち画面を切り替えないと必要な情報が見られない」といった煩わしさがなく、現場のストレスを減らし、誰でも迷わず使える設計になっています。
2. 月額50,000円台~&初期費用都度見積もりで導入しやすい
中小企業にとって、初期費用の有無や毎月のランニングコストは重要な判断ポイント。
ネクストSFA/CRMは初期費用が都度見積もりで、月額50,000円台から導入可能。営業5~10名の小規模チームでも無理なくスタートできます。
「とりあえず試してみたい」という企業でも導入しやすい価格設計になっています。
3. 無料の導入支援&サポート体制が充実
ITツールに不慣れな企業にとって、「導入後に何をどう設定したらよいのか分からない」という不安は大きな壁です。
ネクストSFA/CRMでは、専任担当が導入から活用までを無料で伴走してくれます。
- チャット/メール/Zoomでの操作サポート
- 初期設定のアドバイス
- 活用方法の相談
といった手厚い支援が、すべて追加費用なしで提供されています。
4. 営業支援機能(SFA)も一体化されている
ネクストSFA/CRMは、CRM機能に加えて、営業案件の進捗管理・KPI管理・レポート作成など、SFAとしての機能も充実しています。
顧客情報と営業進捗が連動していることで、「誰が、どの顧客に、どこまでアプローチしたか」が一目で分かる構造になっており、マネジメントにも現場にもメリットの大きいツールです。公式:https://next-sfa.jp/

まとめ:CRMが営業改革と顧客満足の起点になる
CRMは、ただの顧客台帳ではありません。
顧客とのやりとりを蓄積・分析し、関係性を深めていくことで、売上の安定化や継続的な成長を支える“戦略資産”となります。
新規顧客を追い続けるだけでは、営業の手間もコストも膨らみます。
一方で、既存顧客との関係を強化し、再購入・継続契約につなげていくことは、営業の効率化と利益率の改善につながる最短ルートです。
CRMはまさに、その実現を支える仕組み。
本記事で紹介した内容をふまえ、自社の営業や顧客管理の状態を見直し、「今、CRMが必要かどうか」「どのように活用できそうか」をぜひ検討してみてください。
そして、必要性を感じたなら、最初の一歩として導入しやすく、使いやすいツールの活用から始めてみるのがおすすめです。



