更新日:2026/01/21

営業の属人化はなぜ起こる?主な原因と解消方法を分かりやすく解説

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業部門における大きな課題の一つに、営業の属人化があります。営業の属人化が起こると、業績にばらつきが生じたり、業務の引き継ぎに支障を来したりと、さまざまなリスクが発生する恐れがあります。営業活動を円滑かつ効果的に進めるためにも、営業の属人化は早急に解消することが大切です。
本記事では、営業の属人化が起こる主な原因や属人化の概要、想定されるリスク、効果的な解決方法について解説します。併せて、営業の属人化解決に役立つツールや、ツールを活用した解決例も紹介しているのでぜひ参考にしてください。

この記事の目次はこちら
そもそも営業の属人化とは?
営業の属人化とは、特定の営業担当者のスキルや経験に依存し、営業活動のプロセスやノウハウが組織内で共有されていない状態を指します。各担当者の活動がブラックボックス化するため、特定の担当者が不在になると業務が停滞したり、売上が不安定になったりするリスクが生じます。
かつての営業現場では、個人の能力に頼ったスタイルも少なくありませんでした。しかし、人手不足の深刻化や働き方改革の推進といった社会情勢の変化に伴い、営業の属人化は事業継続を脅かす経営課題として認識されるようになっています。
このような背景から、営業活動を標準化し、組織全体の力で成果を出すためには「脱・属人化」が重要です。現在、事業規模の大小を問わず、多くの企業が営業体制の見直しと属人化の解消に向けた取り組みを進めています。
営業の属人化が起こる原因
営業の属人化が起こる原因は、単一ではありません。その要因は、営業担当者自身の意識やスキルに起因する「個人の問題」と、社内の体制や文化に根差した「組織の問題」の2つに大別できます。
多くの場合、これら個人と組織の問題が複雑に絡み合って属人化を招いています。自社の状況と照らし合わせ、何が原因となっているのかを正確に把握することが、解決の第一歩です。
ここでは、営業の属人化が起こる原因を「個人」「組織」の側面からそれぞれ解説します。
個人の原因
営業の属人化につながる個人の原因は、担当者の考え方やスキルセットに起因します。
例えば、自身の立場を守るために意図的に情報を共有しないケースもあれば、ノウハウを共有したくても、自身のナレッジを客観的に分析し、言語化するスキルがないといったケースも考えられます。ここでは、代表的な2つの原因を解説します。
独自ノウハウの囲い込みが発生している
優秀な営業担当者ほど、数多くの成功体験から独自のノウハウを確立しています。しかし、個人の成績が重視される評価制度の下では、そのノウハウが他者との差別化を図るための源泉となり、自身の競争力を維持するために意図的に共有されないケースがあります。
また営業活動の全てを共有することは、成功体験だけでなく、失敗談や非効率な活動内容なども開示することにつながります。そのため自身の評価が下がることを恐れ、立場を守るために情報開示に消極的になる担当者も少なくありません。
このように、個人の意図によるノウハウの囲い込みは、組織としてのナレッジ蓄積を妨げ、営業活動の属人化を深刻化させる一因となっています。
ノウハウの言語化ができない
ノウハウを共有する意思があっても、自身のスキルを言語化できないために属人化を招くケースもあります。特に、長年の経験と感覚で成果を上げてきたハイパフォーマーは、自身の営業活動を客観的に分析し、論理的に説明するのが苦手な傾向にあります。
彼らは無意識に適切な行動を取れるため、経験の浅いメンバーが「どこでつまずき、何が分からないのか」を具体的に理解できません。その結果、的確なアドバイスやマニュアル化ができず、実践的なノウハウが共有されないまま個人の内にとどまってしまうことがあります。
組織的な原因
営業の属人化は、個人の資質だけでなく、企業の体制や文化といった組織的な要因によって引き起こされるケースも少なくありません。担当者自身に情報共有の意識があっても、それを実現するための仕組みがなければ形骸化してしまいます。
ここでは、属人化につながる組織的な原因を解説します。
情報・ナレッジ共有のシステムがない
個人のExcelやスプレッドシートで顧客情報や案件管理を行っているなど、そもそも組織として情報を一元管理する「システム」が整備されていない状況では、属人化しやすいです。この場合、各担当者のPCやファイルの中にしか情報が存在しないため、第三者がリアルタイムで状況を把握することはできません。
過去の商談履歴や成功事例、クレーム対応といったナレッジも共有されず、担当者個人の記憶の中にしか残りません。そのため、担当者が不在の際に他のメンバーが代理で対応したり、上司が案件の進捗を正確に把握してアドバイスしたりすることが困難になります。
こうした情報共有システムの不在は「あの人でなければ分からない」という状況を生み出し、属人化を助長する根本的な原因となります。
人手不足で情報共有が追い付かない
慢性的な人手不足により、営業担当者一人ひとりの業務負荷が増大していることも、属人化を招く組織的な原因です。日々の営業活動や顧客対応に追われ、日報の作成や定例会議といった情報共有のための時間を確保できないケースは少なくありません。
かつては時間外労働で補うこともできましたが、働き方改革によって残業時間も厳しく制限されています。その結果、情報共有の重要性を理解していても、どうしても優先順位が下がってしまい、組織的なナレッジ共有が進まないまま属人化が進行してしまうのです。
営業プロセスが標準化されていない
「誰が・いつ・何を行うか」といった営業活動のプロセスが定義されず、個人の裁量に一任されている状態も、属人化が発生する原因になり得ます。営業プロセスが標準化されていないと、担当者によって提案の質やアプローチ手法がバラバラになり、組織としての成功パターンを確立できません。
また新入社員は何を基準に行動すればよいかが分からず、育成に時間がかかる原因にもなります。このように、営業プロセスが標準化されていない環境そのものが、個人のスキルに依存せざるを得ない状況を生み出し、属人化を助長してしまうのです。
個人成績を重視する評価システムとなっている
個人の売上目標など、個人の成績のみを重視する評価制度は、属人化の温床となります。
特にインセンティブの比重が大きい場合、担当者は情報共有にメリットを感じないでしょう。自身のノウハウを共有して他者の成績を上げるよりも、自分の成果を追求した方が直接的な報酬につながるためです。その結果、チームで成果を上げる意識が薄れ、ナレッジの共有は後回しにされてしまいます。
このような評価制度は個人プレーを助長し、組織的な属人化を招きます。
営業の属人化によって生じるリスク
営業の属人化が進むことによって、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは6つのリスクを解説します。
1. サービスの品質にばらつきが生じる
営業活動の標準化を怠った結果、属人化が進んでしまった場合、営業パーソン間の格差が大きくなります。すると、顧客への接し方や提案内容などにも大きな差が生じ、サービスの品質にばらつきが起こります。優秀な営業パーソンに当たった顧客からは絶賛される一方、そうでない営業パーソンが担当になった顧客からは「対応が悪い」「サービスの質が低い」などとクレームが来る可能性があるでしょう。
世間では総じて悪評の方が広まりやすい傾向にあるため、悪評の流布によって企業全体の評価が下がってしまう恐れがあります。
2. 営業成績に格差が生じる
営業の属人化によって営業ノウハウやナレッジが共有されないと、個々の能力に差が付いてしまい、営業成績に格差が生じる原因となります。営業パーソン一人で挙げられる成績には限度があるため、いくら優秀な営業パーソンが頑張ったとしても、成績不振な営業パーソンが複数いれば組織全体の営業力は低下してしまうでしょう。
また、営業成績に大きな格差が生じていると社内の雰囲気が悪くなったり、モチベーションが低下したりする可能性があり、労働環境の悪化につながることも懸念されます。
3. 人材育成の遅延
営業が属人化していると、営業に必要なノウハウやナレッジなどを共有することができません。すると、新入社員の教育・指導をする際に基本的なノウハウしか教えられず、人材育成が遅延する可能性があります。
人材育成が遅れると売上や業績にも悪影響がおよび、組織全体の成長・発展を妨げる要因にもなります。
4. 業務引き継ぎに支障が出る
営業担当者が代わるとき、あるいは担当者が休職・離職する際は他の営業パーソンに業務を引き継ぐことになります。しかし、営業の属人化によって必要な情報が共有されていないと、その営業パーソンがこれまでどのようなアプローチを行っていたのか、現在どういった案件を抱えているのか、などの情報を引き継ぐのが困難になります。
業務の引き継ぎが遅れると、顧客への対応も不十分になり、不信感を抱かれる原因になるでしょう。
5. 営業トップの離職による瓦解
営業の属人化によって営業パーソンの能力にばらつきが生じていると、優秀な営業トップが休職や離職した場合、営業力が大幅に低下してしまう恐れがあります。営業トップへの依存性が高いほど、休職・離職に伴うダメージは大きく、場合によっては営業部門が瓦解する可能性もゼロではありません。
特に営業トップが同業他社に転職した場合、抱えていた顧客を転職先に持っていってしまうこともあり、顧客離れが起こることも懸念されます。
6. 隠ぺい工作の横行
営業が属人化していると、営業パーソンが個人で抱える業務が増加しやすくなります。業務過多になると必然的にミスを犯すリスクも増え、顧客との間にトラブルが生じたり、クレームが多発したりする原因となります。
トラブルやクレームは本来、上司に報告した上で早急に対処しなければなりませんが、営業パーソンが個人成績への影響を懸念して、隠ぺいを図るケースも少なくありません。
特に営業の属人化が進んでいると、社内で情報を共有する習慣がないぶん、周囲がトラブルやクレームに気付きにくく、発覚したときには大事に発展している可能性もあります。
営業の属人化を解消する6ステップ
営業の属人化を解消するには、原因に応じた対策を講じる必要があります。
ここでは営業の属人化を解消する方法を6つご紹介します。
1. 営業部門全体の目標を明確化する
営業パーソンの中に「自分の成績が良ければよい」などという意識が定着していると、個人プレーに走りやすく、属人化が進む原因となります。こうした営業パーソンの意識を改革するには、営業部門全体の目標を定め、全員が一丸となって同じ方向に向かって歩んでいく体制を整えなければなりません。
そのためには、組織が目指すべき最終目標の指標となるKGI(重要目標達成指標)や、事業目標を達成するためのプロセスを数値化して評価するKPI(重要業績評価指標)などの設定が必要になります。
KGI、KPIは、共に具体的かつ達成可能な目標を設定することが大切なので、現在の経営状況や営業部門の能力などを考慮し、適切なKGI、KPIの設定を目指しましょう。
なお、設定した目標は何らかの形で営業パーソン全員に周知することが大切です。例えばオフィスの目に見えるところに貼り出しておく、コミュニティツールを利用して情報を共有するなどの方法が有効です。
また、目標の達成度も毎月共有すると、営業パーソンのモチベーションアップにつながります。
2. 情報共有の仕組みを整える
属人化の解消には、点在する顧客情報や案件の進捗、成功事例などを一元管理する「仕組み」の構築が不可欠です。SFA(営業支援システム)などのツールを導入し、誰もが必要な情報へいつでもアクセスできる環境を整備しましょう。
ただし、高機能なツールを導入しても、入力・活用されなければ意味がありません。重要なのは、情報共有を当たり前とする「文化」を醸成することです。「なぜ情報を入力するのか」という目的をチーム全体で共有し、入力された情報がどのように活用され、成果につながったかをフィードバックするサイクルを回しましょう。
また情報共有への貢献度を評価制度に組み込むなど、担当者が前向きに取り組める動機付けも効果的です。こうした仕組み(ハード)と文化(ソフト)の両面からアプローチすることで、初めて生きた情報共有が実現します。
3. 共有・管理する情報を決める
情報共有の仕組みを整えたら、次に「何を」「どこまで」共有するかのルールを明確にします。あらゆる情報を闇雲に共有しようとすると、かえって重要な情報が埋もれてしまい、活用されません。
まずは、組織的な営業活動の基盤となる情報を定義しましょう。具体的には、企業の基本情報や担当者といった「顧客情報」、商談の進捗や受注確度などの「案件情報」、日々の活動内容を記録する「行動情報」が挙げられます。さらに、提案書やトークスクリプトといった「成功ナレッジ」も共有することで、チーム全体のスキルアップにつながります。
これらの情報の中から、自社の課題解決に不可欠なものを優先的に共有するのがポイントです。また情報の重要度に応じて閲覧権限を設定するなど、セキュリティ対策も同時に実施しましょう。
4. 営業プロセスの標準化を進める
属人化の解消のためには、個人の感覚や経験に頼った営業スタイルから脱却できるよう、営業プロセスの標準化が欠かせません。まずは、ハイパフォーマーへのヒアリングを通じて、彼らの思考や行動プロセスといった暗黙知を「可視化」することから始めましょう。
次に、可視化された成功パターンを基に、具体的な行動基準を示すマニュアルを作成します。顧客へのアプローチ方法、トークスクリプト、提案書の型などを標準化し、誰もが一定の品質で営業活動を行える状態を目指します。
重要なのは、このマニュアルを継続的に改善していくことです。現場で実践してもらい、得られたフィードバックを基にブラッシュアップを重ねることで、より精度の高い「勝ちパターン」へと進化させていきます。こうして営業プロセスを「見える化」し続けることで、属人化からの脱却につながります。
5. 評価制度の導入・見直しを検討する
情報共有やプロセスの標準化を推進するためには、社員の行動を方向づける「評価制度」の導入・見直しが不可欠です。個人の売上や契約件数といった結果指標だけを評価する制度は、個人プレーを助長し、属人化の原因となり得ます。
そこで、既存の評価項目に加え、「チームへの貢献度」や「ナレッジ共有の実績」といった新たな評価軸の導入を検討しましょう。例えば、質の高い成功事例を共有した担当者や、標準化されたプロセスの改善に貢献したメンバーを積極的に評価する項目などです。
評価の対象が個人の成果だけでなく、組織への貢献にもあることを明確に周知すれば、社員の意識は変わるはずです。情報共有が正当に評価される文化が根付けば、属人化は解消され、組織全体の営業力も向上していくでしょう。
6. SFAツールの導入を検討する
SFAツールとは、営業活動の支援を行うことを目的としたビジネスツールのことです。標準機能として、顧客管理機能や案件管理機能などが搭載されており、営業活動にまつわる情報を適切かつ簡単に管理できる仕様になっています。SFAツールを上手に活用すれば、営業活動の見える化や情報共有を手軽に行うことが可能です。
営業の属人化解消に役立つのはもちろん、業務効率化にも有用なツールなので、導入を検討することをおすすめします。SFAツールが営業の属人化解消にどのような効果を発揮するかについて、詳しくは後述します。
営業の属人化解消に役立つSFAツール
前述したSFAツールが営業の属人化解消に役立つとされる理由は大きく分けて5つあります。
1. 営業活動の情報を手軽に管理できる
SFAツールには、顧客情報や案件情報、商談情報、行動情報などを一元管理できる機能が搭載されています。各々の機能は相互で連携しており、例えば案件情報から顧客情報を引き出したり、行動情報のカレンダー機能から顧客情報に紐付けて予定登録を行ったりすることができます。
そのため、情報を二重入力する手間が少なく、多忙な営業パーソンでも適切な情報管理・共有が可能です。
2. 情報をリアルタイムで共有できる
クラウド型のSFAツールを利用した場合、データは外部サーバーに管理・保存されるため、インターネット環境下にあればいつでもどこでも好きなときに情報を閲覧できます。ツールに入力した情報は自動でアップロードされるため、登録→閲覧可になるまでのタイムラグがほとんどなく、出先でもリアルタイムで最新の情報を共有することができます。
担当者が不在の場合でも、SFAツールで共有された情報をチェックすれば、顧客に対して迅速かつ適切な対応を行えるでしょう。
3. 対応の抜け漏れを防げる
SFAツールにはタスク管理機能が搭載されており、やるべきことを一覧表示することができます。タスクには優先順位を付けることもでき、早急に対応しなければならないタスクは優先的に表示される仕組みになっているため、多忙による対応の抜け漏れを防ぐことが可能です。
また、ツールによっては対応の抜け漏れが発生しているタスクについて警告を出すアラート機能も搭載されています。さらに、タスク情報を社内で共有すれば、上司や管理者が抜け漏れに気付いて的確な指示を与えるなどの対処も行えるため、ミスやトラブル防止につながります。
4. 適切な支援による業務の標準化
営業スキルには個人差があるため、プロセスをマニュアル化していても個々の営業力に差が出る可能性があります。SFAツールに搭載されている行動管理機能や案件管理機能、商談管理機能などを活用すれば、その営業パーソンのアプローチ内容や商談内容、進捗状況などを逐一チェックできるため、営業パーソンに対して必要なときに必要なサポートができます。
適切なサポートを続ければ、営業パーソンもアプローチや商談のコツをつかめるようになり、人材育成の促進にもつながるでしょう。
5. ミスやトラブルの早期発見・早期対応
SFAツールを利用すると、各人の行動やプロセスをチェックできるようになるため、業務上のミスをいち早く発見できるようになります。ミスに対して適切な指示やサポートを行い、大きなトラブルに発展する前に早期対処することが可能です。
また、SFAツールの導入によって「ミスは隠せない」という事実が周知されれば、社員による隠ぺい工作の抑止力となり、営業の属人化対策になります。
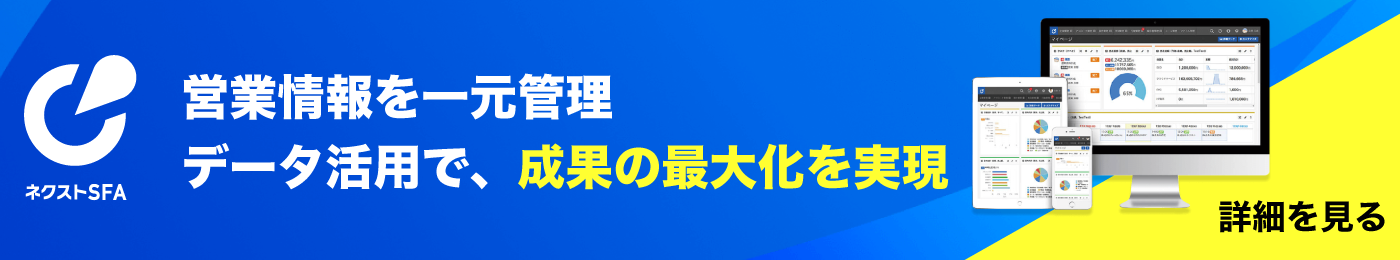
営業の属人化解消に成功した企業の事例
SFAツールを導入したことで営業の属人化を解消できた例は複数あります。ここでは一例として、ネクストSFA/CRMツールの導入によって属人化を解消した事例を2つご紹介します。
エン・ジャパン:複数事業の営業活動記録を一本化
人材支援会社であるエン・ジャパン株式会社のエンSX事業部は、今後セールスやマーケティングを強化していくにあたり、3つの事業を一元管理することを検討していました。しかし、以前使っていたツールでは自社に合わせた営業管理ができず、個々の管理になってしまい、営業活動が見えない状況に陥っていました。
そこで営業の見える化を進めるために、取引先との接点情報を全て履歴として残せるネクストSFA/CRMを導入。履歴は時系列順で表示されるので、誰が見ても情報を把握しやすく、情報共有しやすくなりました。
顧客情報に対してアプローチ情報や案件情報が紐付いているため、企業ごとの提案状況も分かりやすく、営業活動の見える化をスムーズに進められました。
案件管理を行うようになってからは対応の抜け漏れがなくなったり、共有した情報を基に部署間で問題や課題を指摘し合ったりするなどの良い変化も現れたそうです。
プロディライト:業務の引き継ぎや情報管理スピードの大幅短縮
音声ソリューション事業を手がける株式会社プロディライトでは、SFAツール導入以前、営業部門とCS部門間で管理手法に違いがある、成績数値の管理が複数のツールにまたがっているなど、複数の課題を抱えていました。その結果、知りたい情報をすぐ確認できない、情報共有が遅れる、管理の一部が属人化するなどの問題が多発していました。
ネクストSFA/CRMを導入してからは、顧客情報や案件情報など、営業にまつわる情報が可視化された上で一元管理できるようになったため、情報の確認や共有に掛かるスピードを従来の50~60%程度削減することに成功。
また、自社のクラウド電話システムとネクストSFA/CRMを連携させることで、担当者以外でも対応履歴をすばやく把握できるようになり、案件の属人化解消を実現しています。
営業の属人化はリスク満載!早急な解消に努めよう
営業の属人化は個人の意識だけでなく、情報共有の仕組みや評価制度といった組織体制にも根差した課題です。放置すれば、サービス品質の不安定化や人材育成の遅れなど、企業の成長を阻害する深刻なリスクにつながります。
解消するには、情報共有の文化を育み、営業プロセスを標準化し、チームへの貢献を評価する制度へと見直すなど、多角的なアプローチが不可欠です。加えて営業活動を見える化し、迅速に情報共有できるSFAツールを導入することも、営業の属人化解消に役立ちます。
ネクストSFA/CRMは、SFA、MA、CRM全ての機能を搭載したシステムです。初めてSFAツールを利用する方でも使いやすく、見やすいUI・UXを採用しており、誰でも使える画面設計となっています。初期設計も不要、簡単な設定だけで自社に合わせてカスタマイズできるため、営業スタイルにぴったり合った運用が可能です。
無料トライアルも実施しているので、営業の属人化解消の手段としてSFAツールの導入を希望されている方は、ぜひネクストSFA/CRMをご検討ください。



