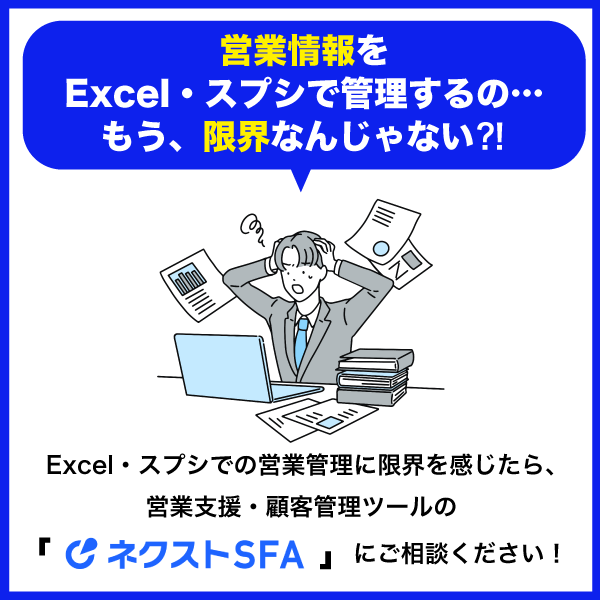更新日:2026/01/21

営業データ分析の基本と活用法|成果につながる手法とツールを紹介

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業活動がスムーズに進まない場合は、その原因を把握し解決策を見つけることが大切です。課題や解決策を把握するにはデータ分析が必要といえます。データ分析には、フレームワークや分析ツールの活用が有効です。
本記事では営業データ分析について必要な理由や手法、実践に活用できるフレームワークなどを解説します。営業データ分析に役立つツールも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次はこちら
営業データ分析が求められる3つの背景とメリット
営業現場では「勘や経験」に頼ったアプローチが今も多く見られますが、環境の変化が激しい今、こうしたやり方には限界があります。
競合との差別化や、継続的な成果創出のためには、営業活動をデータに基づいて見直し、チーム全体で共有・活用していくことが欠かせません。
このセクションでは、営業データ分析が求められる背景と、得られる主なメリットを3つご紹介します。
顧客ニーズをデータから正確に掴む
自社に蓄積されたデータを分析すると顧客ニーズを正確に把握できます。例えば顧客が自社製品・サービスを購入した履歴をデータとして蓄積すれば、顧客が求めている商品・サービスや顧客の属性などを読みとれます。顧客の属性とは性別や年齢、居住地、職業、ライフスタイルなどを分類したものです。
データに基づいて顧客ニーズを調べると予期せぬ発見があるかもしれません。属性と購入パターンがつかめれば、顧客のニーズに沿ったキャンペーン実施といった、戦略的な営業活動を展開できます。
勘・経験に頼らない数値ドリブン営業
成果の出る営業は「感覚」ではなく「根拠ある数字」をもとに動いています。
たとえば、過去の商談数・成約率・受注までのリードタイムなどのデータを定期的に振り返ることで、「何がうまくいって、何が足りなかったのか」を明確にできます。
数字をベースにした営業活動は、再現性が高く、改善サイクルもまわしやすくなります。
感覚頼みの施策よりも、チーム全体で納得できる判断ができるようになるのも大きなメリットです。
データ共有で属人化を防ぎチーム力UP
営業情報が個人の頭の中やメモ帳の中だけにある状態では、組織としての力が発揮できません。
データ分析を通じて顧客情報や進捗状況を共有すれば、誰が担当しても一定水準の提案ができる状態をつくることができます。
また、成果を出している営業メンバーの動きや工夫をチーム内で見える化することで、ノウハウの横展開もスムーズになります。
結果的に、組織全体の営業力が底上げされ、成果につながりやすくなります。
営業データ分析“最初の3ステップ”──動向・要因・検証で流れを掴む
営業データ分析を始める際、いきなり高度な手法や複雑なツールに取り組む必要はありません。
まずは「動向」「要因」「検証」という3つの基本ステップに沿って、現状の営業活動を見える化し、改善点を探っていくことが大切です。
このセクションでは、それぞれのステップで何を意識し、どのように進めていけばよいかをわかりやすく整理してご紹介します。
Step1 動向分析 ― 市場を俯瞰
最初のステップは、自社を取り巻く「市場の動き」や「自社の営業活動全体の傾向」を把握することから始まります。
具体的には、過去の売上推移や成約件数、キャンペーンの成果などをグラフやチャートで可視化し、変化の流れを読み取っていきます。
たとえば、「直近3ヶ月で資料請求数が減っている」「競合製品の伸びが目立っている」といった“兆し”に気づけると、次に注目すべき課題や施策が見えてきます。
ここでは大まかな流れを掴むことが目的なので、細かい要因を掘り下げるのは次のステップに譲ってOKです。
Step2 要因分析 ― 原因を深掘り
動向分析で変化の兆しをつかんだら、次は「なぜそうなったのか?」を探るフェーズです。
この段階では、営業成果に影響を与えている要因を特定していきます。
たとえば「問い合わせ数は増えているのに成約率が落ちている」場合、
・提案の内容にズレがあったのか?
・競合との比較で不利な条件が出ていたのか?
などをデータやヒアリングから読み解き、仮説を立てていきます。
要因分析のポイントは、「結果」ではなく「構造」に目を向けること。
数字の裏にある実態を捉えることで、施策に直結する洞察を得ることができます。
Step3 検証分析 ― 仮説をテスト
最後のステップは、要因分析で立てた仮説が正しかったかを検証するフェーズです。
たとえば「提案資料の構成を変えれば成約率が上がるはず」という仮説があるなら、実際に資料を改善し、その効果を数値でチェックしていきます。
検証にあたっては、
・施策の対象を絞る(エリア/業種など)
・実施期間を区切る
・他条件と比較できるように設計する
などの工夫をすると、判断しやすくなります。
このステップを繰り返すことで、営業活動が少しずつデータに基づいた“改善サイクル”へと進化していきます。
この3ステップは、営業分析を習慣化するベースともいえます。
まずは「感覚ではなく数字を見る」ことから、小さな分析の一歩を踏み出してみるのがよいかもしれません。
営業データ分析でよく使われるKPI指標と計算式
営業データを分析する際は、「何をKPI(重要業績評価指標)とするか」が判断の土台になります。
KPIを正しく設定すれば、現状の課題や改善ポイントが見えやすくなり、営業活動の方向性も明確になります。
このセクションでは、営業分析でよく使われるKPIの例や、簡単に使える計算式をご紹介します。
自社の営業プロセスと照らし合わせながら、参考にしてみてください。
代表的KPI一覧(新規リード・成約率・平均取引額 など)
営業活動におけるKPIは、フェーズごとに異なります。以下は代表的なKPIの一例です。
| フェーズ | 主なKPI例 | 補足説明 |
|---|---|---|
| リード獲得 | 新規リード数/Web問い合わせ件数 | マーケティング連携が重要な指標 |
| アポイント | アポ取得数/アポ率 | 接触から次の商談へつながっているかを評価 |
| 商談進行 | 商談数/提案数/見積提出数 | 受注に直結する中間KPIとして有効 |
| 成約 | 成約率/受注件数 | 最終的な成果を可視化するゴール指標 |
| 売上貢献 | 平均受注単価/LTV/クロスセル率 | 単発で終わらない継続的な収益性も評価対象に |
業界や自社の営業スタイルによって、KPIの重点は変わることがあります。
まずは現在の営業フローを分解し、それぞれに対応するKPIを整理してみるとよいでしょう。
計算式サンプル
数値の見える化には、シンプルな計算式を活用することが効果的です。以下に基本的な指標の算出式をご紹介します。
| 指標 | 計算式 | 解説 |
|---|---|---|
| 成約率 | 成約件数 ÷ 商談件数 × 100 | 商談の中から何件受注できたかを示す |
| アポ率 | アポ取得件数 ÷ リード数 × 100 | リードの質や初期接触の有効性を判断 |
| 平均受注単価 | 売上金額 ÷ 成約件数 | 1件あたりの売上規模を把握 |
| リード獲得単価 | マーケ予算 ÷ リード数 | 1件のリードを獲得するためにかかったコスト |
これらの式を使えば、日々の営業活動を数値で振り返りやすくなります。
また、複雑な分析が必要な場合はExcelやGoogleスプレッドシートを使って、自社用のダッシュボードを作るのもおすすめです。
KPIは「設定して終わり」ではなく、定期的に見直して、現場に合ったものへと育てていくことが大切です。
まずは無理なく追える数値から始めて、少しずつ精度を高めていきましょう。
5つのフレームワークで始める営業データ分析|KPI設計からパイプライン管理まで
営業データを活用して成果につなげるには、「何をどう分析するか」の視点を整理することが大切です。
そこで役立つのが、目的や課題に応じて使い分けられる営業データ分析のフレームワークです。
このセクションでは、営業現場でよく使われる5つの代表的なフレームワークをご紹介します。
KPIの設計や、パイプラインの見直しにも活かせる内容なので、実務の参考として役立ててみてください。
KPI分析|トップ営業との違いを見える化する
KPI分析は、自社の営業チームと“成果を出している営業パーソン”の行動や数字を比較し、差分から改善点を探る手法です。
たとえば、「訪問数は同じでも成約数が違う」場合、提案内容やクロージングの質に注目するといったように、課題のポイントを数値から読み解くことができます。
エリア分析|地域ごとの特性を営業戦略に反映
地域ごとの反応や購買傾向を把握するためのフレームワークです。
たとえば「Aエリアは競合が強いが、Bエリアは自社商材の成約率が高い」といったデータから、エリアごとの戦略やターゲティングを最適化できます。
行政データや商圏情報とあわせて活用すると、より効果的です。
行動分析|営業担当者ごとのアプローチを可視化
営業メンバーの行動データ(訪問数・架電数・商談時間など)を分析することで、成果につながる動き方の傾向を把握します。
結果の良し悪しだけでなく、「どのようなアクションが結果につながっているか」を掘り下げることで、ナレッジの共有や営業手法の標準化にもつながります。
商談分析|提案内容と顧客の反応から学ぶ
「どのような提案をして」「顧客がどう反応したか」を振り返るフレームワークです。
ヒアリング内容や提案資料の内容、質問への対応などを見直すことで、成約率を左右するポイントが明らかになります。
営業の質を底上げしたいときに効果的です。
パイプライン分析|フェーズごとの進捗と課題を見える化
営業プロセス全体をフェーズに分け、各段階での進捗状況やボトルネックを可視化する手法です。
「どの段階で案件が止まりやすいのか」「目標の受注数に対して、いまどの位置にいるのか」を把握でき、マネジメントの精度を高めることができます。
フレームワーク別KPI早見表
どのフレームワークで、どのようなKPIが活用できるのか。以下に簡単に整理してみました。
分析の目的やフェーズに応じて、使い分けのヒントにしてみてください。
| フレームワーク | 主な活用シーン | 代表的なKPI指標 |
|---|---|---|
| KPI分析 | トップセールスとの比較/育成 | アポ数・商談数・CV率・案件化率 |
| エリア分析 | 地域別戦略立案 | 地域別リード数・成約率・商談数 |
| 行動分析 | 営業担当の動きの改善 | 架電数・訪問件数・商談時間・商談化率 |
| 商談分析 | 提案品質の見直し | 提案件数・失注理由別件数・商談満足度 |
| パイプライン分析 | 案件管理・フェーズごとの進捗管理 | 各フェーズの滞留数・CV率・平均リードタイム |
Excel/SFA/BIを比較!営業データ分析ツールの選び方と導入のコツ
営業データを活用するには、手元の情報を「いかに整理し、分析しやすい形にできるか」がカギになります。
その土台となるのが、分析ツールの選定と運用体制です。
世の中には多くの営業支援ツールや分析ソフトがありますが、
実際の現場でよく使われているのは Excel/SFA/BIツール の3つ。
このセクションでは、それぞれの特徴を比較しながら、導入時に意識したいポイントをわかりやすくまとめます。
Excel・スプレッドシート
SFAを導入していない企業では営業データ分析にExcelやスプレッドシートなどの表計算ソフトが使われているケースもあります。Excelやスプレッドシートは手軽に使えて柔軟性が高く自由な形式が特徴です。一方、ゼロから手動で仕組みを作る必要があるため、運用に大きな手間がかかります。膨大なデータの処理も得意ではないため、フリーズしてしまうリスクもあるでしょう。
事業規模が大きくなるにつれてデータの量も増えていくため、手動でデータを入力し分析を進めるには大きな労力が必要となります。データ分析の業務負担が重い場合はSFAの導入によって改善可能です。
SFA(営業支援ツール)
営業データ分析に活用するならSFA(営業支援ツール)がおすすめです。SFA(Sales Force Automation)とは企業の営業活動に関するデータを蓄積・分析でき、自動化によって業務効率化を実現できるツールを指します。SFAに搭載される機能としては、以下のようなものが一般的です。
- 顧客管理機能
- 行動管理機能
- 案件管理機能
- 予実管理機能
- レポーティング機能
SFAを導入すれば営業プロセスが数値化・可視化され、営業活動を効果的に進められます。属人化しがちな営業活動のデータが整理され共有しやすくなるので部署を超えた組織での戦略立案が可能です。マーケティングに特化したMA(Marketing Automation)ツールと連携させれば、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)を担当するマーケティング部門とも協力して業務を進めやすくなります。
データ分析にSFAツールを検討する際は下記の記事も参考にしてください。
BIツール
BIツールも営業データ分析に活用できます。BI(Business Intelligence)とはビジネス戦略の意思決定において、蓄積したデータの分析結果を活用することです。BIツールでもSFAと同様に、企業のデータを一元管理し分析できます。SFAやExcelと連携させればシームレスにデータを取り出せて、チームや部門を超えた共有が可能です。リアルタイムでのデータ収集と分析が可能なBIツールもあるため、タイムラグを生じさせずに業務を進められます。
ビッグデータを取り扱ったり、自社の競争力をより高めたりするなら、BIツールの導入を検討してもよいでしょう。
機能・価格・導入工数の比較表
ツール選びの際に見落としがちなのが、「現場との相性」と「運用までのハードル感」です。
以下に3種のツールを比較した表を掲載します。導入検討時の参考にしてみてください。
| ツール種別 | 主な機能 | 初期費用感 | 学習コスト | 向いている規模・組織 |
|---|---|---|---|---|
| Excel/スプレッドシート | 手動分析/表計算/グラフ作成 | ほぼ不要 | 低〜中(自由度が高い反面属人化しやすい) | 小規模〜中規模/分析初心者向け |
| SFA(営業支援ツール) | 顧客管理/案件進捗/レポート作成/予実管理 | 中〜高(ライセンス課金制が多い) | 中〜高(慣れれば一元管理が便利) | 中規模以上/営業部門の管理強化を図りたい組織 |
| BIツール | ダッシュボード/多軸分析/リアルタイム可視化 | 中〜高(大規模データ対応も可) | 中〜高(連携設計がカギ) | データ量が多く分析視点を拡げたい企業 |
※ツールにより個別の価格・機能差があるため、導入前にトライアルやサンプル活用をおすすめします。
社内浸透を進める3ステップ
どんなに高機能なツールを導入しても、現場で活用されなければ意味がありません。
実際には「使われない」「入力されない」という悩みも少なくありません。
ここでは、ツールを定着させるための流れを3つのステップに整理してご紹介します。
ステップ1:まずは“使う理由”を共有する
現場でよく聞くのが、「これって何のためにやってるの?」という声。
新しいツールを導入する際は、「なぜ今必要なのか」「どう役立つのか」をあらかじめ丁寧に伝えることが大切です。
納得感があれば、面倒な入力作業も目的をもって取り組んでもらいやすくなります。
ステップ2:小さく始めて、使い方を“共通化”する
最初から完璧を求めず、まずは少人数や一部機能から始めるのが現実的です。
併せて、「この項目は必ず入力する」「週1回ダッシュボードを確認する」といったルールをシンプルに設定することで、全員の使い方が揃っていきます。
ステップ3:成果を“見える化”して現場に還元する
「ツールを使うほど成果が出る」という実感があれば、自然と活用は広がっていきます。
たとえば、「入力項目を改善したら成約率が上がった」「ダッシュボードで進捗が明確になった」など、小さな成功体験を共有していくことが定着化につながります。
営業データ分析でつまずきやすいポイントと回避策
営業データ分析を取り入れる企業は増えていますが、実際には「うまくいかない」「思ったほど活用できない」と感じているケースも少なくありません。
原因はツールやフレームワークの使い方ではなく、運用そのものに起因することが多いのが実情です。
このセクションでは、営業データ分析に取り組む中でつまずきやすいポイントと、その回避策を2つの視点からご紹介します。
データ品質を保つ4つのルール
データ分析の精度を左右するのが、もととなるデータの「質」です。
入力ミスや二重登録、更新漏れがあると、せっかくの分析も正しく機能しません。
現場でよく起こる問題と、日々の運用で意識したいポイントを以下にまとめました。
| よくある課題 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 入力内容がバラバラ | 項目ごとの入力例をチームで共有する(例:会社名表記を統一) |
| データの抜け漏れ | 必須項目にマークをつける/定期的な入力確認のタイミングを設ける |
| 更新されないまま放置される | 商談の節目で入力を促す(アポ設定時・見積提出時など) |
| 無効データが溜まる | 一定期間以上アクションがないデータは棚卸し対象にする |
「正確に入力しよう」と声をかけるよりも、無理なく続けられるルールを設計し、仕組みでミスを防ぐことが重要です。
属人化を防ぐ運用フロー事例
営業データの管理が特定の担当者に偏っていると、その人が不在になった瞬間に業務が止まってしまうリスクがあります。
また、他のメンバーが内容を把握できない状態では、分析も機能しにくくなります。
以下は、属人化を防ぎながらチーム全体で運用するための事例の一部です。
① 役割を分担する
- 営業担当:日々の入力・ステータス更新
- マネージャー:月次で入力状況をチェックし、集計結果を共有
- 管理部門(または企画):定期的なデータ棚卸しと品質確認
担当を明確にしておくことで、「入力されないまま放置」や「管理がブラックボックス化する」事態を回避できます。
② ダッシュボードを“全員が見る”前提にする
一部の人だけが見るのではなく、「全員が週次で見ることを前提に作る」ことで、自然とデータの重要性が浸透していきます。
あえてトップ画面にKPIサマリーを設置するなど、見やすさ・使いやすさの設計も定着に効果的です。
営業データ分析の成功は、ツールや手法以上に、「チームで続けられる仕組み」をどう作るかにかかっています。
最初は完璧でなくてもOK。少しずつ、改善を重ねながら運用をブラッシュアップしていく姿勢が大切です。
まとめ|営業データ分析を成果につなげるポイント
営業データの分析は、売上アップに向けた特別な取り組みではなく、チームが感覚ではなく数字に基づいて判断し、着実に改善の一歩を重ねる「習慣」として捉えるのが理想です。
動向・要因・検証のステップに沿って、KPIやフレームワークを活用することで、現場感を損なわずに組織全体の営業力を高めていく原動力になります。
しかし実際には、「記録して→集めて→振り返る」までをこなすのは、現場にとって少しハードルが高いもの。
そこで注目してほしいのが、「入力したらそのまま使える形で可視化される仕組み」です。
ネクストSFA/CRMなら、案件の進捗をドラッグ&ドロップで管理できるフェーズ管理、スマホからもサクッと商談履歴を登録できる入力設計で、営業現場にフィットする使いやすさが魅力です。
さらに、MA機能も統合されているため、リードの育成から案件化、受注後の追客まで、一つのツールで一気通貫のデータ活用が可能です。
営業活動の記録を「面倒な作業」ではなく「成果につながる自然なステップ」に変えたいなら、ぜひ一度チェックしてみてください。