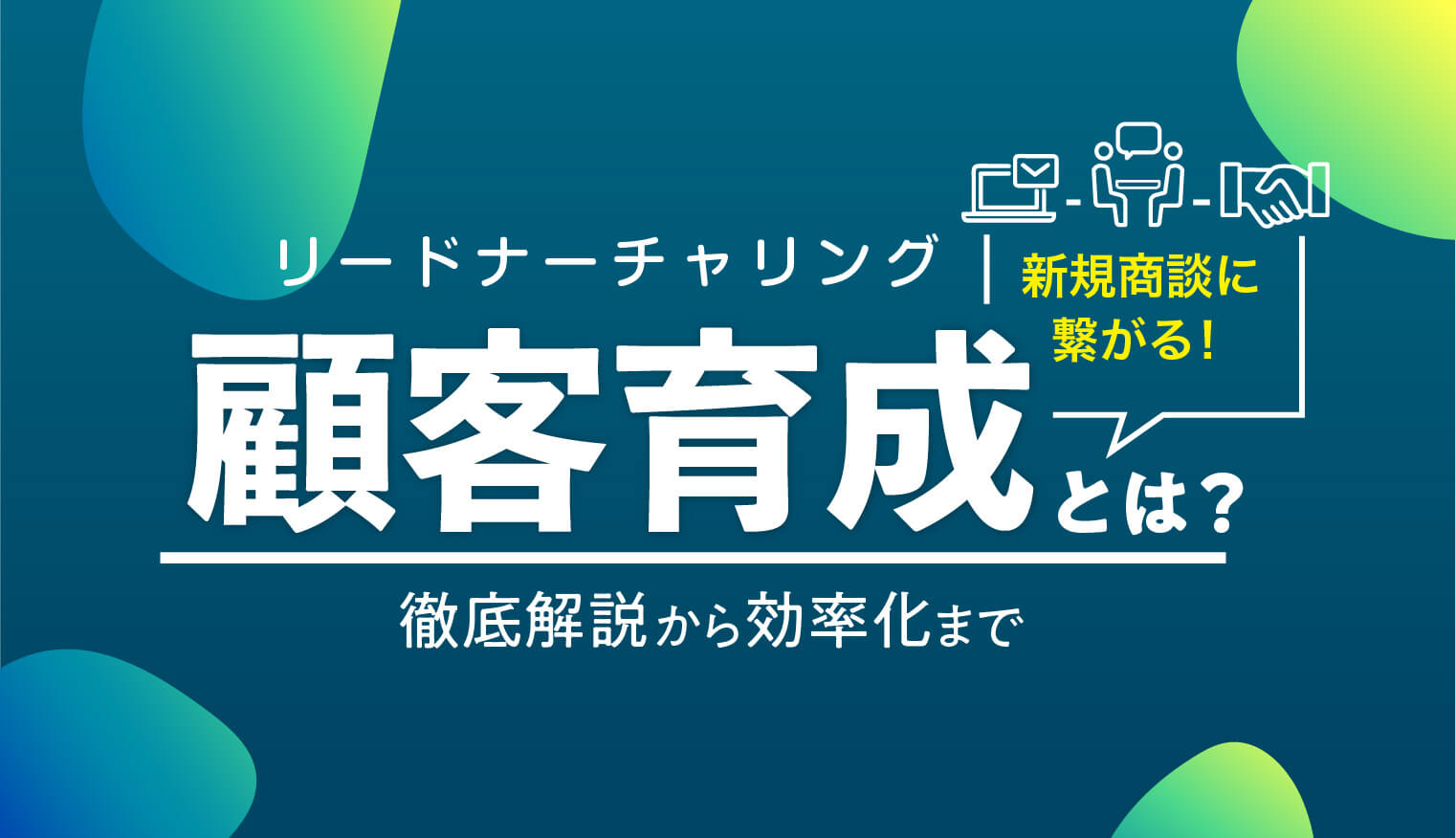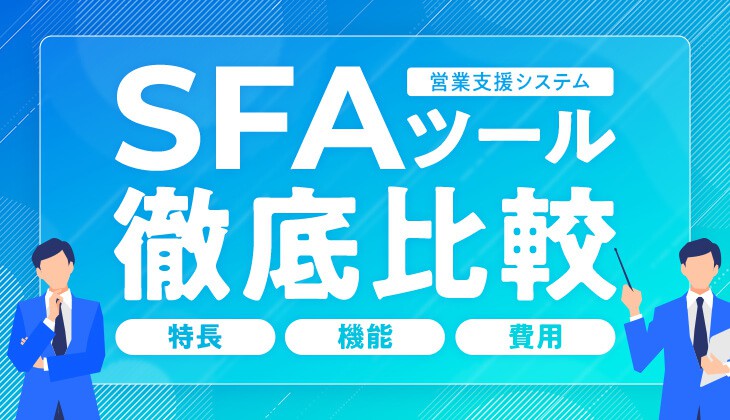更新日:2025/06/16

SFAの選び方ガイド|11のポイントと選ぶ前にやるべきことや導入のメリット・デメリットもご紹介

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
営業活動の効率化や成果向上を目指すなら、SFA(営業支援システム)の導入がおすすめです。しかし、SFAと一口に言ってもさまざまな製品があり、「どれを選べばよいか分からない」という企業担当者の方も多いでしょう。導入の目的や自社の課題に合わないSFAを選ぶと、現場に定着しなかったり、SFAへ入力する手間だけが増えてしまったりして後悔する可能性もゼロではありません。
そこで本記事では、SFAの選び方や導入前にやるべきことなどをご紹介します。SFAの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
SFAとは?
SFAとは「Sales Force Automation」の略称で、営業活動を支援するシステムです。営業部門が保有するさまざまなデータを入力することで、営業活動の状況や案件の受注金額、売上進捗などを可視化できます。
また営業に関するデータを一元管理できるので、過去から現在までのデータを分析して営業活動の効率化や成果向上につなげられます。
SFAに搭載されている主な機能は、以下の通りです。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 案件管理 | 案件ごとの詳細や進捗状況を管理できる具体的には、案件ごとの営業担当者名や顧客側の担当者名、商材、受注予定日、見積金額、売上金額などを管理できる |
| 顧客管理 | 顧客に関する情報を管理できる具体的には、企業名や担当者名、連絡先、担当者の役職、問い合わせ・商談履歴、取引履歴などを管理できる |
| 行動管理 | 営業担当者の日々の行動を管理できる具体的には、アポイント数やコール数、訪問数、商談回数、受注数・受注率などを管理できる |
| 日報・週報管理 | 営業担当者の日報や週報を作成・管理できる |
| タスク・スケジュール管理 | 営業担当者のタスクやスケジュールを設定・管理できる |
| 予実管理 | 予算と実績を比較し、どれだけ差分があるかを確認できる |
製品によって標準搭載されている機能は異なるので、詳細については運用会社(ベンダー)に問い合わせてみましょう。
失敗しない!SFA選びで押さえるべき11のポイント

SFA選びで失敗しないために、おすすめの選び方をご紹介します。複数のSFAの中からどの製品を選べばよいか迷っている方は、参考にしてください。
1. SFAの形式は何にするか
SFAの形式は、主に以下の2つのタイプに分かれます。
- クラウド型
- オンプレミス型
クラウド型とオンプレミス型で、特長やメリット、デメリットが異なるので、導入の目的や自社の状況に合った形式を選びましょう。
クラウド型
クラウド型とは、インターネットを通じて、ベンダーと呼ばれる運用会社が提供するサービスを利用する形式のことです。
クラウド型のSFAは、自社でサーバーやネットワーク機器を用意する必要がありません。インターネット環境が整っていれば、すぐに利用できます。また利用ユーザー数や欲しい機能に応じて複数のプランがあり、ニーズに合わせて自由に選択できるケースが多いです。導入時は最低限のプランにして、慣れてきたり他の機能が必要になったりしたらプランを変更するのもよいでしょう。
ただし、クラウド型のSFAはベンダーが提供しているツールであるため、後述するオンプレミス型と比べるとどうしてもカスタマイズできる範囲が限られます。事前にどの程度カスタマイズ可能かを確認しておくことが大切です。
オンプレミス型
オンプレミス型とは、自社内にサーバーやネットワーク機器などを設置して、自社でシステム全体を保守・運用をする形式です。
オンプレミス型のSFAは、クラウド型のSFAに比べて高水準のセキュリティ環境を構築できる他、必要な機能を追加したり自社の業務フローに応じた設計にしたりと、柔軟にカスタマイズできる点が特長です。
一方で初期費用が高額になりやすいだけではなく、障害が起きたときには自社で対応しなければなりません。保守契約を結んでいる場合は緊急時の対応やメンテナンスを依頼できますが、その分費用がかかる可能性があります。
2. 自社に合った機能がそろっているか
SFAにはさまざまな機能が搭載されていますが、自社に必要な機能がそろっているかを確認しましょう。自社に必要な機能がそろっていないと、別のツールや手作業で補わなければなりません。結果、SFAを導入したのにもかかわらず、担当者の負担が大きくなってしまいます。導入の目的や自社の課題に合わせて、事前に必要な機能を洗い出しておくことが大切です。
なお、SFAは搭載されている機能が多いほどよいわけではありません。不要な機能が多過ぎても分かりにくくなったり、使いこなせなかったりします。そのため、自社に必要な機能に絞って導入するのがおすすめです。
3. スマートフォン対応しているか
スマートフォンに対応しているかどうかも、SFAを選ぶ際のポイントです。
SFAを利用する営業担当者は、取引先との打ち合わせや商談のため外出していることも多いです。スマートフォンに対応しているSFAであれば、外出先でも手軽に営業状況や進捗、顧客・案件情報などを確認できるので業務の効率化につながります。
打ち合わせや商談後も、移動時間を使って話した内容をスマートフォンから入力でき、迅速な情報共有が可能です。
4. 現場が使いやすいか
SFAは、導入後に案件や顧客データの入力、データ分析といったさまざまな用途で頻繁に使われます。作業をする上で、営業担当者が「使いにくい」「分かりにくい」と感じるSFAだと、次第に利用されなくなってしまうかもしれません。そのため、手入力の項目が少ないシンプルなSFAや読み込みが速いSFA、直感的に操作しやすいSFAなどを選ぶのがおすすめです。
なお、SFAによっては無料トライアルを実施しているものもあります。積極的に活用して、実際の操作感や画面構成、入力項目の数などを確認しましょう。
5. 柔軟にカスタマイズできるか
カスタマイズ性の高さも、SFAを選ぶ際の重要なポイントです。製品によってどの程度カスタマイズができるかは異なります。
自社の業務フローや商材に合わせて、SFAの入力項目や画面構成、権限設定などを柔軟に設計できるかを確認しましょう。カスタマイズ性が高ければ、現場にとって使いやすい形に調整できるため導入後の定着にもつながります。
さらに、追加開発の可否についても事前に確認してください。市場の変化に合わせて新しい事業を始めたり、新たな商品やサービスを扱ったりする可能性もあります。追加開発ができるSFAであれば、新しい業務フローや営業プロセスに合わせて必要な機能や入力項目を柔軟に追加できます。
6. 他のツールとどの程度連携できるか
MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客管理)ツール、会計システムなどと連携できるSFAも多いです。SFAを選ぶ際には、他のツールとどの程度連携できるかも確認しておきましょう。
SFAはさまざまなデータを蓄積するツールです。社内で使っている他ツールと連携できれば、データを自動で反映させられるので手入力の工数を削減可能です。また部署間での情報共有も手軽に行えます。例えば、SFAと会計システムを連携させれば、SFAに入力した予算や売り上げのデータが自動で会計システムに反映され、経理部門との情報共有も容易になるでしょう。
7. アップデートはどのくらいの頻度か
SFAを選ぶ際には、アップデートやバージョンアップの頻度も確認しましょう。SFAは長く利用するツールだからこそ、その時々のニーズや状況に合ったアップデートやバージョンアップが欠かせません。
定期的にアップデートやバージョンアップを実施しているSFAの場合、市場の状況やユーザーの意見などが反映されやすく、使いやすいSFAである可能性が高いです。
なお、不定期で細かなアップデートを行うものや定期的に大型のバージョンアップをするものなど、製品によって更新頻度やスピードはさまざまです。過去のアップデートやバージョンアップの内容を確認し、使いやすいと感じるものを選びましょう。
8. コストと費用対効果が合っているか
検討しているSFAを導入した場合、どのくらいのコストがかかるのかや、どのくらいの費用対効果になるのかを事前にシミュレーションしましょう。費用対効果が見合わなければ、せっかく導入しても早期に見直しが必要になるかもしれません。
SFAを利用する場合、初期費用や月額費用、オプション費用、サポート費用など、さまざまなコストがかかります。SFAを導入してコスト以上の成果を見込めるのか、事前に見極めることが大切です。
9. サポート体制が充実しているか
SFAの導入前には、運用フローの構築や現場メンバーへの使い方のレクチャーなど、多くの作業が発生します。またSFAの導入後も、利用に当たって不明点が出てきたりトラブルが発生したりとさまざまな課題が生じやすいです。
企業の担当者がこれら全ての対応を行うと、大きな負担がかかってしまいます。そのため導入前の初期設定の対応から従業員へのレクチャー、導入後の質問・トラブルへの対応まで、丁寧にサポートしてくれるSFAを選ぶのがおすすめです。SFAによっては、企業ごとに専任のカスタマーサクセス担当者が付いたり、専門チームが作られたりするケースもあります。
なお、何か困ったことがあったときに、どのくらいのスピードで対応してくれるのかも確認しておきましょう。
10. セキュリティは万全か
SFAには、顧客や売上に関する以下のような情報が登録されます。
| 対象機能 | 機密情報例 |
|---|---|
| 案件管理 | 商談の進捗度や受注見込み、見積もり、売上など |
| 顧客管理 | 顧客名や企業情報、担当者や役職、商談履歴、名刺情報など |
| 行動管理 | 企業への訪問回数や提案数、受注率など |
セキュリティが万全ではないと、情報漏えいのリスクが高まります。万が一、情報漏えいが起こると、顧客や取引先に損失を与える可能性があるだけではなく、自社の信用が損なわれたり法的な責任を問われたりする恐れもあります。
検討しているSFAに、多要素認証や二段階認証、IPアドレス制限、権限設定機能、データ暗号化機能など、セキュリティ対策の機能が付いているかどうかを確認しておきましょう。
11. 自社と類似した事例が豊富にあるか
検討しているSFAに、自社と類似した事例があるかどうかも押さえておきたいポイントです。業種・業態はもちろん、企業規模やSFAを導入する目的など、自社と類似した事例が豊富にあれば、その分導入後のイメージが湧きやすいです。
事例はサービスサイトに掲載されていることが一般的ですが、詳細を確認できない場合は問い合わせてみてください。
SFAを選ぶ前にやるべきこと
ここまでSFAの選び方をご紹介しましたが、SFAを選ぶ前にもやるべきことがあります。詳細を見ていきましょう。
導入する目的を明確にする
まずは、何のためにSFAを導入するのか、自社の課題や導入目的を明確にする必要があります。「人気のあるSFAだから」「コストが安いから」といったようにあいまいな理由で導入すると、社内でSFAの必要性が理解されずなかなか定着しません。さらにせっかくSFAを導入したのにもかかわらず、自社の課題を解決できない可能性もあります。
導入目的を明確にするには、以下のフローで細かく現状の課題をまとめるのがおすすめです。
- 管理側・現場側それぞれで、営業に関する現状の課題を洗い出す
- それぞれの課題に対して、優先順位を付ける
- 優先順位の高い課題を解決できるSFAを選ぶ
SFA導入・定着の担当者を設ける
SFAを導入して組織に定着させるには、先述した通り多くのフローや作業が必要です。導入から運用までスムーズに進めるためには、SFAの担当者を設けましょう。
SFAの担当者には、ITリテラシーが高く営業の現場を把握している人材が適しています。専任の担当者を設けるのがよいですが、難しい場合は複数人で対応できるようにプロジェクトチームを作るのがおすすめです。
運用ルールを作っておく
運用ルールやフローがあいまいなままSFAを導入すると、データが入力されずに放置されてしまう恐れがあります。データが適切に入力されなければ、データ分析も正しく行えません。データ入力の頻度やタイミング、入力内容などをまとめた運用ルールや運用フローを事前に作っておくことが大切です。
SFAや企業によって適切な運用ルールは異なりますが、実際にデータを入力する営業担当者に疑問を持たせないようなルールやフローを作りましょう。
SFAを導入するメリット
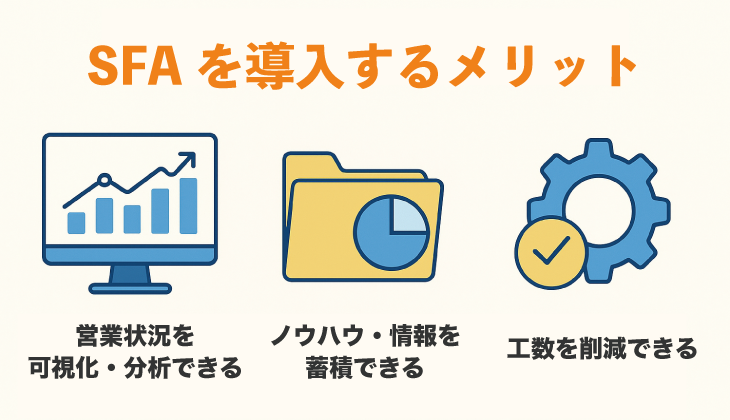
最後に、SFAを導入するメリットとデメリットをご紹介します。主なメリットは以下の通りです。
営業状況を可視化・分析できる
SFAを導入すれば、日々の営業活動や顧客情報を社内全体で効率良く共有できます。その結果、特定の営業担当者しか情報を把握していないという、属人化を防げるでしょう。
さらに、営業担当者がルールに沿って正しくデータを入力していれば、常に最新の情報がSFAに反映されるため、営業戦略の見直しや施策の検討・立案がしやすくなります。売上状況などもリアルタイムで確認できるため、社員一人ひとりの達成感やモチベーションの向上にも効果的です。
ノウハウ・情報を蓄積できる
SFAには営業に関するさまざまなデータが蓄積され、そのデータを分析することで営業の成功パターンやノウハウをまとめられます。
新人や若手の営業担当者も、SFAを確認することで営業に必要な知識やスキルを身に付けやすくなるでしょう。さらに営業担当者が退職や休職、異動する場合も、SFAを活用すれば必要な情報をすぐに共有できるのでスムーズに引き継ぎが可能です。
工数を削減できる
SFAに蓄積されたデータは自動で集計され、レポートやグラフなどで可視化されます。スピーディかつ正確に集計されるので、分析にかかっていた時間や手間を減らせるでしょう。商材別や担当者別、案件別、チーム別といったさまざまな視点で、瞬時に集計できるのもポイントです。
タスク・スケジュール管理機能を搭載しているSFAであれば、営業活動のタスクや商談スケジュールをまとめて管理することもできます。「タスクはタスクツールを確認し、スケジュールはスケジュールツールを確認する」といった無駄な確認作業がなくなるので、業務の効率化につながるでしょう。
SFAを導入するデメリット
SFAを導入する際の主なデメリットは、以下の通りです。
一定のコストがかかる
SFAを導入する際には、一定のコストがかかることを認識しておきましょう。製品によってもかかる費用は異なりますが、初期費用や月額費用、カスタマイズ費用(オプション費用)がかかるケースが多いです。
毎月どのくらいのコストがかかり、費用対効果が見合うのかを導入前にしっかり検討することが大切です。
SFAの費用相場や内訳については、以下の記事もご確認ください。
入力作業が必要
SFAを新たに導入する場合、今まで使っていた管理ツールやエクセル、スプレッドシートからデータを移行しなければなりません。これまで蓄積していたデータが多ければ多いほど、移行作業に手間と時間がかかるでしょう。
またSFAを導入した後も、営業担当者は自身の案件や顧客情報、営業進捗を都度入力する必要があります。なるべく楽に入力できるように、入力項目の少ないSFAや操作性の良いSFAを選ぶのがおすすめです。
まとめ
SFAを導入すれば、営業状況の可視化や営業ノウハウの蓄積、業務の効率化などさまざまなメリットを得られます。一方で、自社に必要な機能が搭載されていないSFAや使いにくいSFAを選んでしまうと、現場で定着せずにコストだけかかってしまう恐れもあります。
SFAの導入から定着までを成功させるには、事前の準備が非常に大切です。本記事でご紹介した選び方のポイントや事前にやるべきことを参考に、自社に合ったSFAを導入しましょう。
「ネクストSFA」は、サービス継続率98.6%(2025年3月時点)という高い実績を持つSFAです。テレアポや営業活動などのアプローチ管理から、案件・受注管理、営業担当者の日報・週報・月報作成・管理まで、営業活動において必要な機能が搭載されています。
その他にも、以下に挙げるMA機能やCRM機能もあり、案件や顧客に関する情報を一元管理できるのが特長の一つです。
- MA機能
メール一括配信機能、シナリオメール設定機能、スコアリング&トラッキング機能、問い合わせフォーム生成機能 - CRM機能
企業管理、売上管理、顧客別予算管理、請求書・見積書作成機能
クラウド会計ソフトや請求書管理システムなどの各種ツールとも連携できるので、営業だけではなくバックオフィスにもスムーズに情報共有が可能です。
使いやすさと見やすさを徹底追求した画面設計なので、SFAを導入したことがない企業にもおすすめです。複雑な初期設計をする必要はなく、柔軟にカスタマイズができます。また必ず1名以上の専任担当者が付き、使い方の説明会やマニュアルの作成、定着後のフォローなどを全て無料で対応します。回数制限はないので、困ったことがあったら気軽に相談できるでしょう。
無料トライアルも行っているので、SFAを検討している企業担当者の方はお気軽にお問い合わせください。