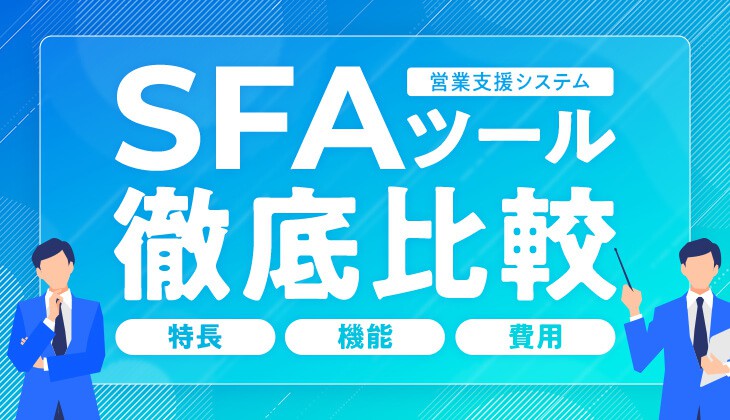更新日:2026/01/08

SFAって必要??必要性を示す3つのポイント

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者
庭田 友裕
SFAは営業の業務効率化を図る上で有効な手段であり、案件の進捗状況を共有・管理してチームの業務的・時間的な負担を分散させることができます。
さらにSFAは営業がクライアントに対して行った商談内容などのアプローチをデータとしてリザーブできるので、成果率の高いトップ営業マンの業務プロセスを分析して社内で共有させれば、営業チーム全体のレベルアップを図ることも可能です。
さらに、SFAは営業効率を高めることができるツールですが、効果的に運用するためにはメンバーにSFAの必要性を示して、SFAを活用することによって得られるメリットを理解してもらわなくてはなりません。
導入または運用を検討しているが、現場からの理解を得られないので思うように進んでいない、というケースも多いのではないでしょうか。

こちらでは、SFAの必要性を示す3つのポイントをお伝えします。
SFAツールの導入を検討中の方はSFAツール比較記事も要チェック!
この記事の目次はこちら
1. 案件の進捗を管理して営業チームをバックアップ

SFAを導入することで営業マンはクライアントとの商談といった報告内容を帰社することなく随時報告することができるので、案件の進捗管理が簡易になり、営業チームを効率的にバックアップことが可能です。
帰社しないと進捗報告ができないということは、営業マンにとってその分クライアントとの貴重な接触時間が削られてしまうということ。
営業活動の効率化を図る上で、直近に改善するべきポイントといえるでしょう。
SFAには営業の活動履歴や商談内容をレコードできる機能が備わっていますので、営業マンは帰社することなく、外出中でも進捗状況の報告を行うことができます。
SFAによって営業からリアルタイムで進捗報告を受けた上司や担当者は、抱えている案件がどのようなフェーズにあるかを把握し、営業に対しアドバイスやフォローを臨機応変に講じることができるので、チーム全体の業務的・時間的な負担を分散させたいと考えている場合は導入を検討してください。

2. トップ営業マンのスキルをチーム内で共有

成果率の高い営業マンがクライアントに対して行ったアプローチ方法をSFAでデータとしてリザーブし、他の営業マンに共有させることで営業チーム全体のレベルアップに貢献することができます。
チームの中でも群を抜いて成果率の高いトップ営業マン。
そんなトップ営業マンのスキルがチーム全体で共有できたら、一体どれほど利益を出せるだろうと考えたことはありませんか。
SFAはそれぞれの営業マンがクライアントに対して行ったメールや提案といった営業のアプローチ方法がデータとして記録できるので、トップ営業マンが行っている営業プロセスをチーム内で共有すれば、他の営業マンが参考にしながら業務に取り組むことができます。
これを言い換えると、なかなか成果が上がらない営業のボトルネックを洗い出して改善策を練るというフローも実現可能です。

3. 営業担当の属人化を防ぎ引き継ぎをスムーズに実現

クライアントごとに行った営業の形跡をデータとして管理・共有できるという点はSFAで得られるメリットであり、営業担当の属人化を防いで担当変更時の引き継ぎをスムーズに進めることができます。
従来の営業モデルでは、個々の営業マンが形成する人的ネットワークや我流なノウハウといった担当者それぞれのマンパワーに頼って業務が属人化しながら進められているケースが多いものでした。
しかし、これでは営業担当が変わる際に引き継ぎが煩雑となり、新しい営業担当が十分なノウハウを得られず、場合によってはクライアントに不適切なアクションを起こして今まで築き上げてきた信頼関係を損ねてしまう事態も考えられます。
営業担当が変わった時でもクライアントとの円滑な関係を保つためには十分な引き継ぎ作業が必要不可欠であり、そのためにはSFAによってクライアントと各営業担当のやり取りをデータとしていつでも確認できるように日頃から共有しておかなくてはなりません。
また、引き継ぎ自体が行われずに担当の営業が急に辞めてしまった場合であってもSFAはクライアント・案件ごとに進捗を記録することができるので、チームが受けるダメージを最小限に食い止めることも可能です。

SFAは現場の理解を得た上で導入を!
SFAは営業の業務効率化を図るために講じられる一つの手段であり、導入すること自体が目的ではありません。
「SFAを導入したことで売上が伸びた」という企業の話を聞いたことはありませんでしょうか。
しかし、このような成功例はSFAを効果的に活用できたケースの話であり、運用するメンバーの理解を得ずに中途半端な導入・運用を行うと、かえって逆効果になりかねません。
また、メンバーが「そもそもSFAを活用する必要性が分からない」というモチベーションのまま運用を開始してしまうと、メンバーが情報入力する作業自体をストレスに感じてしまう可能性もあります。このような宝の持ち腐れ状態を避けるためには、SFAを導入するにあたって明確な目的を開示し、現場の声によく耳を傾けた上で判断する必要があります。